先に ■熊本藩豊後鶴崎のはなし でご紹介した「川の中の美しい島・輪中ー熊本藩豊後鶴崎からみたせかい」を読んでいる。
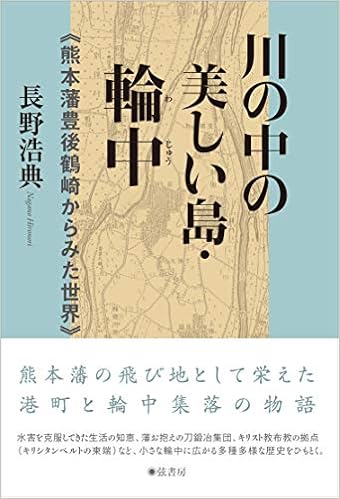
この本は三本の柱で構成されている。1・高田地区の輪中、2・輪中の刀鍛冶、3・切支丹布教の拠点としての高田である。
それぞれが大変興味深く面白く読ませていただいた。まさか九州のそれも熊本藩豊後領にこのような輪中があるとは知らず、その独特の景観に一度訪れてみたいという思いを強くした。
一方「豊後切支丹布教の拠点」として高田が上げられているが、その中で「清田」地区の名前があった。
天正13年の切支丹数として豊後府内に1,052人、輪中を構成する大野川流域に4,565人の数が上げられているが、そのうち高田地区に1,365人、清田地区が一番多く1,474人であったとされる。
そして筆者は「イエスズ会日本年報(上)」の記事を引用しておられるが、その文章は「府内より2レグワ(二里)を隔てた高田においては、初め少数のキリシタンがあつたが、多数の貴族が説教をするためにイルマンを派遣せんことを懇願し、これを派遣した後700人が洗礼を受け、その後暫くして更に50人が洗礼を受けた。つぎにその家に200人を有した一人の殿が洗礼を受けたが、夫人は偶像に熱心であったため、夫は彼女にデウスの教を聞かせることが出来なかった。併し彼女は室内にあって密かに説教を聴き、精霊に動かされて、身分の高さを厭はず、多数の親類及び家臣が聴いていた室に入り、イルマンにむかって、「自分はキリシタンとなる決心でなかったが、汝の説教を聴いて審理を悟りまた今日までの一生の誤を知った故洗礼を浮(?)くることを望む。またこれについての自分の喜びを知らんためわが家に来たりてみよ」と言ひ、彼女は一家を支配してゐた故、子女、親戚及び夫と共にキリシタンとなった」とある。
そして筆者はその一族を吉岡氏と比定された。夫人とは天正15末~16年にかけて薩軍と戦った妙林尼と想起しておられるが、一方夫人が受洗した記録がないともされている。
私はすぐさま「大友の末葉・清田一族」編者であられる清田幸一氏から頂戴した一枚の絵図が頭に浮かんだ。
高田の輪中こそ描かれていないが、大野川の対岸に「清田」地区が描かれている。
清田一族の発祥の地は大分市上判田の小嶽山であるとされる。「清田」地区はまさにこの上判田であろう。
高田と清田は距離にして7~8㌔である。
そうすると著者が否定されたその一族は吉岡氏ではなく、大友一族の清田氏と考えるのが妥当ではないのか?
殿とは清田鎮忠であり、夫人はジュスタのことであろう。ジュスタの先夫との娘・マダレイナは後に殉教する。
再婚した鎮忠には二男一女があり、女・涼泉院はキリシタンであり、肥後切支丹史調査資料に「私(細川)家来清田石見母轉切支丹涼泉院」という類族系図が残されている。
涼泉院はこれも切支丹の志賀氏から養子をむかえたが、これが清田鎮乗(寿閑)であり、その嫡男が名高い清田石見であり、女・幾知は細川忠興の側室として、立孝(宇土細川家祖)、興孝(細川刑部家祖)をなした。
一冊の佳書が私の心をとらえている。私は著者のご努力に大いに敬意を表する中で、密かな疑問としてこのように思い至った。是が正しいかどうか今後の問題としたいが、清田家関係者の皆様にもご連絡して研究を続けたいと思っている。














