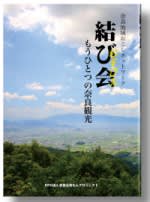昨年に続き今年も、四国にお参りしてきた。とある講の「四国八十八ヶ所巡拝団」(旅行実施:琴参バス株式会社観光部)に参加させていただき、10月16日(土)~21日(木)の5泊6日の日程で、第29番国分寺から第1番霊山寺まで回り、最後に高野山(和歌山県伊都郡高野町)の金剛峯寺奥の院にお参りしてきたのである。
※参考:行ってきました!四国巡礼2009(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/613e19bbcb66b1b4709a69409e265b38
このバス巡礼(総勢22名)は、一昨年に第88番大窪寺(香川県さぬき市)からスタートし、88か所を逆に回っている(=逆打ち)。私は昨年から参加し、第53番圓明寺(愛媛県松山市)~第30番善楽寺(高知市)までお参りしてきた。今回はその残りを回って「結願(けちがん))」となる。さらに、高野山奥の院に詣でて「満願成就」とする。私はまだ第88番から第54番間までを回り残しているが、皆さんについて高野山までお参りしてきたのである。
※利用させていただいた「琴参バス」のホームページ
http://www.kotosan.co.jp/

第21番太龍寺で(10/18)
昨年は初の参加だったので、戸惑うことが多かった。今年は2回目なので「バスから降り、金剛杖(こんごうづえ)を携えてお寺へ→手水舎(てみずや)で手と口を清める→本堂前でろうそく1本と線香3本に火を灯してお供え→納め札を納札箱に→お賽銭を供えて拝む→皆でお経を唱える→大師堂の前でそれを繰り返す→バスへ戻る」という慌ただしい動作が、比較的スムーズにできた。
「四国巡礼に行くよ」というと、よく引き合いに出されるのが菅直人首相の歩き遍路のことである。私は当時の報道により、04年7月、菅氏は第1番霊山寺(りょうぜんじ 徳島県鳴門市)から第24番最御崎寺(ほつみさきじ 高知県室戸市)まで歩いただけで終わった、とカン違いしていたが、よく調べてみるとその後、菅氏は4回も四国遍路に通っていた(=区切り打ち)。訂正を兼ねてブログ「kojitakenの日記」から引用させていただく。
http://d.hatena.ne.jp/kojitaken/20100606/1275784083

室戸岬(10/17)
《菅直人が泊まった遍路宿に泊まり、おかみさんの話を聞いたことがある。おかみさんは、菅直人は家族も秘書も連れず、本当に一人で歩いて、宿でも変名を使っていたにもかかわらず、報道陣に足取りを突き止められてしまい、以後は報道陣を引き連れてお寺を回る羽目になったと言っていた。この時、菅直人は徳島県の遍路を踏破し、室戸岬にある高知県最初の札所、24番の最御崎寺(ほつみさきじ)まで歩いた》。
《特に、23番薬王寺から最御崎寺までの、80キロ近くもある単調な道を歩いていたことは事実で、あんなところを歩いたからには、全行程を手抜きせずに歩いたことは間違いないだろう。しかも、菅直人が歩いたのは、酷暑だった2004年7月。あの夏の暑さは尋常ではなかった。それを歩き抜いたのだから、さすがに政治家はタフだ。宿では菅直人の食事中もテレビカメラが回っていて、最御崎寺到着の映像を撮るや否や東京に空輸され、夕方のニュースで放送されたとのことだった》。

室戸岬御厨人窟(みくろど 10/17)。19歳の弘法大師は、ここで求聞持の法を成就
《その後も菅直人が四国遍路歩きを継続していて、53番札所の円明寺(愛媛県松山市)まで、5度に分けて歩いていることを知っている人はほとんどいないだろう。つまり、菅直人は(初回を除いて?)黙って四国遍路を歩いているわけだ》。
初回の遍路を終えた直後の菅氏の公式HPには《お遍路の旅 空海が若い時修行をしたとされる四国の88箇所の寺を巡るお遍路の中で、徳島と高知の室戸までの1番から24番のお寺を、歩きで巡るお遍路の旅を終えて今日帰京。さすがの足はくたびれたが気持ちはすっきり。四国の皆さんをはじめ多くの皆さんから多くの親切と激励を受けた。心から感謝の気持ちで一杯。ありがとうございました》とある。
http://www.n-kan.jp/2004/07/post-725.php

第1番霊山寺(りょうぜんじ)前で(10/20)
私の知らないうちに菅氏は遍路を続けていて、すでに第53番圓明寺までお参りしていたとは、大したものだ。1番から53番までということは、ちょうど私と同じになる。バスで回った私と違い、菅氏は歩いて踏破されたのである。前置きが長くなったが、日付順に、私たちがお参りしたお寺と、記憶に残るシーンをピックアップする。

第28番大日寺
10/16(土)
29 国分寺(こくぶんじ)真言宗智山派 千手観世音菩薩(高知県南国市)
28 大日寺(だいにちじ)真言宗智山派 大日如来(高知県香南市)
この日はスタート日だったので、お参りしたのは2か寺だけだった。国分寺は、名前の通り「土佐の国の国分寺」である。四国八十八ヶ所霊場会の公式HPによると《聖武天皇(在位724~49)が『金光明最勝王経』を書写して納め、全国68ヶ所に国分寺を建立したのは天平13年のころ。土佐では行基菩薩が開山し、天下の泰平と五穀の豊穣、万民の豊楽をねがう祈願所として開創された》。
《土佐の国分寺といえば、平安中期の歌人、紀貫之(868~945頃)が浮かんでくる。とくに貫之が著した『土佐日記』は、女性の筆に託して書かれた仮名日記であることはあまりにも有名であるし、貫之が国司として4年間滞在した国府は、国分寺から北東1kmほどの近くで「土佐のまほろば」と呼ばれ、土佐の政治・文化の中心であった》。
http://www.88shikokuhenro.jp/kochi/29kokubunji/index.html

四国巡礼は「信仰、健康、観光」の「3コウ」だという。この日は、大歩危峡(おおぼけきょう 徳島県三好市)で遊覧船に乗った。「ぼけ」とは「断崖」を意味する古語だそうだ。東洋文化研究家のアレックス・カーが住んでいた祖谷渓(いやだに)も、すぐ近くだ。大歩危峡(吉野川)の両岸の岩(変成岩類)は、徳島県の天然記念物に指定されている。2億数千万年を経て侵食された岩は、見ものである。

10/17(日)
27 神峯寺(こうのみねじ)真言宗豊山派 十一面観世音菩薩(高知県安芸郡安田町)
26 金剛頂寺(こんごうちょうじ、西寺)真言宗豊山派 薬師如来(高知県室戸市)
25 津照寺(しんしょうじ 、津寺)真言宗豊山派 延命地蔵菩薩(高知県室戸市)
24 最御崎寺(ほつみさきじ、東寺)真言宗豊山派 虚空蔵菩薩(高知県室戸市)
別格4 鯖大師本坊(さばだいしほんぼう、八坂寺)高野山真言宗 弘法大師(徳島県海部市海陽町)

津照寺は、室津港(室戸市)のすぐ近くにあり、本堂までは百八段の急な石段を登る。伽藍は、とても派手な色だった。参拝後の昼食は、室戸岬新港「海の駅とろむ」内の「海鮮リストランぢばうま八」でいただいた。新鮮なトロかつおの刺身が、口の中でとろける。

最御崎寺は、菅氏が初回(04年7月)の歩き遍路を終えた寺だ。このお寺と第23番薬王寺(徳島県海部郡美波町)までは、実に単調な道が延々82kmも続く。鉄道も、途中までしか通っていない。この距離を歩き通したとは、大したものだ。菅さんは、エラい!
鯖大師本坊(八坂寺)には、こんな伝説がある。弘法大師空海が《ある朝通り掛かった馬子に積み荷の塩鯖を乞われましたが、口汚くののしられ、ことわられました。馬子が馬引坂まできた時、馬が急に苦しみだし、先ほどの坊様がお大師様と気づいた馬子は鯖を持っておわびし、馬の病気をなおしてくれるように頼みました。お大師様がお加持水を与えると馬はたちまち元気になり、お大師様は八坂八浜の法生島で塩鯖をお加持すると生きかえって泳いでいきました》。
http://www.bekkaku.com/map/04.html

《そこで仏の心を起こした馬子は、この地に庵をたて古今来世まで人々の救いの霊場といたしました。鯖を三年絶ってご祈念すると願いごとがかない、病気がなおり、幸福になれるといつしか人々に、鯖大師と呼ばれているのです。鯖大師でこの由来により鯖を三年食べないことにより子宝成就、病気平癒はじめ、あなたのお願いごとがかなえられます》。
夜(ホテルリビエラししくい泊)は、鯖ならぬカマスの姿造りにカマスの塩焼きと、美味しいお魚を堪能した。

10/18(月)
23 薬王寺(やくおうじ)高野山真言宗 薬師如来(徳島県海部郡美波町)
22 平等寺(びょうどうじ)高野山真言宗 薬師如来(徳島県阿南市)
21 太龍寺(たいりゅうじ)高野山真言宗 虚空蔵菩薩(徳島県阿南市)
20 鶴林寺(かくりんじ)高野山真言宗 地蔵菩薩(徳島県勝浦郡勝浦町)
19 立江寺(たつえじ)高野山真言宗 延命地蔵菩薩(徳島県小松島市)
18 恩山寺(おんざんじ)高野山真言宗 薬師如来(徳島県小松島市)
17 井戸寺(いどじ)真言宗善通寺派 七仏薬師如来(徳島市)
太龍寺は《「西の高野」とも称される。四国山脈の東南端、標高61メートルの太龍寺山の山頂近くにある。樹齢数百年余の老杉の並木が天空にそびえ、境内には古刹の霊気が漂う》(四国八十八ヶ所霊場会のHP)。このお寺へは、なんと!専用のロープウェイに乗ってお参りするのだ。全長2,775メートルで西日本最長。スイス製のゴンドラは、101人乗りだというからすごい。約10分の空の旅を楽しんだ後、お寺の石段の下に到着する。
http://www.88shikokuhenro.jp/tokushima/21tairyuji/index.html

《四国巡礼者にとって、屈指の難所であったこの山岳寺院にロープウエーが開通したのは平成4年である。徒歩では、中腹の駐車場から坂道を登るのに30分も要していた。1,200年のむかし、大師の修行時代をしのばせる迫力、風格をそなえた古刹である》(同)。

夜(徳島グランドホテル偕楽園泊)には、地鶏のすき焼きなどをいただいた。徳島県に入ると海の幸のウエイトが下がるが、その埋め合わせか、仲居さんが阿波踊りを披露してくれた。これは楽しい。
10/19(月)
16 観音寺(かんのんじ)高野山真言宗 千手観世音菩薩(徳島市)
15 国分寺(こくぶんじ)曹洞宗 薬師如来(徳島市)
14 常楽寺(じょうらくじ)高野山真言宗 弥勒菩薩(徳島市)
13 大日寺(だいにちじ)真言宗大覚寺派 十一面観世音菩薩(徳島市)
12 焼山寺(しょうさんじ)高野山真言宗 虚空蔵菩薩(徳島県名西郡神山町)
11 藤井寺(ふじいでら)臨済宗妙心寺派 薬師如来(徳島県吉野川市)
10 切幡寺(きりはたじ)高野山真言宗 千手観世音菩薩 (徳島県阿波市)
9 法輪寺(ほうりんじ)高野山真言宗 涅槃釈迦如来(徳島県阿波市)
8 熊谷寺(くまだにじ)高野山真言宗 千手観世音菩薩 (徳島県阿波市)
7 十楽寺(じゅうらくじ)高野山真言宗 阿弥陀如来(徳島県阿波市)
6 安楽寺(あんらくじ)高野山真言宗 薬師如来(徳島県板野郡板野町)
この日は11か寺にお参りした。徳島県はお寺が近接しているので、効率よく参拝できるのだ。ただし焼山寺への参道は狭いので、途中でバスを降り、マイクロバスに乗り換える。マイクロに乗り換えてしばらくすると、杖杉庵(じょうしんあん)が見えてくる。四国遍路の元祖といわれる衛門三郎(えもんさぶろう)終焉の地に建てられたお堂で、今も弘法大師と衛門三郎の銅像が建っている。

衛門三郎伝説は四国巡礼には必修知識なので、Wikipedia「衛門三郎」を引用しつつ紹介しておく。《伊予国を治めていた河野家の一族で、浮穴郡荏原郷(現在の愛媛県松山市恵原町・文殊院)の豪農で衛門三郎という者が居た。三郎は権勢をふるっていたが、欲深く、民の人望も薄かったといわれる。あるとき、三郎の門前にみすぼらしい身なりの僧が現れ、托鉢をしようとした。三郎は家人に命じて追い返した。翌日も、そしてその翌日と何度も僧は現れた。8日目、三郎は怒って僧が捧げていた鉢を竹のほうきでたたき落とし(つかんで地面にたたきつけたとするものもあり)、鉢は8つに割れてしまった。僧も姿を消した。実はこの僧は弘法大師であった》。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9B%E9%96%80%E4%B8%89%E9%83%8E
《三郎には8人の子がいたが、その時から毎年1人ずつ子が亡くなり、8年目には皆亡くなってしまった。悲しみに打ちひしがれていた三郎の枕元に大師が現れ、三郎はやっと僧が大師であったことに気がつき、何と恐ろしいことをしてしまったものだと後悔する。三郎は懺悔の気持ちから、田畑を売り払い、家人たちに分け与え、妻とも別れ、大師を追い求めて四国巡礼の旅に出る》。
《二十回巡礼を重ねたが出会えず、大師に何としても巡り合い気持ちから、今度は逆に回ることにして、巡礼の途中、阿波国の焼山寺の近くの杖杉庵で病に倒れてしまう。死期が迫りつつあった三郎の前に大師が現れたところ、三郎は今までの非を泣いて詫び、望みはあるかとの問いかけに来世には河野家に生まれ変わりたいと託して息を引き取った》。
《大師は路傍の石を取り「衛門三郎再来」と書いて、左の手に握らせた。天長8年10月のことという。翌年、伊予国の領主、河野息利(おきとし)に長男が生れるが、その子は左手を固く握って開こうとしない。息利は心配して安養寺の僧が祈願をしたところやっと手を開き、「衛門三郎」と書いた石が出てきた。その石は安養寺に納められ、後に「石手寺」と寺号を改めたという。石は玉の石と呼ばれ、寺宝となっている》。この石手寺(いしてじ)は第51番札所になっていて、私は昨年お参りした。

バスの乗り換え場の近くにある田中食堂で、昼食をとった。なんと、地粉で打ったうどんが食べ放題(お代わり自由)だという。3杯食べた人もいたが、私は2杯でグッとこらえた。野趣に富む、とても美味しいうどんであった。

夜は、御所温泉観光ホテルで、名物「焼石鍋」(味噌味)をいただいた。この鍋は琴参拝バスからのお接待(差し入れ)だそうで、たっぷり入った山海の珍味がまったりと煮え、有り難くいただいた。
10/20(火)
5 地蔵寺(じぞうじ)真言宗御室派 勝軍地蔵菩薩(徳島県板野郡板野町)
4 大日寺(だいにちじ)東寺真言宗 大日如来 (徳島県板野郡板野町)
3 金泉寺(こんせんじ)高野山真言宗 釈迦如来(徳島県板野郡板野町)
2 極楽寺(ごくらくじ)高野山真言宗 阿弥陀如来(徳島県鳴門市)
1 霊山寺(りょうぜんじ)高野山真言宗 ご本尊=釈迦如来(徳島県鳴門市)

第1番札所の霊山寺では、妖しい雰囲気のマネキンが迎えてくれる。ここは四国八十八ヶ所のスタート地点なので、巡礼グッズがすべて揃うのだ。昼食は鳴門・うづ乃家の弁当を車中でいただいたが、これがめっぽう旨い。泊まりは高野山の宿坊・蓮花院だった。こちらの精進料理(夕食)は、バラエティ豊かでとても美味しかった。ご住職の奥様が精進料理の大家だと、あとで知って納得した。
http://www.shukubo.jp/05_syukubo/a20.html
講のメンバーに、蓮花院住職で大僧正、伝燈大阿闍梨でもいらっしゃる東山泰清(ひがしやま・たいせい)師の知人がいたおかげで、師自らお経を上げて下さり、堂内もご案内いただいた。このお寺は徳川家総菩提所なので、徳川家の位牌など、ゆかりの品々がたくさん収められている。
師は、日本経済新聞の名物コラム「交遊抄」(10/9付)に、ユーモラスな文章を寄せられている。《ゴルフは「まる」づくしだ。世に球技は多いが、まるい球をまるい穴に入れるスポーツは意外に少ない。おまけにグリーンもまるい。だからというわけではないが、ゴルフは人間関係をまるく取り持つようだ。日本女子プロゴルフ協会会長の樋口久子さんも、そんなゴルフ観の持ち主》。
《あるとき、話題がパットの心構えに及んだ。カップにボールをどう沈めるか。コースの見極めに、グリップ、構え、力加減――。誰であれ神経を研ぎ澄ます瞬間だ。「東山さん、宗教家だったら、パットのときも平静でいられるんでしょうね」思わぬ質問に虚を突かれた。とっさに「チャコ、あんたこそプロなんだし、平静でおられるはずでしょう」とまぜ返してその場はおさめた》。
《10代で手を染め、半世紀余り、クラブを振ってきた。「まるいスポーツ」なのにパットの時ばかりは肩に力が入るあまり、四角くなっている。「まだまだ」、と内省する背中に樋口さんの笑顔が重なる》。大僧正でもパットの時は平静ではいられない、と知って安心した。況(いわ)んや凡人をや。
10/21(水)
金剛峯寺(こんごうぶじ)奥の院(和歌山県伊都郡高野町高野山)
http://www.koyasan.or.jp/

奥の院参道で
高野山は、私の出身地の隣町にあるので、子どもの頃から何度も訪れている。夏の涼しい時季も良いし、冬の雪景色も楽しめる。今回は紅葉の始まりを見ることができた。奥の院参道は何度も歩いているし、友人を案内したこともあるが、プロのガイドさんにご案内いただいたのは今回が初めてだった。ガイドさんの説明は簡潔明瞭で、歯切れがいい。予備知識がなくてもスッと分かる。これは、奈良のお寺をガイドする際の参考にさせていだこう。
M先生はじめ講の皆さま、貴重な機会を与えていただき、また温かく受け入れて下さり、有り難うございました。おかげさまで、たくさんの願をかけさせていただきました。添乗員の野田さんはじめ琴参バスの皆さま、大変お世話になりました。来年からは順打ち(1番から回る)に戻るそうですので、少なくとも、あと3年はお世話になることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
※トップ写真は、第23番薬王寺(10/18撮影)