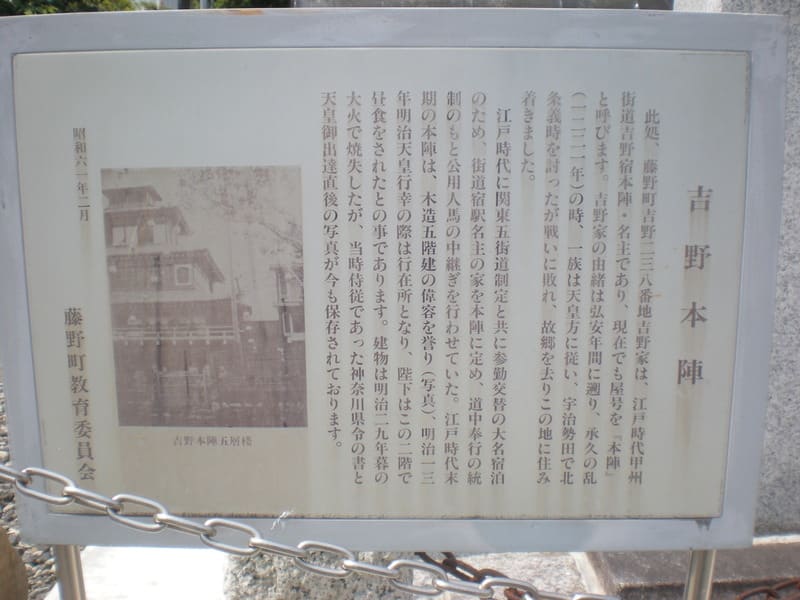甲州街道は徳川幕府が設置した街道の一つで江戸と甲州を結んでいる。関東地方の五街道は甲州街道、奥羽街道、日光街道、中仙道、東海道。全て重要な街道である。
江戸から大月までの甲州街道の宿場を順に記せば、新宿、高井戸、布田、府中、日野、八王子、駒木野、小仏、小原、与瀬、吉野、関野、上野原、鶴留川、野田尻、犬目、鳥沢、猿橋、大月となる。
6月10日は梅雨の一休みで晴天であったので車をゆっくり走らせて、旧甲州街道の小原宿、吉野宿、鶴留川宿の3宿を散策して来た。本陣を保存し、歴史展示館のあるのもあるが、何も無く、昔の通りが有るだけのところもある。





現在の甲州街道の大垂水峠を越し、相模湖町へ近づくと、右手に大きな「小原の郷」という歴史展示館がある。駐車場は無料で広い。そこから100m位歩いたところに小原宿本陣がある。よく手入れされ、公開している。展示館と本陣の2階部分もお見逃し無く。
最後から2枚目の写真は高島藩、高遠藩、飯田藩などの大名の泊まった部屋の写真で、「控えの間」の奥の8畳間が泊まった部屋。随分と狭い所に泊まったものと感心したので撮ってきた。入場料はいずれも不要。
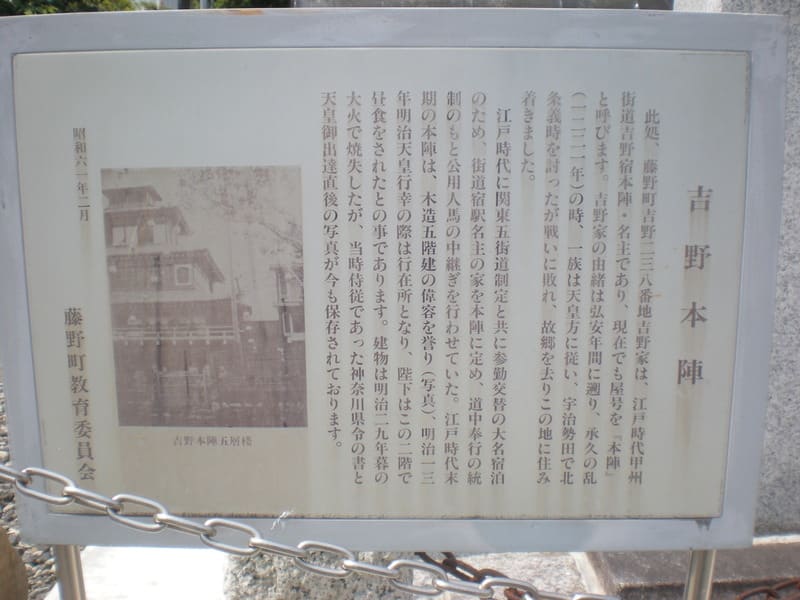




吉野宿は現在の藤野町にあり、JR藤野駅に近い。甲州街道を相模湖に沿って走って行くと本陣であった吉野浦(はじめ)氏の家が右にあり、その向かいに「吉野宿ふじや」 という看板の出ている歴史展示館がある。説明をしてくれた地方歴史家から聞いた話。承久の乱(1221年)で鎌倉側に負けた後鳥羽上皇側の主な貴族や武将がこの桂川流域に配流されたので大和、京都の地名が残ったという。JR中央線の高尾、大原(現在は小原)宿、吉野宿、付近の嵯峨野、奈良本、など現在の地名は承久の乱の後に配流された人々がつけたという。歴史的検証を一番深くされた方が、現在でも本陣に住んでいる吉野浦氏と聞き、後日、電話をした。いつでも詳しい話をして上げますから来て下さい、とのお言葉を頂く。天気の良い日に参上しようと思っている。





鶴留川宿は現在の甲州街道の上野原町を通り過ぎて上野原警察署の前の切通うしの坂を下り、左へ曲がるところで右折して鶴留川の川原の方角へ下る(交差点は信号が無く、右折可であるかは不明。要注意!)。その下る道が旧甲州街道である。鶴留川の橋を渡った処に写真に示したような「鶴留川宿」という石碑が立っている。そこを上ると宿場町のような、でも現代風の家並みが道の両側に続いている。
本陣の建物も、展示館も一切無い。昔の、街道であった道が一本あるだけである。静かな町なのでしばらく散策していると当時の様子が何となく想像できる。(終わり)
撮影日時:6月10日午後1時から3時。尚、展示館「吉野宿ふじや」の電話番号は、042-687-5022である。吉野浦(はじめ)氏へお会いしたい方は此処の取次があると良い。
 調
調 布飛行場と国土交通省の宇宙航空研究所の間には一般の都道があります。
布飛行場と国土交通省の宇宙航空研究所の間には一般の都道があります。