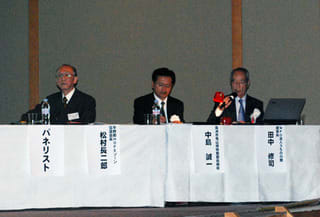近鉄奈良駅ビル4・5階にあるなら奈良館(奈良市東向中町28)が、この3月末で廃止されるそうだ。N先輩から情報をいただいた。この展示館は、同館のHPによると《2001年開設以来世界遺産「古都奈良の文化財」を美しい画像や実物大の精巧な模型で紹介する奈良市の展示施設として親しまれてきました。 奈良観光の前にお奨めしたい、奈良時代の文化・歴史の理解を深められるミュージアムです》。

写真はすべて07.8.15の撮影
館内では《「なら・観光ボランティアガイドの会」による無料ガイドをご利用いただけます。予約された団体の入館時には、天平風衣装を身に付けたガイドがご案内します。着用する衣装は、男性ガイドが上級役人風衣装、女性ガイドが女官風衣装です》。

王龍寺の十一面観音磨崖仏(レプリカ)
N先輩からのコメントによると《3月末までに一度じっくり見ておきたいと早速訪れました。元々同地で近鉄歴史教室としてあったものを10年ほど前ひき継いだのが現状とのこと。無料ガイドしてくださった方は、「長年親しんでいただき、子供たちの喜ぶ顔を思いだせば、残念でならない。既定方針らしいが何とかならないだろうか…」と顔を曇らしておられました》。

《ポスト1300年、これからも大効果が期待でき、抜群のロケーション、奈良の玄関にふさわしい施設をなぜ廃止するのでしょう? 新薬師寺十二神将レプリカ、ならまちの復元模型、子供たちが乗っかって写真を撮ったという大仏様の手のひらなど本当に展示も素晴らしいのです。入場料大人300円、奈良をよく知るガイドさんは楽しそうに1時間もご説明くださいます。読者の皆さん、何とかなりませんか?》。

新薬師寺十二神将レプリカの1体
うーん、これは残念だ。ここは新薬師寺の十二神将像や山田寺仏頭などの精巧なレプリカがあり、写真撮影も可だったので、とても重宝した。特に雨の日は、奈良に来た友人に「とりあえず止むまで、なら奈良館で待とう」といって、訪ねることも多かった。何しろ近鉄奈良駅ビル内なのである。

新薬師寺十二神将レプリカ(トップ写真はバサラ大将)
もとは「奈良歴史教室」として、近鉄が経営していたのだが、00年6月に一旦閉館し、奈良市に受け継がれたのである。過去の近鉄のHPによると《30年の歴史に幕を下ろすことになった「奈良歴史教室」 奈良市に貸し出され世界遺産の紹介施設に… 近畿日本鉄道が県内の沿線案内施設として昭和45年にオープンさせた「奈良歴史教室」が、今月30日で閉館、30年の歴史に幕を下ろすことになった。閉館後のスペースは奈良市が引き継いで改装し、世界遺産の紹介施設として再出発する。今月21日から閉館まで、入場無料で公開される》。

山田寺の仏頭(興福寺蔵)のレプリカ
《奈良歴史教室は近鉄奈良駅ビルの4、5階にあり、年間の入場者は約4万人。約1300平方メートルのフロアを仏像、古墳、古建築など4つのコーナーに分け、薬師寺西塔の模型(10分の1)や樹脂で造った新薬師寺十二神将像などを展示している。市は既存の展示物を生かしながら世界遺産に登録された市内の8資産群(東大寺、春日大社、唐招提寺など)を中心とする文化財の紹介施設に改装、今秋から公開したい考え》。
仕分けの際のやりとりが、奈良市行政経営課の“平成21年度「事業仕分け」議事録”に掲載されている(議論の実施日は、09.11.24)。《A:当施設は、駅の上に必要なのか。市:確かに目の前に本物があるという考え方はあるが、奈良市は日帰り旅行者が非常に多い(宿泊キャパが1万人程度に対し、年間約1,400万人の観光客)ことから、どうしても奈良地域を一日で観光できる範囲が限られてくる。市としての狙いは、当施設で解説を受けたということで、奈良の観光リピーターになってほしい、少しでも奈良のことを知ってほしいということがあり運営している訳である》。

《B:当施設だけをみて判断をするとあった方が良い施設かもしれないが、全体的にみると、近くに様々な市の箱もの施設があって、重複していたり、スペースが有効活用されていない現状があると思う。こういった問題に対する庁内での議論はないのか。市:確かに、今年の7月にJRの旧奈良駅舎を市の総合観光案内所として開設したが、JR奈良駅から春日大社まであがっていく三条通りには市の観光センターがあり、総合的な観光戦略の中でこれをどう位置づけていくのかという議論は行っている(例えば観光センターの廃止なども含めて)》。

《評価 不要3人・市実施(要改善)2人 班としての結論は、不要となった》《A:生活者である市民の立場からすると、駅ビルの一等地になければならない施設であるのか疑問に思った。但し、修学旅行生の獲得に役立っているといわれると判断に迷うところではある。B:この施設だけをみるとあった方が良いのかもしれないが、奈良市の観光全体を考えたときに、奈良市内にはいろいろな施設があって様々な取り組みをされていることを考えると、なぜこの施設がこの場所に必要なのか、ゼロベースで考えてみるべきである》。
《C:実績が上がっていること、NPOによる指定管理が効果をあげていることは評価するが、本物を見せる努力ではなく、バーチャルなものをダイジェストで駅前で見せてしまうことに対して理解に苦しむ。D:入場者を増やす努力をするべきである(市の持っている媒体でのPR活動や新しい展示物を入れるなど)。E:インターネットでバーチャルな体験ができる時代だからこそ本物にふれることが大事だと思われる。かえってこの施設を利用して満足して観光客が帰ってしまう恐れがあるので、この施設がないほうがよいと考える。コーディネーター:班としては不要となったが、指定管理期間が来年まであることから、市としての方針を市民の意見を聞きながら検討してほしい》。

ならまちの大模型
昨年、同館のHPへのアクセス状況は、4~10月のページビューで前年同月比134.9%、平均アクセス(滞留)時間は139.1%。同じく宮跡会場閉幕後の11~12月でも、それぞれ115.6%と203.3%と、極めて好調である。1年以上も前に《市としての方針を市民の意見を聞きながら検討してほしい》という結論となって以来、どのように「意見を聞きながら検討」したのかはよく知らないが、昨年の近鉄奈良駅周辺の賑わいを知る者としては、残念至極である。
テナント料とか、委託料(なら・観光ボランティアガイドの会に運営委託)が高額だったのだろうか。三条通の「奈良市観光センター」やJR旧奈良駅舎の「総合観光案内所」なんかより、よほどこちらの方が使い勝手の良い施設だと思うが…。

写真はすべて07.8.15の撮影
館内では《「なら・観光ボランティアガイドの会」による無料ガイドをご利用いただけます。予約された団体の入館時には、天平風衣装を身に付けたガイドがご案内します。着用する衣装は、男性ガイドが上級役人風衣装、女性ガイドが女官風衣装です》。

王龍寺の十一面観音磨崖仏(レプリカ)
N先輩からのコメントによると《3月末までに一度じっくり見ておきたいと早速訪れました。元々同地で近鉄歴史教室としてあったものを10年ほど前ひき継いだのが現状とのこと。無料ガイドしてくださった方は、「長年親しんでいただき、子供たちの喜ぶ顔を思いだせば、残念でならない。既定方針らしいが何とかならないだろうか…」と顔を曇らしておられました》。

《ポスト1300年、これからも大効果が期待でき、抜群のロケーション、奈良の玄関にふさわしい施設をなぜ廃止するのでしょう? 新薬師寺十二神将レプリカ、ならまちの復元模型、子供たちが乗っかって写真を撮ったという大仏様の手のひらなど本当に展示も素晴らしいのです。入場料大人300円、奈良をよく知るガイドさんは楽しそうに1時間もご説明くださいます。読者の皆さん、何とかなりませんか?》。

新薬師寺十二神将レプリカの1体
うーん、これは残念だ。ここは新薬師寺の十二神将像や山田寺仏頭などの精巧なレプリカがあり、写真撮影も可だったので、とても重宝した。特に雨の日は、奈良に来た友人に「とりあえず止むまで、なら奈良館で待とう」といって、訪ねることも多かった。何しろ近鉄奈良駅ビル内なのである。

新薬師寺十二神将レプリカ(トップ写真はバサラ大将)
もとは「奈良歴史教室」として、近鉄が経営していたのだが、00年6月に一旦閉館し、奈良市に受け継がれたのである。過去の近鉄のHPによると《30年の歴史に幕を下ろすことになった「奈良歴史教室」 奈良市に貸し出され世界遺産の紹介施設に… 近畿日本鉄道が県内の沿線案内施設として昭和45年にオープンさせた「奈良歴史教室」が、今月30日で閉館、30年の歴史に幕を下ろすことになった。閉館後のスペースは奈良市が引き継いで改装し、世界遺産の紹介施設として再出発する。今月21日から閉館まで、入場無料で公開される》。

山田寺の仏頭(興福寺蔵)のレプリカ
《奈良歴史教室は近鉄奈良駅ビルの4、5階にあり、年間の入場者は約4万人。約1300平方メートルのフロアを仏像、古墳、古建築など4つのコーナーに分け、薬師寺西塔の模型(10分の1)や樹脂で造った新薬師寺十二神将像などを展示している。市は既存の展示物を生かしながら世界遺産に登録された市内の8資産群(東大寺、春日大社、唐招提寺など)を中心とする文化財の紹介施設に改装、今秋から公開したい考え》。
仕分けの際のやりとりが、奈良市行政経営課の“平成21年度「事業仕分け」議事録”に掲載されている(議論の実施日は、09.11.24)。《A:当施設は、駅の上に必要なのか。市:確かに目の前に本物があるという考え方はあるが、奈良市は日帰り旅行者が非常に多い(宿泊キャパが1万人程度に対し、年間約1,400万人の観光客)ことから、どうしても奈良地域を一日で観光できる範囲が限られてくる。市としての狙いは、当施設で解説を受けたということで、奈良の観光リピーターになってほしい、少しでも奈良のことを知ってほしいということがあり運営している訳である》。

《B:当施設だけをみて判断をするとあった方が良い施設かもしれないが、全体的にみると、近くに様々な市の箱もの施設があって、重複していたり、スペースが有効活用されていない現状があると思う。こういった問題に対する庁内での議論はないのか。市:確かに、今年の7月にJRの旧奈良駅舎を市の総合観光案内所として開設したが、JR奈良駅から春日大社まであがっていく三条通りには市の観光センターがあり、総合的な観光戦略の中でこれをどう位置づけていくのかという議論は行っている(例えば観光センターの廃止なども含めて)》。

《評価 不要3人・市実施(要改善)2人 班としての結論は、不要となった》《A:生活者である市民の立場からすると、駅ビルの一等地になければならない施設であるのか疑問に思った。但し、修学旅行生の獲得に役立っているといわれると判断に迷うところではある。B:この施設だけをみるとあった方が良いのかもしれないが、奈良市の観光全体を考えたときに、奈良市内にはいろいろな施設があって様々な取り組みをされていることを考えると、なぜこの施設がこの場所に必要なのか、ゼロベースで考えてみるべきである》。
《C:実績が上がっていること、NPOによる指定管理が効果をあげていることは評価するが、本物を見せる努力ではなく、バーチャルなものをダイジェストで駅前で見せてしまうことに対して理解に苦しむ。D:入場者を増やす努力をするべきである(市の持っている媒体でのPR活動や新しい展示物を入れるなど)。E:インターネットでバーチャルな体験ができる時代だからこそ本物にふれることが大事だと思われる。かえってこの施設を利用して満足して観光客が帰ってしまう恐れがあるので、この施設がないほうがよいと考える。コーディネーター:班としては不要となったが、指定管理期間が来年まであることから、市としての方針を市民の意見を聞きながら検討してほしい》。

ならまちの大模型
昨年、同館のHPへのアクセス状況は、4~10月のページビューで前年同月比134.9%、平均アクセス(滞留)時間は139.1%。同じく宮跡会場閉幕後の11~12月でも、それぞれ115.6%と203.3%と、極めて好調である。1年以上も前に《市としての方針を市民の意見を聞きながら検討してほしい》という結論となって以来、どのように「意見を聞きながら検討」したのかはよく知らないが、昨年の近鉄奈良駅周辺の賑わいを知る者としては、残念至極である。
テナント料とか、委託料(なら・観光ボランティアガイドの会に運営委託)が高額だったのだろうか。三条通の「奈良市観光センター」やJR旧奈良駅舎の「総合観光案内所」なんかより、よほどこちらの方が使い勝手の良い施設だと思うが…。