 | ワインとミルクで地域おこし―岩手県葛巻町の挑戦 |
| 鈴木重男 | |
| 創森社 |
日本酒の味はそこそこ分かるが、ワインの味はあまりよく分からない。日本酒感覚で飲める辛口の白ワインをよく飲んでいた時期もあったが、赤ワインのアントシアニン(ポリフェノール類の一種)が体に良いといわれてから、白より赤を好むようになった。三輪のY社長のようなワイン通ならいざ知らず、私は産地もブドウの種類もヴィンテージ(当たり年)もよく知らないので、もっぱら国産のワインを飲んでいる。関西では、なんといってもカタシモワイナリー(大阪府柏原市)の「カタシモ河内ワイン」だが、東日本大震災以降は、東北のワインを取り寄せて飲んでいる。それが岩手県岩手郡葛巻町の「くずまきワイン」である。
葛巻町は、「ワインとミルクとクリーンエネルギーの町」である。仕掛け人は、町役場の職員出身で、現在、葛巻町長を務める鈴木重男氏である。くずまきワインとは、どんなワインか。「くずまきワイン楽天市場店」の説明書きによると《ミルクとワインとクリーンエネルギーの町“くずまき” 葛巻町は人口8,000人余りの小さな町ですが、飼育している牛の数は10,000頭を超える人より牛の多い町・・・・酪農が盛んな町です。豊かな自然を利用し東北一の酪農郷“くずまき高原牧場”では主に牛乳、ヨーグルト、チーズなどを造っています。また、風力発電やバイオガスなど環境問題にも積極的に取り組んでいる町でもあります》。
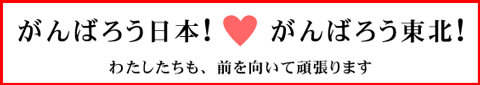
《山ぶどうから始まったくずまきワイン・・・ 昭和61年第3セクターとして当時の葛巻町長高橋吟太郎氏が葛巻高原食品加工株式会社を創立。ここ葛巻町は決してぶどう栽培に適した土地ではありません。その中で山ぶどうは比較的寒さにも強く当地方にも昔から自生していました。これをなんとか地域の活性化にできないかというのがきっかけです。昭和63年度果実酒製造免許を取得し山ぶどう100%の山ぶどうワインとフォーレ(赤)を発売したのを皮切りに山ぶどうにこだわった商品の他、白ワインも発売しており、現在では国産ワインコンクール銅賞などと表彰されるクオリティの高いワインを製造するに至っています》。

《山ぶどうは古来より滋養強壮や増血などに効果があるとされ、愛飲されてきたぶどうです。果実も小さく搾汁率も低いため希少な品種とされてきました。酸味が強いのが特徴ですが、通常のぶどうより鉄分、ポリフェノールが豊富に含まれています。現在では品種改良も進み、酸味も少なくワインに適した品種もあります。当ワイナリーでは自生の山ぶどうの他に町内にカ所の山ぶどう畑で山ぶどうを栽培しています。圃場を管理する従業員は計8人。雨の日も雪の日も葛巻の過酷な環境の中で作業をしています》。
《山ぶどうは体にもおいしい! ○山ぶどう原液にはポリフェノールがいっぱい含まれています。山ぶどうの濃い赤紫色は、抗酸化物質ポリフェノールのアントシアニジンによるものです。アントシアニジンは、活性酸素の生成を抑え血液をサラサラにし、また血圧をさげるとも言われています。○鉄分が豊富なので、貧血の方にも最適です。○リンゴ酸を豊富に含みます。リンゴ酸等の有機酸は、カラダの代謝を活発にし、疲労回復をたすけます》。

ナドーレ・赤(辛口・ライトボディ)
ワインの主力ブランドは「ナドーレ」1,000円と「フォーレ」1,500円。それぞれ赤・白・ロゼがあるが、私は「ナドーレの赤」(辛口・ライトボディ)が好みである。洗練されたフランスワインとは違って、山ぶどうと山ぶどう交配種をブレンドした野趣に富む「地ワイン」である。特大瓶(1,500ml)が1,890円と割安なのも魅力である。何しろ奈良までの送料が別途1,050円かかるので、安いのが有り難いのだ。なおフォーレとは「Foret」(フランス語で森)だが、ナドーレとは「Ngadoure」つまり「んが(あんた)ど(と)おれ(俺)」という意味だそうで、方言をブランド名にしたところがいい。
くずまきワインをここまで育てた鈴木重男氏の苦労話は、ご著書『ワインとミルクで地域おこし ~岩手県葛巻町の挑戦~』に詳しい。同書の「著者プロフィール」によると《昭和30年、岩手県葛巻町生まれ。岩手県立葛巻高等学校を卒業後、町役場に就職。町のワイン事業参画のため東京都国立市の農業科学化研究所に派遣され、ブドウの栽培、ワインの醸造技術等を学ぶ。57年、同研究所修了。葛巻町にてブドウ苗木の育成、圃場管理、ワイン工場の設立等に奔走する。特用林産課長、事業部長を経て、平成19年、葛巻町町長に就任》。版元のHPによると、
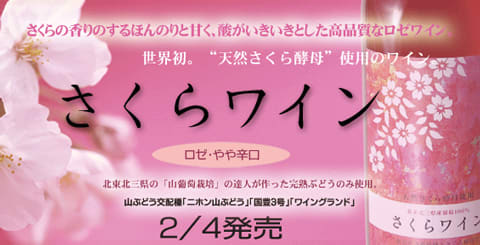
「ミルクとワインとクリーンエネルギーの町くずまき」は、北緯40度、岩手県の県北に位置する人口9300人あまりの山村の町。地域で丹精込めたブドウ100%で醸すワイン、高原での体験学習、草を存分に食んで育った牛たちのミルクやヨーグルトを求めて、全国から年間35万人もが葛巻町を訪れる。大手ディベロッパー主導の観光地化ではなく、地元の豊かな自然を何よりの恵みとし再生をはかった、小さな町の大きな挑戦の物語。
[主なもくじ]
第1章 高原のワイナリーから届くワイン
第2章 東京で鍬を握ってブドウ修業
第3章 ワインを飲まない町でワイン造り
第4章 くずまきワインの支持者を増やせ
第5章 待望の白ワイン完売作戦で波に乗る
第6章 慈しみ育てるブドウ畑の四季物語
第7章 ブドウがワインに生まれ変わる
第8章 人が集まる日本一元気な山村に

ワインを飲む町民が1人もいない町で、黒くて酸っぱい野生の山ぶどうを獲ってきて始めたワインづくり。数々の失敗をしでかしながら、ドブ板営業や囮(おとり)作戦で、くずまきワインを拡販していくさまは、圧巻である。同書から、エピソードを1つ拾ってみる。
最初の売り出し方は奮っていた。テレビコマーシャルを作り、美しいメロディーに乗せて、「くずまきワイン、新発売」と、岩手県全域に流した。そして、昭和63年12月9日、盛岡のホテルで各界で活躍の県内の名士をたくさん招待して、発表会を兼ねたパーティーを開いたのだ。ところが、1杯飲んでノーサンキューとなる。それは、ワインの味に慣れていないからということではない。むしろ彼らがワインのおいしさを知っているからこそ、それ以上は飲みたくないと言われたのだった。「いやー、葛巻のワインパーティに行ったら、ひどいワインが出てきて」「テレビでやっている葛巻のワイン、あれはおいしくないよ」せっかくのパーティーもテレビコマーシャルも、そんな話をあちらこちらで広めさせる結果となってしまったのだ。
これはほんの一例であるが、自慢話より失敗談の方が多く、つくづく「“地域おこし”って、生半可な覚悟ではできないな」と思ってしまう。そんな苦労話を頭に置きながら飲む山ぶどうのワインは、また格別の味わいである(味はコンテストで賞を取るほどに改善されている、念のため)。そんな岩手の地ワインを、1本いかが?
















