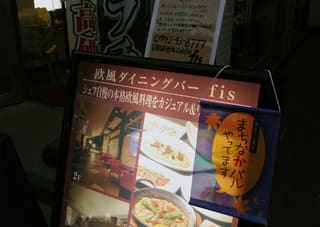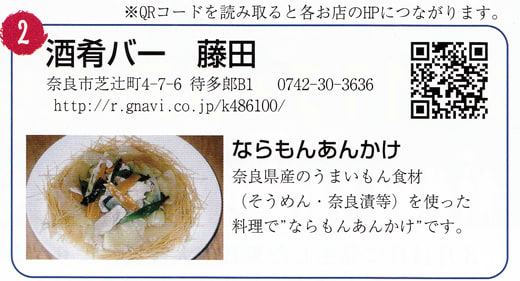以前(3/13)当ブログで、 B-1グランプリ(B級ご当地グルメの祭典)で全国にその名をとどろかせた
「富士宮やきそば」を紹介した。この焼きそばは、「食」による地域おこしの典型的な事例である。関満博・古川一郎編『「ご当地ラーメン」の地域ブランド戦略』(新評論刊)によると《近年、「B級グルメ」によるまちおこしが各地で取り組まれている。ラーメン、焼きそば、カレー、ハンバーガーなど、私たちの周りのごく普通の「食」に光が当てられ、人びとを楽しませてくれている》。

天ぷら飛鳥(ヤマトポークソースカツむすび)
《これまでのまちおこしと言えば、伝統的な地場産業の再生、企業誘致など、まなじりを決して取り組まれてきたものが多いが、「B級グルメ」によるまちおこし、地域産業振興は、そうしたものとはかなり様相が異なるように見える。多くの市民が参加できること、当事者は必死の面持ちであるにしても、どこかほのぼのとしたゆとりのある取り組みであることも興味深い。私たちの社会が、それだけ成熟してきたことの証(あかし)なのかもしれない》。

《大きな工場の誘致などによる雇用の創出などとは性格が異なるが、その人びとの輝きを見ていると、地域の活性化は雇用の増大、税収の増加ばかりでなく、人びとの「こころ」の問題でもあることを痛感させられる》。

かねてより、奈良で「食」による地域おこしができないかと考えあぐねていたところ、うまい具合に5/5(木・祝)、
「ならB級グルメ決定戦」(主催:奈良市飲食店組合など)が開催されることになった。平城宮跡で開かれた「平城京天平祭」のイベントの1つで、出場チームは同組合所属の10か店。会場には約1,200人が訪れた。
結果は以下の通りである。


1位「大和焼きそうめん」(目茶旨地鶏焼家ごちどり) 510票
2位「ヤマトポークの角煮 スティックフライ(揚げ春巻)」(Parum cafe) 258票
3位「ならもんあんかけ」(酒肴バー藤田) 255票

優勝した「大和焼きそうめん」(目茶旨地鶏焼家ごちどり)
ご覧のとおり、「大和焼きそうめん」は約半数の票を獲得し、文句なしの圧勝であった。生そうめんとたっぷりの野菜を特製の塩ダレで炒め、大和肉鶏のスライスをトッピングするというスグレモノで、これは確かに美味しかった。ちゃんと地元産品を使っているし、味付けも良い。
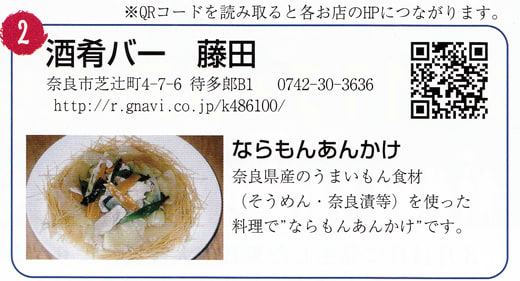

3位の「ならもんあんかけ」(酒肴バー藤田)
開始時刻の午前11時30分に会場に到着すると、すでにたくさんの人が割り箸(これで食べるだけでなく、投票にも使う)を求めて並んでいた。その後もどんどん人が増え、お店の前には長蛇の列ができた。12時半を過ぎる頃から売り切れ店が続出。1時半頃には、ほぼ全ての店が売り切れとなった。

イベントの運営には、問題がなかったわけではない。決定戦の公式ホームページが立ち上がったのは、天平祭の始まる4/29の直前になってから。HPに結果が載ったのも、イベントが開催された5/5の3日ほどあとになってからだった。

すぎ乃新大宮店の「大和やきそば」。トップ写真とも
「前売り券」がないと、当日の午前11時50分にならないと食べられなかったが、これは会場に到着して初めて分かった。あとで、アップされたばかりのHPを見ると、そのように書いてあったが、肝心の前売り券の「入手方法」すら出ていない。5/2に放送された奈良テレビの「ゆうドキッ!」では、このイベントのことが詳しく紹介されていたが、そこでも、前売り券の情報は出ていなかった。

女性が頬張っているのが2位の「ヤマトポークの角煮 スティックフライ」(揚げ春巻)
内輪のイベントではないのだから、このような情報発信はきちんとやっていただきたい。列の並ばせ方や、お店の対応(代金を受け取る人と、料理を出す人が一緒)、料理を出すまでのタイムラグなど、様々な問題があった。何より、来場者数に見合うだけの料理が用意されていなかったのは、とても残念だ。

しかし、このような多くの問題があったにせよ、とにかくイベントは成功した。来場者はいそいそと列に並び、美味しく料理をほおばっていた。割り箸の売上げに見合うだけの投票があったことを見ても、それは分かる(投票せずに帰った人は少なかった)。


優勝チームへの表彰式(ならB級グルメ決定戦のHPより拝借)
これまで私が「『食』の魅力で、もっと県下へ観光客を呼びこもう」と提案しても、「奈良県に『食』のイメージはない」「海のない奈良県で、グルメはムリだ」と、周囲は乗ってこない。 B-1グランプリにも奈良県代表チームを送り込みたいのだが、出場資格である「食のまちおこしについて、一定の活動実績のある団体」という条件に当てはまるところが見当たらない。「地元で広く販売され、食べられている料理」も、なかなか見つけることができない(特定の事業者・飲食店などが、営利を目的として出場することはできない)。
ないないづくしの奈良県だが、これまでに「食」イベントの成功例はあった。1つがA級グルメの祭典
「クーカル奈良」であり、1つが
「黒米(くろまい)カレー選手権」である。クーカルは行政主導だし、黒米カレーは、いかにも規模が小さいが、一定の支持は集めて来た。この秋には
ミシュランに奈良のお店が登場する。小さな波が集まって、ようやく少し大きな波になりそうな絶好のタイミングで、「ならB級グルメ決定戦」が登場したのである。

飛鳥の
あーすかふぇは、周辺でパフェを販売していた。トマトのパフェ500円が大人気だった
「B-1グランプリ」は、A級とかB級ということではなく、「ご当地グルメ」というところに力点がある。地域の美味しいものを食べることは、地域の食文化を味わうことである。地域の食文化は、地域文化そのものである。地域文化を廃れさせる訳にはいかないのだ。
奈良公園周辺で開かれた「クーカル奈良」には、多くの県民が足を運んだ。カウンターで隣り合った上品な老夫婦や、中年女性のグループとお話しする機会もあった。皆さん美味しいものが好きな人たちで、これまでは、大阪や京都のレストランに足を運んでいたのだそうだ。「ならB級グルメ決定戦」に来られていた人にも、地元民が多い。県民は、美味しい食べ物が大好きなのだ。県下で「食」による地域おこしができる素地は、十分に整っていると見た。

猪肉を使ったメンチカツ(奈良イベント事業協同組合)
『「ご当地ラーメン」の地域ブランド戦略』には、「食」を題材にして地域を活性化するためのロジックが紹介されている。要点を抜粋すると、
話題を作るということは、地域おこし、地域の活性化のきっかけ作りとして極めて重要な作業である。そこでまず、「話題になる」とはどういうことか
Ⅰ.人びとの間で関心が共有される必要がある。
Ⅱ.対話が成立するためには、会話の対象についての事前知識をある程度共有していることも必要である。
Ⅲ.何かを伝えるためには、その何かを伝えるための媒体、すなわちメディアが必要になる。
この点については少し補足が必要だろう。バレンタインデーのチョコレート、婚約指輪のダイヤモンド(しかも給料3カ月分の)、ボジョレーヌーボーといった事例を思い浮かべてもらえば、言わんとしていることがお分かりいただけるのではないか。

話題作りにより人びとを巻き込み、人びとの対話を活性化することを「コトづくり」と呼ぶことにしたい。
B級グルメを使ったコトづくりの典型的な成功例として、。富士宮やきそばの事例をあげることができる。富士宮市では、地元で長年食されていた無名の「やきそば」、つまりただのコモディティを「富士宮やきそば」として見事にブランド化することに成功し、地域の活性化に一役も二役も買わせている。「富士宮やきそば」をネタにして、様々な人びとを巻き込み、人びとに地域の活性化について対話するきっかけを作ったことは特筆に値しよう。

これまでの議論をまとめると、以下のようになる。
1.地域活性化のためには、「多様な人びと」が積極的に関わりを持たなくてはならない。
2.そのためには、「対話が行われる状況」を生み出さなくてはならない。すべての知識は対話から生まれるのである。
3.対話を始めるきっかけを作るには「話題作り」が重要である。
4.話題作りには、多くの人が感心を持っている「テーマ設定」が重要である。その際、地方の地域にとって「食」は常に有望な候補である。
5.メディアとなる素材は、「分かりやすく」、より多くの人が「体験」しているものが望ましい。
6.メディア素材には、「意外性」や「エンターテインメント性」が無くてはならない。イメージしたときにワクワクするようなものが望ましい。
7.メディア素材は「地域」と深くつながっており、さらには「物語」を持つものでなくてはならない。
8.そして「新しい物語」が作られ続けなくては、コトづくりは長続きしない。
9.対話の輪が広がっていくために、話題作りには常に「新規性」と「継続性」が必要である。
やや理屈っぽくなった。私はいつも「奈良は観光資源の『宝庫』なのに、『倉庫』になり下がっている」といっている。それは「食」という地域資源にも当てはまる。伝承料理研究家の奥村彪生氏は、常々「奈良は日本の食文化発祥の地」とおっしゃっているのである。
「ならB級グルメ決定戦」のおかげで、県下でご当地グルメが受け入れられることがよく分かった。これは大きな収穫だ。富士宮やきそばのようにブレイクするかどうかは別としても、、「意外性」「エンタメ性」のある奈良県の「食」(メディア素材)は、どこかにないものか。