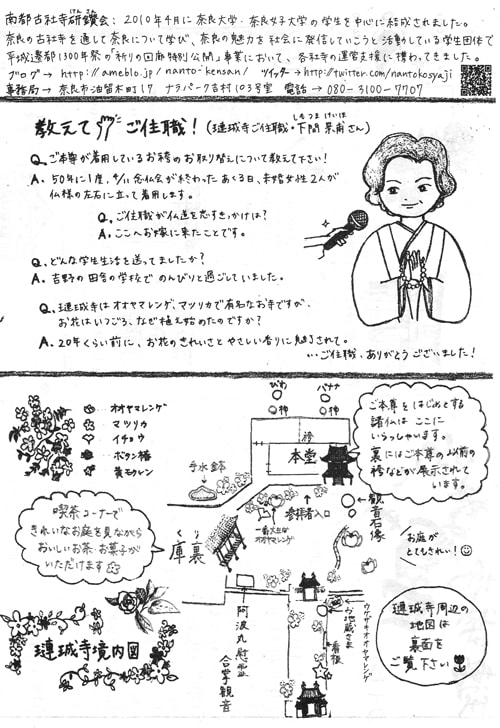さわやかな好天となった日曜日(5/15)、橿原市今井町の年に一度の大イベント「今井町並み散歩」を訪れた。これまで見たことのないほどの人出には、驚いた。期間中(5/7~15)の来訪者は、約5万人に上った!(5/7~13で計5千人、14日は1万5千人、15日は3万人)。今日の奈良新聞(5/16付)の1面に、このイベントがカラー写真入りで大きく紹介されている。見出しは「宗久や利休、練り歩き 茶行列や物販、重文公開」。



《江戸期の商家が残る国の重要伝統的建造物群保存地区、橿原市今井町の歴史・文化に親しむ催し「今井町並み散歩」が14、15日に現地で開かれた。同町ゆかりの商人で茶人の今井宗久らに扮(ふん)した茶行列や物産市、重文指定の建造物の公開などがあり、町中を散策する観光客らで賑わった》。


茶行列の前に記念撮影(町並み散歩開会セレモニーで)
《同町は浄土真宗本願寺派称念寺を中心に江戸期に商業都市として発展した寺内町。町の魅力を伝えようと、住民らでつくる今井町町並み保存会が町全域を会場に毎年実施。16回目の今年は、東日本大震災の被災地復興支援のため、催事を通じて義援金募集を行った》。



《15日の茶行列には約60人が参加し、今井宗久や千利休などの茶人に扮して町内を練り歩いた。中心通りでは江戸期に月6回あった市「六斎市」を模して食品や雑貨を扱う約200店が軒を連ねた。また、普段は非公開の商家や同寺の壁画などが公開されたほか、同町在住の木工芸師、川鳳嶽さんら茶道具師の作品展示もあった。橿原市上品町の竹村猶司(64)、信江さん(61)夫妻は「地元の文化的な魅力を再発見した」と話し、楽しんでいた》。


学研都市周辺住民で作る「地域SNSけいはんな」代表のFUTAN(ふーたん)さんが、昨夜SNSに書き込んでおられた。《第16回今井町並み散歩に行ってきました。直通の橿原神宮前行きの急行だと、正味35分で行ける。これまでに比べて、まちかどアートが新しく加わって、いっそう楽しくなっていた。また、スタッフの大和屋絣さんによれば、この10月の連休中に、全国の町家再生交流会が今井町を中心に奈良県であるそうです。行かなくては》《700戸のうち500戸が歴史的な建物。世界遺産級だと思います》。第4回全国町家再生交流会の情報は、こちら(PDF)に載っている。


今年は早くから、各メディアがこのイベントを競って紹介していた。とりわけ大きかったのは朝日新聞大阪本社版の「週刊まちぷら 関西ワイド」(5/10付)である。見出しは「橿原・今井町かいわい 濠と町家 自衛と繁栄」である。《「海の堺」に対し、「陸の今井」と呼ばれた奈良県橿原市の今井町。商人を中心に、最盛期には約4千人が暮らす商業都市として栄えた。東西約600メートル、南北約310メートルの町には、今でも500軒を超す町家が残り、町に入ると江戸時代へとタイムスリップしたかのような錯覚に陥る。14、15両日、着物を着た時代行列などが練り歩く「今井町並み散歩」が開かれ、町に往時のにぎわいが戻る》。

「さぁさ、皆さん。これから茶行列が通るよ!」と元気に呼び込み

《戦国時代、一向宗の門徒らが称念寺を造り、自衛のために濠(ほり)や土塁を巡らせたのが今井町の始まりとされる。織田信長とも戦ったが、1575年に降伏。その後自治権を認められ、商業都市として発展を遂げた。大和の金は今井に七分――。この言葉が繁栄を物語るように、町内には「八つ棟造り」と呼ばれる巨大な民家「今西家住宅」や、金物商だった「旧米谷家住宅」など、国の重要文化財の町家が8軒も残る》。


《1993年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。町家の数は全国の保存地区約90カ所の中でも日本一の規模を誇る。町家を研究する奈良女子大4年、山本梨花さん(22)は「最初は建物の重要性に興味を持ったが、実際に来てみると、生きた町をみることができるのが面白い」と魅力を語る。町を歩くと、子どもたちが町の中を走り回り、多くの家の軒先に花が飾られているのに気付く。長年観光地化されず、土産物屋や食事を取る場所は少ないが、07年にテレビ番組で「懐かしい風景が残る街」の全国1位になるなど、町の魅力に気付く人が増えている》。



《「町並み散歩」は、今年で16回目。町内にある重要文化財の内部が公開されるほか、実際にかまどに火を入れ、伝統食「茶がゆ」を作ったり、今井町ゆかりの商人、今井宗久や織田信長らの衣装を着た時代行列(15日のみ)が登場したりする。主催する今井町町並み保存会の若林稔会長(70)は「今井町は400年以上続く町。さらに400年先へと続いていける町になるよう、様々な試みをしていきたい」という。町並み散歩の問い合わせは同会(0744・22・1128)へ》。



若林稔さん(町並み散歩開会セレモニーで)
今井町町並み保存会会長の若林稔さんも、大きく紹介された。《1971年に住民らが発足させた「今井町町並み保存会」。イベントの開催以外にも、市が進める町並み整備のサポートや機関誌の発行など、活動は多岐にわたる。最近は、不要になった着物を集めて、素人でも着やすい着物に仕立て直し、着物姿でそぞろ歩く人を増やす取り組みも始めた。若林稔会長は「今井の価値は、古い町並みだけじゃない。この町をつくり上げた先人のエネルギーこそ、我々はまねをしなければいけない」と話す》。

今年も手打ちそばが大人気(提供:NPO法人泉州そば打ち普及の会)

みやざき地頭鶏(じとっこ)専門店・門出さん

友人、知人にもたくさん出会った。今年も堺魚市場の「門出(かどで)」さんが屋台を出されていた。ここは「みやざき地頭鶏(じとっこ)」の専門店で、炭火で炙(あぶ)った美味しい焼鳥を提供されていた。黒板には《橿原市と宮崎市は、姉妹都市と言う事で!!本物の宮崎の地鶏をご賞味下さい。イベント価格1パック500円 年に数回、宮崎に足を運び、鶏処理場を視察し、安全な鶏をみなさまに提供できるよう、スタッフ一同心がけています。本物の味をご賞味下さいませ さめてもやわらか・ジューシー 堺にお越しの際は、堺魚市場内当店「門出」へ》。


今井景観支援センターの「呈茶席」では、美味しい抹茶と「塩屋の宗久饅頭」(山本鈴音堂)をいただいた。高木家住宅では、「箏・尺八の演奏」を聞かせていただいた。

町角のお地蔵さんの前で、何人かが集まっていたので耳を澄ましてみると「これはすごいで。桟(さん)がすり減っとる。よほど毎日丁寧に葺いてるんやな」。なるほど。格子がすり減るほど、きちんと拭き掃除をされているのだ。これが今井のすごさである。

吉田遊福さんは公式カメラマンとして飛び回っておられたし、Yさんもカメラを手に、ご夫婦で来られていた。銀とき子さんは土・日の2日間、着物姿で来られ、ムードを盛り上げておられた(残念ながら、すれ違いだった)。
回を重ねるたびに参加者が増える「今井町並み散歩」。関係者のご苦労は並大抵ではないと思うが、今に伝わる今井のエネルギーを感じる絶好の機会である。若林さんはじめ、関係者の皆さん、有難うございました。また来年を楽しみにしています!



《江戸期の商家が残る国の重要伝統的建造物群保存地区、橿原市今井町の歴史・文化に親しむ催し「今井町並み散歩」が14、15日に現地で開かれた。同町ゆかりの商人で茶人の今井宗久らに扮(ふん)した茶行列や物産市、重文指定の建造物の公開などがあり、町中を散策する観光客らで賑わった》。


茶行列の前に記念撮影(町並み散歩開会セレモニーで)
《同町は浄土真宗本願寺派称念寺を中心に江戸期に商業都市として発展した寺内町。町の魅力を伝えようと、住民らでつくる今井町町並み保存会が町全域を会場に毎年実施。16回目の今年は、東日本大震災の被災地復興支援のため、催事を通じて義援金募集を行った》。



《15日の茶行列には約60人が参加し、今井宗久や千利休などの茶人に扮して町内を練り歩いた。中心通りでは江戸期に月6回あった市「六斎市」を模して食品や雑貨を扱う約200店が軒を連ねた。また、普段は非公開の商家や同寺の壁画などが公開されたほか、同町在住の木工芸師、川鳳嶽さんら茶道具師の作品展示もあった。橿原市上品町の竹村猶司(64)、信江さん(61)夫妻は「地元の文化的な魅力を再発見した」と話し、楽しんでいた》。


学研都市周辺住民で作る「地域SNSけいはんな」代表のFUTAN(ふーたん)さんが、昨夜SNSに書き込んでおられた。《第16回今井町並み散歩に行ってきました。直通の橿原神宮前行きの急行だと、正味35分で行ける。これまでに比べて、まちかどアートが新しく加わって、いっそう楽しくなっていた。また、スタッフの大和屋絣さんによれば、この10月の連休中に、全国の町家再生交流会が今井町を中心に奈良県であるそうです。行かなくては》《700戸のうち500戸が歴史的な建物。世界遺産級だと思います》。第4回全国町家再生交流会の情報は、こちら(PDF)に載っている。


今年は早くから、各メディアがこのイベントを競って紹介していた。とりわけ大きかったのは朝日新聞大阪本社版の「週刊まちぷら 関西ワイド」(5/10付)である。見出しは「橿原・今井町かいわい 濠と町家 自衛と繁栄」である。《「海の堺」に対し、「陸の今井」と呼ばれた奈良県橿原市の今井町。商人を中心に、最盛期には約4千人が暮らす商業都市として栄えた。東西約600メートル、南北約310メートルの町には、今でも500軒を超す町家が残り、町に入ると江戸時代へとタイムスリップしたかのような錯覚に陥る。14、15両日、着物を着た時代行列などが練り歩く「今井町並み散歩」が開かれ、町に往時のにぎわいが戻る》。

「さぁさ、皆さん。これから茶行列が通るよ!」と元気に呼び込み

《戦国時代、一向宗の門徒らが称念寺を造り、自衛のために濠(ほり)や土塁を巡らせたのが今井町の始まりとされる。織田信長とも戦ったが、1575年に降伏。その後自治権を認められ、商業都市として発展を遂げた。大和の金は今井に七分――。この言葉が繁栄を物語るように、町内には「八つ棟造り」と呼ばれる巨大な民家「今西家住宅」や、金物商だった「旧米谷家住宅」など、国の重要文化財の町家が8軒も残る》。


《1993年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。町家の数は全国の保存地区約90カ所の中でも日本一の規模を誇る。町家を研究する奈良女子大4年、山本梨花さん(22)は「最初は建物の重要性に興味を持ったが、実際に来てみると、生きた町をみることができるのが面白い」と魅力を語る。町を歩くと、子どもたちが町の中を走り回り、多くの家の軒先に花が飾られているのに気付く。長年観光地化されず、土産物屋や食事を取る場所は少ないが、07年にテレビ番組で「懐かしい風景が残る街」の全国1位になるなど、町の魅力に気付く人が増えている》。



《「町並み散歩」は、今年で16回目。町内にある重要文化財の内部が公開されるほか、実際にかまどに火を入れ、伝統食「茶がゆ」を作ったり、今井町ゆかりの商人、今井宗久や織田信長らの衣装を着た時代行列(15日のみ)が登場したりする。主催する今井町町並み保存会の若林稔会長(70)は「今井町は400年以上続く町。さらに400年先へと続いていける町になるよう、様々な試みをしていきたい」という。町並み散歩の問い合わせは同会(0744・22・1128)へ》。



若林稔さん(町並み散歩開会セレモニーで)
今井町町並み保存会会長の若林稔さんも、大きく紹介された。《1971年に住民らが発足させた「今井町町並み保存会」。イベントの開催以外にも、市が進める町並み整備のサポートや機関誌の発行など、活動は多岐にわたる。最近は、不要になった着物を集めて、素人でも着やすい着物に仕立て直し、着物姿でそぞろ歩く人を増やす取り組みも始めた。若林稔会長は「今井の価値は、古い町並みだけじゃない。この町をつくり上げた先人のエネルギーこそ、我々はまねをしなければいけない」と話す》。

今年も手打ちそばが大人気(提供:NPO法人泉州そば打ち普及の会)

みやざき地頭鶏(じとっこ)専門店・門出さん

友人、知人にもたくさん出会った。今年も堺魚市場の「門出(かどで)」さんが屋台を出されていた。ここは「みやざき地頭鶏(じとっこ)」の専門店で、炭火で炙(あぶ)った美味しい焼鳥を提供されていた。黒板には《橿原市と宮崎市は、姉妹都市と言う事で!!本物の宮崎の地鶏をご賞味下さい。イベント価格1パック500円 年に数回、宮崎に足を運び、鶏処理場を視察し、安全な鶏をみなさまに提供できるよう、スタッフ一同心がけています。本物の味をご賞味下さいませ さめてもやわらか・ジューシー 堺にお越しの際は、堺魚市場内当店「門出」へ》。


今井景観支援センターの「呈茶席」では、美味しい抹茶と「塩屋の宗久饅頭」(山本鈴音堂)をいただいた。高木家住宅では、「箏・尺八の演奏」を聞かせていただいた。

町角のお地蔵さんの前で、何人かが集まっていたので耳を澄ましてみると「これはすごいで。桟(さん)がすり減っとる。よほど毎日丁寧に葺いてるんやな」。なるほど。格子がすり減るほど、きちんと拭き掃除をされているのだ。これが今井のすごさである。

吉田遊福さんは公式カメラマンとして飛び回っておられたし、Yさんもカメラを手に、ご夫婦で来られていた。銀とき子さんは土・日の2日間、着物姿で来られ、ムードを盛り上げておられた(残念ながら、すれ違いだった)。
回を重ねるたびに参加者が増える「今井町並み散歩」。関係者のご苦労は並大抵ではないと思うが、今に伝わる今井のエネルギーを感じる絶好の機会である。若林さんはじめ、関係者の皆さん、有難うございました。また来年を楽しみにしています!