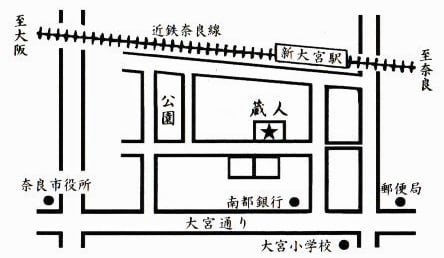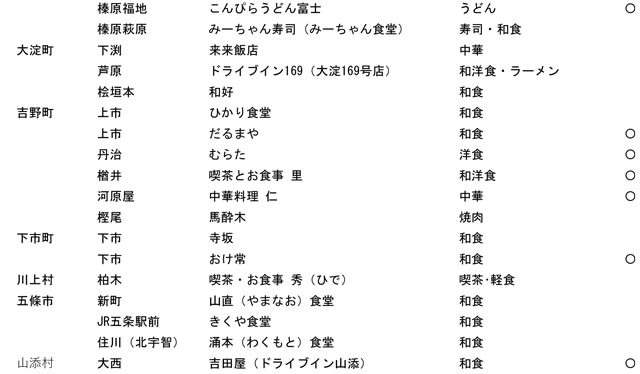昨日(2023.12.10)、NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、「師走の文化イベント」として、奈良ロイヤルホテルで「雅楽・舞楽公演」と「懇親会」を開催した。公演には50人(ゲスト2名様を含む)、懇親会には40人(ゲスト11名様を含む)が出席した。
※トップ写真は、この日の舞楽 『陪臚(ばいろ)』。両手の指2本を揃える独特の仕草に注目!

中央は当会の豊田理事長、左端はゲストの難波利光さん(周南公立大学教授)
コロナ禍でイベントの中止・延期が相次いでいたが、今回は久々の大イベントとなった。雅楽公演は、実に10年ぶりの開催だ(10年前のイベントは、こちら)。

豊田理事長の開会挨拶

山口創一郎さんのレクチャーが始まった
雅楽公演は、雅楽演奏家の山口創一郎さんが主宰する「陽雅会」(陽気に雅楽をやろうという団体)にお願いした。演目は、管絃 平調(ひょうじょう)『五常楽 急』、管絃 平調『鶏徳』、神楽歌『其駒(そのこま)』、舞楽 『陪臚(ばいろ)』(毘盧遮那仏にまつわる曲)、太食調(たいしきちょう)『長慶子(ちょうけいし)』(三度拍子=舞立のテンポ)。その合間に、山口さんのレクチャーが入る。「雅楽とは何か」「雅楽の楽器紹介」「雅楽の練習方法について」。

深い意味は分からなくても、雅楽の管絃の調べは、心に響くものがある

楽器の紹介。女性が手にするのは龍笛。天と地の間、空を翔ける龍の鳴き声を表しているという


笙(しょう)の奏者がお2人いたが、しょっちゅう電気火鉢(電熱器)で温めている。笙は湿気に弱いので、呼気による水蒸気が楽器のなかに溜まらないよう、温めるのだそうだ。 電熱器の上で手の中でくるくる回し、全体が均一に温まるようにするのだという。なお音色は、天から差し込む光を表すとされる。

舞楽には「左方」と「右方」があるという。もっとも根本的な基準は、もととなる舞や器楽の由来による違いで、中国系の楽舞を源流とするものを左方の舞として「左舞(さまい)」、朝鮮半島系の楽舞を源流とするものを右方の舞として「右舞(うまい)」と呼ぶ。舞に伴って奏される音楽は、それぞれ「唐楽(とうがく)」と「高麗楽(こまがく)」を用いることが基本だそうだ。

この舞楽『陪臚』(林邑八楽の1つ)は、東大寺の大仏(毘盧遮那仏)開眼供養(752年)のときに演奏されたとも言われる。槍や刀を持ち、力強い舞だった。なんと、舞うのは中学2年生だった!もっとも、2歳の頃から舞楽を学んでいたそうだから、堂に入ったものである。

部屋を変えて懇親会が始まった。司会は副理事長の松浦文子さん。

開宴の挨拶は副理事長の小野哲朗さん。ずいぶんテンションが高い!


陽雅会の皆さんにもステージに上がっていただき、お話をしていただいた。「ピアノやバイオリンではなく、なぜ雅楽なのですか?」との質問があった。ほとんどの人は親御さんが雅楽をされていたので、それを受け継がれたようだ。しかし「雅楽が大好きです」と、頼もしい答えが返ってきた。

依然としてコロナやインフルエンザを心配する人が多いので、参加者数こそ伸び悩んだが、とても充実したイベントだった。次のイベントは、「研究発表会」。どんな話が聞けるのか、今から楽しみだ。
※トップ写真は、この日の舞楽 『陪臚(ばいろ)』。両手の指2本を揃える独特の仕草に注目!

中央は当会の豊田理事長、左端はゲストの難波利光さん(周南公立大学教授)
コロナ禍でイベントの中止・延期が相次いでいたが、今回は久々の大イベントとなった。雅楽公演は、実に10年ぶりの開催だ(10年前のイベントは、こちら)。

豊田理事長の開会挨拶

山口創一郎さんのレクチャーが始まった
雅楽公演は、雅楽演奏家の山口創一郎さんが主宰する「陽雅会」(陽気に雅楽をやろうという団体)にお願いした。演目は、管絃 平調(ひょうじょう)『五常楽 急』、管絃 平調『鶏徳』、神楽歌『其駒(そのこま)』、舞楽 『陪臚(ばいろ)』(毘盧遮那仏にまつわる曲)、太食調(たいしきちょう)『長慶子(ちょうけいし)』(三度拍子=舞立のテンポ)。その合間に、山口さんのレクチャーが入る。「雅楽とは何か」「雅楽の楽器紹介」「雅楽の練習方法について」。

深い意味は分からなくても、雅楽の管絃の調べは、心に響くものがある

楽器の紹介。女性が手にするのは龍笛。天と地の間、空を翔ける龍の鳴き声を表しているという


笙(しょう)の奏者がお2人いたが、しょっちゅう電気火鉢(電熱器)で温めている。笙は湿気に弱いので、呼気による水蒸気が楽器のなかに溜まらないよう、温めるのだそうだ。 電熱器の上で手の中でくるくる回し、全体が均一に温まるようにするのだという。なお音色は、天から差し込む光を表すとされる。

舞楽には「左方」と「右方」があるという。もっとも根本的な基準は、もととなる舞や器楽の由来による違いで、中国系の楽舞を源流とするものを左方の舞として「左舞(さまい)」、朝鮮半島系の楽舞を源流とするものを右方の舞として「右舞(うまい)」と呼ぶ。舞に伴って奏される音楽は、それぞれ「唐楽(とうがく)」と「高麗楽(こまがく)」を用いることが基本だそうだ。

この舞楽『陪臚』(林邑八楽の1つ)は、東大寺の大仏(毘盧遮那仏)開眼供養(752年)のときに演奏されたとも言われる。槍や刀を持ち、力強い舞だった。なんと、舞うのは中学2年生だった!もっとも、2歳の頃から舞楽を学んでいたそうだから、堂に入ったものである。

部屋を変えて懇親会が始まった。司会は副理事長の松浦文子さん。

開宴の挨拶は副理事長の小野哲朗さん。ずいぶんテンションが高い!


陽雅会の皆さんにもステージに上がっていただき、お話をしていただいた。「ピアノやバイオリンではなく、なぜ雅楽なのですか?」との質問があった。ほとんどの人は親御さんが雅楽をされていたので、それを受け継がれたようだ。しかし「雅楽が大好きです」と、頼もしい答えが返ってきた。

依然としてコロナやインフルエンザを心配する人が多いので、参加者数こそ伸び悩んだが、とても充実したイベントだった。次のイベントは、「研究発表会」。どんな話が聞けるのか、今から楽しみだ。