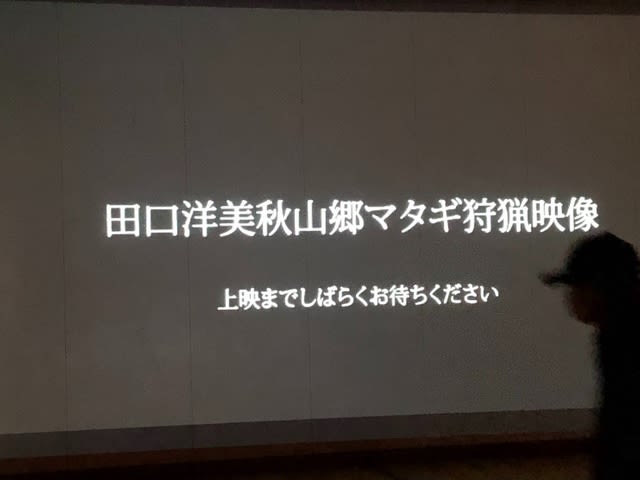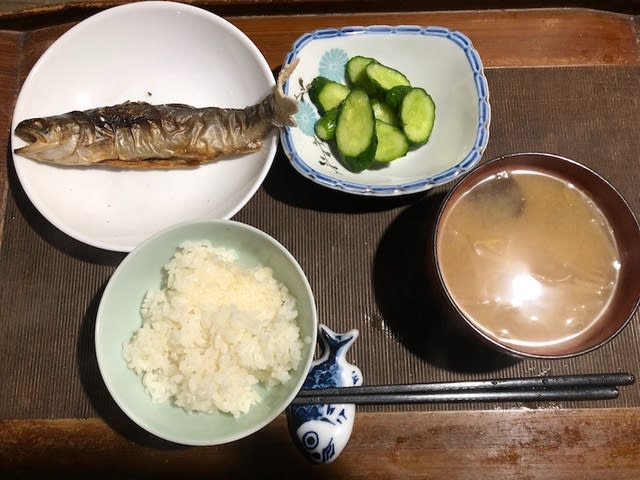今まで見たことのない、花蜂か花虻のどちらか判断しかねるヤツが菊にやってきていた。
腰に目立つ太い帯があるので、見たことのないのが不思議なくらいだ。
10kmほど離れた知人の玄関先に飾ってある菊にも同じヤツがいた。
両方の菊は、共通の友人の夫君が育てたのをプレゼントされた同じもの。
ということは、この時季のこの菊だけを頼りに生きる種類なのかも知れない、などと早とちりしそうだ。
検索してみると、オオハナアブという普通の名前で、日本全国どこにでもいるらしいし、出現期は4月~12月とある。
虫好きのような振りをしてきたけれど、自然に目を向けるようになったのは、ここ数年でしかなかったのかと思い知らされた気分だ。
白いカントウヨメナ(関東嫁菜)の花に芋虫が丸くなっていたので、目にしたと同時に指でつまもうとした。
そうしたら、触れると同時にすっくと立ち上がったので、思わず手を引っ込めた。
擬態の術と思われるので、シャクガ(尺蛾)の仲間かも知れない。
調べても、たどりつけない気がして、まだ検索をしていない。
何枚も撮っておけば良かったのに、目的のある通りすがりだったので、この1枚しか撮らないでしまった。
竹でできた蛇のおもちゃのようにも見える、この芋虫には、また是非とも会ってみたい。
これら二つはブログにあげる機会がこの先見つけられないかも知れないので、田舎を離れたのにあえて取り上げた。