
708 御代田町塩野
■ 火の見櫓と防災行政無線柱のツーショット、よく目にするようになった光景。ちょっと複雑な心境。
避雷針の風向計は実際に動くものも見たことがある。この羽根はどうだろう、確認しなかった。しもぶくれした見張り台の手すり。

708 御代田町塩野
■ 火の見櫓と防災行政無線柱のツーショット、よく目にするようになった光景。ちょっと複雑な心境。
避雷針の風向計は実際に動くものも見たことがある。この羽根はどうだろう、確認しなかった。しもぶくれした見張り台の手すり。

◎ 前稿の火の見櫓(739)を背景に小諸市のマンホール蓋を撮った。


市章 小諸市のHPより
小諸市のマンホール蓋をネットで調べると浅間山と懐古園をデザインしたものが見つかった。私が見た蓋は地味な模様のデザインで中央に小さく小諸市の市章を入れている。
小諸市の木・ウメの花、その中に野球のボールのようにも見える「小」をデザインした文字を配している。

707 火の見櫓のある風景 撮影日161103
屋根の下にどっしりと存在感のある半鐘を吊り下げてある。半鐘を叩く木槌も2本下げてある。
屋根頂部の避雷針の飾りに注目。鎌の形をしたもの(名前を知らない)を2本(?)交差させて取り付けてある。更に七夕で飾るようなもの(これも名前を知らない、分からない)も付けている。火伏の飾りではないかと思うがどうだろう・・・。たかが火の見櫓の飾りなどと思うことなかれ、と自戒。飾りにも意味があるはずだ。
避雷針から接地線を伸ばしているが、このようにしている事例をいままで見たことがあったかどうか。
4角形の櫓の2面に踊り場を張り出している。これをカンガルーポケットと呼んだものかどうか・・・。この踊り場の平面形、なかなか好い。

◎ 東御市(旧東部町)のマンホール蓋 亀甲模様、蓋の中心の円の中に東部町の町章を配し、「下水道」と表記している。
合併前の市町村のマンホール蓋を網羅的に集めることは端から目指していない。長野県に現在ある77市町村で火の見櫓を背景に写真を撮れれば良しとする。

706 火の見櫓のある風景 東御市(とうみし)県
■ 予定通り東信方面へ出かけた。先ずは東御市。東御市は2004年(平成16年)に小県郡東部町と北佐久郡北御牧村が合併して誕生した。市の名前は旧町村から一文字ずつ取って付けられた。東御市役所の近くに立っている火の見櫓。



■ この錦絵に描かれているお城は松本城です。濠に橋が架けられています。橋の先の建物は1885年(明治18年)に竣工した長野県中学校松本支校(松本深志高校の前身)の校舎。現在の松本市立博物館の場所です。大通りの向かいの建物(現在の日本銀行松本支店の位置)は師範松本支校の校舎。
先日松本市内の古書店の店先で見つけた絵はがきです。


松本深志高校創立140周年 企画展会場にて
松本城の南側はこんな様子だったんですね。左端に写っているのは上の錦絵に描かれている松本城の遺構、南櫓。

■ 月末の新聞に岩波書店の広告が載る。昨日(10月31日)の広告に『弘法大師空海と出会う』川崎一洋/岩波新書が他の新刊書と共に載っていた。早速買い求めてスタバで少し読んだ。
『日本の景観』樋口忠彦/春秋社を読み終えたら、読もうと思う。他にも読みたい本(高田郁の「みをつくし料理帖」シリーズなど)があるが、この本を優先する。
菩提寺が真言宗の寺ということが直接のきっかけでここ数年、空海の関連本を読んでいる。このブログの過去ログを検索してみたところ、次のような本が見つかった。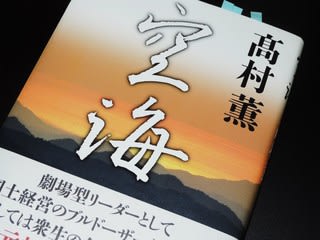



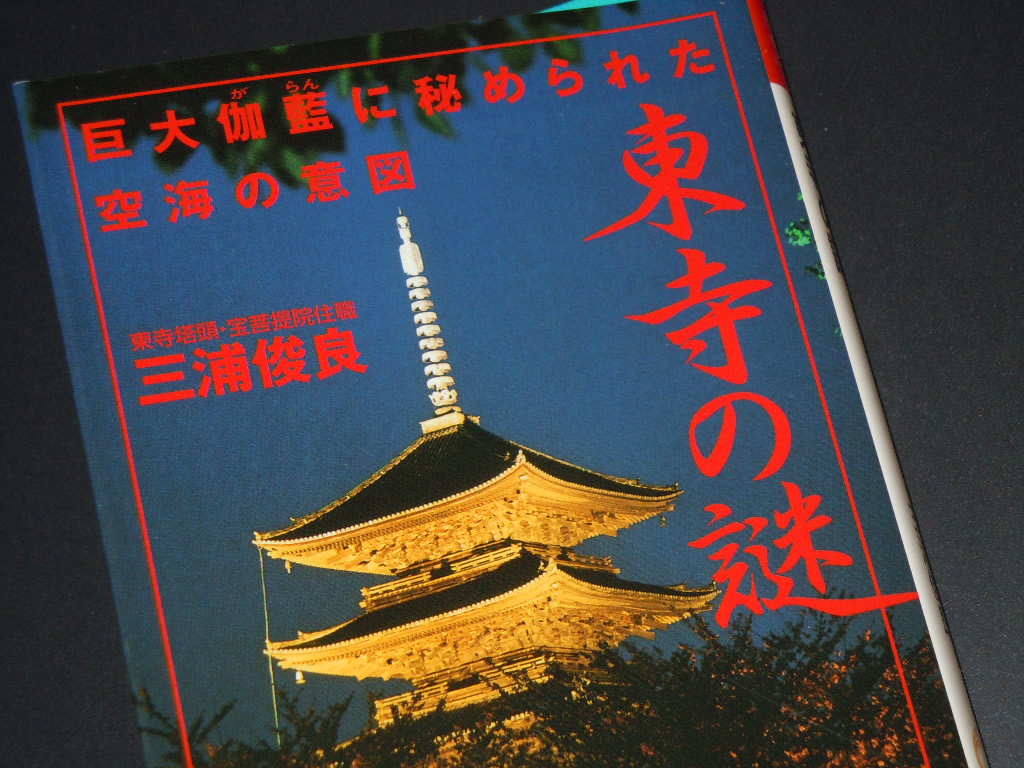
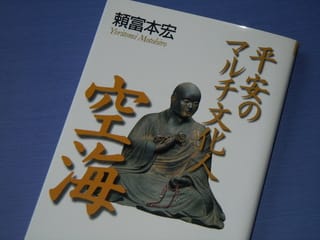
4艘の船で構成された遣唐使の船団のうち2艘が悪天候で消息を絶ってしまう。最澄と空海が乗った2艘は唐に流れ着く。恵果和尚は空海に密教を余すことなく伝授して間もなくこの世を去る。少しタイミングがずれていたら、空海は恵果に会うことができなかった。
そう、空海は天才だが、強運の人でもあった。空海の帰国後、数年(3年だったかな)して嵯峨天皇が即位する。もし嵯峨天皇という空海のよき理解者がいなかったら、空海にあれ程の活躍の場があったかどうか・・・。

撮影日161101
▲ 正面のアイストップとなっている山は常念岳、そしてこの通りは「常念通り」。この通りが常念岳をいわゆる「山あて」にして計画されたものなのか、偶然なのかは知らない。
常念通りという名称がついたのはそれ程昔のことでもないようだ。このことに関する新聞記事を以前読んだが、確かこの地域の役員の方が名付けたということだった。
今日の松本市の最低気温は8℃くらいでそれ程寒くはなかったが、標高2857メートルの常念岳では松本より12℃くらい低いから(*1)、気温は氷点下。朝、平地では雨だったが常念岳では雪が降り、山肌が白くなっていた。
もう冬がそこまで来ている・・・。
*1 松本市の標高はおよそ600m、標高が100m上がると気温は0.6℃下がるから常念岳のてっぺんは-5、6℃。