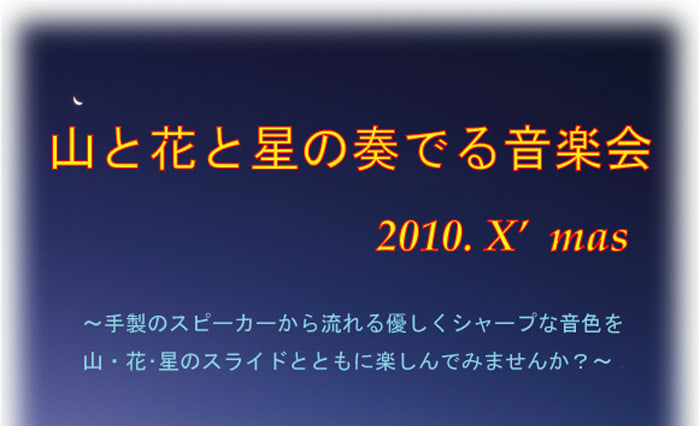平成22年12月14日
週間予報では曇りだった天気予報が変わり、午後から青空となった甲府盆地。この夜は双子座流星群極大となる日だった。しかし生憎の平日、翌日は仕事もあるし、天気は回復したが撮影は半分あきらめていた。ところが・・・翌日予定していた業務が一つ中止となり、午前中で終わってしまうような仕事内容となる。これは・・・山の神様が私を呼んでいるのか?そんな気さえして、夜9時に甲府を出発して、かねてから夜の撮影を狙っていた御坂山塊釈迦ヶ岳に向かう。この山は黒岳から節刀ヶ岳に延びる尾根が河口湖の町灯りをカットしてくれるため、富士山側の星空を撮影するには絶好の場所だ。夜間登山だが、何度も登っているこの山、道を間違えることはまずあり得ない。

甲府盆地の灯りと南アルプスに沈む月 甲府盆地は南側だけ、アルプスは雲がかかる。

富士に南中するオリオン座と冬の大三角形 富士の上に流星が流れる。

構図の解説

拡大図。この山を選んだもうひとつの理由はこの低空に輝くカノープス。パソコン上の計算では見えるか見えないかぎりぎりの位置だが、見えることが確認された。

流星流れる富士の空
すずらん峠の駐車場に10時過ぎ到着、2台ほど駐車場から星空を観察している先客がいた。新道峠はゲートが閉じているのか、林道を歩いている人のヘッドライトも見える。10時半、出発。ほとんど休憩せずに黙々と歩き、11時40分、釈迦ヶ岳山頂に到着した。ちょうど南アルプスに月が沈んで行くところだった。見上げる空は澄み、流星が一つ二つと流れて行くのが見える。さっそく三脚とカメラをセットして撮影に取りかかる。富士山の上にオリオン座と冬の大三角形が南中した頃で、この星が写る構図を決めて、あとはシャッタースピード30~40秒、記録のためのインターバル3秒をおいて、これを繰り返すようにレリーズタイマーをセットして電池が無くなるまでひたすらシャッターを切り続ける。レンズを変え、構図を変えて再び同作業を繰り返し、約4時間ひたすら撮影した。その間、山頂にテントを張り、2~3時間翌日の仕事のことを考えて眠った。

横位置構図の解説図

流星2個

流星2個

流星1個

山頂に張ったテントと甲府の灯り
何度か流星群の時に山上で撮影を試みているが、1時間に10個流れれば良い方で、2~3カット写れば良い方である。昨年の双子座流星群は御座山で一夜を過ごしたが、天候が悪かったこともあるのだが、流星が写ったのは2カットだけだった。しかし今年は別格、360カットほど撮った中に大小合わせて14カット、16個の流星を撮ることができた。撮影しているのは全天空の10分の1ほどの狭い範囲なので、換算してみると1時間あたり30~50個のたくさんの流星が流れたことになる。ここ数年では最高の流星群であったと言えるだろう。

夜明けの夫婦地蔵と富士

朝日射す釈迦ヶ岳山頂
夜明け前にはテント撤収し、朝日が昇るのを見て下山開始。甲府市街で渋滞に巻き込まれてしまい、10分遅刻で職場に到着した。30秒でシャッターを切り続けた画像をビデオ編集ソフトでつなげると、実は動画のように編集することができる。今回初めて試みた手技だが、パソコン上では十分に楽しめる。しかし、先日行った「山と花と星の奏でる音楽会」で上映してみると・・・プロジェクターの解像度が悪く、細い筋のように見える小さな流星はほとんど見えてはくれなかった。もう一工夫必要なのかもしれない。
週間予報では曇りだった天気予報が変わり、午後から青空となった甲府盆地。この夜は双子座流星群極大となる日だった。しかし生憎の平日、翌日は仕事もあるし、天気は回復したが撮影は半分あきらめていた。ところが・・・翌日予定していた業務が一つ中止となり、午前中で終わってしまうような仕事内容となる。これは・・・山の神様が私を呼んでいるのか?そんな気さえして、夜9時に甲府を出発して、かねてから夜の撮影を狙っていた御坂山塊釈迦ヶ岳に向かう。この山は黒岳から節刀ヶ岳に延びる尾根が河口湖の町灯りをカットしてくれるため、富士山側の星空を撮影するには絶好の場所だ。夜間登山だが、何度も登っているこの山、道を間違えることはまずあり得ない。

甲府盆地の灯りと南アルプスに沈む月 甲府盆地は南側だけ、アルプスは雲がかかる。

富士に南中するオリオン座と冬の大三角形 富士の上に流星が流れる。

構図の解説

拡大図。この山を選んだもうひとつの理由はこの低空に輝くカノープス。パソコン上の計算では見えるか見えないかぎりぎりの位置だが、見えることが確認された。

流星流れる富士の空
すずらん峠の駐車場に10時過ぎ到着、2台ほど駐車場から星空を観察している先客がいた。新道峠はゲートが閉じているのか、林道を歩いている人のヘッドライトも見える。10時半、出発。ほとんど休憩せずに黙々と歩き、11時40分、釈迦ヶ岳山頂に到着した。ちょうど南アルプスに月が沈んで行くところだった。見上げる空は澄み、流星が一つ二つと流れて行くのが見える。さっそく三脚とカメラをセットして撮影に取りかかる。富士山の上にオリオン座と冬の大三角形が南中した頃で、この星が写る構図を決めて、あとはシャッタースピード30~40秒、記録のためのインターバル3秒をおいて、これを繰り返すようにレリーズタイマーをセットして電池が無くなるまでひたすらシャッターを切り続ける。レンズを変え、構図を変えて再び同作業を繰り返し、約4時間ひたすら撮影した。その間、山頂にテントを張り、2~3時間翌日の仕事のことを考えて眠った。

横位置構図の解説図

流星2個

流星2個

流星1個

山頂に張ったテントと甲府の灯り
何度か流星群の時に山上で撮影を試みているが、1時間に10個流れれば良い方で、2~3カット写れば良い方である。昨年の双子座流星群は御座山で一夜を過ごしたが、天候が悪かったこともあるのだが、流星が写ったのは2カットだけだった。しかし今年は別格、360カットほど撮った中に大小合わせて14カット、16個の流星を撮ることができた。撮影しているのは全天空の10分の1ほどの狭い範囲なので、換算してみると1時間あたり30~50個のたくさんの流星が流れたことになる。ここ数年では最高の流星群であったと言えるだろう。

夜明けの夫婦地蔵と富士

朝日射す釈迦ヶ岳山頂
夜明け前にはテント撤収し、朝日が昇るのを見て下山開始。甲府市街で渋滞に巻き込まれてしまい、10分遅刻で職場に到着した。30秒でシャッターを切り続けた画像をビデオ編集ソフトでつなげると、実は動画のように編集することができる。今回初めて試みた手技だが、パソコン上では十分に楽しめる。しかし、先日行った「山と花と星の奏でる音楽会」で上映してみると・・・プロジェクターの解像度が悪く、細い筋のように見える小さな流星はほとんど見えてはくれなかった。もう一工夫必要なのかもしれない。