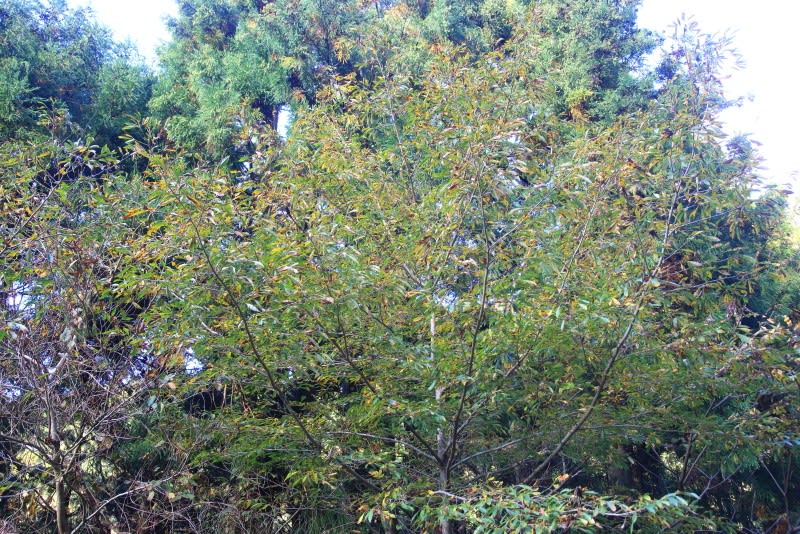11月中旬に紅熟したカナクギノキの実を期待して南部町に見に行ってみたがまだ青いままだった。では、黒熟するというクロモジの実はどうだろうか?クロモジは甲府市やその近傍の山にも多く生育しており、今回は出張の帰り際に韮崎市にある林道を訪れてみる。

これがクロモジの木だったはずだが、ボタンヅルがからみ付いている。

枝先に付いている実を探して見てみると、黒くはなっていないようである。

カナクギノキと同じくまだ青色ないしは黄色である。

これが本当に実なのか?と疑問を持ってしまいたくなるが、間違いないだろう。

紅葉している別のクロモジ。林道脇には他にもたくさん生えていた。

おそらく多くの実が脱落した後であろう。しかし、実は黒くなっていなかった。
今年は暑い夏が続いてほとんど秋らしい爽快な日が無く急に寒くなってしまったことが実の熟成に影響を与えているのかも知れないが、クロモジもカナクギノキと同様に色付いてはいなかった。今年が特別なのか、それともいつも色付くのはもっと後なのか、今後も経過を見て行きたいと思う。