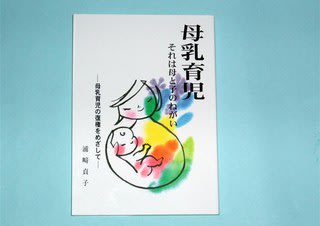平成18年1月16日(月) 後
後
昨日の「的ばかい」の熱気の余韻がまだ残っています。
先日、浦川の川岸で2羽の鳥を見かけました。初めは、ハマシギかなと思っていましたが、良く見ると嘴が上に反っています。チョーチョーチョーとやや甲高い、澄んだ声で鳴いています。こっちも口笛で呼応しました。本物の鳥の鳴き声には遠く及びません。

川は水量が減り、鳥達には小魚などのエサが見つけやすい状況になっています。水の中にいるのでアオアシシギの脚が全部は見えませんが、実際はもっと長いので、大きく見える中型のサギです。
エサをあさるときには、嘴を水中に入れたまま小走りに走り回ります。海辺では余り見かけませんでしたが、野鳥の会の安尾さんの話では川縁の方を好むのだそうです。

やがて、飛びたっていきましたが、上の羽は褐色で、下から見るのと大違いでした。

 後
後
昨日の「的ばかい」の熱気の余韻がまだ残っています。
先日、浦川の川岸で2羽の鳥を見かけました。初めは、ハマシギかなと思っていましたが、良く見ると嘴が上に反っています。チョーチョーチョーとやや甲高い、澄んだ声で鳴いています。こっちも口笛で呼応しました。本物の鳥の鳴き声には遠く及びません。

川は水量が減り、鳥達には小魚などのエサが見つけやすい状況になっています。水の中にいるのでアオアシシギの脚が全部は見えませんが、実際はもっと長いので、大きく見える中型のサギです。
エサをあさるときには、嘴を水中に入れたまま小走りに走り回ります。海辺では余り見かけませんでしたが、野鳥の会の安尾さんの話では川縁の方を好むのだそうです。

やがて、飛びたっていきましたが、上の羽は褐色で、下から見るのと大違いでした。






























































 。ピリッとした柚コショウが程よい甘みを一層引き立ててくれます。癖のない舌触りは今まで味わったことのない食感
。ピリッとした柚コショウが程よい甘みを一層引き立ててくれます。癖のない舌触りは今まで味わったことのない食感 。これはいけます。
。これはいけます。