私が参加している「道民カレッジ」では、ただ一方的に学ぶだけではなく、積極的に地域に関わり、地域に貢献していくことを推奨している。私たちができる地域活動についての実践例を聞き、参加者同士で協議した。
9月6日(水)午後、かでる2・7において、道民カレッジが主催する「地域活動実践講座」が開催され、参加した。
講座は、私と同じように道民カレッジの各種講座を受講している二人の方が地域において活動している実践の様子について報告した。
続いて、参加者が6~7名のグループに分かれてグループ討議を行う、という形で進められた。

A氏の発表のテーマは「札幌からの遠隔地域支援活動の実践~『プラチナの会』による『FMもえる』を通した活動~」という発表だった。
テーマ名から実践の内容がイメージしずらいと思われるが、M氏が現職時代に長く過ごした留萌市を盛り上げるため、留萌のコミュニティFMを通してふるさとへエールを送り続けているという実践例だった。
発表内容は一つの実践例として「面白い取り組みだなぁ」とうかがった。コミュニティFMの電波を通して留萌に住まわれている方々を元気づけるような話題を札幌から送り届けているというユニークな実践だった。
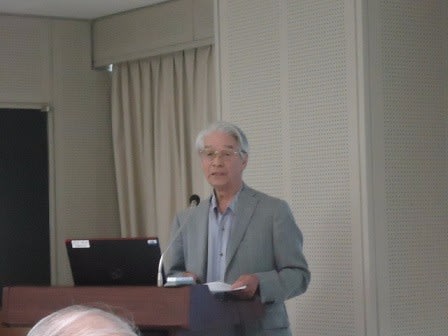
続いて発表したB氏のテーマは「地域活動(町内会活動)の実践」と題しての発表だった。こちらは退職されて町内会の役職を担わされたことがキッカケとなって、積極的に町内会活動をリードする立場になって、さまざまなことに取り組んだ事例を発表された。M氏のように退職されて、町内会の役員を委任されて活躍している例は聞くことが多い。
実際、私の昔の同僚も今春から道東のある街で町内会長を委任され、活躍していることを夏に会ったときに話していた。
B氏の場合、道民カレッジ連携講座で知ることができた講師を、町内会行事の講師として招請したということだったが、この例などは道民カレッジで学んだことが活かされた好例として受け止めた。

続いて行われたグループ討議で、私はBグループのコーディネーターを依頼された。グループ内で各自が、自分が実践している地域活動について発表してもらった。
するとやはり町内会の活動を担っている方の事例が多かった。ただ、マンション住まいの人たちは地域活動ということを意識されている方が少ないように思われた。
しかし、町内活動だけではなく、意識すれば札幌市内には地域活動に参加する機会がたくさん用意されていることも紹介された。こうした交流の機会に参加することによって、地域活動に参加を促す機会にもなるようである。
グループ討議は、最後に地域活動を盛り上げるためのキーワードをそれぞれに考えていただき、それをカードに書き出すというKJ法的手法によって、発表してもらった。
提起されたキーワードをメモすることができなかったが、「積極的に挨拶する」、「声掛けを心がける」、「広報活動が大切」、「一歩踏み出す勇気」、「共感者の出現を待つ」などなど、いろいろなワードが提起されたと記憶している。
自らの地域のことを考え、その地域づくりに積極的に関わる人が増えていくことは、人と人の繋がりを広げ、深めることに繋がる。そうした地域にはある種の潤いをも産まれてくるものと思う。そのような地域が増えていくことに私も微力ながら関わっていきたいと思う。
9月6日(水)午後、かでる2・7において、道民カレッジが主催する「地域活動実践講座」が開催され、参加した。
講座は、私と同じように道民カレッジの各種講座を受講している二人の方が地域において活動している実践の様子について報告した。
続いて、参加者が6~7名のグループに分かれてグループ討議を行う、という形で進められた。

A氏の発表のテーマは「札幌からの遠隔地域支援活動の実践~『プラチナの会』による『FMもえる』を通した活動~」という発表だった。
テーマ名から実践の内容がイメージしずらいと思われるが、M氏が現職時代に長く過ごした留萌市を盛り上げるため、留萌のコミュニティFMを通してふるさとへエールを送り続けているという実践例だった。
発表内容は一つの実践例として「面白い取り組みだなぁ」とうかがった。コミュニティFMの電波を通して留萌に住まわれている方々を元気づけるような話題を札幌から送り届けているというユニークな実践だった。
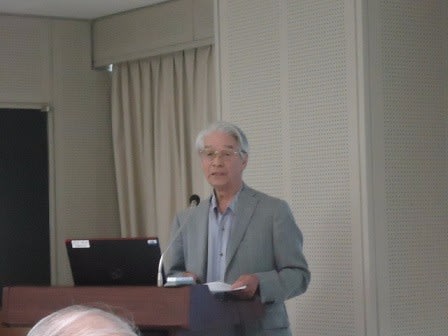
続いて発表したB氏のテーマは「地域活動(町内会活動)の実践」と題しての発表だった。こちらは退職されて町内会の役職を担わされたことがキッカケとなって、積極的に町内会活動をリードする立場になって、さまざまなことに取り組んだ事例を発表された。M氏のように退職されて、町内会の役員を委任されて活躍している例は聞くことが多い。
実際、私の昔の同僚も今春から道東のある街で町内会長を委任され、活躍していることを夏に会ったときに話していた。
B氏の場合、道民カレッジ連携講座で知ることができた講師を、町内会行事の講師として招請したということだったが、この例などは道民カレッジで学んだことが活かされた好例として受け止めた。

続いて行われたグループ討議で、私はBグループのコーディネーターを依頼された。グループ内で各自が、自分が実践している地域活動について発表してもらった。
するとやはり町内会の活動を担っている方の事例が多かった。ただ、マンション住まいの人たちは地域活動ということを意識されている方が少ないように思われた。
しかし、町内活動だけではなく、意識すれば札幌市内には地域活動に参加する機会がたくさん用意されていることも紹介された。こうした交流の機会に参加することによって、地域活動に参加を促す機会にもなるようである。
グループ討議は、最後に地域活動を盛り上げるためのキーワードをそれぞれに考えていただき、それをカードに書き出すというKJ法的手法によって、発表してもらった。
提起されたキーワードをメモすることができなかったが、「積極的に挨拶する」、「声掛けを心がける」、「広報活動が大切」、「一歩踏み出す勇気」、「共感者の出現を待つ」などなど、いろいろなワードが提起されたと記憶している。
自らの地域のことを考え、その地域づくりに積極的に関わる人が増えていくことは、人と人の繋がりを広げ、深めることに繋がる。そうした地域にはある種の潤いをも産まれてくるものと思う。そのような地域が増えていくことに私も微力ながら関わっていきたいと思う。









