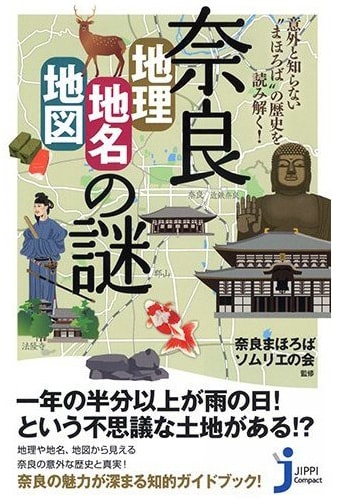今日は休暇を取りましたので、ブログ更新が遅くなりました。さて皆さん、ご注目ください! NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」が監修した『奈良「地理・地名・地図の謎」』(じっぴコンパクト新書=実業之日本社)が、いよいよ発刊されます!本体価格は762円です(消費税5%だと800円)。
版元のHPには2/28発売となっていますので、まもなく県下書店の店頭にも並ぶ予定です。Amazonが早くから予約販売を受け付けていて、私には今朝(2/28)、「発送のお知らせ」が届きました。拙宅へは3/2(日)の到着予定です。
監修者の1人として、私のところへはひと足早く、版元から現物をが到着しています。東大寺の大仏や大仏殿、石舞台、聖徳太子、柿の葉寿司などをあしらったカラフルで楽しいカバー。帯には
地理・地名・地図からわかる「奈良」の奥深い歴史
1年の半分以上が雨の日!という不思議な土地がある?
「飛鳥」と「明日香」どちらが正しいの?
知っていますか?奈良にある謎の数々
「奈良」とありますが、これは奈良市にとどまらず、「奈良県」全体を指します。
Amazonの「内容紹介」によりますと、
奈良の魅力が深まる知的ガイドブック!
「東大寺に神社の注連縄がかけられている門がある! 」
「大和と難波を結ぶ、地図に隠された巨大な道があった」
「なぜ、平城京には大極殿の跡がふたつもあるのか」
「日本最古の道『山の辺の道』は、なぜ曲がりくねっているのか」
「日本最古の地名「忍坂(おっさか)」が、統治機構の名前になった?」
「かぐや姫の伝承地は奈良にあり! 」
「ピアノ所有率全国トップクラスなのには地理的理由がある!?」
……など。古刹に残された謎、古代王朝から伝わる信仰など、意外な歴史のエピソードを中心に集め、奈良県の「今」もわかってしまう一冊。奈良県人も驚く、観光するだけではわからない雑学ネタ満載の本。
【目次】
■第1章 奈良の古刹のミステリー地図
■第2章 地図に残された古代王朝の足跡
■第3章 大和に伝わる信仰・伝説の謎
■第4章 古式ゆかしい地名のルーツ
■第5章 古都奈良の「今」がわかる迷宮地図
監修者について
奈良まほろばソムリエの会
奈良のご当地検定「奈良まほろばソムリエ」検定の最上級である「奈良まほろばソムリエ」資格を取得したメンバーが中心となって発足した「奈良通」の会。2011年4月に発足、13年2月にNPO法人化。会員数は約240名(14年1月現在)。奈良を愛する者の熱意と知識・経験を活かし、様々な活動に取り組んでいる。
東京にいらっしゃる複数のライターさんが執筆されたものを、 NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」が監修した格好ですが、ネタも当会がたくさん提供しています(私の提供ネタは、聖林寺のご本尊が汗をかく、早起きは三文の得の意味、スイカのタネは全国シェア8割以上 などなど)。文章をまるごと書き替えた項目もあります。
監修に携わった当会会員は理事(役員)や広報グループのメンバーなど、総勢約20人。全体の取りまとめは私が担当しましたので、12月から1月までは、その作業に忙殺されました。とりわけ年末年始8日間の休日は、まるごと監修作業に費やしました。おかげで刊行にこぎつけた今となっては、感慨もひとしおです。
最後の最後になって依頼のあったのが「まえがき」の執筆で、これは2/1に先方に送りました。執筆されたのは当会の石田一雄さんで、私が少し手を加えました。最も思い出深い文章です。以下、全文を紹介しますと、
奈良には「謎」が多い。というと他の都道府県から文句が出そうだが、謎に「古代の歴史」がからむとなると、対抗できるところは少ないのではないだろうか。『古事記(こじき)』や『日本書紀(にほんしょき)』に記されているように、奈良県は日本で最初に都が置かれ、古代日本の中心となった土地である。
古代日本最大の謎といえば、やはり「邪馬台国(やまたいこく)」だろう。畿内にあった、いや九州にあった、と今も論争が続いているが、まだ決着はついていない。ただし奈良県内では、その謎を解く有力な考古学上の手がかりが最近相次いで発見されている。桜井市にある纏向(まきむく)遺跡や箸墓(はしはか)古墳である。
「謎」は古代だけではない。かつては当たり前の「常識」であったことも、時が過ぎると「謎」に変わる。とりわけ「地理・地名・地図」となると、歴史を積み重ねてきた土地ほど「謎」が多くなる。平城京から平安京に都が移り、奈良は歴史の表舞台からはずれてしまうが、平安時代以降も現在に至るまで、奈良は激動の歴史の舞台になってきた。
奈良を代表する仏像といえば東大寺の大仏だが、この仏像も歴史の産物である。幾度も戦火などの災害にあい、その都度修復されてきた。顔は江戸時代、胴部は鎌倉時代、台座の一部は奈良時代と修復の歴史が積み重ねられてきて、今の姿がある。法隆寺も唐招提寺もその他の社寺も古墳も遺跡も、先人たちが創建以降、何度も修復を重ねてきて、現代のわれわれに残してくれているものだ。
本書で取り上げられた「地理・地名・地図の謎」は、奈良県の長い歴史の積み重ねの結晶として現れてきたものであり、それは本文を読んでいただければ、よく分かっていただけるだろう。
「奈良まほろばソムリエ」とは何か、これは謎ではない。奈良商工会議所が主催する「奈良まほろばソムリエ検定」(奈良検定)というご当地検定があり、その最上級が「奈良まほろばソムリエ」である。「まほろば」(真秀場)とは素晴らしい場所、住みやすい場所という意味で、大和の代名詞である。ヤマトタケルの有名な歌「倭(やまと)は国のまほろば たたなづく青垣 山隠(やまこも)れる倭しうるはし」に歌われている。
NPO法人奈良まほろばソムリエの会は、「奈良まほろばソムリエ」有資格者を中心とした、まほろば(奈良)好きの集まりである。奈良好きが集まって、本書を監修した。ぜひ本書を携えて、奈良・大和路を巡っていただきたい。そして奈良に興味を持ち、奈良を好きになってもらいたい。1人でも多く奈良ファンになっていただきたい、と切に願っている。
面白くてためになり、奈良検定受験に際しては絶好の参考資料にもなります。皆さん、ぜひお買い求めください!
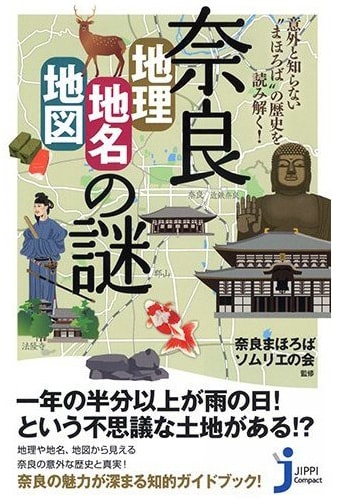
版元のHPには2/28発売となっていますので、まもなく県下書店の店頭にも並ぶ予定です。Amazonが早くから予約販売を受け付けていて、私には今朝(2/28)、「発送のお知らせ」が届きました。拙宅へは3/2(日)の到着予定です。
監修者の1人として、私のところへはひと足早く、版元から現物をが到着しています。東大寺の大仏や大仏殿、石舞台、聖徳太子、柿の葉寿司などをあしらったカラフルで楽しいカバー。帯には
地理・地名・地図からわかる「奈良」の奥深い歴史
1年の半分以上が雨の日!という不思議な土地がある?
「飛鳥」と「明日香」どちらが正しいの?
知っていますか?奈良にある謎の数々
 | 奈良「地理・地名・地図」の謎 (じっぴコンパクト新書) |
| 奈良まほろばソムリエの会 監修 | |
| 実業之日本社 |
「奈良」とありますが、これは奈良市にとどまらず、「奈良県」全体を指します。
Amazonの「内容紹介」によりますと、
奈良の魅力が深まる知的ガイドブック!
「東大寺に神社の注連縄がかけられている門がある! 」
「大和と難波を結ぶ、地図に隠された巨大な道があった」
「なぜ、平城京には大極殿の跡がふたつもあるのか」
「日本最古の道『山の辺の道』は、なぜ曲がりくねっているのか」
「日本最古の地名「忍坂(おっさか)」が、統治機構の名前になった?」
「かぐや姫の伝承地は奈良にあり! 」
「ピアノ所有率全国トップクラスなのには地理的理由がある!?」
……など。古刹に残された謎、古代王朝から伝わる信仰など、意外な歴史のエピソードを中心に集め、奈良県の「今」もわかってしまう一冊。奈良県人も驚く、観光するだけではわからない雑学ネタ満載の本。
【目次】
■第1章 奈良の古刹のミステリー地図
■第2章 地図に残された古代王朝の足跡
■第3章 大和に伝わる信仰・伝説の謎
■第4章 古式ゆかしい地名のルーツ
■第5章 古都奈良の「今」がわかる迷宮地図
監修者について
奈良まほろばソムリエの会
奈良のご当地検定「奈良まほろばソムリエ」検定の最上級である「奈良まほろばソムリエ」資格を取得したメンバーが中心となって発足した「奈良通」の会。2011年4月に発足、13年2月にNPO法人化。会員数は約240名(14年1月現在)。奈良を愛する者の熱意と知識・経験を活かし、様々な活動に取り組んでいる。
東京にいらっしゃる複数のライターさんが執筆されたものを、 NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」が監修した格好ですが、ネタも当会がたくさん提供しています(私の提供ネタは、聖林寺のご本尊が汗をかく、早起きは三文の得の意味、スイカのタネは全国シェア8割以上 などなど)。文章をまるごと書き替えた項目もあります。
監修に携わった当会会員は理事(役員)や広報グループのメンバーなど、総勢約20人。全体の取りまとめは私が担当しましたので、12月から1月までは、その作業に忙殺されました。とりわけ年末年始8日間の休日は、まるごと監修作業に費やしました。おかげで刊行にこぎつけた今となっては、感慨もひとしおです。
最後の最後になって依頼のあったのが「まえがき」の執筆で、これは2/1に先方に送りました。執筆されたのは当会の石田一雄さんで、私が少し手を加えました。最も思い出深い文章です。以下、全文を紹介しますと、
まえがき [奈良 イズ ミステリー!]
奈良には「謎」が多い。というと他の都道府県から文句が出そうだが、謎に「古代の歴史」がからむとなると、対抗できるところは少ないのではないだろうか。『古事記(こじき)』や『日本書紀(にほんしょき)』に記されているように、奈良県は日本で最初に都が置かれ、古代日本の中心となった土地である。
古代日本最大の謎といえば、やはり「邪馬台国(やまたいこく)」だろう。畿内にあった、いや九州にあった、と今も論争が続いているが、まだ決着はついていない。ただし奈良県内では、その謎を解く有力な考古学上の手がかりが最近相次いで発見されている。桜井市にある纏向(まきむく)遺跡や箸墓(はしはか)古墳である。
「謎」は古代だけではない。かつては当たり前の「常識」であったことも、時が過ぎると「謎」に変わる。とりわけ「地理・地名・地図」となると、歴史を積み重ねてきた土地ほど「謎」が多くなる。平城京から平安京に都が移り、奈良は歴史の表舞台からはずれてしまうが、平安時代以降も現在に至るまで、奈良は激動の歴史の舞台になってきた。
奈良を代表する仏像といえば東大寺の大仏だが、この仏像も歴史の産物である。幾度も戦火などの災害にあい、その都度修復されてきた。顔は江戸時代、胴部は鎌倉時代、台座の一部は奈良時代と修復の歴史が積み重ねられてきて、今の姿がある。法隆寺も唐招提寺もその他の社寺も古墳も遺跡も、先人たちが創建以降、何度も修復を重ねてきて、現代のわれわれに残してくれているものだ。
本書で取り上げられた「地理・地名・地図の謎」は、奈良県の長い歴史の積み重ねの結晶として現れてきたものであり、それは本文を読んでいただければ、よく分かっていただけるだろう。
「奈良まほろばソムリエ」とは何か、これは謎ではない。奈良商工会議所が主催する「奈良まほろばソムリエ検定」(奈良検定)というご当地検定があり、その最上級が「奈良まほろばソムリエ」である。「まほろば」(真秀場)とは素晴らしい場所、住みやすい場所という意味で、大和の代名詞である。ヤマトタケルの有名な歌「倭(やまと)は国のまほろば たたなづく青垣 山隠(やまこも)れる倭しうるはし」に歌われている。
NPO法人奈良まほろばソムリエの会は、「奈良まほろばソムリエ」有資格者を中心とした、まほろば(奈良)好きの集まりである。奈良好きが集まって、本書を監修した。ぜひ本書を携えて、奈良・大和路を巡っていただきたい。そして奈良に興味を持ち、奈良を好きになってもらいたい。1人でも多く奈良ファンになっていただきたい、と切に願っている。
面白くてためになり、奈良検定受験に際しては絶好の参考資料にもなります。皆さん、ぜひお買い求めください!