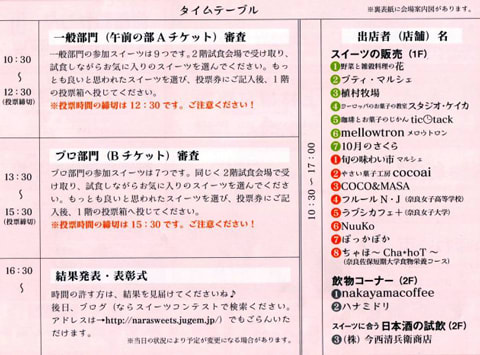『奈良の将来ビジョン(第一次提案)』という冊子を読んだ。朝日新聞奈良版「
奈良の将来ビジョンを一冊に 市民らの76提案盛る」(1/6付)に概要が紹介されている。《市民や企業家、研究者らでつくる「奈良の将来ビジョンをつくるフォーラム実行委員会」(委員長=村田武一郎・県立大教授)が昨年6~11月に計13回の討議を重ねた成果を、「奈良の将来ビジョン(第一次提案)」という冊子にまとめた。「ネットワーク型シンクタンク」「新商品づくり支援機構」など重点プロジェクトの一部は、今年中に具体化させる予定だ》。
《フォーラムは、経済社会の構造転換が進む中、奈良という地域の特色を生かした地域づくりを市民からの提案に基づいて進めようと昨年2月に発足。「第一次提案」は76の市民提案を盛り込んでいる》《県の各部局とも複数の研究会をつくってビジョンの具体化を図るとともに、2011年度は農林業、医療・福祉、教育に関する市民提案を公募し、「第二次提案」づくりを目指す。冊子はB5判、50ページ。1千部発行。525円(税込み)。実行委にファクス(0742・24・2261)、メール(vision@nit-ass.jp)で申し込む》。
早速取り寄せて読んでみたところ、これがとても面白い。まさに「巻を措(お)くあたわず」、蛍光ペンと付箋だらけにしながら一気に読み終えた。巻末に載っている同フォーラム実行委員のリストには、朝廣佳子さん、野村幸治さん、平原正樹さん、松村洋子さん、室雅博さん、山本太治さん、山本善徳さんなど、存じ上げている方のお名前をたくさん拝見した。
私は学者ではないので、この冊子の提案を網羅的に紹介するのは止め、とにかく読んでピンときて、思わずマーカーを走らせた部分だけを、掲載順にずらずらと並べてみる。ご興味のある方は、ぜひ冊子を入手して読んでいただきたい、何しろ525円なのだから。なお本冊子は観光にとどまらず、幅広い領域を対象としているが、私は主に観光に関する提案のところに注目したので、「観光地奈良の勝ち残り戦略」シリーズの一環とした。
「はじめに」で、
同フォーラム実行委員会の村田委員長は《どのような奈良にすべきであるのか、どのような奈良での生活がここちよさと誇りをもてるのかを、政治・行政に任せきりにせず、県民・産業界・学界等が一緒になって議論し、将来ビジョンをつくるためのフォーラムを、2010年2月にスタートさせました》と書いている。続いて将来ビジョンが3つと、3つめのビジョンに付随した8つの目標が示される。以下[tetsuda私見]と「注」以外は、すべて同冊子からの引用文である。
奈良の将来ビジョン-1.奈良県の将来発展方向と将来に向けての施策の目標
《※奈良県が抱える問題 奈良県は、1)高質・多大な資源(注:地域資源のこと)の未活用、2)県民の能力発揮環境の不備、3)人口と高次都市機能の北部への偏在、4)産業の自律性の欠如、5)マスツーリズムへの依存、6)農地・山林の荒廃、7)新しい発展戦略の不足などの問題を抱えている》。

写真は大和民俗公園(大和郡山市矢田町)みんぱく梅林で撮影(05.3.5)。今年の梅は、まだかいな
奈良の将来ビジョン-2.重点プロジェクトの提案
○盛年(元気なリタイアド層)の社会参画の促進
《地域の中心になる人材が不足しており、また、継続的な人材供給の仕組みづくりがなされていない。盛年に活躍してもらえるように、学習機会の拡大、活動拠点づくり、コーディネーターの配置、地域・企業との交流会など社会参画支援システムを整備する》《※盛年層には社会参画意欲があるにも関わらず、参画の方法が不明で、また、参画の仲間がいない。盛年層は、自由な時間と公民としての役務に参加する方法・機会を見失っている》《各市町村の生涯学習センター等は、趣味・習いごとが中心で、幅広い人的ネットワークづくり、地域活動の教育と人材発掘の場にはなっていない》《※奈良県では、生産に携わらない人の割合が、2015年には40%を超える》。
[tetsuda私見]上記のうち「社会参画意欲があるにも関わらず、参画の方法が不明で、また、参画の仲間がいない。盛年層は、自由な時間と公民としての役務に参加する方法・機会を見失っている」という部分には、特に共感する。リタイア組の大半は、お稽古ごとに時間を費やしたいとは思っていない。地域や社会のために、何か役に立ことをしたい、と考えているのだ。
○産学官と県民による政策検討委員会の設置
《行政スタッフの視点・感覚・経験だけで政策がつくられる場合、その政策には、地域の人々や産業人の視点・感覚・経験や将来への思いが欠落してしまうことが生じる》。
[tetsuda私見]別の箇所に「ノウハウをもたないスタッフが専門性を必要とする部署に配属されて四苦八苦している例が見られる。産業振興、観光振興など行政スタッフがノウハウをもたない分野は、必要に応じて、民間に委託し、民間のノウハウを活用することが適切である」とあった。行政に通じた書き手が、行政に対して厳しい目を向けている印象だ。
○地域資源を活かす新観光・交流産業の開発・振興
《地域の多様な主体が協力して、奈良の地域資源を活かすオルタナティブツーリズム(注:マスツーリズムに取って替わる観光)を開発すること、また、その新観光・交流と連携する産業を開発・振興することを、助成金・支援金の提供、盛年層をはじめとする知識・ノウハウ・人的ネットワークをもつ人材の投入などにより支援していく必要がある》。
○奈良の産学官の総力を結集した産業ビジョンの策定と実施
《奈良の産業界の中核を担っている組織が、奈良の学官ならびに盛年層との交流・共働および関西の産業界等との交流・共働を主体的・積極的に進めることが、その前提として必要である》《奈良の盛年層は、社会再参画の面で問題を抱えているが、優れた能力を有している人たちが多く、アメリカでの事例と同様な新産業開発に関わることを期待したい》。
○地域資源を活かした新商品づくり支援機構の設立
《※奈良には「食」のイメージがなく、日帰り観光客の消費額(ひとり3,500円程度)は、神戸・京都(同7,000~8,000円)に遠く及ばない。当面、奈良らしい、奈良独自の商品を、他府県の消費者の協力も得て開発し、日帰り観光客の消費額を少なくとも1,000円増やしてもらうことが肝要である。それだけで、1,000円×3,500万人=350億円もの消費額が生まれる。※農業者等で商品開発意欲を持つ人はいるが、方法論や流通がわからず、諦めてしまっている》。
[tetsuda私見]これは鋭い指摘だ。せっかく良い農畜産物があるのに、流通やマーケティング、PR方法が分からず、埋もれている事例が多い。このような支援機構があれば、いろんな「食の魅力」が発掘できそうだ。
 奈良の将来ビジョン-3.奈良県の将来に向けての施策の提案
目標-1.県民が能力を発揮できる機会が多い奈良県を創る
奈良の将来ビジョン-3.奈良県の将来に向けての施策の提案
目標-1.県民が能力を発揮できる機会が多い奈良県を創る
方針-1.各世代が社会との関わりをもって生き生きと活動する状況を創出する
《老若男女すべての人が奈良県に愛着を持つことができる状況となることが望ましい》《盛年は、知識・ノウハウ・人的ネットワークを持っており、地域社会の運営の中核を担う存在として位置づけたい。定年退職者には地域デビューの問題があり、学習機会を提供すること、学校等公的機関から知識・ノウハウ等の提供を要請すること、地域でのたまり場を提供することなど、社会再参加の機会を提供する》。
○地域を知り、地域愛を育む活動の支援
《奈良には祭が多いにもかかわらず、その来歴を知る住民は少なく、学校で、祭の来歴や地域の歴史を学ぶ機会も減っている。※高校では、日本史を学ばない生徒もいるという問題がある》。
[tetsuda私見]「地域を知り、地域愛を育む」という点については、私も以前「そこに愛はあるのかい」というブログ記事を書いたことがある。1300年祭で変わったと思うが、かつての奈良県では、地元に関する知識不足→関心不足→誇り・愛情不足という悪魔の循環が回っていた。県民は、奈良県のことを知らなさすぎたのだ。これを逆に回し、地元に誇り・愛情をもつ→関心を持つ→知識を持つ、という好循環に変えよう、というのが私の持論である。
方針-2.地域住民が潜在的な人的資質を開花させるとともに、主体的に地域の魅力を発見し、地域発展に結びつける活動を支援する
《奈良は奈良のまま(古さ)を生かしつつ新しさを取り入れる。つまり、リフォーム(元へ戻す改善・再生)ではなく、リノベーション(価値を高めるために変えていく改革・刷新)を進めたい》《住民は、地域づくりに非地ような知識やノウハウを必ずしも備えているわけではなく、住民の主体的な行動・活動を支援する体制を整える必要がある》。
○地域プランナー・コーディネータの活動支援・育成
《各地域では、地域資源の発掘・活用、誘客・もてなしサービスなどのノウハウを持ち合わせている人材が少ない。このため、地域の将来像作成と将来発展計画づくりを支援する地域プランナー、その実現と地域間連携を支援する地域コーディネータを制度化し、各地域へ派遣する仕組みづくりが必要である》。
○地域づくり会社設立の支援
《各地域にある農林・商工・観光等の団体の縦割を超え、それらを総合化して「地域づくり会社」を設立することを支援する。地域づくり会社は、地域づくりのビジョンを示すとともに、その実現に向けた事業を実施する》。
目標-2.NPO・ボランティア・地域団体と行政が共働し、安心して、活力をもって暮らせる奈良県を創る
方針-1.地域社会を再生する
《特に都市部では、地縁型コミュニティの単なる押しつけではなく、地域にいくつものソサイエティをつくっていくことで、ソサイエティ型の人たちが自治会など地縁型コミュニティの人たちとも親しくなり、共働して何かを動かす状況をつくることができる。このようなネットワークの形成を支援する必要がある》。
○課題解決型ソサエティの育成
《課題解決型ソサイエティへお金が回っていく仕組みをつくり、行政の負担を減らしていく。このため、課題解決型ソサイエティから地域づくりの提案を出してもらい、審査のうえ活動を助成する》《※奈良に多いサラリーマンのまちでは、みんなで地域のために何かをしようという意識は希薄である》。
[tetsuda私見]リタイアすると自治会(地縁型コミュニティ)へ、というのがお決まりだが、それよりもっと広い意味での地域おこし有志グループ(課題解決型ソサエティ)に参加してもらい、得意分野で能力を発揮してもらうのが良い。先に「奈良の盛年層は、社会再参画の面で問題を抱えているが、優れた能力を有している人たちが多く…」とあったとおり、奈良のリタイア組には、能力の高い人が多い。それは、昨年の平城宮跡ツアーガイドボランティアで痛感した。
目標-3.利便性が高く、各地域の個性・特性を発揮できる地域・広域生活圏をもつ奈良県を創る
方針-2.各地域の個性・特性を活かすブランディング作戦を展開する
○各地域のブランディング作戦の支援
《概ね市町村単位で、個性・特性を活かし、広域・国際的に存在感のあるまちづくりを支援する。地域プランナー・コーディネータを送り込み、地域住民・市町村と一緒に取り組む》《※例えば、天理市には、優れた資源(古代、日本文化、国際的な文化・民族、西洋音楽・雅楽、スポーツ文化など)があり、それを活用する広域・国際交流拠点、新価値創造拠点としてのまちづくりが望まれる》。
方針-3.利便性が高い総合交通体系を効率的に構築する
○JR桜井線のLRT化と奈良公園への延伸
《JR桜井線をLRT(注:軽量軌道交通)化し、奈良公園まで延伸する。その際、気軽に乗れるように駅間距離を短くし、利用利便の拡大を図る》。
○近鉄線・JR線の接続
《JR大和路線・近鉄橿原線の交差箇所(大和郡山市内)に両者の接続駅を設け、利便の拡大を図る》。
[tetsuda私見]これは良い提案である。LRTは、ならまち周辺を通過するルートとするのも面白い。JR大和路線と近鉄橿原線を接続できれば、奈良公園→薬師寺→法隆寺というゴールデンルートができる。いろんなところで、提案し続けよう。
○奈良サイクルロードの整備促進
○全県をめぐる歩行者専用道路「緑の回道」の整備
目標-4.資源を活かし、国内・世界各地域に貢献する高次人材を育成する奈良県を創る
方針-3.奈良各地域の潜在力を開花させるために、専門的知識をもって地域づくりを支援する地域プランナー・コーディネータを育成する
目標-5.他地域の人々との交流により新たな価値を生み出す奈良県を創る
方針-1.地域主権・道州制時代の奈良のポジションづくりを行う
○関西州の「迎賓拠点」としての奈良づくり
《奈良には、高質な宿泊施設がないため、迎賓館としても利用できる宿泊施設を誘致する》。
○関西州に向けての大阪府との先行的連携
《大阪を近くにある巨大マーケットとして再認識し、活用する。また、大阪の産業・技術・人材集積との連携をねらったパートナーとして活用する。大阪側は、奈良県を、大阪には少ない農林資源の供給地、農山村を府民の癒しの地として活用する。また、大阪には少ない歴史文化系の観光資源を活かし、特にインバウンド対応において、大阪の都市型観光との広域連携を図る》。
方針-2.20年先の時代への対応のため、観光・交流を再構築する
《観光・交流は、奈良が比較優位を持ち得る数少ない分野である。そして、観光・交流は、農業・工業・工芸・商業など多様な産業活動と結びついており、観光・交流の振興は、それらの産業の活性化にもつながる可能性を持っている。観光・交流に関連する産業群は、雇用・所得・税収の拡大にとって重要な、今後の奈良県を支えるリーディング産業であると言える。一方、観光・交流は、それを通じた友好関係の構築、相互理解の促進、相互の気づきや発想の獲得、文化の進展をもたらす多面的な価値を持っている》。
《※地域に存在しなかった視点や感性は、地域が新価値を生み出す刺激となり、情報源となるものである。さらに、来訪者は、地域の人々の人的資源の開花を促す。来訪者と地域の人々との十分な関わりを確保するために、滞在・交流地域づくりが必要である。十分な関わりを持った来訪者は、大切なパートナー、理解者として育ち、再び来訪してくれる。※観光・交流の進展は、観光関連産業への直接的な効果にとどまらず、県民に、来訪者との出会いによる刺激と地域再発見の機会をもたらす》。
 ○ミニ観光・交流の振興とミディ観光・交流への発展
○ミニ観光・交流の振興とミディ観光・交流への発展
《現在、幾つもの地域において、小さな観光・交流地域づくり(年間来訪者数千人~数万人)が進められている。このような「ミニ観光・交流地域」を、年間来訪者十万人~数十万人の「ミディ観光・交流地域」へと発展させ、それらが相互に繋がる「ミディ観光・交流地域」の集合体としての奈良県を創ることが望ましい》。
○人を中心とした観光・交流への再構築
《※そこへ行かなければ出会えない「人」「地域固有のもの」が、これからの観光・交流にとって重要である。そこへ行かなければ出会えない「人」「もの」は、各地域に存在し、住民主導の小さな工夫でそれを活かしている地域が活力をもっている》。
○奈良二十四ヶ所めぐり
《丸1日を楽しめる規模を基本に奈良県を24地域に分け、各地域それぞれにおいて、喜んでもらえるサービスをつくり上げることが新しい観光・交流と関連産業の開発になる》。
○南都八大寺セミナーの常時開催
《南都八大寺の僧侶により、毎日持ち回りで仏教や奈良に関係するセミナーを開催することが望まれる》。
[tetsuda私見]「奈良二十四ヶ所めぐり」「南都八大寺セミナー」とは、面白い。現状の「大和七福八宝めぐり」「大和十三佛霊場めぐり」とのタイアップも考えられる。「(見どころが多すぎて)どこへ行けば良いのか分からない」「せっかく来たのだから、法話も聞きたい」というニーズに応えることが、「人を中心とした観光・交流への再構築」につながる。
方針-3.各地域・地区が連携し、総合的な機能をもつ体制づくりを進める
《いくつもの地域が「むらがる」状況を創出することにより、来訪者への多様な選択肢の提供、来訪したことの満足の向上に結びつけられる》。
○宇陀の高原地帯における総合力がある観光・交流地域づくり
《夏場は、「家族向け資源」「歴史文化」「名物料理と温泉」の3本柱を立て、宿泊所を強化し、連携できれば、1~2泊の観光・交流ルートが成立する。冬場も料理を強化して「ゆっくり、ゆったり」を売りにすることができる》。
方針-4.もてなしの心を醸成するとともに、もてなしの質の向上を図る
○国際観光大学院大学の開設

方針-5.地域情報の発信力の強化を図る
○奈良の観光・交流の質の向上を目指す観光・交流評価情報提供システムの構築
○奈良ゴト知らしめ隊の設立
《奈良各地が宝もの(人・もの・出来事)を知らしめようとしても、知識や技術が未熟であり、専門会社に依頼しても、多額の費用が必要で、継続実施が困難である。このため、利益追求を求めない「広告会社」のような仕組みを、行政とNPO等の共働により設置する》《広告会社や調査会社、企業の広報・広告担当のOB等を核として活動する。また、地域活動家にそのノウハウを伝授・教育する》《※まちには歴史があるので、「ものがたり」を知らせ、広げることが望ましい。※奈良の人物アピール作戦を展開することが望まれる。人は人の生きざまに感動する。奈良にも歴史上の偉人、魅力ある地域人がたくさんいる。その人たちを丁寧にズームアップし、発信する必要がある》。
[tetsuda私見]非営利の広告屋(奈良ゴト知らしめ隊)とは、ユニークな発想だ。奈良県民の広告下手は、つとに知られているからだ。私は長年、企業の広報担当を務めているが、広報(マスコミ対応)や広告(宣伝)にノウハウを持つリタイア組も、県下にはたくさんおられることだろう。私も、定年後の楽しみの1つに数えておきたい。
方針-6.都心に交流空間を設け、県民・来訪者に提供する
○ならまちロードの設定(注:東向、もちいどの、三条通の店舗閉店時刻を21時に)
○屋根付き・簡易トイレ付きの団体用休憩所(おべんと広場)の設置
方針-7.新しい観光・交流産業を開発・振興する
《奈良の地域資源を考えた時、グリーンツーリズム(体験・交流を伴う農業・酪農観光など)、工房ツーリズム(工房めぐり、ものづくり体験、工房主の指導による自分だけのものづくりなど)、林業ツーリズム(林業体験、山歩き、山菜採取と山菜料理など)、ラーニングツーリズム(特に歴史上の人物の生き方・エピソードに重点を置いた古代史の学習)、やすらぎツーリズム(神社仏閣での講話・写経など)、食文化ツーリズム(地域の伝統料理、川魚釣りと川魚料理、ジビエ料理、こだわり栽培の野菜料理、伝統調味料に出会う旅など)、産業ツーリズム(伝統技術をもつ工場の見学、工場での技術体験、起業家との交流など)の開発が望まれる》。
方針-8.観光・交流の促進に結びつくインフラストラクチャーを整備・再編成する
○景観の保全と修復
《奈良には、まち中の景観、里山や棚田の景観、農山村・田園の景観、産地を遠望する景観など優れた景観が多いが、建造物・広告等によって阻害されており、景観の保全と修復が必要である》。
引用は以上である、いかがだろう。この冊子には「どのような奈良にすべきであるのか、どのような奈良での生活がここちよさと誇りをもてるのか」というヒントが、随所に散りばめられている。参考資料として巻末に掲載されている「諸指標から見る奈良県の現状」は、同フォーラムのサイトからダウンロードできるので、参考にしていただきたい。
良いレポートをができ上がった。次はぜひ、具体的な1歩を踏み出したいものである。荒井知事曰く「1人の100歩より、100人の1歩」。今年こそ、何か具体的なムーブメントを起こしたいものだ。皆さん、いかがですか?
(1/30)追記 同フォーラム実行委員のお1人である
鏡清澄さん(筆名)から、当記事にコメントをいただいたので、その一部を紹介させていただく。
《自らが行動する必要性 町おこしに行政と市民のタイアップは欠かせませんが、行政に頼り過ぎるのは良くないです。将来ビジョンも提案だけして、何も実現できなかったら意味がありません。結果として、「また言っただけだった」とフォーラムメンバーに不満が残ってはいけません。何か一つでも自分たちのできることを努力していくということが必要でしょう》。
[tetsuda私見]今回の「第一次提案」ほどのレベルに達しないまでも、、この種の提言は毎年、様々な団体や個人から出されている。だから「実現されなければ意味がない」のである。昨年の当県が盛り上がったのは、県下各所で同時多発的にイベントが行われ、それを目がけて人が集まったからである。今回の提案を受けて、1つでも具体的な動きが出てくることを期待する。
《強みをさらに磨いてアピール》《誰もがイメージする古都、奈良。仏都であり古典の地である奈良。この強烈なイメージこそ大切にすべきです。強みに特化してこそ戦略は成り立ちます。他府県にないこの強みこそ奈良を売り込む最大の武器だと思います。問題は、十分心しないと神社仏閣が単なる見て回るだけのものになってしまうことでしょう。神社仏閣が人々の心や生き方に影響を与える本来の役割を果たしていくなら、悩める人の多い現代、奈良は大きな役割を世の中に果たせると思います》。
[tetsuda私見]昨年大ヒットした1300年祭の事業に、「祈りの回廊 奈良大和路 秘宝・秘仏特別開帳」がある。これは、他所では決してマネのできない事業であった。仏像ブームだけでなく、最近では若い女性を中心に、パワースポット(スピリチュアルスポット)めぐりが盛んで、県下の古社の参拝客が増えている。古社めぐりをうまく取り込んだ事業が、ポスト1300年祭の観光振興のヒントになるのではないか。