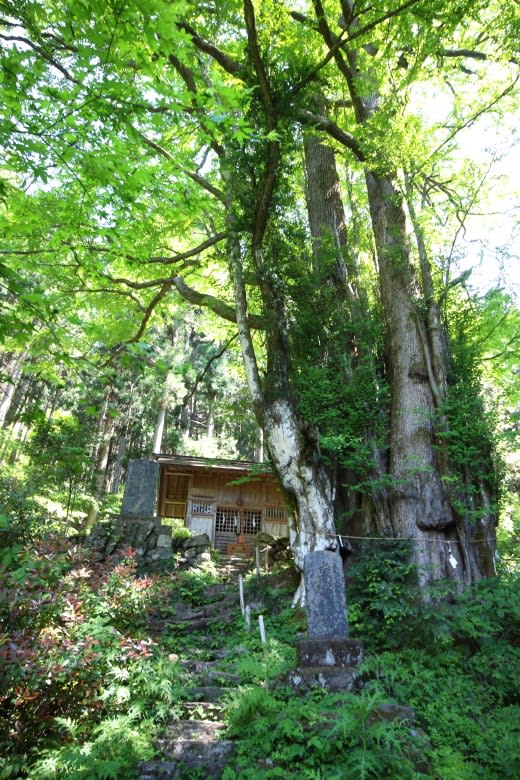今回は個人的に保護柵で囲った場所がどうなのか、その効果と植物の保護効果について述べたい。このブログの読者の方ならば私の行っている保護活動についてほぼご存知かと思うが、改めてここで総括してみたいと思う。
個人的に保護ネットを設置した山域は4ヶ所あり、うまくいっているところもあればそうでは無い場所もある。まずは効果のあった場所2ヶ所について記載する。
茅ヶ岳オキナグサ保護作戦
本来は毒草のはずなので食害とは無縁だったはずのオキナグサだが、咲き始めの花芽や出始めたばかりの新芽が食害に遭うようになり1輪も咲かせること無く終わってしまった年があった。3年間食べ続けられると絶滅してしまう危険性が高く、昨年の平成29年4月に保護柵を設置した。

平成27年5月、茅ヶ岳ではたくさんのオキナグサが咲いた。

茅ヶ岳のオキナグサ

ところが、平成28年4月には花どころか葉もほとんど見当たらない。

良く見れば出始めた新芽が食害に遭っていた。これはまずい。翌年の春、新芽が出る前に保護柵で囲うことにする。

平成29年4月に設置した保護柵。荷揚げと設置と補修のため3度現地に足を運んだ。

平成29年5月、食害に遭うことなく花が咲いた。上を向いて喜んでいるように見える茅ヶ岳のオキナグサ。

花数はだいぶ減ってしまっているがひとまずは保護に成功する。

保護柵は冬を越せずに倒壊してしまい、平成30年4月補修作業を行う。

補修して強化された柵。

平成30年5月、この年も食害に遭わずに花が咲いてくれた。

訪問時期が遅かったが、たくさん咲いてくれたオキナグサ。

前年の2倍くらいの花が咲いた。囲った甲斐があった。
茅ヶ岳のオキナグサ保護作戦は想定していた以上の効果が上がり、平成30年は前年を遥かに上回る数の花が咲いてくれた。直接の食害で花が咲かなくなった植物に対しては保護柵の効果が絶大であることがわかる。ただ、素人がやっている保護柵なので強化したつもりの保護柵だったが6月には既に部分的に倒壊してしまっている。食害に遭うのは新芽と花芽の頃なので今年はこれで良しとして、また来年の春に修復しなければならない。
カモメラン保護作戦
御坂山塊のカモメランであるが、盗掘も然ることながらそれ以上に鹿の食害による2次的な変化で山肌が乾燥化し、カモメランは花を咲かせなくなりさらには葉数も減少し始め、場所によっては消滅してしまった群落もある。人の踏み荒らしも目立つため平成29年5月に2ヶ所保護柵を設置して囲い込んだ。直接の食害は少なく、この囲い込み作戦でどこまで効果が出るのかはかなり疑問があったのだが、現時点でこれ以外に有効な手段は思いつかなかった。

平成26年6月、かつてはたくさん咲いていた御坂山塊のカモメランだが、その後減少の一途をたどる。

平成29年6月に設置した保護柵その1

同その2。こちらの場所はユキザサやツルシロカネソウ、ショウマ類など種々の植物を囲い込んだ。

平成28年に設置した人避けのロープ。人には有効だったが動物には全く無効だった。後に被害に遭うことになってしまう。

平成29年5月に設置した保護柵だが、なんとか一冬越してくれた。平成30年5月に撮影したもの。その後修復、補強作業を行った。

平成30年6月、保護柵の中のカモメラン。見事に咲いてくれた。囲う前の2年前が1株、囲った年の昨年が3株、そして今年は9株咲いてくれた。

囲いの中はこの山塊に特有なちょっと変わったカモメランが咲いている。

もう1ヶ所の柵の中も見事に咲いてくれた。

明らかに昨年よりは増えている。

それでは柵の外はどうなのだろうか?食害で食べられたと思われる花穂。

直接の葉の食害も散見される。

何よりも問題なのはこの乾燥化してしまった山肌だろう。

そして保護ロープで囲った場所は・・・平成29年8月に大規模な食害に遭ってほとんど葉が見られなくなってしまった。

平成29年8月の様子。足跡と思われる穴と食いちぎられたカモメランの葉。これで終わってしまったかと思ったが・・・

平成30年6月の様子。花はほとんど咲かなかったが根は残っていたようで葉は出てくれた。それでも前年の半分ほど、70株くらいに減ってしまった。

今後の食害を避けるために新たに保護柵で囲う。数年できっと復活してくれると信じている。
この場所のカモメランを見にやって来る登山者に配慮して保護ロープだけ張っておいた最大の群生地は鹿の食害で大打撃を受けてしまったが、根だけは残っていてくれたようでまだ救いはありそうである。他の2ヶ所は明らかに保護柵設置の効果が出ており、おそらくは食害に遭った場所も数年で復活してくれるだろうと信じている。保護柵を設置した当初はどれだけの効果が出るのか疑問があったのだが、設置後2年にして明らかな効果が出ていることが証明された。
花咲じじい作戦
この作戦は平成24年6月に花を咲かせて以来咲かなくなってしまった某所のアツモリソウを復活させて咲かせてやろうという作戦である。平成27年から作戦が始動し、今年で4年目を迎えるが残念ながら思ったほどの効果が上げられていない。

平成24年6月、3輪の花を咲かせたアツモリソウ。

今にして思えばこの時既に花の色が薄く元気が無い。危険信号を発していたのだろうが気付かなかった。

平成25年6月、葉は出たが花芽は付いていなかった。

平成26年6月、元気のない葉がなんとか出てくれたが・・・

その前の年からテンニンソウやスゲの除去作業を開始していたが、平成28年6月、とうとう何も出なくなってしまう。鹿の食害跡が目立つ。

平成29年4月、保護柵で囲い込む。

平成29年6月、なんとか葉が出てくれて一安心する。

平成30年6月、保護柵は破損無く一冬を越した。草が茂ったがテンニンソウが増えたように思う。

昨年以上に元気な葉を出してくれるだろうと期待していたのだが・・・今年は葉が出ていない。残念無念・・・。
前年の秋にもテンニンソウとスゲの除去作業を行ってはいたのだが、不十分だったのかも知れない。残念ながら今年はアツモリソウの葉が確認できなかった。株自体が年老いていて元気が無い可能性もあるのだがテンニンソウをはじめとする他の植物がはびこっていて栄養分を取られてしまっている可能性も高い。秋になったらもう少し丁寧に周辺の草を除去してまた来年に備えたいと思っている。
保護柵の効果は期待できるのだがそれが全てでは無く、植生維持のための手入れをしてやることも必要なのだと思う。しかしどれをどこまで除去すれば良いのか?除去を行うこと自体が植生を乱しているのではないか?など、植物の保護はわからないことだらけである。これからも十分な観察を行いつつ多方面からの情報を集めて保護について考えて行動しなければならないと思う。