来年の9月に山梨大学が主幹で鼻科学会なる全国学会が甲府市で開催される。そのポスターの画像を撮影するために、夜明けの富士山と月の位置をカシミール3Dとステラナビゲーターでずっとチェックしていた。撮影場所は山梨県内からで、山梨県らしい景色と富士山を追い求めている。8月18日の朝、高指山から見る富士山が一番良さそうだったのだが、この日は天候不良で富士山は見えず、翌日の朝を狙って高指山に撮影に行く計画を立てた。火星、土星、アンタレスが接近していることだし、未明に西に傾いた夏の大三角形も良さそうだ。テントを担いで山頂泊と考え、夕方6時ごろに山中湖に到着した。ところが、昼間は晴れていた空が一変し、真っ黒な雲が富士山周辺を覆い始め、ついには小雨が降り出してしまった。予定変更、山中湖湖畔で車中泊することにして車内を寝られる体制に整えた。すると夜の8時ごろになると、雲が晴れて星が見え始めた。間もなく東の空から月が昇り始めた。これならば山頂泊で大丈夫なのではないか?ということで、ザックにテントを詰め込んで8時半から高指山山頂を目指して登り始める。
中腹まで行くと霧雨が降り始めた。空を見上げると雲の切れ間から星が見えている。9時半、山頂に到着した頃には霧雨に小雨も混じるようになり、富士山は全く見えない。テントを設営するが、雨は降らないと見ていたのでフライシートを持ってこなかったため、当然の如くテントの中は結露して水浸しになってしまう。テントの中だというのにカッパを着て一夜を過ごすこととなる。

霧雨と小雨の高指山山頂。富士山は全く見えず。
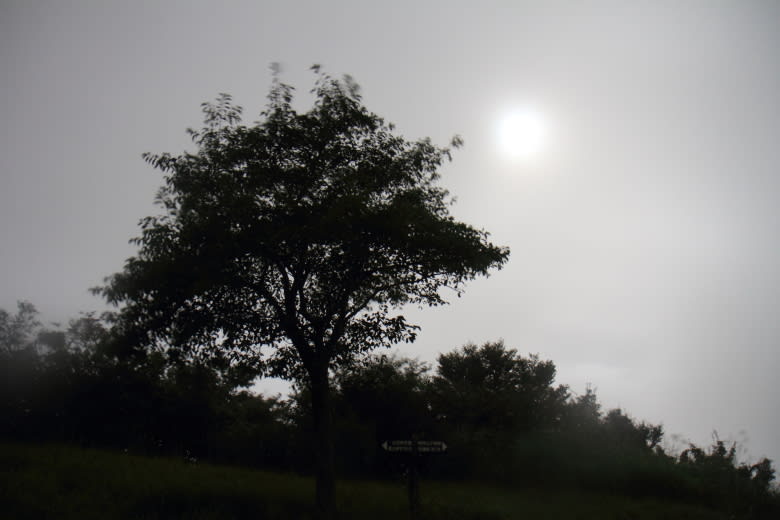
雲を透かして見える月。星も時々姿を現していた。
9時半ごろに富士山の左側に接近した火星・土星・アンタレスが輝いているはずだったのだがこれでは撮影は困難だ。天気予報と雲画像を見る限りでは未明から晴れてくれそうなので、明朝を期待して10時半に寝る。
未明3時半に目覚まし時計の音で目が覚める。外を見ると・・・霧雨だがだいぶ小降りになっている。残念ながら富士山は見えないが、軽く朝食をとって再び外に出ると月が見え始めていた。日の出までにはなんとか回復してくれそうに見える。

未明4時半の空。雲が多いが青空も見える。

やがて月が見え始めた。

4時45分、雲がだいぶ晴れてきた。日の出は5時2分ごろ、もう少し!

4時54分、笠雲を被った富士山が姿を現し始めた。

よし、なんとかなりそうだ。とこの時は思ったが・・・。

富士山の後ろ側にうっすらとアースシャドウが出ている。日の出目前、しかし雲が増えてきた。

ちょうど日の出の頃だが、残念ながら富士山は雲に覆われてしまった。

その後はさらに雲が増えて富士山は2度と姿を現すことは無かった。

残念、撤収。
ポスター用には縦位置で山中湖・富士山・月と良い位置に収まってくれたとおもうのだが、この雲では富士山の裾野が見えず、富士山なのかどうかが判別できず残念ながら使い物にならない。またの機会に月の位置を見て狙ってみたい。

この周辺にはヒオウギという稀少なアヤメの仲間が咲き、手厚く保護されている。

保護ネットの中で咲いたヒオウギ。鹿の食害を逃れるためには仕方ないのだが、これでは受粉出来ないのではないか?と疑問を持ってしまう。
中腹まで行くと霧雨が降り始めた。空を見上げると雲の切れ間から星が見えている。9時半、山頂に到着した頃には霧雨に小雨も混じるようになり、富士山は全く見えない。テントを設営するが、雨は降らないと見ていたのでフライシートを持ってこなかったため、当然の如くテントの中は結露して水浸しになってしまう。テントの中だというのにカッパを着て一夜を過ごすこととなる。

霧雨と小雨の高指山山頂。富士山は全く見えず。
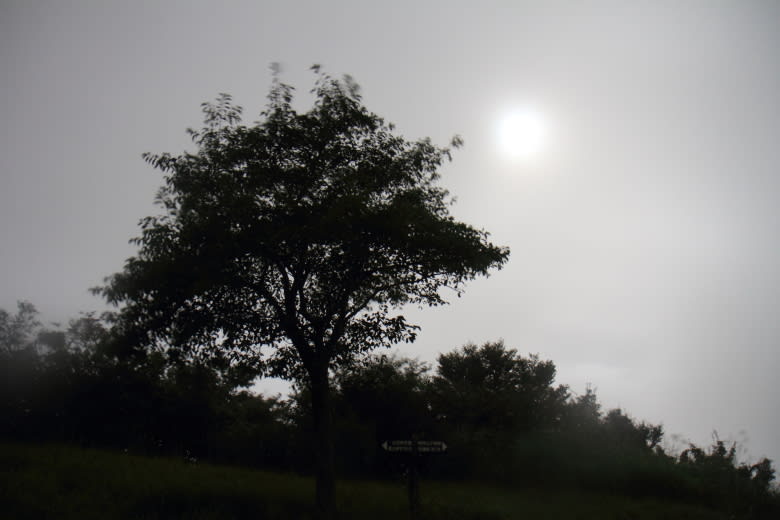
雲を透かして見える月。星も時々姿を現していた。
9時半ごろに富士山の左側に接近した火星・土星・アンタレスが輝いているはずだったのだがこれでは撮影は困難だ。天気予報と雲画像を見る限りでは未明から晴れてくれそうなので、明朝を期待して10時半に寝る。
未明3時半に目覚まし時計の音で目が覚める。外を見ると・・・霧雨だがだいぶ小降りになっている。残念ながら富士山は見えないが、軽く朝食をとって再び外に出ると月が見え始めていた。日の出までにはなんとか回復してくれそうに見える。

未明4時半の空。雲が多いが青空も見える。

やがて月が見え始めた。

4時45分、雲がだいぶ晴れてきた。日の出は5時2分ごろ、もう少し!

4時54分、笠雲を被った富士山が姿を現し始めた。

よし、なんとかなりそうだ。とこの時は思ったが・・・。

富士山の後ろ側にうっすらとアースシャドウが出ている。日の出目前、しかし雲が増えてきた。

ちょうど日の出の頃だが、残念ながら富士山は雲に覆われてしまった。

その後はさらに雲が増えて富士山は2度と姿を現すことは無かった。

残念、撤収。
ポスター用には縦位置で山中湖・富士山・月と良い位置に収まってくれたとおもうのだが、この雲では富士山の裾野が見えず、富士山なのかどうかが判別できず残念ながら使い物にならない。またの機会に月の位置を見て狙ってみたい。

この周辺にはヒオウギという稀少なアヤメの仲間が咲き、手厚く保護されている。

保護ネットの中で咲いたヒオウギ。鹿の食害を逃れるためには仕方ないのだが、これでは受粉出来ないのではないか?と疑問を持ってしまう。































































































































































































































































































































































































































