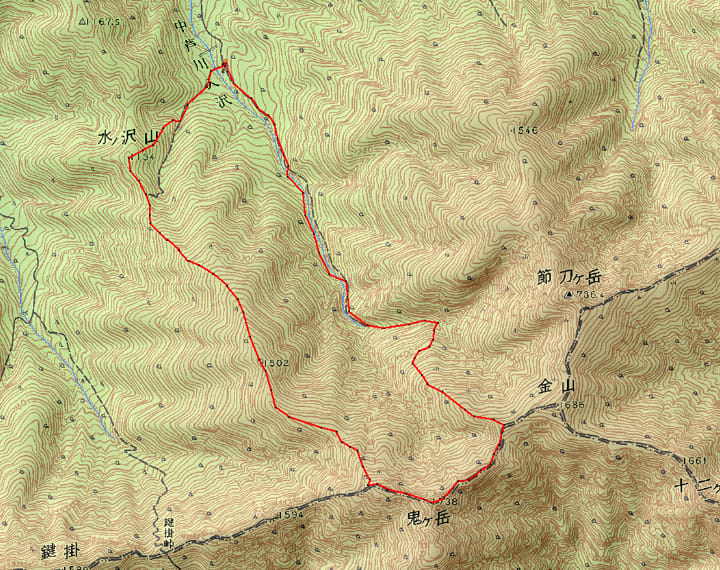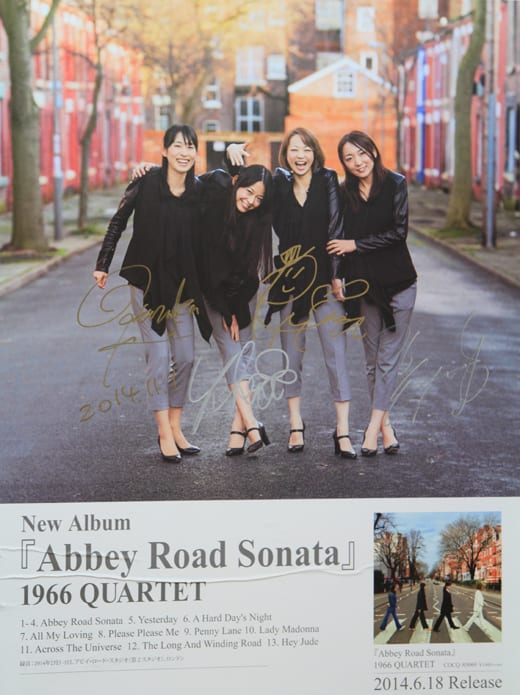初めて北海道遠征の時にクモキリソウを見たは凄いものを見つけたと思ったのだが、その後山梨の山でもあちらこちらに分布していて意外と容易に見られる花であることがわかってきた。一方、今回訪れるジ・ガ蜂・草は現在3ヶ所の自生する山を把握してはいるが決して数は多く無い。そして心配しているのは年々数が減っているように見えることだ。昨年観察に行った時はもしや盗掘なのでは?と思ったのだがそれにしてはおかしい。もっと見つけ易い場所があるのにそちらの株は無傷で盗掘された様子は無く、探しにくい場所で数を減らしている。掘られたような穴も無い。これは鹿の食害なのではないだろうか?

森の中にひっそりと咲いていたジ・ガ・蜂・ソウ。

別株

別株

こんな小さな株にも花をつけている。この一角はこの花にとって快適な場所なのだろう。

まさに蜂が飛ぶ花。

登山道脇で踏まれて痛んでしまった株もある。

まだ蕾のオオヤマサギソウ

オオヤマサギソウの葉はほとんどが虫に喰われている。

蕾のイチヤクソウ

ウメガサソウ。今年は一株しか見つからない。
昨年大株が咲いていた場所を訪れてみるが、残念ながら今年は見当たらない。周辺にも大きなものが何株かあったはずだが、中型の株を1株見つけただけで、さらにその先を探したが小さな株を数株見つけたのみだった。掘られたような痕跡は見つからない。鹿の保護柵設置の必要があるのかも知れない。

昨年の大株は消失しており、見つけたのはこの株のみ。

ジンバイソウ

穂を出したジンバイソウ。昨年は1本だけだったが、今年は5本出ている。花が咲くのが楽しみ。

林道脇に生えたクモキリソウ

こんなところで大丈夫なのか?と思ってしまうが、クモキリソウはこのようなセメントの上が好きなようだ。
やはり年々減少しているように見えるジ・ガ蜂・草、何らかの保護が必要なのかも知れない。山岳連盟自然保護グループに報告することとしたい。

森の中にひっそりと咲いていたジ・ガ・蜂・ソウ。

別株

別株

こんな小さな株にも花をつけている。この一角はこの花にとって快適な場所なのだろう。

まさに蜂が飛ぶ花。

登山道脇で踏まれて痛んでしまった株もある。

まだ蕾のオオヤマサギソウ

オオヤマサギソウの葉はほとんどが虫に喰われている。

蕾のイチヤクソウ

ウメガサソウ。今年は一株しか見つからない。
昨年大株が咲いていた場所を訪れてみるが、残念ながら今年は見当たらない。周辺にも大きなものが何株かあったはずだが、中型の株を1株見つけただけで、さらにその先を探したが小さな株を数株見つけたのみだった。掘られたような痕跡は見つからない。鹿の保護柵設置の必要があるのかも知れない。

昨年の大株は消失しており、見つけたのはこの株のみ。

ジンバイソウ

穂を出したジンバイソウ。昨年は1本だけだったが、今年は5本出ている。花が咲くのが楽しみ。

林道脇に生えたクモキリソウ

こんなところで大丈夫なのか?と思ってしまうが、クモキリソウはこのようなセメントの上が好きなようだ。
やはり年々減少しているように見えるジ・ガ蜂・草、何らかの保護が必要なのかも知れない。山岳連盟自然保護グループに報告することとしたい。