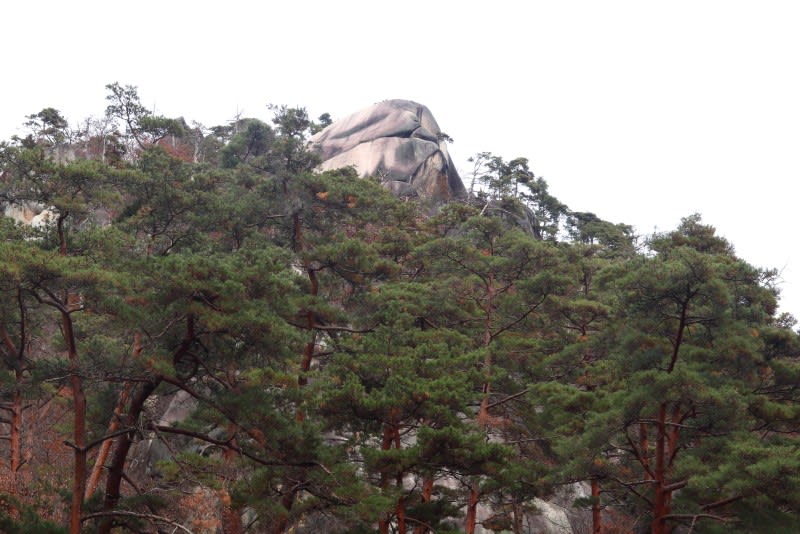シダを含めて植物は分からないことだらけである。ずっと分からないでいるのがミドリカナワラビとオニカナワラビの違いである。以前に見たものでミドリカナワラビだと思っていたシダは大部分がオニカナワラビなのではないかとずっと疑問を抱いている。おそらくじっくりと観察して、かつ季節を変えて見に行かないと答えは出ないのではないかと思っている。ヤマヒルが居ないこの季節の南部町は歩き易くて常緑のシダを観察するには良い季節ではあるが、反面痛んでいるシダが多くてソーラスが付いていないことがあるのが難点である。何度も訪問している場所であるが、果たしてこの2種類のシダの区別が出来るのかどうか、他にも見ておきたいシダが多数あり、訪問してみる。

林道脇に生えていたアリドオシ。山梨県では絶滅危惧種であるが、南部町に行くと良く見かける。

ヘラシダ。3年前に比べるとずいぶん大きくなった。

中肋と鈍角に付着する線状のソーラス

コモチシダ

この場所ではあまり多くは生育していない。このシダも南部町では比較的良く目にする。

フモトシダ。どこにでも普通にあるのであまり撮影したことが無いが、それなりに美しいシダである。

ナチシダ。南方系のシダであるが数年前に山梨県にも入り込んできた。

本来は常緑性のシダのはずだが、山梨県では冬期に大部分枯れるようだ。

ナガバノイタチシダ。ミヤマイタチシダに非常に良く似ている。西俣川や大城川で見たものもこれかも知れず、再確認の必要がありそうだ。

側面から見たナガバノイタチシダ。長い柄があるのが特徴である。

ソーラスは円形でやや大き目。
さて、問題のミドリカナワラビとオニカナワラビであるが、明らかにオニカナワラビと分かるものは何株か確認しており、まずはそれを見に行ってみる。

何度も見ている株。これはオニカナワラビで間違いない、はずだ。

頂羽片がはっきりしない。葉は光沢があり固めである。

ソーラスは裂片の中肋と辺縁の中間あたりに付着する。

鱗片は細くてこげ茶色、ないしは中央部が濃いこげ茶色をしている。

こちらがミドリカナワラビであろうと思って観察している個体である。まだ小型でなかなか成長して来ない。

やっとソーラスが確認出来た。先ほどのオニカナワラビに比べるとこちらの個体はソーラスが辺縁寄りに付着している。

鱗片はこげ茶色だが、やや幅が広い。しかし、図鑑に掲載されているほどの薄茶色の鱗片では無い。
さて、オニカナワラビは良いとして、今までミドリカナワラビと思って観察してきた個体は本当にミドリカナワラビなのかどうか?本来はかなり大きくなるはずのシダだが、あまりにも小さすぎる。ソーラスの位置は違うのだが、これが決め手として良いのかどうか?もう少し大きく成長するのを待ってから判定したいと思う。では本物のミドリカナワラビはどこにあるのだろうか?引き続き探索を続けたいと思う。

こちらもオニカナワラビ。このシダは栄養葉と胞子葉が不完全に分かれていることが分かってきた。下のほうに斜めに生えているのが栄養葉、光沢が強い。

胞子葉のソーラス。

典型的なオニカナワラビのソーラスで、裂片の中肋と辺縁の中間に付着する。

ところが、栄養葉と思わしき葉にソーラスが付着しているものがあった。これを見ると、ミドリカナワラビと思わしきものに良く似ている。どうなっているのか?

色気を出して沢を少し登ってみる。

ヒメカナワラビが生えていた。

あふれんばかりの山盛りソーラス。

鱗片は黒茶色で下向きに付着している。

群生していたヒメカナワラビ。このシダも南部町では比較的良く目にすることが分かってきた。

上流まで詰められそうだが、適当なところで撤退する。
ミドリカナワラビとオニカナワラビの判別にはもう少し時間がかかりそうである。典型的なミドリカナワラビを探し出して良く観察することが必用であろう。
もう1ヶ所、確認しておきたいシダがあって移動する。