半藤一利さんが亡くなりました。
つい最近も読んだばかりでした(保阪正康さんとの対談)『そして、メディアは日本を戦争に導いた』。
今、読んでいる丸谷才一さんの『月とメロン』にも登場します。
むろん、『決定版 日本のいちばん長い日』、『日露戦争史』など大部のものから軽い(といっては失礼ですが)ものなどけっこう濫読気味に。
何を隠そう、墨田区にある「曳舟図書館」(「京成曳舟」駅至近)には、墨田区ゆかりの作家として、半藤一利さんの作品がずらりと並んでいます。それを借りて読んだ、ということですが。
このブログでも何冊か取り上げました。追悼の意味で再掲。

自称(他称もありか。自他共に認める)歴史「探偵」・半藤一利さんの書。永井荷風の日記「断腸亭日乗」を題材に、荷風の同時代的昭和史を、ちょっと遅れてやってきた筆者が後追いしながら、昭和30年代までの自己史をも語るという趣。
後書きで、ご本人は「荷風さんの昭和」という題名が気に入っているようですが、読後感としては、初出の時のように「荷風さんと『昭和』を歩く」という方が適切な感じがします。
戦争へ、破滅へと進んでいった「乱世」の日本、昭和3(1928)年~昭和20(1945)年。その時代を荷風の日記を基としながらそこから派生した話題を披露していく(歴史の裏側・真実を探偵していく)、という変幻自在な文章タッチ。恐れ多くも天下の文人・荷風さんを旅先案内人(杖代わり)にしてとは、大胆不敵です。
P278の「付記」
『日乗』原本の扉の表記が昭和16年8月以降から「昭和」が追放され、西暦で統一されているという。荷風の魂はもはや日本から離れ、西欧とくにフランスこそが自分の精神の故郷と、この扉の表記で示したのであろうか。ふたたび「昭和」が原本の扉に記されるのは昭和21年、日本占領がはじまってからである。おおかたの日本人が日本の過去をぶざまにののしりだしたとき、荷風の心はかえって日本へ向いたというのであろう。この壮大なへそ曲がりを見よ、である。
このあたりが、半藤さんの「荷風」像の基と言えそうです。そして、ご自身のスタンスでもあるか。向島に生まれ、隅田川の産湯につかったご自身の、失われた(つつある)地域社会への熱い思いを語っていきます。
俗世間にあって、その世界から超越しつつ、遠く、広く世界を歴史(未来)を見透かしていた荷風。その荷風の孤独な晩年の言動を尊敬の眼差しで(それでいて記者としての目はぬかりない)見つめる半藤さんの血気盛んな、若き頃。その頃から、こうして自らも半生を振り返る時期が迫ったときに、改めて荷風の偉大さに気づかされる、そんな思いが伝わってきます。
読者の一人としては、隅田川、浅草、向島・・・、長年なじんできた土地でもあるので、よりおもしろさが増してきました。

半藤一利。東京下町生まれ。東京大空襲の体験も。「文藝春秋」に所属していたこともあり、一頃は保守派の論客でしたが(今も?)、太平洋戦争当時の日本軍部(特に日本陸軍)及び靖国神社におけるA級戦犯の合祀には極めて批判的で、昭和天皇の戦争責任についても否定していません。また近年は護憲派としての活動を積極的に行っています。
そのため、保守派のドン(?)西尾幹二などから手厳しく批判されています。
対する保阪正康。第二次世界大戦当時の軍部については極めて批判的であり、「大東亜戦争は自衛の戦争」と主張する靖国神社にも否定的。そのため総理大臣の靖国神社参拝にも極めて批判的で、一般人の靖国神社参拝についても「個人の自由」としながらも、「靖国神社に参拝することは靖国神社の主張を受け入れるということだ」と批判的です。
これもまた、保守派論壇からは批判も多く、小林よしのりからは、当時の国際関係を無視しての、当事者の聞き書きスタイルの歴史観は、「蛸壺史観」とやはり手厳しい(どっちがそうなのか、と思いますが)。
この二人。反対の立場から言わせれば、「俗人」(世俗)受けする歴史観の持ち主?
いずれにせよ、保守派からは目の敵に近い存在。戦争の犠牲となった自国の民衆、朝鮮半島をはじめ、他国の人々の目線から歴史を読み解くなどというのは、正統派歴史学者から言わせれば邪道なのかもしれません。
かといって、西尾や小林の依拠する(きちんと学んだのだか、考えもせずに受け入れただけなのか、わかりませんが)、説く歴史観も、またきわめて偏っているとしか思えません。
そこでこの書。とことん彼らが忌み嫌う、俗物受けするタイトル(小見出しで)で対談しようという、ある意味、痛快な小気味よい対談集になっています。その志たるやよし!
だから、昭和を点検すると題していても、その内容は昭和20年8月15日敗戦に至るまでの「戦前昭和」を点検する、という内容になっていて、ま、反対派の「こいつら、また何を勝手なことを、俗受けする言葉で言い出すか」という手ぐすね引いて待っている連中をちょっと手玉にかけている、といった風情です。これが、お見事です。
さて、対談の内容は、日本が負けることは明らかだったのに、どうして昭和20(1945)年8月15日まで続いたのか、とりわけ「ポツダム宣言」受諾まで20日間。この間に広島・長崎の原爆をはじめ、どれほど多くの犠牲が出たか・・・。そこにまで次第に話を狭めていくかたちになっています。
では、何が「失敗の本質」であったのか。「どうせ」「いっそ」「せめて」。このありふれた言葉をもとに、半藤さんが他の書で昭和前史を読み解いていったわけですが(むしろ日本人の心性が、この三語によって括られる、とのことで)、その続編という趣です。まさに対談のなかでのベーシックなキーワードとなっています。
この対談では、この三つの言葉の他に、「世界の大勢」「この際だから」「ウチはウチ」「それはおまえの仕事だろう」「しかたなかった」の五つ。
証拠隠滅とか公文書の破棄とかで、資料も実は乏しい昭和戦争史。それは今でもなお闇の中のものも多いのです。そうした中での、ある意味、歴史を「探偵する」、そういうおもしろさがあります。その手法の中で、続々と登場する人物の発言、人となり、責任感、責任回避、黙殺、・・・、生身の人間像が浮かび上がっていきます。
そうして読み進むうちに、実はこの対談は、けっしてかつての敗戦という結果に至った、戦ばなしではないことに気づかされます。
今の官僚機構。役所や組織の体質、政治家の処世・・・。特に五つのキーワードがずばり大きく言えば、今の日本の政治状況、国際関係などの混乱につながっている体質。勤め先の上司の姿勢、無責任体制、成果主義、結果オーライ・・・、などまったく60年以上も少しも変わっていないことに気づきます。
特に身近な官僚組織。個人的な思惑だけで、組織を勝手に動かし、計算尽くの人間関係がかえって無責任体制を生み、誇大報告(失敗を隠蔽し)で上司をだまし、縦割り組織の中で見て見ぬふりをする、他の部署の過ちを冷笑する、「ホウ・レン・ソウ」が根回しにすり替わり、そして、上も、中間も、ぜったいに責任を取らない、部下にその損失・失敗を押しつける・・・、そんな組織が今もはびこっている。ここに目を向けなければならないなのに、誰も気づいていて言わない! そこに歴史の悲劇があり、教訓があるはずなのですが。

「昭和史の語り部」半藤さんのあちこちで発表された文章をまとめたもの。発表時期は1973年から2007年まで。表題のような括りで、ひとまとめにしてある。
そこに見えるのは、一貫性ということである。歴史観というか、歴史の見方が一貫していることに驚嘆さえ感じる。ここに、筆者の面目躍如たる所以がある。
歴史における「真」と「実」の問題。事実としての「実」はちょっと資料を探れば手に当たる。しかし「真」は、多くを読み、調べたところで簡単に手に入るものではない。常に歴史に親しみ、追体験し、想像力をふくらませ、よく考えながら育成していく「歴史を見る眼」の問題。自分の見方をもつことなくしては、歴史を楽しみ、そこから意義や教訓を多く引きだすことができない。
このように喝破する筆者。長年の編集者としての眼が養った、確信から生み出されたものである。
では、何が「失敗の本質」であったのか。「どうせ」「いっそ」「せめて」。
すでに昭和20年に入って日本が負けることは明らかだったのに8月15日まで続いたのか、とりわけ「ポツダム宣言」受諾まで20日間。この間に広島・長崎の原爆をはじめどれほど多くの犠牲が出たか・・・。
このあたりの実証的な分析が見事だった。学者でもなく、評論家でもなく、たんなる一市民の目でなく、複眼的な評論姿勢がすばらしい。

吉川英治の小説「三国志」。高校のころ読んだことがあったが、長じてから、ずっと後に書かれた横山光輝の漫画「三国志」。。長編の漫画で、何十巻あったかしら、次々と買い込んでは私のようないい大人も読んでいた。それからゲームの「三国志」(私はやらなかったが、ちょっとした大人も夢中になっていたそうだ)。こうみると、世代を超えて人気のある物語が、「三国志」のよう。
本場の中国でも京劇でさかんに演じられる。かつて日本に来た京劇で関羽にまつわるものを観たことが。あの独特の、キーの高い発声と賑やかな音楽と派手な立ち居振る舞いに圧倒されたことをふと想い出した。
この本は、画家の安野さんが「繪本三国志」の出版記念に企画された、作家の半藤さんとの対談集。 談論風発。お二人の自在な対談が楽しめる。
現地に取材して中国の悠久の大地に根ざし、栄枯盛衰の時代に目を向けた対話の妙から始まり、歴史観、人物観など時に日本の戦国時代の武将像や明治以降の軍部のあり方など、時空を越えた対談が興味を大いに誘った。
3世紀に書かれた古い歴史書の「三国志」(正史)そのものよりも、14世紀に書かれた小説の「三国志演義」のほうが一般的にはなじみが深かったらしい。何しろ、蜀の興隆と滅亡の歴史が中心。劉備玄徳や諸葛亮孔明など多彩な登場人物が織りなす、感動のドラマ仕立てだから。三国のうち、魏や呉は旗色が悪かった。お二人は、それをふまえた上で、教養豊かな三国志論を語り合っている。それでいて、コンパクトに仕上がっている。安野さんの絵も、小さいながらいくつも紹介されている。味わい深い絵の数々。・・・
(本の写真は、すべてAmazonより)










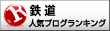


 」HPさんの訪問記事。
」HPさんの訪問記事。

 エンブレムがすてきね。
エンブレムがすてきね。



 1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。
1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。











 「道の起点としての日本橋」。
「道の起点としての日本橋」。 







 明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)
明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)

 「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。
「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。 「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。
「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。 「日本橋魚河岸」。
「日本橋魚河岸」。 「両替商の街」。
「両替商の街」。 「昔からある店」寿司貞。
「昔からある店」寿司貞。
 (「
(「 」HPより)
」HPより)




 (「首都高速道路日本橋区地下化事業」HPより)
(「首都高速道路日本橋区地下化事業」HPより) 「日本橋」付近。
「日本橋」付近。 「日本橋川」。
「日本橋川」。













 『名所江戸百景』「鎧の渡し小網町」。歌川広重画。谷崎が描いたように、
『名所江戸百景』「鎧の渡し小網町」。歌川広重画。谷崎が描いたように、

 クレヨン、サインペン、シャープペンシル・・・。けっこうお世話になっているわよね。
クレヨン、サインペン、シャープペンシル・・・。けっこうお世話になっているわよね。





 たしかに独特の橋のかたちだわね。
たしかに独特の橋のかたちだわね。



 (写真は、「Wikipedia」より)
(写真は、「Wikipedia」より)






 歌川広重「東都名所永代橋全図」
歌川広重「東都名所永代橋全図」 栄泉「東都永代橋之景」。
栄泉「東都永代橋之景」。 奥に「日本IBM箱崎ビル」。
奥に「日本IBM箱崎ビル」。 「隅田川」、「日本橋川」、「亀島川」に囲まれたところが、「霊岸島」ね。
「隅田川」、「日本橋川」、「亀島川」に囲まれたところが、「霊岸島」ね。






 2010年代のようす。島の縦横に幹線道路。
2010年代のようす。島の縦横に幹線道路。






 2010年代のようす。架かる橋は、「清洲橋」。 「箱崎JCT」付近
2010年代のようす。架かる橋は、「清洲橋」。 「箱崎JCT」付近





