つい先日まで満開だった桜は、もう8割位散ってしまいました。桜の前に咲いていたユスラウメは小さな緑色の実ができています。桜,梅,ユスラウメなどの代わりに、今度はハナズオウ(花蘇芳)が満開です。桃よりもさらに濃いピンク色の花がびっしりと枝に付いています。4月初めは、咲く花が次々へ入れ替わります。
濃いピンク色の花びらが枝にびっしりのハナズオウ(花蘇芳)
ハナズオウ(花蘇芳)はマメ科です。花びらをよく見ると豆特有の形をしています。実もマメ科特有の莢ができて、その莢の中に並ぶように実が入っています。一方、山では山ツツジが満開です。桜ほど大木にならず、ちょうど視線の高さで咲きます。このため、山道の周りの山ツツジは観賞するには最適です。
マメ科特有の花びらがびっしり やさしいピンク色の山ツツジ

我家はもともと桜をあまり植えていませんでした。その代わり、山ツツジが普通に山にたくさん生えていました。このため昔は、この時期になると山ツツジで山全体がピンク色になりました。
山ツツジは桜のように大木になりません。また花びらは桜のように風に舞い散ることがありません。ポトリと地面に落ちるのです。このため、桜吹雪と例えられる散り際が綺麗な桜の方が好まれます。これらの理由により、田布施町全体でも山ツツジよりも桜の方が目立つようになりました。山ツツジは桜より病気に強く、世話いらずなのですが。
昔は山全体に咲いていた山ツツジ
今年も、田布施町 麻郷 高塔の祇園牛頭天王社の祭典がありました。一昨年の祭典と去年の祭典は天候に恵まれて、石鳥居(186年前の文政11年1828年建立)がある祇園牛頭天王社で祭典がありました。しかし、今年は雨に降られたため高塔公会堂での祭典です。昨日は発明クラブの開講式に行かなくてはならなかったため祭典の準備のお手伝いに行けませんでした。祭典当日朝9時頃に行って、少しですがポン菓子などのお手伝いをしました。
雨が降りしきる祭典当日、祭典開始1時間位前
ポン菓子製造機で作った膨れたお米を大きなザルに入れるとすぐに、溶かした砂糖液を振りかけました。そして、素早くへらで砂糖が全体に行き渡るようにかき混ぜました。しかし、なかなかサラサラしてきません。雨が降って湿気が強いのか、熱いためだと思います。1年以上ポン菓子を手伝っていないと、こつを忘れてしまいます。そのうちベテランの女性に交代しました。
もうすぐポン菓子製造機を暴発 赤くした砂糖液をポン菓子にかけ混ぜる

私が子供の頃のことですが、冬になるとポン菓子専業者が村々にやって来ました。空き地にポン菓子製造機を置いて、子供達を待っていました。確か、お米と駄賃を渡すとポン菓子を製造してくれたように思います。火は今のようなガスではなく、薪だったように覚えています。お米以外にもトウモロコシを膨らませてポップコーンも作ってくれたように記憶しています。
完成したポン菓子を袋に詰めているお母さん方
10時頃、高松八幡宮の宮司さんが高塔公会堂に来られました。祇園牛頭天王社の祭典の始まりです。小学新一年生を前に宮司さんのお祓いです。今年は、12人もの新一年生です。麻郷小学校の新1年生が確か33人だったように聞いていますので、新一年生の1/3が高塔区の子供達です。今年はとても新一年生が多いです。私が子供の頃(昭和30年代)の高塔区は35世帯位しかありませんでした。しかし、今は約230世帯の方が暮らしており、田布施で一番多い地区とのことです。隔世の感があります。
新一年生12人を前に宮司さんのお祓い
宮司さんのお祓いなどが滞りなく済むと、お祭りは俄然賑やかになりました。ポン菓子を食べたり、綿菓子を楽しんだり、お汁粉などを堪能しました。雨が降らなければ広場で玉入れなどの余興を楽しむことができたのでしょうが、今年は雨が降りましたので公会堂やテント内で行える行事だけです。
綿菓子作りを楽しむ子供達 美味しそうな白玉入りお汁粉

私はもっぱら、お汁粉を配ったり、出たゴミを集めたりしました。その合間をみて、お汁粉を食べたり、綿菓子のかけらを摘まんで甘みを楽しみました。雨が降り続いていましたので、公会堂やテント内はとても混雑しました。しかしながら、皆さんの笑顔が絶えず、とても良かった祭典ではなかったかと思います。
お汁粉を作り盛るAさん、いつもいつもご苦労様
祭典が終わると片づけです。ポン菓子製造機や綿菓子製造機を綺麗に清掃して片付けました。長椅子なども畳みました。ただし、雨で濡れているテントは後日晴れた日に有志が集まって畳みます。
全ての後始末が終わると、お手伝いした方々が高塔公会堂内に集合しました。そして談笑しながら反省会などをしました。今年の一番の話題は、新一年生に関わることだったとのこと。これだけ世帯数,班数,子供数が多いと行き違いのリスクが高まるようです。
最後、余った景品をあみだくじで分けました。雨にも関わらず、予定通り楽しく祭典が終わって良かったです。参加された方々、お手伝いされた方々、お疲れ様でした。
綿菓子製造機、イスなどの片づけ 余った景品を皆さんで分ける

少年少女発明クラブと言うのものがあることを、何かで読むか聞くかで知っていました。去年、田布施にもそのようなクラブがあることを知りました。そして、その指導者の一人が、私が中学生時代に所属していた科学クラブ顧問だった森山先生であることを初めて知りました。
先日、約45年ぶりに森山先生に郷土館で再会しました。そして、当時の科学クラブで空中浮遊する乗用ホバークラフトを3年がかりで自主制作したことを懐かしくお話ししました。その森山先生、ご高齢のためかお体の調子が思わしくないとのこと。少しでも森山先生をお手伝いする意味で、この田布施町少年少女発明クラブのお世話をさせていただくことになりました。私は、3人の子供達と一緒に活動することになりました。( )付きで森山先生と西本先生の名前がありました。よろしくお願い致します。
少年少女発明クラブで配られた資料の一部
解散後、他の指導者の方々と談笑しました。そして、子供達の置かれている環境を少しばかりお聞きしました。昔の子供と今の子供では、置かれている環境に雲泥の差があるようです。私が子供の頃はまだ日本全体が貧しく、何か使えそうな物がないかゴミ捨て場をよくあさったものでした。たまに壊れた扇風機や真空管などを見つけると大喜びでした。今は、おおむね購入できるなど容易に手に入れることができるようで、とても恵まれているように思います。
子供達と同じ目線になることができるように、子供向けの発明ヒントに関する本を2冊借りました。どれもカラーでとても分かりやすく書かれています。今後、2回/月の活動です。指導すると言うよりも、子供達の自主性を高めるように支援又は見守りしようかと思っています。
ところで、異論もあるでしょうが、昔の田布施と比べて子供の置かれている環境がずいぶんと良くなっていると感じました。スポーツセンターなどによる子供関連スポーツ振興活動,山城太鼓や少年少女合唱団などによる文化振興活動,この少年少女発明クラブなどのような知の創出活動,そして郷土館などによる郷土愛を育む活動、などなどです。私見ですが、田布施はバランス良く子供達を育成しているように思います。
借りた2冊の発明ヒント集 開講式があった西田布施小学校

健康ウォーキングクラブは毎月の初め、いつもは田布施高齢者いきいき館で打ち合わせをしています。ウォーキング以外でも各家に招かれるなどお世話になっているため、今回は我家ですることにしました。桜の花びらが舞い散る中で、野外にテーブルを広げて打ち合わせをしました。
野外パーティー形式打ち合わせ、左からFさん,Tさん,N君,Eさん,そしてO君
最初、会食パーティーとなりました。手料理を持ってきていただいたTさん,Eさん,そしてN君、本当にありがとうございました。携帯コンロを使って貝汁を作るなど、数々の料理をご馳走になりました。7人が参加しての、楽しい野外パーティー形式の打ち合わせです。
Tさん,Eさん,そしてN君の手料理に舌鼓、美味しい! 
楽しい食事が終わった頃、先月の琴石山ウォーキングの振り返りをしました。一つの反省点として、9:30集合を10時集合と間違えた方がいました。このため、今後の案内ハガキでは集合時間を太字にするか赤字にして目立つようにすることにしました。次に、20日の呉麓山とひかり観音ウォーキングの下見報告をしました。そして、5月11日の祝島ウォーキングと5月18日の田布施町小行司周辺を巡る田布施川源流ウォーキングの説明をしました。
打ち合わせが終わる頃、I君参加 整備中の裏山をのんびり散策

打ち合わせが終わる頃、仕事のためTさんが帰り、入れ替わるようにI君がやって来ました。談笑後、我家の裏山を散策しました。桜はだいぶ散っていましたが、ピンク色が濃い山ツツジが咲き始めていました。やや歩きにくい山道をのんびり散策しました。山の上からN君宅の屋根が直下に見下ろせました。50年位前、N君も私もこの山でチャンバラごっこなどをしながら走り回ってよく遊んだものです。
裏山は去年から、雑木を伐採するなど整備を続けています。そして農作業小屋も、近いうちに囲炉裏か暖炉を設けようと思っています。そうすれば、冬でも皆さんに楽しんでもらえると思っています。
左より、Fさん,Eさん,N君,私
90cmごとに細断した椎茸(しいたけ)用の原木に、種駒(椎茸菌)を打ち込みました。最初に、種駒を打ち込む穴の位置(原木の表面約4cmx10cmの面積ごとに1個)を決めました。
私は次のようにして位置決めをしています。最初に原木の幹回りの長さ(外周)を計り、その値を8cmで割ります。その値で幹の切断面を分割するようにチョークで印を付けます。例えば、下左画像の幹の外周は約50cmです。50/8=約6です。そして、下右画像のように値6で幹の直径を6等分するようにチョークで印を付けます。
幹周りの長さや約50cm 幹の切断面を6等分

次に原木の円柱線上に20cmごとにチョークでマーキングします。そして、隣り4cmの円柱線上に、今度は5cmずれて20cmごとにマーキングします。このようにして6 x 4 x 2 = 48箇所にマーキングします。このマーキングした箇所すべてに穴を開けるのです。
原木の円柱面に、チョークで20cm間隔でマーキング
マーキングした個所に穴を開けるには、二つの方法があります。昔は、専用の金槌のようにものを原木を打ち込んで穴を開けていました。今は、電気ドリルで穴を開けます。電気ドリルを使った方が、正確に早く疲れることなく穴を開けることができます。ただし、電気ドリルは、電気が来ない山の中では使えません。充電式ドリルも良いのですが、すぐに充電池が無くなってしまいます。このため、打ち込み式か,電気ドリルか,または充電式電気ドリルかは、植菌する場所と穴を開ける数によって最適なものを選びます。
打ち込み式金槌を使って穴開け 電気ドリルで穴開け

最初打ち込み式金槌を使って穴を開けていましたが、何個もの原木に穴を開けていると、腕が疲れてきました。疲れてくると、穴あけの位置がずれてきます。このため、途中から電気ドリルを使って穴あけしました。やっぱり電動ドリルは楽です。
開けた穴に、椎茸菌の駒を打ち込む
穴開けが終わると、椎茸菌の駒を丁寧に打ち込みました。駒には椎茸の菌がびっしりと生えていて白い菌で覆われています。この菌が駒から原木に移り、、2年後頃に原木全体に菌が生えると椎茸が収穫できるのです。植菌した原木は仮伏せして、上から黒い遮光ネットで覆っておきました。
去年の3月に植菌した原木の皮を試しに一部剥がしてみると、白い菌らしきものがびっしり見えました。早ければこの秋に椎茸が収穫できそう。植菌から2年後頃に収穫とは、椎茸栽培はとても気の長い農業です。
原木を仮伏せして遮光ネットで覆う 去年植菌した原木、この秋収穫できるか 

田布施町庁舎近くのあいさつ橋で田布施川を外れ、用事のある山口銀行に行きました。銀行の用事を済ませると、再びあいさつ橋に戻って田布施川をさらに上流に向けて歩きました。
あいさつ橋~新定位堰のコースと史跡
ところで、あいさつ橋から少し20m位砂田交差点方面に行った場所にお地蔵様があります。このお地蔵様、私が中学高校の時も同じ場所にありました。しかし、不思議な事に向きが180°反対なのです。私が中学生の頃は道路側を向いていましたが、今は歩道側を向いています。道路工事のさい、歩く人の方に向きを変えたのでしょう。
向きが180°変わっていたお地蔵様 田布施幼稚園裏の石碑

山口銀行の用事を済ませると、再び田布施川沿いに上流を目指して歩きました。桜の並木を過ぎた頃、右手に龍厳寺と田布施幼稚園が見えてきました。赤茶色の屋根側はとても立派です。その幼稚園の北側に接するように昭和15年建立の石碑が建っていました。このお寺の創建に関することと思われることが書いてありました。岩城山と彫られていますが、石城山の間違いではないでしょうか?
昔はお寺が経営する幼稚園があちこちにありました。今でも幼稚園を経営していると思われるこの龍厳寺はとても稀有な存在です。幼稚園前の広場で幼児たちが元気に遊んでいました。はきはきとした、良い挨拶をしてくれました。
赤茶色の屋根瓦がとても立派な龍厳寺
龍厳寺から田布施川の堤防に戻ると、再び上流に向けて歩きました。この付近は、江戸時代に田布施川の向きを変えた場所です。江戸時代前期まで、田布施川の本流は薬師川として田布施町の街中を流れていました。そして、灸川に流れ込んでいました。
江戸時代は、この薬師川から灸川や堀川を経由して瀬戸内海へ通じる船での物流が盛んでした。航空写真を見ると、かつて薬師川の川幅が広かったことが分かります。法寺坊近くに船が係留されていた船回しがあったそうです。
龍厳寺から上流に向かう 昭和11年定堰耕地整理の石碑

田布施川の流れを変えた場所は、台風などでよく決壊したようです。最後に決壊したのは、昭和25年のキジヤ台風の時のようです。この時は、田布施の街が水浸しになったとか。この災害を契機に昭和30年、田布施川の川幅が拡張されました。
江戸時代に田布施川の流れを変えて以降、川幅を広げたり定期的に浚渫を繰り返しています。自然を改造した結果、維持するコストもそれなりにかかるようです。
薬師川に水を取り込む取水口 田布施川に関わる竣工の石碑

新定位堰傍に昭和20年代竣工の石碑があります。文字が読みにくいため分からないのですが、田布施川に関する竣工の石碑だと思われます。その石碑から上流側30m位の道脇に2体のお地蔵様が安置されています。詳細な文字が刻まれていないため、何のために安置されてのかは分かりません。水害か何らかの災害にあった方々を弔うためではないかと思われます。いつかこの近くに住む古老に聞いてみたいと思います。時間をみて、古い石碑の拓本を取るなどしてみようと思います。
瀬戸地区の道路脇に安置された2体のお地蔵様
※
八海をスタートして田布施川左岸の堤防を上流に向かって歩き、新開橋から引き返して右岸の堤防を歩いて八海へ戻りました。途中、田布施川沿いの史跡や神社仏閣を訪ねました。歩いたコースを7ヶ所に分けました。それぞれをクリックしてください。
(1/7)八海天神社~こくぼ橋 (2/7)平生湾~灸川河口
(3/7)川添橋~旧関戸橋 (4/7)あいさつ橋~新定位堰
(5/7)水戸橋~詩情公園 (6/7)田布施町庁舎~旧関戸橋
(7/7)川添橋~八海公会堂
田布施川沿い史跡巡り往復ウォーキングコースの概略
私の友達であるYさんとEさんとで、大波野の坪曽,天王原,そして上段にある古墳や史跡を巡るミニウォーキングをしました。途中、N君と合流しました。早朝はとても寒かったのですが、朝日が眩しいほどに照っていました。このため、昼は暖かくなると思われたため、あまり厚着して出かけませんでした。
誓立寺から納蔵原古墳へ向かう道 納蔵原古墳の後円墳部 

最初、9:00に交流館に集合しました。そして、車1台に私を含む3人が載って大波野の誓立寺に向かいました。誓立寺に着くと、納蔵原古墳に向かいました。ありがたいことに誓立寺のご住職のTさんに古墳を案内していただくことになりました。お忙しいところ、ありがとうございました。
納蔵原古墳に向かう途中、誓立寺の納骨式典会場の横を通りました。何人かの檀家さんが草取りなどをしていました。その中に中学同級生のKさんがいました。彼は今、総代をしているそうです。納骨式典会場を通り過ぎてしばらくすると、納蔵原古墳です。納蔵原古墳に着いた頃、N君がやって来ました。
納蔵原古墳の前方墳部 暗い石室内部

納蔵原古墳は前方後円墳です。最初円墳部に登って、次に後方部を歩いてみました。長さ13m位の小型の古墳です。この古墳から出土した遺物は、田布施町郷土館に展示してあります。郷土館に勤めている関係で、今回この実物の古墳を見て良かったです。
この古墳は、大波野地区を支配していた族長のお墓なのでしょう。この古墳は古墳時代の後期に作られたようで、古墳の形式からして当時の大和朝廷となんらかの関係があったのでしょうか。
納蔵原古墳の石室前にて、右から誓立寺ご住職のTさん,N君,私,前はEさん
納蔵原古墳を見学し終わると、来た道を戻って天王原古墳に行きました。途中、古道に立っている道しるべの石塔を見ました。昔の人はこの石塔を見て、余田,塩田,または宿井方面に向かったようです。いったん誓立寺に戻って、天王原古墳の案内標識に沿って行きました。
余田,塩田等を示す道しるべの石塔 天王原古墳への案内標識

納蔵原古墳と比べて、天王原古墳は石室がわずかに残っているだけで、かつて石室を覆っていた墳土は跡形もありませんでした。よく前方後円墳だとよく分かったものです。
石室は素人目には並んだ庭石のようにしか見えません。石室の上を覆っていた石が落下しているようにも見えました。古墳,奈良,鎌倉,室町,江戸,そして明治と少しずつ壊されてしまったのでしょう。人が住みやすい場所に作られた古墳は少しずつ破壊されていくようです。不便な場所に作られた古墳だけが、千百年後の今も残るようです。
大きめの庭石にしか見えない天王原古墳の石室
坪曽は河岸段丘になっているため、古代において余田方面に広がる海岸を見下ろせたと思われます。古代の住人は坪曽や天王原に住んで、河岸段丘下に広がるの海に漁に出たのではないでしょうか。
坪曽を後にして、次に大波野の広大な田んぼに出ました。古代海岸だった大波野を想像してみました。この海辺はとても豊かだったでしょう。古墳を建てることができる豪族がいてもおかしくありません。田んぼに出ると、明地遺跡の場所を探しました。
明地遺跡の分銅形土製品が出土した場所に立つ
明地遺跡は大波野の田んぼを圃場整備した時に発掘した遺跡です。古墳のように特定の場所ではありません。田んぼ全体に住居跡などの遺跡が散在していたようです。今回、郷土館にレプリカが置いてある分銅形土製品が発掘された場所を特定しました。その場所は田んぼの真ん中です。まだ代かき前でしたので、出土場所を、かろうじて歩くことができました。
明地遺跡にて、左からYさん,私,N君 魚がたくさん泳いでいた灸川

明地遺跡は、有名な分銅形土製品が出土した遺跡です。せめてこの出土付近の道か畔に石碑でも立ててあればと思います。後世になってその場所が分からなくなっては惜しいことです。ところで、この遺跡近くの農道は、農閑期を除けばとても良いハイキングコースでないかと思いました。
納蔵原古墳,天王原古墳,そして明地遺跡の位置
明地遺跡の次は、大波野の上段にあるため池の史跡に行きました。このため池は、江戸時代に大波野の日照り時に備えて作られた池です。その後、昭和になって近代的なため池に作り替えられました。
昭和13年工事の碑 大波野を守るための神社

大波野の上段に住む方から、このため池そばある小さな神社の話をお聞きしました。その神社は山の向こうからやってくる悪しき霊から大波野を守るために建てられたそうです。その神社は、ため池脇にひっそりと建っていました。石鳥居に文政と書かれていました。江戸時代後期に建立されたのでしょう。
大波野を向いて建つ、堰の中央に置かれた石碑
江戸時代にため池を立てた碑が、せき止めたダムの堰中央に建っていました。大波野の方向を見守るように建っていました。今から250年位前江戸時代中期の宝暦(1760年頃)の年号が刻んでありました。なお、ため池の東側にも神社か祠が建っているとのことでしたが、今回は時間の関係で立ち寄ることができませんでした。
ミニウォーキングが終わると、田布施のオレンジシャワーに行って昼食とコーヒーを取りました。その後、私とEさんは家に帰り、Yさんは誓立寺の納骨式典に、N君は仕事に戻りました。ほど良い疲れで、夜はよく寝ることができそうです。皆さん、お疲れ様でした。
ため池周辺の石碑や神社
これからの季節、春から夏にかけていろいろな野菜を栽培しようと思っています。そのために、冬に収穫が終わったキャベツなどの野菜を片付けて整地して畝を作っています。ところで、3月上旬に種芋を植え付けた春ジャガイモが芽を出し始めていることに気が付きました。このまま順調に育ては、夏には美味しいジャガイモが収穫できそうです。
花盛りのチューリップを避け、春夏野菜用の畑を耕耘中
ジャガイモをはじめとして、イモ類は圧倒的に稲や麦に比べて生産量が高いです。
一つ目の理由は、葉が枯れるまで常に澱粉を根に蓄えるからだそうです。稲は、葉が大きくなる7,8月でしか澱粉を生産しません。花が咲いて籾ができたらもう澱粉生産は終わりです。それに対してサツマイモは葉が枯れる11月近くまでずっと澱粉を生産します。
二つ目の理由が、澱粉が根に蓄えられることです。地中は温度の差があまりありません。芋類に対して、稲は花が冷害に合うともう実はできません。
三つ目の理由は、地中に澱粉を蓄えるためスズメなどの被害に合うことがありません。
これらの理由により、稲のような手間をかけずに確実に芋を収穫できます。ジャガイモやサツマイモは自給用として最適な作物です。
芽が出たジャガイモ、もう少し経ったら芽欠きや土寄せ
一昨年はとても良い暖かい桜まつりでした。去年は天候不順でいくつかの催しが中止になりました。今年は去年と同じように、肌寒い天気に加えて一時小雨が降りました。このため、釣りやカヌーなどの催しは中止になりました。このさくら祭りの当日、私は郷土館に出勤のためすべての催しを見ることができませんでした。11時頃交代して、桜まつりを1時間程度見学しました。
時折みせる青空の下、田布施町庁舎と満開の桜
最初、この桜まつりを計画した田布施町観光協会の桜まつり本部を訪れました。観光協会の事務局長のN君は忙しそうにしていました。祭りの進行が気がかりだったのでしょう。このため、声を掛けるにとどめました。
次に、ボーイスカウトのコーナーに行きました。すると、例年と同様にバームクーヘンを作っていました。リーダーの同級生達数人と談笑しました。私は東京で10年位しかボーイスカウト活動できませんでしたが、彼らは何十年とボーイスカウト活動を通じて地域に貢献しています。
忙しそうな桜まつり本部 ボーイスカウトコーナーで少し談笑

ボーイスカウトコーナーでM君にバームクーヘンをいただきました。昼前でしたので、ほんのりした甘さはとても美味しかったです。ご馳走様でした。
続いて、消防と自衛隊のコーナーに行ってみました。何人かの子供たちが消防車を見ていました。自衛隊のジープはとても幅広で、トラックほどの幅がありました。乗り心地はどんなでしょうか。武骨な装甲車はちょっと運転してみたい気がします。
家族連れで賑わう消防車 自衛隊の装甲車と大型ジープ

今日は郷土館に勤務していますので、あまりお祭り会場に長居できませんでした。ざっと催しの内容をチェックするにとどめました。急ぎ足で歩いていると、私の知っている方々と時折すれ違いました。いろいろなお店をじっくり見まわって、気に入ったものがあれば購入したいのですが今回は時間が許しませんでした。ざっと見た感じでは、天候不順だった去年よりは人が多かったのではないかと思います。
昨日の大雨で地面が濡れるものの、けっこうな人数
今回はお店を回るよりも催しに時間をかけて見学しました。子供にホッケーを楽しんでもらっているコーナー、チェーンソーで木の彫刻を実演しているコーナー、椎茸(しいたけ)の植菌を体験してももらうコーナーなどです。もう少し時間があれば、私も体験したかった催しがたくさんありました。
ホッケーを楽しむ子供達 いい匂い、牡蠣の販売コーナー

お店は歩きながら、ちら見する程度でした。雑貨販売のお店、風船を売るお店、焼きそば屋台、各種食品販売のお店などです。私見ですが、今年は肌寒い風が吹いていましたので売れ行きはいま一つだったのではないでしょうか。
子供向けの雑貨のお店 各種ぬいぐるみや風船を売るお店

毎年のことですが、色とりどりの屋台がたくさん並んでいました。焼きそば,今川焼き,フライドポテトなど定番の屋台が並んでいました。そして、呼び込みの威勢がいい声が響いていました。しかし、のんびりする時間がなかったため今年は1円も使いませんでした。
フライドポテトや焼きそばなど、鮮やかな色彩の屋台が立ち並ぶ
私がこのお祭りで一番見たかったのは、毎年高校生が実演するロボットフットボールです。無線操縦でロボットカーが動く競技です。おそらくそれぞれの車には、PICが使われているのだと思います。そして、無線操縦によって車が自由自在に動くのだと思います。
東京に住む家内は、去年から工業高校に勤めています。工業高校には、このようにロボットコンテストが必ずと言っていいほどあります。いつか、家内の勤める高校の文化祭に行ってみたいと思っています。
ロボットフットボール競技 特命戦隊ゴーバスタズショー

特設ステージ方面から、賑やかな音が聞こえてきたので行ってみました。すると、特命戦隊ゴーバスターズショーをやっていました。幼児向けのショーです。ステージの前に座れなかった子供達は、お父さんに肩車されてショーを見ていました。
ステージのショーを見終わると、ジャグリングショーや長風船遊びなどを見て回りました。そして次に、田布施川さくら健康マラソンの走者に声援を送りました。
長い風船を使った遊び 楽しいふわふわドーム

今年は肌寒い風で吹き、ときおり小雨が降りました。しかも、田布施川の堰堤工事のため川が泥水のように濁っていました。カヌーや釣りの中止はやむを得えません。約1時間でざっと会場を見回った後、郷土館にも戻りました。そして、郷土館長Nさん,同級生のYさん,Eさんと今回のお祭りなどについて談笑しました。
そして、午後5時に郷土館を閉めました。帰りに交流館脇を通ると、会場がだいぶ片づけられていました。来年はぜひ今年より天気が良くなって欲しいと思いました。
左から、郷土館長Nさん、私、Eさん ※撮影Yさん
我家の桜もようやく満開になりました。天候が不安定ですが、時折見せる青空に桜の薄い桃色がとても映えます。風が吹くと、ときおり花びらが舞います。裏山の尾根沿いに植えてある20本位の桜が一斉に咲くと、ようやく長い冬が去って春が来たことを実感します。
これらの桜は、父親が30年位前に植えたものです。植えてから10年後頃に何本かが台風で倒れたことがあります。その頃、山に木々が少なかったため風が桜に直接当たったためでしょう。
時折見せる青空に、桜の薄い桃色がとても映える
この桜、見事に咲くようになるまでに約20年近くかかりました。桜に限りませんが、植林は成果が見えようになるまでに何年と時間がかかります。子や孫の代になってようやく収穫できるのが林業です。私が子供の頃、私の家作りのためにと何十本もの苗木を一家総出で植林したことを覚えています。その苗は確か、杉だったと思います。
山の尾根に並べるように、父親が植えた桜
父親は、林業組合や農業委員会に何年も勤めるなど林業など農業に貢献したようです。平成13年に農林水産大臣賞を、さらに平成17年に知事賞をいただました。それほど農林業が好きで、中でも木を植えることが大好きでした。今、我家の近くに孫(私の息子)の家作りのためのケヤキが何十本も植えてあります。私も私の息子も、この木をどうしたものかと考えています。直径30cm以上もあるケヤキは、伐採するだけでも大仕事です。
桜に少し遅れて満開の桃、桜より花びらが大きく色が濃い
桜以外に桃も満開になりました。桃は、桜より数日ほど遅れて満開になります。桜より花びらが大きくて色が濃いので、遠くからでもすぐに桃だと分かります。桃は花も綺麗ですが、甘くて美味しい実を収穫することができます。個人的には、実も楽しむことができる桃の方が好きです。
オキザリスの黄花 ハナカイドウの花

ところで、地面ではオキザリスの黄色い花が咲き始めました。ピンクの花は初夏に咲き始めます。さらに、ハナカイドウの花がちらほら咲き始めました。地味ですがグミの花も咲いています。赤い実を5月下旬に収穫できます。我家の木で、花の咲く順番はオウバイ,梅,ボケ,スモモ,ユスラウメ,桜,桃,グミ,そしてハナカイドウです。さらに、まだ咲いていませんが、山ツツジ,ハナミズキなどと続きます。なお、畑では収穫しなかった大根の花が咲いています。
収穫しなかった大根の花 地味なグミの花

父親が思いを込めて植えた2本の桜があります。遠くから見ると2本の桜ですが、根元は1本なのです。私が結婚した30年位前、父親が2本の桜を30cmほど離して狭く植えたのです。2本の桜が仲良く融合するようにと。
これまでささいな事で家内とよくけんかしましたが、今この桜のおかげなのか私も家内も仲良くしています。私の娘が結婚する時に、同じような桜を植えようかと考えています。
〇:30年前に父親が植えた、今は根元が1本に融合した2本の桜
このCB無線機 GORILLAの修理履歴です。それぞれをクリックしてください。
修理(1/3) 修理(2/3) 修理(3/3)
故障したダイオード(1N4002)とほぼ同じ規格のものを、同じ郷土館に勤めているHさんに2個いただきました。耐圧1000Vで最大平均電流が1Aです。このいただいたダイオードを取り付けることにしました。Hさんありがとうございます。
Hさんにいただいた交換品2個 左:短絡したダイオード,右:交換品

交換用のダイオードを取り付ける前に、故障したダイオードと同じようにプラス側の線をU字型に曲げました。そして、二つの穴に通してから回路基板に半田付けしました。半田付けが完了すると、はみ出た線をニツパ―で取り除きました。あっけなく修理が終わりました。
ただ不思議なのは、なぜこの無線機にはヒューズが使われていないかです。使われていれば、今回のように誤操作(電源+-逆接続)による故障の場合はヒューズ交換だけで容易に修理できるはずなのですが。車載のヒューズで守られるからでしょうか。しかし、この無線機を車以外の例えば家に持ち込んで使った場合、この無線機は無防備になります。車に装着して使うだけの前提で設計されているようにも思えます?
交換用のダイオードを回路基板に半田付け
半田付けが終わると、ダイオードを摘まんでちゃんと固定されているか確認しました。確認が終わると、無線機の上下の蓋を取り付けました。そして、電源コードを差し込みました。正規品のコネクタではないので、+と-を間違えないように注意して差し込みました。
40年位前の事でしょうか、私は簡単な2石程度のAM送信機を作ったことがあります。1石は音声増幅に、1石は発振器に使いました。さらに1石のFM送信機も作りました。確かFM変調はコンデンサマイクの音声容量変化で実現したように思います。その無線機がどのくらい届くのか、東京の奥多摩湖まで行って実験しました。300m位は電波が飛んだでしょうか。たった1石の発振器(電源9V 006P)で、送信距離を競ったのです。
〇:交換したダイオード 電源用コードの取り付け

安定化電源の電圧を12Vにして、このCB無線機に電気を流しました。すると、前面パネルが光りました。実際に送受信したわけではありませんが正常のようです。電流は300mA程度でした。このCB無線機、ICや水晶周りが故障していたらとても直せなかったかも知れません。電源周りの故障でよかったです。直したこのCB無線機、Aさんの奥様に昼間届けておきました。
正常に光っている無線機の前面パネル
1月初めに伐採して横倒しにしておいた椎茸(しいたけ)用原木を90cmごとに細断しました。3月中に細断しようと思っていましたが、少し時期が遅れてしまいました。椎茸の菌を植え付けるにはぎりぎりの季節です。早めに菌を植え付けて寝かせようと思います。
原木の切り方ですが、まずは巻尺を使って90cmごとに白いチョークで印を付けました。その印に沿って幹を切るのですが、最初に270cmごとに大まかに切断しました。
90cmごとにチョークで印 270cmごとに大まかに切断

伐採後3ヶ月位経っていますので、少しは乾燥して軽くなっているかと思いました。しかし、ほとんど重さは変わっていません。切りやすい向きに幹を転がすのがなかなか大変です。やっとの思いで幹の向きを変えると、チェーンソーを使って一気に幹を切断しました。
270cmごとに原木を切断、これを90cmごとに3分割
原木を切っていたチェーンソーの切味がだんだん悪くなってきました。このため、いったん切断作業を止めてチェーンソーを納屋に持って帰りました。そして、丸ヤスリを使って刃を研ぎました。チェーンソーは刃を研いでいないと、時間ばかりかかって木が思うように切れません。チェーンソー持つ手や腕も疲れます。
刃を研いだチェーンソーを再び山に持ち込んで、切断作業を続行しました。
90cmごとに細断した原木、この原木に植菌
細断した原木の年輪を数えてみました。すると20ありました。つまり年齢20歳の木であることが分かります。しかし林の中で育ったためか、先日細断した年齢13歳の原木より細い幹でした。20年も育ったのに日当たりが良くなかったのでしょう。
細断作業を終わり遠くを見ると、林の向こう側に満開の桜が見えました。山に植えられた桜も満開を迎えたようです。
年輪の数が20の原木 林の向こうに満開の桜

桜など春の花がたくさん咲き乱れています。その中で、散りかけているのはユスラウメとスモモです。スモモは幹が高く伸びているので、下からは花の写真を撮影できませでした。
6月上旬にはユスラウメの小さな赤い実が食べられるようになります。スモモは6月下旬に桃より少し小さ目の赤い実が食べられるようになります。八王子に住んでいた時、サクランボの木が一本あり初夏にわずかなサクランボを収穫できました。山口県の我家にもサクランボを一本だけ植えたのですが、残念ながら花が咲きません。サクランボは来年に期待しましょう。
6月上旬に、小さな甘酸っぱい小さな赤い実がなるユスラウメ
その他、レンギョが満開で遠くからでも黄色が目立ちます。レンギョは、旺盛に育つので花が散った後に枝が蔓のように伸びます。このため、花が散った後の細かな剪定が欠かせません。
園芸用の花では、秋に種をまいたキンセンカが橙色の花を咲かせるようになりました。まだ寒いのか茎が伸びていませんが、これからさらに暖かくなると、たくさんの茎を高く伸ばしたつぼみが出てくると思います。
黄色の花が群生するレンギョウ まだ背が低いキンセンカ

庭で一番輝くように咲いているのは、チューリップです。混色チューリップの球根を秋に植えたのですが、3月末から白,色,赤,黄,紫,そして桃などの色が咲くようになりました。春の花壇は、チューリップが欠かせません。咲いているチューリップの中では、鮮やかな赤色が多く咲いています。
黄色のチューリップ 紫のチューリップ

チューリップに限らないのですが、来年も花を咲かせる場合は花が散るとすぐに花柄を切除します。球根にだけ栄養を貯めるためです。ところで、八王子の我家に住む家内に電話すると野生化したムスリカや花ニラがたくさん咲いているそうです。来年は、ムスリカ,ヒヤシンス,アネモネなどのスタンダードな球根をさらに植えてみようと思います。
花数が一番多い、鮮やかな赤いチューリップ
我家傍の山に行くと、二つの低木に地味な花が咲いていました。一つ目はお墓などに切葉を供える非榊(ひさかき)です。二つ目は仏事や神事に使われる樒(しきび)です。非榊(ひさかき)も樒(しきび)も父親が植えたようです。なお、樒(しきび)の実は漢方にする実によく間違えられるそうで、実際には猛毒だそうです。なお、榊もあるのですが花は咲いていません。花期が違うのでしょう。
地味な非榊(ひさかき)の花 実が猛毒の樒(しきび)の花

桜がようやく満開になった今日この頃、母親の和歌山県に住む従兄弟(Uさん)のお墓参りに同行しました。U家に嫁いだ、母親の父親(小林安太郎)の姉の子供がUさんです。今年84歳になるそうです。UさんやUさんの父母は大阪で暮らしていましたが、U家は元々柳井市の阿月にありました。このため、U家のお墓が柳井市の阿月の山にあるのです。Uさんの母親(小林安太郎の姉)は、夫が亡くなった後に阿月に戻り、阿月で亡くなったそうです。ところで、Uさん老夫婦に会ったのは一昨年のお墓参り以来です。
左から、母親の従兄弟のUさん,母親,Uさんの奥様
11時頃、田布施駅に着いたUさん夫婦を迎えに行きました。我家に着くと、私,母親,Uさん,Uさんの奥様の4人で談笑しながら昼食をとりました。
戦前~戦後にかけて、Uさんは大阪の住友商事に勤めながら苦学して夜間高校を卒業したそうです。そして、定年まで住友商事を勤めあげたとのこと。Uさんが苦学をしていた頃、Uさんの奥様は住友商事の就活に落ちたそうですが、たまたま枠が1人分空いていた住友商事のエレベーターガールに受かったそうです。そして、同じ住友商事で働いていたことが知り合うきっかけになったそうです。Uさんと奥様、美味しい話をありがとうございます。
阿月の山にあるU家のお墓に向かう 瀬戸内海を見下ろしながらお墓の掃除

Uさん夫婦は歩けるものの、長距離は歩くことができません。私の車にUさん夫婦を乗せて、柳井市阿月にある山の高台のお墓に向かいました。ペットボトル数本に入れた重い水は私が持って、一緒に山に向かって歩きました。Uさんの父母や兄弟が眠るお墓に着くと、この2年間の間に生えた草などを綺麗に取り除きました。私も草刈りなどを手伝いました。
お墓の周りを綺麗に掃除しているUさん夫婦
U家のお墓は5つ並んで立っており、一番古いお墓は文政年間(1820年頃)の年号が刻まれていました。周りにある他家のお墓を見ると、同じ年代頃のものが多いのに気が付きました。幕末に築かれた墓地ではないでしょうか。老境を迎えたUさん夫婦はいずれ、子や孫達にこのお墓を任せるようです。
職人肌で少し頑固なUさんと、それをうまく受け流していつも笑顔の奥様。何十年と苦楽を共にして老境に落ち着いた今、Uさん夫婦は穏やかで幸せな雰囲気を醸し出しています。
U家のお墓に花を飾っているUさんの奥様
1ヶ月ほど前でしょうか、田布施のたぶせ山城太鼓の定期演奏会チラシをいただきました。それまでは、この太鼓グルーブの名前は聞いていましたが、どこで活動して,どこで練習して,どこで演奏して,どんな子供達が演奏しているのかなど、全く知りませんでした。
太鼓の演奏会と言えば、何年か前に家内が太鼓の演奏を聴きに行くのが好きで、太鼓プロ集団「鼓童」の話をよくしていたのを思い出すくらいでした。
会場のアクティブ柳井 受付でいただいたパンフレット
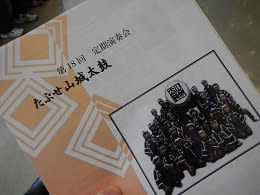
さて太鼓と言えば去年、私は麻郷ふるさと会で嵯峨音頭の太鼓,歌,そして踊りを少しばかり練習しました。しかしどれも覚えることができず、40年以上音楽から離れていたブランクを嫌と言うほど感じました。やはり、若いうちに、いや子供のうちに音楽を経験して、さらに持続して練習することが大切だと思い知りました。
13:30から太鼓演奏第一部の開演です。最初から、子供達の元気の良い太鼓演技の始まりです。小さな子も、大きな子ものびのびと迷うことなく太鼓を叩いていました。これまで、毎日のように練習したり演奏したりした成果ではないでしょうか。
第一部 動画
開演とともに、太鼓曲「上に」を元気に演奏する子供達
たぶせ山城太鼓は、20年ほど前に城南地区の盆踊りの太鼓が契機だったそうです。おそらく、今の麻郷の盆踊りの太鼓のようだったのかも知れません?城南地区は、代表の熱い思いや太鼓の良き指導者に恵まれて、今のようなたぶせ山城太鼓に発展したのではないかと思います。今は、借りてきた曲だけでなく自分たちの太鼓曲も創作しているようです。
迫力の屋台太鼓の演奏 息の合った太鼓演技 

第一部は、子供達の太鼓演技が中心でした。最初、第一部だけで5曲程度しかないのではないかと誤解していました。しかし、いろんな曲を数多く演奏していました。これは、小学1年生頃から長年にわたって叩き続けてきた積み重ねの成果だと思います。一期生はすでに30歳位になり、仕事の合間に後輩たちを指導しているとのこと。20年以上にもわたって、次の世代へと演奏を引き継いでいく伝統が息づいているのでしょう。
高学年生による演奏 低学年生も出て演奏

第一部は、11曲の太鼓が演奏されました。その中で、「ニュー三宅」と「三宅」と呼ばれる曲を、それぞれ高学年生と低学年生で演奏していました。同じ旋律ですが年齢の差が少し現れていました。さすがに高学年生は力強い演奏でした。第一部の最後は「山城」と呼ばれる山城太鼓のテーマ曲でしょうか、子供達のほぼ全員が演奏していました。
第一部最後の曲、山城太鼓テーマ曲「山城」
第一部が終わると小休憩です。ところで、アクティブ柳井の会場は観客席が階段式になっているため、後ろの人もステージをよく見ることができます。普通の公民館と違って、音響が良くなるように工夫されている会場のようでした。私は、前から3番目の席で観賞しました。
さて、いよいよ第二部の始まりです。
第二部 動画
第一部は子供達の太鼓演奏が主でした。第二部は、子供達の演奏に加えて、先輩である中学生達や高校生以上の演奏がありました。それぞれ山城組風、山城組空と呼んでいるそうです。特に、高校生以上のメンバーはセミプロを目指しているとか。ぜひ頑張って欲しいと思いました。
第二部最初の太鼓曲「精悍」 山城組風による太鼓曲「金魚島」

太鼓の演奏会なので、楽器は太鼓だけかと思っていたら違いました。叩いて音が出るものは何でも演奏対象でした。その一つは、体を叩くボディーパーカッションです。一時期芝居の世界で流行ったように思います。どこかで聞いたようなリズムと音でした。ボディーパーカッションに続いて、勇壮な山城組空の演奏です。さすがに動作も大きく音もよく響きました。強く叩くので太鼓がずれるほどです。
子供達によるボディーパーカッション 山城組空による太鼓曲「疾風」

第二部最後の曲は、竹竿を使ったパフォーマンス曲「野戦」の演奏です。考えてみれば、叩いて音が出るものは何でも楽器として使えます。出土した石器時代の数本の石棒が考古学的に楽器として認められたとの記述を思い出しました。木琴ならぬ石琴です。またインドネシアの竹楽器であるアンクルン(angklung)も打楽器の一つだと思います。また、田布施竹楽坊で使っている竹琴も打楽器の一つではないでしょうか。
第二部最後の演奏、竹竿を使用した曲「野戦」
第二部が終わると、小休憩です。受付前のソファに座って少し休みました。5分程度休むと、会場内に入って第三部の演奏が始まるのを待ちました。第三部は第一部,第二部と違って、オカリナやバイオリンなどとコラボした曲が演奏されました。
第三部 動画
最初の曲は「荒波」で、波のように太鼓を打つ列が移動したりして、見ていても楽しい曲でした。子供達は太鼓を打つだけでなく、移動する練習もしたのだと思います。続いて、太鼓指導者の演奏披露がありました。指導者のNさんは田布施観光協会の会長でもあり、私も時々顔を合わせます。音楽の演奏者としての,そして音楽指導者としての一面を拝見させていただきました。
オカリナを演奏するNさん バイオリンとコラボした曲「カノン」

オカリナに続いて、バイオリンがメロディーを奏でる曲「カノン」でした。それまで太鼓演奏が中心でしたので、バイオリンをとても新鮮に聞くことができました。その後再び太鼓曲になり、続いて木琴がメロディーを奏でて太鼓とコラボした曲「ギャロップ」、そしてこの定期演奏会最後の「剣の舞」と続きました。
私はかつてジャズオーケストラ(ビッグバンド)で、演奏旅行,各種コンサート,海援隊や青い三角定規などフォークグループの前座,そして定期演奏会などに出たことがあります。主催する演奏会はほとんど有料でしたので、チケットを販売するのに苦労しました。当時のお金で500~1000円位だったでしょうか。なかなか売れなくて、演奏会近くになると売らないで配っていたように覚えています。アルバイトとして年末にダンスパーティーの伴奏をしたり、ビアガーデンなどで演奏をしたこともありました。演奏会に行くと、つい自分の若かりし頃の音楽活動を思い出してしまいます。
練習が大変だった?太鼓曲「道」 私が20歳頃、関わった演奏会やチケット

最後の演奏が終わると、団員全員がステージに立ちました。そして、観客席に向かって挨拶をしていました。20年以上続く山城太鼓だけあって、礼儀正しい姿勢には共感できます。将来太鼓から離れることになっても、太鼓で学んだことは私生活を豊かにするはずです。今日演奏した子供たち、将来模範的な社会人になって欲しいと思います。
素晴らしい太鼓を聞かせてくれた子供達や指導者の方々
ところで、先日たぶせ少年少女合唱団の定期演奏会にも行ってきました。たぶせ山城太鼓もたぶせ少年少女合唱団も、共に素晴らしい演奏会でした。私は40年以上も田布施を離れていたため、田布施の現状に疎くなっていました。このため、スポーツに加えて音楽などの文化活動も盛んなことを知りませんでした。
私は一昨年から、田布施を中心にした史跡を巡る健康ウォーキングを毎月企画し実行しています。さらに、どう言う訳か今年の2月から郷土館に勤めることになり、さらに4月から田布施町少年少女発明クラブで指導する1人になりました。
たぶせ山城太鼓指導者のNさん、たぶせ少年少女合唱団指導者のSさんになんとか追いつけるように、音楽とは別の道で田布施に貢献できたらと思っています。今回とても良い刺激をもらいました。ありがとうございました。
演奏を終えた子供達に見送られて 山城組の方々、素晴らしい演奏でした
















