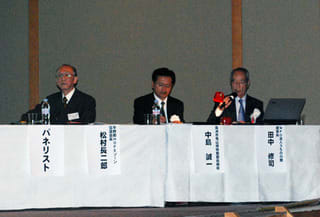またまた、社寺案内人になってしまいました。近鉄ケーブルネットワーク(KCN)の「大和七福八宝(やまとしちふくはっぽう)めぐり」という30分の特番(前編・後編の2回)に出演します!
同局の「ファミリーチャンネル」(独自制作番組)枠で放送されている「Kパラ next(ケーパラ・ネクスト)」という番組の「冬のスペシャル」です。昨夏は「奈良の秘仏めぐり」(夏のスペシャル)として、7か寺と史跡頭塔の計8か所を案内しましたが、今回も8つの神社仏閣を案内します。
本放送は、前編が1月18日(火)、後編が1月20日(金)の、いずれも午前11時30分~12時までの30分ですが、再放送が何度もありますので、放送当日にチャンネルを合わせていただくと、そのうちご覧いただけると思います(たいてい00分から30分までの放送です)。後日、ネットでも公開される予定ですので、アップされ次第、当ブログにも掲載します。
夏季と同じく、レギュラー出演されている藤原了さんと中村百合さんというタレントさんを案内し、御福掛(おふくかけ)にご朱印をいただきながら、8社寺をお参りします。収録に際しては、安倍文殊院執事長の東快應さん、大神神社権禰宜の山田浩之さんはじめ、関係社寺の方にご協力いただきました、有難うございました。

御福掛(おふくかけ)に、すべての社寺のご朱印をいただいた
雪の残る談山神社(トップ写真)や寒風吹きすさぶ信貴山寺、受験生でごった返す安倍文殊院、初詣の参拝者が列をなす大神神社(三輪明神)など、いま思い返しても大変なロケでした(この特番は真夏と真冬に撮影があるので、苦労します)。しかし神さまのご加護でカゼもひかず、またお若いのに信心深い藤原さん、神社めぐりがお好きという中村さんのお二人に助けられて、無事、収録を終えることができました。自分用の御福掛にも、すべてご朱印をいただくことができました。
案外、奈良県民は「大和七福八宝めぐり」のことを知りませんし、「お寺で福の神さま参り」という取り合わせは意外なのかも知れませんが、KNT(近畿日本ツーリスト)の「クラブツーリズム」で訪ねて来られる団体さんも多く、大和七福八宝が広く認知されていることが、よく分かりました。KCNにご加入の方は、ぜひご覧下さい!
同局の「ファミリーチャンネル」(独自制作番組)枠で放送されている「Kパラ next(ケーパラ・ネクスト)」という番組の「冬のスペシャル」です。昨夏は「奈良の秘仏めぐり」(夏のスペシャル)として、7か寺と史跡頭塔の計8か所を案内しましたが、今回も8つの神社仏閣を案内します。
本放送は、前編が1月18日(火)、後編が1月20日(金)の、いずれも午前11時30分~12時までの30分ですが、再放送が何度もありますので、放送当日にチャンネルを合わせていただくと、そのうちご覧いただけると思います(たいてい00分から30分までの放送です)。後日、ネットでも公開される予定ですので、アップされ次第、当ブログにも掲載します。
夏季と同じく、レギュラー出演されている藤原了さんと中村百合さんというタレントさんを案内し、御福掛(おふくかけ)にご朱印をいただきながら、8社寺をお参りします。収録に際しては、安倍文殊院執事長の東快應さん、大神神社権禰宜の山田浩之さんはじめ、関係社寺の方にご協力いただきました、有難うございました。

御福掛(おふくかけ)に、すべての社寺のご朱印をいただいた
雪の残る談山神社(トップ写真)や寒風吹きすさぶ信貴山寺、受験生でごった返す安倍文殊院、初詣の参拝者が列をなす大神神社(三輪明神)など、いま思い返しても大変なロケでした(この特番は真夏と真冬に撮影があるので、苦労します)。しかし神さまのご加護でカゼもひかず、またお若いのに信心深い藤原さん、神社めぐりがお好きという中村さんのお二人に助けられて、無事、収録を終えることができました。自分用の御福掛にも、すべてご朱印をいただくことができました。
案外、奈良県民は「大和七福八宝めぐり」のことを知りませんし、「お寺で福の神さま参り」という取り合わせは意外なのかも知れませんが、KNT(近畿日本ツーリスト)の「クラブツーリズム」で訪ねて来られる団体さんも多く、大和七福八宝が広く認知されていることが、よく分かりました。KCNにご加入の方は、ぜひご覧下さい!