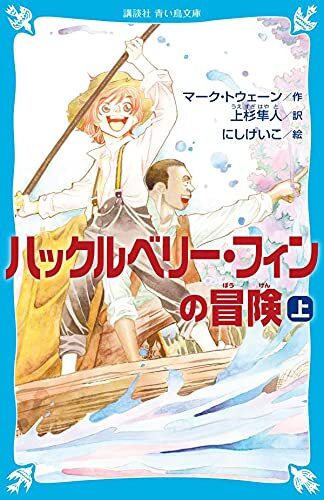grand-scale, grand scaleは、「大規模な、多大な」。
今日のGetUpEnglishはこの表現を学習する。
○Practical Example
I don't think Mr. K's retirement party should be so grand-scale.
「K先生のお別れ会はそんなに盛大にする必要はない」
●Extra Point
現在翻訳中の本の1冊に、この表現があった。
◎Extra Example
Jewellery was used on a very grand scale in Byzantine art, particularly when depicting sovereigns. It was a way of signaling importance — the more elaborate, the better. There were even explicit rules about the types of jewellery that could be worn — sapphires, emeralds and pearls were only allowed to be worn by an emperor, while any free man was entitled to wear a gold ring.
「宝石はビザンティン芸術において非常に広く使われ、特に君主を描く際には必ず見られるものでした。重要性を示し、精巧であるほどよいとされました。どの宝石が身につけられるかの規則もはっきりしていて、サファイアとエメラルドと真珠は皇帝しかつけられませんでしたが、金のリングは誰もが着用できました」
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
transfusionは「注入、移注」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
○Practical Example
The project badly needs a transfusion of cash.
「当プロジェクトは資金注入が絶対必要だ」
●Extra Point
現在、鋭意翻訳中の本の1冊に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
◎Extra Example
It takes courage to turn your back on modern society and reject all its values, including the way it practises medicine. Jehovah’s Witnesses won’t accept blood transfusions. Blood is life to them and only God can give it.
「現代社会に背を向けて、たとえば薬を摂ることも含めてその効用をすべて拒むのは勇気のいることだった。エホバの証人は輸血を認めることはない。血は自分たちに与えられた生命であって、それをもたらすのは神だけだ」
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
restlessは「落ち着きのない」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
現在、鋭意翻訳中の本の1冊に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
○Practical Example
The Protestantism they took with them was a restless religion that imprinted its character on the USA itself. It created a culture driven by desire, forever dissatisfied and constantly on the make. There were always new frontiers to conquer.
彼らのプロテスタンティズムは落ち着くことを知らない宗教で、この特色がアメリカ合衆国自体に植えつけられた。これが作り上げたのが、永遠に満足しない、常に増大する欲望に突き動かされる文化だ。制服すべき新たなフロンティアが常に存在した。
●Extra Point
状況によっては、次のように訳してもいいだろう。
◎Extra Example
"You've been restless ever since morning, Reiko."
"Today they're announcing the results of my son's highschool entrance exam."
「朝から何だかそわそわしてるね、玲子」
「今日は息子の高校受験の発表があるんですよ」
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
polarは「極の、北極の、南極の」という意味であるが、状況によっては「対極の」という意味でも使われる。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
○Practical Examplme
The parents' position is often the polar opposite of the child's.
「親の立場は子供の立場と対極にあることがよくある」
●Extra Point
もう一例。現在、鋭意翻訳中のこの本に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
◎Extra Example
But the land the invaders overran wasn’t a religious vacuum. Its natives had their own spiritual traditions, the polar opposite of the dynamic Protestantism that attacked them. Native Americans went with the grain of nature, not against it. They had a sacred connection to the land that sustained them.
だが、ヨーロッパからの侵入者たちが踏み荒らした土地は宗教的真空地帯ではなかった。先住民は独自の宗教伝統を保持していたし、それは彼らが攻撃を受けた動的なプロテスタンティズムと正反対のものであった。アメリカの先住民は自然の本質とともに生き、それに逆らうことはなかった。自分たちを支える土地との神聖なつながりを維持していた。
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
airs and gracesは「大げさにもったいぶった態度」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
○Practical Example
He was always putting on airs and graces.
「彼は大げさでもったいぶった態度を取る」
●Extra Point
現在、鋭意翻訳中のこの本に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
◎Extra Example
That’s how it was for George Fox, one of the most attractive figures in the history of religion. It was a time in seventeenth-century England when the mighty in Church and society gave themselves airs and graces. They loved titles and the vestments that came with them. They insisted on inferiors bending their knees and sweeping off their hats in deference to them. The titles they gave themselves emphasised how far above the common herd they were. Your Holiness, Your Excellency, Your Grace, Your Majesty were forms of address that set them above the ordinary humans who scurried like ants beneath their feet.
宗教史においてもっとも魅力的な人物のひとりであるジョージ・フォックス(1624~1691)には、まさにそうだった。時代は17世紀、当時のイギリスに見られる教会や社会の権力者たちの態度は仰々しくもったいぶったものだった。彼らは肩書と礼拝の際に着る祭服を愛した。下々の者たちには、自分たちにひざまずき、遠くから帽子をとるようなことを求めた。自分たちに肩書を与え、それによって彼らが凡百の者たちのはるか上にいることを強調した。聖下、閣下、閣下夫人、陛下といった言い方は、アリのように足元で蠢く一般の民の上に自分たちはいるとするものであった。
好評発売中!
*********************
英語マニアなら知っておくべき500の英単語 単行本 – 2018/11/21
キャロライン・タガート (著), 大工原彩 (翻訳), 國方 賢 (翻訳)
商品の説明
内容紹介
究極の語彙センスが身につく「読む」英和辞典。
気持ちの表し方からお金の話、人生の快楽と難局、雑談レベルの教養まで、
身近だけど一癖ある、高校までの学校教育ではあまり教わらない500の英単語を紹介します。
ある単語から思いがけない派生のしかたをして生まれた単語や、神話や思想と関わりながら発展してきた単語、「そんな言い方があるのか」と感心する単語が盛りだくさん。
あなたはいくつ使いこなせる?
出版社からのコメント
「そんな言い方あったのか! 」「聞いたことあるような、ないような……」
「これは、さすがに学校では教えてくれない」「一見ばかばかしいけど深い! 」
そんな楽しくて使える単語を500個紹介。決して特殊ではなく、日常に密着したものが厳選されています。それぞれの単語に対して派生語、反意語、取り違えやすい単語なども充実し、簡潔な語源の解説と具体的な用例で使いどころもバッチリ。 英単語の世界の魅力を味わい、関連知識がみるみる増える、読んで楽しい英和辞典です。
第1章 親愛、尊敬、称賛の言葉——urbane(あか抜けした)、versatile(多才な)など
第2章 悪口、批判、ちょっとした軽蔑の言葉——histrionic(わざとらしい)、virago(ガミガミ女)など
第3章 気分次第——forlorn(見捨てられた)、lachrymose(涙もろい)、ribald(下劣な)など
第4章 ちょっと考えてみよう——putative(うわさの)、surreptitious(こそこそした)など
第5章 楽あれば苦あり——catharsis(感情の浄化)、furore(騒動)、regale(楽しませる)など
第6章 天国と、地獄と、その間にあるもの——miasma(毒気)、xenophobic(外国嫌いの)など
第7章 科学と芸術——analogy(類推)、dilettante(素人の)、primeval(太古の)など
著者について
【著者紹介】
キャロライン・タガート(Caroline Taggart)
ロンドン生まれ。シェフィールドの大学を卒業後、出版社に10年あまり勤務。フリーの編集者に転向し20年活躍したあと、著述業へ。歴史、宗教、文学、科学、自然、料理、英国文化など幅広い知識分野の書籍を刊行している。ベストセラーとなった大人のための学び直しの書籍I Used to Know That (2008)のほか、The I Used to Know That Activity Book: stuff you forgot from school (2011), The Book of London Place Names (2012), Her Ladyship's Guide to the British Season: The Essential Practical and Etiquette Guide (2016), A Slice of Britain: Around the Country by Cake (2014), Her Ladyship's Guide to Greeting the Queen: And Other Questions of Modern Etiquette (2016), Bognor and Other Regises: A Potted History of Britain in 100 Royal Places (2018), Christmas at War: True Stories of How Britain Came Together on the Home Front (2018)ほか多数。時代とともに変わっていく言葉への関心が高く、読み手に親切かつ、人の心を捉えるウィットに富んだ筆致で、英語学習書籍においてもニッチな領域を切り開いている。
【訳者紹介】
大工原彩(だいくはらあや)
1978年生まれ。東北大学法学部卒業。東北大学法学研究科修士課程終了。外務省勤務。
國方 賢(くにかたさとる)
1983年生まれ。早稲田大学大学院先進理工学研究科修士課程修了。東京大学大学院工学系研究科博士課程単位取得退学。翻訳者。
acknowledgmentsは「謝辞」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
実際にはこんな形で使われる。
12月22日発売の『若い読者のためのアメリカ史』(すばる舎)に、このacknowledgmentsがあった。
Acknowledgments
For me, the writing of history has very often been collaborative. The list of colleagues and coauthors I’ve worked with in the making of American histories is too long to include, to say nothing of the hundreds of scholars whose work I have drawn on in writing this tale. But I owe a particular debt of gratitude to those who read this Little History in draft: Mark Lytle, Christine Heyrman, Michael McCann, John Rugge, Ken Ludwig, Mary Untalan, and Antonia Woods. Chris Rogers, my friend and steadfast editor at Yale Press, provided more than one close reading, while Margaret Otzel and Erica Hanson eased my way through production. I owe a special thanks to Gordon Allen. Forty years ago, he executed the drawings for my first book, a guide to wilderness canoeing written with John Rugge. It is especially satisfying to have him back, pen in hand, once more.
謝 辞
わたしが歴史を書くときは誰かとの共同作業になることがほとんどだ。これまでにアメリカ史を作り上げきた過程で一緒に作業を進めた人たちと共著者の名前のリストはおそろしく膨大ものとなり、本書執筆にあたって参考にさせていただいた数多くの文献を著した学者の方々については言うまでもなく、この人たちについてもここで謝辞を述べることができない。だが、この『若い読者のためのアメリカ史』を原稿段階から読んでくれたマーク・ライトル、クリスティン・ヘイルマン、マイケル・マキャン、ジョン・ルジェ、ケン・ラドウィッグ、メアリー・アンタラン、アントニア・ウッズの各氏には、この場を借りて厚く御礼申し上げる。また友人でイェール大学出版局の堅実な編集者クリス・ロジャースにも数回精読してもらい、同局のマーガレット・オッゼルとエリカ・ハンソンのおかげで本書制作を滞りなく進めることができた。最後に、ゴードン・アレンには最大限の感謝を表する。40年前になるが、ジョン・ルジェと共同執筆したわが最初の著作『原野をカヌーで下る完全ガイド』(The Complete Wilderness Paddler [1975])にも、アレンは挿絵を描いてくれたのだ。その彼がこうしてふたたびペンを手にして戻ってきてくれて、万感胸に迫る思いだ。
動詞acknowledgeは「謝意を表明する」の意味でもつかわれるので、あわせて覚えておこう。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/eb797e6b55725781d804ee5eb142e878
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
lieは「横たわる」。まだGetUpEnglishではまだこの語を紹介していなかった。
○Practical Example
Hideaki lay on the grass enjoying the sunshine.
「英昭は芝生に寝転がって日光浴を楽しんでいた」
●Extra Point
自動詞lieはいろいろな意味があるが、「〈利益・困難・選択の道などが〉存在する、見出される」の意味でも使われる。
現在、鋭意翻訳中のこの本に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
◎Extra Example
Though he led a life of privilege in the royal palace of the Pharaohs, Moses was aware that he was an Israelite and not an Egyptian. He had a growing sense that his destiny lay with the slaves and not with their oppressors who had adopted him.
エジプト王パロの娘の子となったモーセは宮殿で満たされた生活を送ることになったが、自分はイスラエルの民であり、エジプト人ではないと気づいた。わが運命はこの国の奴隷とともにあり、自分を養子として受け入れた抑圧者たちとともにはないという意識をかねてより持っていたのだ。
若い読者のためのアメリカ史
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン (著), 上杉 隼人 (翻訳), 下田 明子 (翻訳)
単行本: 464ページ
出版社: すばる舎 (2018/12/22)
言語: 日本語
ISBN-10: 4799107690
ISBN-13: 978-4799107690
発売日: 2018/12/22
【内容紹介】
航海者コロンブスの視点からはじまる
手に汗握る激動の500年
どのようにして今のアメリカ合衆国が形作られてきたのか。
利害がぶつかるなかで、人々は何を求め、いかに行動してきたのか。
本書では、衝突を繰り返し、大陸に広がり、多種多様な人々を抱え、
自由と平等のもとに結合しようと悪戦苦闘してきたアメリカの変遷をたどる。
大陸発見から現代までをその時代の人の目線で描き出し、
ひとつの物語のように繰り広げる躍動感にあふれた歴史書である。
【出版社からのコメント】
誰もが自由であるために、国家はいかに成長するべきか
本書はいかにしてアメリカ合衆国が成り立ったかを記す歴史書である。アメリカの物語は500年におよぶ瞠目すべきものだ。いかにして一国が途方もないほどさまざまな人たちを抱えながらひとつの大陸に広がっていくか、本書に記した。さらにアメリカの人々がいかにして自由と平等の旗印のもとに結合したかも論じた。アメリカのモットーは、国璽にラテン語で記されているE pluribus unum, すなわち「多数から成るひとつ」だ。国家の独立を宣言した創設者たちが強調したのは、アメリカ国民は、事実上すべての人間は、公平に創られ、生命、自由、および幸福追求の権利を保持するということだった。
一見、こうした自由や平等や単一といった考え方はほとんどおとぎ話というか、現実世界から遠くかけ離れているように思える。国内の数十万人もの住民は外から拉致されて奴隷として連れて来られたというのに、どうやって自由を宣言できるというのか? 国内の半分の人間――すなわち女性たちだ――が男性と同等の権利を与えられていないというのに、どうして創設者たちは平等を礼賛できるのか? 真にひとつに結合した国家が、非常に多くのそれぞれさまざまに異なる人たちを受け入れてはたして成り立つのか?
あまりにたくさんの異なる人たち。あまりに違い過ぎて、自分とはまったく関係ない人たち! ほんとうにそうだろうか? 誰もがみな歴史を生き抜き、書き上げたいと願う。だが忘れてはいけないのは、歴史を読み解いて、書いて、記憶すればするほど、その行いも記憶されつつ歴史を生き抜く可能性もさらに広がるということだ。
【著者について】
著者─ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン(James West Davidson)
歴史学者、作家。イェール大学で、アメリカ史研究により博士号取得。アメリカ史を詳細に調査・分析したうえで魅力的な物語として読ませる手法に定評がある。著書に、Virginia Teacher's Edition, America History of Our Nation(2011), They Say: Ida B. Wells and the Reconstruction of Race(2006), Nation of Nations (1981), Great Heart: The History of a Labrador Adventure(1988), After the Fact: The Art of Historical Detection(Volume 1[1981], Volume 2[1986])など。著作は全米の中学、高校の教科書として、多くの教師、学生に読まれている。
訳者─上杉隼人(うえすぎはやと)
翻訳者、編集者。訳書に『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』『マイティ・ソー バトルロイヤル』『スパイダーマン ホームカミング』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス』『シビル・ウォー キャプテン・アメリカ』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』(ディズニーストーリーブック)、ダイアン・ディズニー・ミラー+ピート・マーティン『私のパパ ウォルト・ディズニー』、デイビッド・A・ボッサート『ロイ・E・ディズニーの思い出』(講談社)、『スター・ウォーズ』I, II, III, IV, V, VI(講談社文庫)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(岩波現代文庫)ほか多数。
訳者─下田明子(しもだあきこ)
早稲田大学第一文学部卒業(専攻は英米文学)。企業で海外関係の業務に携わったのち、2000年から翻訳業。訳書に『エコ・デザイン・ハンドブック』(共訳、六耀社)、『パスタ』(共訳、クーネマン社)がある。
http://www.subarusya.jp/book/b377937.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4799107690
【目次】
1鳥たちはどこへ導いた?/2空間と時のなかにおける大陸/3ひとつから成る多数 /4黄金時代と黄金の時代/5世界が衝突する時/6われはいかにして救われるか?/7天使たちと見知らぬ者たち/8好景気に浮かれる国/9公平と不公平/10啓蒙と覚醒/11願いごとは慎重に/12口論ではすまない/13平等と独立/14より完全な連邦/15ワシントンの懸念 /16自由の帝国 /17大衆の味方/18綿花王国/19焼き尽くされて/20フロンティア /21国境を越えて/22今後の事態/23どう再建するか/24次なるブーム/25襟の色/26二都物語/27 新西部/28幸運か勇気か?/29進歩派 /30衝突/31大衆/32ニューディール/33世界大戦/34超大国/35世界の終わり/36あなたかもしれない、あるいはあなたかもしれない/37雪崩/38保守派の転換/39つながる/40過去はさらに問いかける 訳者あとがき
ruseは「策略、計略、たくらみ」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
○Practical Example
Ken's friendliness was only a ruse. He was actually digging a pit for me.
「健の友好的な態度は計略にすぎなかった。実際にはぼくを陥れようとしてたんだ」
●Extra Point
もう一例。現在、鋭意翻訳中のこの本に、次の表現がある。
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208832/little-history-religion
◎Extra Example
One mother decided that she would rather give her newborn son away than see him slaughtered. So she placed him in a carefully waterproofed basket and left him in the reeds on the banks of the Nile at a spot where she knew the daughter of the Pharaoh, the Egyptian king, came to bathe. The ruse worked. When the king’s daughter came upon the baby floating in the bulrushes she adopted him as her own and gave him the Egyptian name Moses.
イスラエルのひとりの母は産んだばかりの男の子が殺害されるのであれば、誰かに差し出してしまおうと決心した。母は水が入らない籠に生まれたばかりの自分の子を入れると、エジプト王パロの娘がナイル川の岸辺に体を洗いにやって来ると知っていから、そこに生い茂る葦の藪のなかにそっとその子を置いたのだ。これがうまくいった。王の娘は紙草に浮かんで流れてくる男の子を受け入れて養子にし、モーセというエジプトの名前を付けた。