■平和を考えているか
平和ってなんだろう、戦争が無い状態が平和だというならば飢餓や圧政や貧困でも戦争さえ無ければ平和なのか、という素朴な疑問を寄せられた際にはどうこたえるべきでしょう。

本日は終戦記念日、昭和20年の今日、日本はポツダム宣言の受諾を公式表明し第二次世界大戦は終わりました。欧州大戦と呼ばれた第一次世界大戦から二十余年の時を経て始まった第二次世界大戦は、航空機と潜水艦といった各種兵器はより洗練され、大洋狭しと繰り広げられた航空母艦同士の艦隊決戦やレーダーと電子空間に及んだ戦争となった。

核兵器が使用された最初であり現在は最後の世界大戦となっている第二次世界大戦は日本の降伏により終戦を迎えることとなりました。これは基本的人権と人間の尊厳や海洋自由原則といった国際公序が普遍化するというかたちでの終戦となり、一応、戦後の日本では平和が訪れた日、として認識されています。現実問題として本土決戦が避けられたが。

無条件降伏と占領統治、憲法改正と平和憲法、朝鮮戦争と東西冷戦。昭和は遠くになりにけり。これは昭和の終焉と平成から令和への移ろいを経まして落ち着いた2023年という視点から見返しますと、当時と現代の価値観や死生観が根本から異なりますし、なにより国際公序への考え方や情報共有の水準が違い過ぎる点が当時を想像することが難しくなる。

終戦記念日は、台風七号の本土直撃が重なることとなり、これは稀有な事例とはいえるのでしょうが、終戦記念日政府行事はCOVID-19感染拡大下を思い出させるほどの縮小開催となり執り行われました。これは災害との重なりではあるのでしょうが、それでもNHK中継を含め、ああ終戦か、という程度に受け止められている様な印象さえ受けてしまう。

しかし、終戦記念日、日本にとり終戦記念日とは日露戦争でも日清戦争でも応仁の乱でもなく、やはり終戦といえば第二次世界大戦の終戦を示すものであり、ここから日本の価値観が大きく転換した事はやはり事実なのでしょう。一方で、終戦記念日、という考え方を世界、特に周辺国や友好国と今までのように共有するには限界が近いようにも思えます。

終戦の価値観、一応、ロシアや中国などは対日戦勝記念日を掲げていますが、問題は日本が示した国際公序と似た、つまり力による現状変更による人間の尊厳への侵害や、海洋自由原則に相反する海洋閉塞主義の強要、単に対日戦勝記念日を国際公序と異なる正義の闘争ではなく、当時の競合国の脱落を記念したかたちとなっているのではないか、と。

国際公序という視座に立てば、連合国の制度はそのまま国際連盟から国際連合への発展的昇華により、第二次世界大戦のような戦争は根絶されるはずでしたが、現実はそうなっていません。結果的に日本は戦後、戦時中までの軍事へそそいだ国家資源を経済と教育に注いだことで経済的な発展を実現することとなり、その発展は新しい義務を生んでいました。

安全保障という視点からは、これが終戦記念日とその後の価値観は、果たして平和というものに指向しているのだろうか、少し考えさせられることがあるのです。むろん、これは一国平和主義という視座から早い時期に批判は存在していましたが、結局のところ平和を目的とせず手段とした平和憲法を堅持しているため、それが国民の選択ではあるのですが。
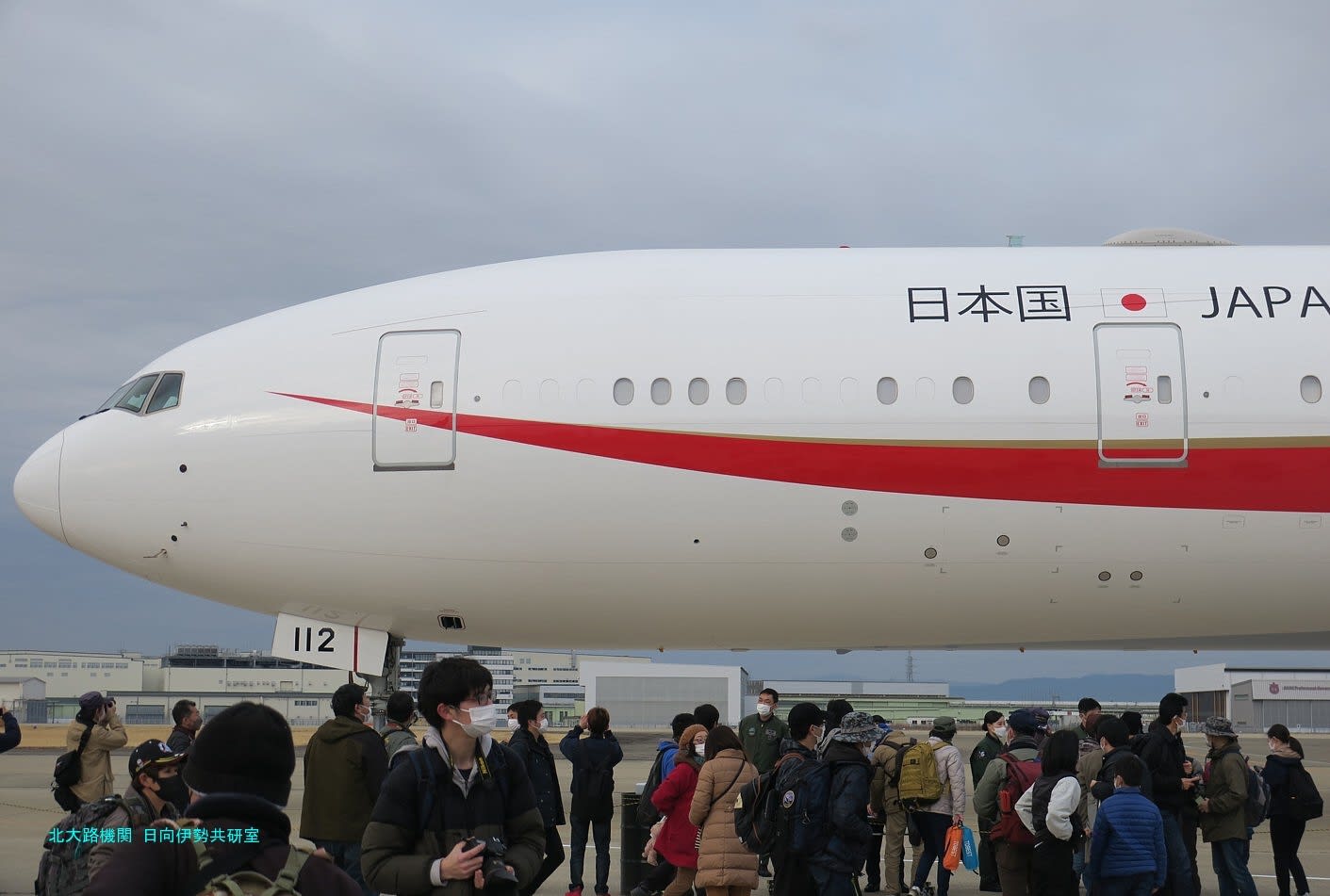
平和憲法が問題ではなく、平和を目的とした憲法が必要であり平和を手段とし、結果的に国民が平和を享受できない状態であっても瑕疵は無いとした理念を憲法が利用されていることが問題であり、この状況が放置されているのは、果たして平和というものを正面から考えているのか、考える努力をしているのかという素朴な危機感を受けてしまうのです。

反撃能力。もう一つ考えさせられるのは、2022年末に示された国家安全保障戦略に明示された反撃能力という概念で、これは伝統的な専守防衛の終焉を意味する、つまり、周辺国が日本本土に侵攻するまでは戦わず、逆に日本が侵略されて初めて、国土で国民の居住する国内で大規模な地上戦と国民を巻き込み戦うという従来の理念を脱したということ。

専守防衛は、国土が戦場になる、という前提があり、つまり侵攻された地域の住民や工業地帯や人口密集地の住民は戦闘に巻き込まれるか、ミサイルや航空攻撃による被害をある程度耐えなければなりません、絨毯爆撃を第二次世界大戦のように行う可能性は低いものの、ミサイルや自爆型無人機が数千から一万数千来ることは想定しなければならない。

政治はこうした視点から、国家防衛戦略に今後防衛力整備により国土戦を避ける防衛体制への転換を目指すとしています。もちろん、これは、結果としての平和を国民が享受するには、少なくとも、本土決戦主義、と揶揄されるような防衛政策よりは国民の生命財産に資するものなのかもしれませんが、憲法解釈の限度を超えているのではないか、とも。

本土決戦主義からの脱却は、個人的には必要だと考えます、けれどもその際には一内閣の憲法解釈ではなく、憲法改正を伴うべきであり、また政権与党以外の政党は現状の矛盾と、そして本土決戦主義の是非を含めて議論する、またはそうした政治家を国民が選び代議士とする選択肢があって然るべきなのですが、国会の議論はそこまで踏み込みません。

神学論争と揶揄されている通り、本来ならば現在の本土決戦主義という専守防衛の堅持か、反撃能力という国土と国民を戦争に巻き込まないが域外での戦闘を基本とする防衛戦略への転換かを議論すべきですが、具体的な防衛戦略まで言及することなく、後追いで、泥縄式に防衛政策を追認するか、議論せず金額などを批判するという状況に留まります。

大和とか敷島とか扶桑とか、いっそ日本国家が日本という名前を超えることができたならばこうした忸怩たる思いといいますか、敗戦や終戦というものの見方を自分事ではなく歴史として受け止められたのかもしれませんが、結局は自我自存の拠り所として共通する価値観、一億の日本人が共有できる価値観を直ぐには見つけられず、今に至ったよう思う。

日本が敗戦したのであり、日本が続いている。ただ、世界を見れば第二次世界大戦の延長線上で現在の各国情勢があるわけではありません、第二次世界大戦とニジェールクーデターは関係ありませんし、ロシアはそのつもりかもしれませんがロシアウクライナ戦争にナチスの影響はありません、台湾海峡もアフガニスタンのタリバン政権も、現代の問題だ。

平和について。そもそも普遍的な価値観と思われる平和についても、実のところその定義は何かと問われれば確たる答えを見つけられていないのではないか。単純に平和を戦争がない状況というならば、例えば飢餓は平和か、差別は平和か、投獄や強要が社会に満ちていた場合でも戦争が無ければ平和なのか、これ即ち、平和を考えていないだけでは、と。

終戦記念日は平和を重視するという視点では同意します、しかし、日本が参加した国際公序を守るための日本の責務に目を背ける口実となっていないか、平和とは戦争を考えない事ではない、こうした視点が必要なのではないか。昭和は遠くになりにけり、しかし次の戦争というものを回避する努力を十分行っていないよう、いま危惧してしまうのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
平和ってなんだろう、戦争が無い状態が平和だというならば飢餓や圧政や貧困でも戦争さえ無ければ平和なのか、という素朴な疑問を寄せられた際にはどうこたえるべきでしょう。

本日は終戦記念日、昭和20年の今日、日本はポツダム宣言の受諾を公式表明し第二次世界大戦は終わりました。欧州大戦と呼ばれた第一次世界大戦から二十余年の時を経て始まった第二次世界大戦は、航空機と潜水艦といった各種兵器はより洗練され、大洋狭しと繰り広げられた航空母艦同士の艦隊決戦やレーダーと電子空間に及んだ戦争となった。

核兵器が使用された最初であり現在は最後の世界大戦となっている第二次世界大戦は日本の降伏により終戦を迎えることとなりました。これは基本的人権と人間の尊厳や海洋自由原則といった国際公序が普遍化するというかたちでの終戦となり、一応、戦後の日本では平和が訪れた日、として認識されています。現実問題として本土決戦が避けられたが。

無条件降伏と占領統治、憲法改正と平和憲法、朝鮮戦争と東西冷戦。昭和は遠くになりにけり。これは昭和の終焉と平成から令和への移ろいを経まして落ち着いた2023年という視点から見返しますと、当時と現代の価値観や死生観が根本から異なりますし、なにより国際公序への考え方や情報共有の水準が違い過ぎる点が当時を想像することが難しくなる。

終戦記念日は、台風七号の本土直撃が重なることとなり、これは稀有な事例とはいえるのでしょうが、終戦記念日政府行事はCOVID-19感染拡大下を思い出させるほどの縮小開催となり執り行われました。これは災害との重なりではあるのでしょうが、それでもNHK中継を含め、ああ終戦か、という程度に受け止められている様な印象さえ受けてしまう。

しかし、終戦記念日、日本にとり終戦記念日とは日露戦争でも日清戦争でも応仁の乱でもなく、やはり終戦といえば第二次世界大戦の終戦を示すものであり、ここから日本の価値観が大きく転換した事はやはり事実なのでしょう。一方で、終戦記念日、という考え方を世界、特に周辺国や友好国と今までのように共有するには限界が近いようにも思えます。

終戦の価値観、一応、ロシアや中国などは対日戦勝記念日を掲げていますが、問題は日本が示した国際公序と似た、つまり力による現状変更による人間の尊厳への侵害や、海洋自由原則に相反する海洋閉塞主義の強要、単に対日戦勝記念日を国際公序と異なる正義の闘争ではなく、当時の競合国の脱落を記念したかたちとなっているのではないか、と。

国際公序という視座に立てば、連合国の制度はそのまま国際連盟から国際連合への発展的昇華により、第二次世界大戦のような戦争は根絶されるはずでしたが、現実はそうなっていません。結果的に日本は戦後、戦時中までの軍事へそそいだ国家資源を経済と教育に注いだことで経済的な発展を実現することとなり、その発展は新しい義務を生んでいました。

安全保障という視点からは、これが終戦記念日とその後の価値観は、果たして平和というものに指向しているのだろうか、少し考えさせられることがあるのです。むろん、これは一国平和主義という視座から早い時期に批判は存在していましたが、結局のところ平和を目的とせず手段とした平和憲法を堅持しているため、それが国民の選択ではあるのですが。
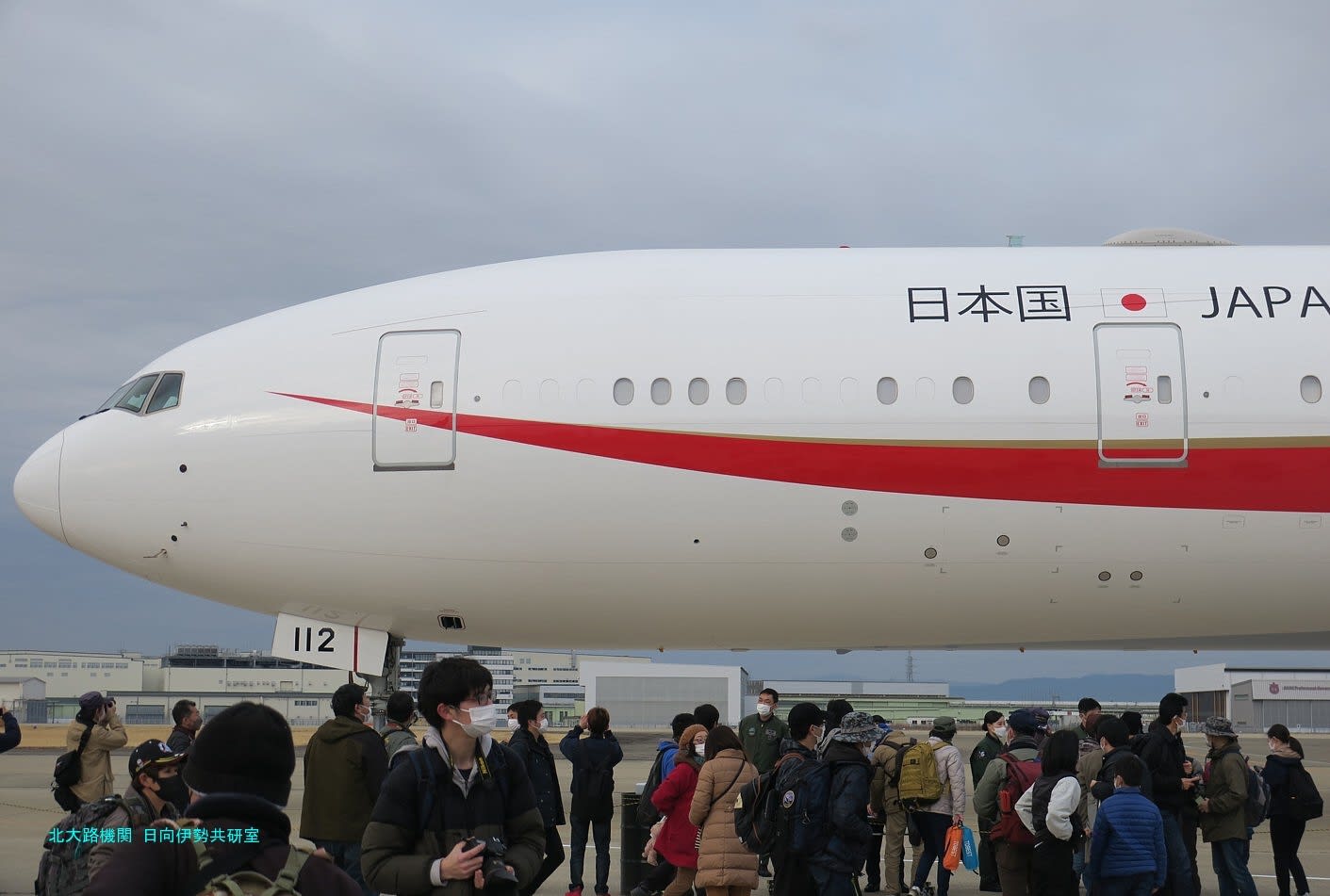
平和憲法が問題ではなく、平和を目的とした憲法が必要であり平和を手段とし、結果的に国民が平和を享受できない状態であっても瑕疵は無いとした理念を憲法が利用されていることが問題であり、この状況が放置されているのは、果たして平和というものを正面から考えているのか、考える努力をしているのかという素朴な危機感を受けてしまうのです。

反撃能力。もう一つ考えさせられるのは、2022年末に示された国家安全保障戦略に明示された反撃能力という概念で、これは伝統的な専守防衛の終焉を意味する、つまり、周辺国が日本本土に侵攻するまでは戦わず、逆に日本が侵略されて初めて、国土で国民の居住する国内で大規模な地上戦と国民を巻き込み戦うという従来の理念を脱したということ。

専守防衛は、国土が戦場になる、という前提があり、つまり侵攻された地域の住民や工業地帯や人口密集地の住民は戦闘に巻き込まれるか、ミサイルや航空攻撃による被害をある程度耐えなければなりません、絨毯爆撃を第二次世界大戦のように行う可能性は低いものの、ミサイルや自爆型無人機が数千から一万数千来ることは想定しなければならない。

政治はこうした視点から、国家防衛戦略に今後防衛力整備により国土戦を避ける防衛体制への転換を目指すとしています。もちろん、これは、結果としての平和を国民が享受するには、少なくとも、本土決戦主義、と揶揄されるような防衛政策よりは国民の生命財産に資するものなのかもしれませんが、憲法解釈の限度を超えているのではないか、とも。

本土決戦主義からの脱却は、個人的には必要だと考えます、けれどもその際には一内閣の憲法解釈ではなく、憲法改正を伴うべきであり、また政権与党以外の政党は現状の矛盾と、そして本土決戦主義の是非を含めて議論する、またはそうした政治家を国民が選び代議士とする選択肢があって然るべきなのですが、国会の議論はそこまで踏み込みません。

神学論争と揶揄されている通り、本来ならば現在の本土決戦主義という専守防衛の堅持か、反撃能力という国土と国民を戦争に巻き込まないが域外での戦闘を基本とする防衛戦略への転換かを議論すべきですが、具体的な防衛戦略まで言及することなく、後追いで、泥縄式に防衛政策を追認するか、議論せず金額などを批判するという状況に留まります。

大和とか敷島とか扶桑とか、いっそ日本国家が日本という名前を超えることができたならばこうした忸怩たる思いといいますか、敗戦や終戦というものの見方を自分事ではなく歴史として受け止められたのかもしれませんが、結局は自我自存の拠り所として共通する価値観、一億の日本人が共有できる価値観を直ぐには見つけられず、今に至ったよう思う。

日本が敗戦したのであり、日本が続いている。ただ、世界を見れば第二次世界大戦の延長線上で現在の各国情勢があるわけではありません、第二次世界大戦とニジェールクーデターは関係ありませんし、ロシアはそのつもりかもしれませんがロシアウクライナ戦争にナチスの影響はありません、台湾海峡もアフガニスタンのタリバン政権も、現代の問題だ。

平和について。そもそも普遍的な価値観と思われる平和についても、実のところその定義は何かと問われれば確たる答えを見つけられていないのではないか。単純に平和を戦争がない状況というならば、例えば飢餓は平和か、差別は平和か、投獄や強要が社会に満ちていた場合でも戦争が無ければ平和なのか、これ即ち、平和を考えていないだけでは、と。

終戦記念日は平和を重視するという視点では同意します、しかし、日本が参加した国際公序を守るための日本の責務に目を背ける口実となっていないか、平和とは戦争を考えない事ではない、こうした視点が必要なのではないか。昭和は遠くになりにけり、しかし次の戦争というものを回避する努力を十分行っていないよう、いま危惧してしまうのです。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
































