伝統ある明治大学のマンドリン倶楽部の演奏会を久しぶりに聴くことができ、素晴らしいマンドリンの音色に酔った。そしてまた演奏を聴きながらいろいろことに想いも巡らせた…
詰襟の学生服姿での演奏会は珍しいなぁ…。
選曲は聴衆のOBを意識して大人しい選曲になったのだろうか?
マンドリンに合う曲とそうでない曲があるなぁ…。
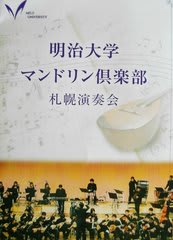
明大OBの知人からチケットを譲っていただき、思わぬ形で演奏会を聴く機会を得た。
9月10日(金)夕刻、ニトリ文化ホールを満杯に埋めた客の多くは私と同じようにかなり年齢が高い年代のようだった。
演奏会は、第1部「マンドリンとギターが奏でるクラシックの世界」、第2部「抒情あふれる珠玉のメロディー」、第3部「ザッツ・マンクラワールド」の三部構成だった。
倶楽部員は指揮者・司会者を含めて36名、それに数名の賛助出演があったようだ。
明大マンドリン倶楽部の創設は大正12年に遡るそうである。その当時は各大学にマンドリンのオーケストラができるなど一種のブームであったようだ。そうした数ある大学のマンドリンオーケストラの中で今日まで長く全国に名を轟かせているのは明大マンドリン倶楽部くらいしかないのではないだろうか。
その要因は倶楽部創設当初からクラッシックだけの選曲ではなく、童謡・民謡・歌謡曲、はてはラテンやジャズなどあらゆるジャンルの音楽を取り入れて演奏してきたことが多く方々から支持を得、今日に繋がっているのではないだろうか。

※ 真面目な指揮ぶりだけでなく、コミカルなパフォーマンス
が人気だった指揮者の前崎さん。
今回の演奏会でも1部・2部でクラッシックから、古賀メロディーや歌謡曲、民謡と多彩なメロディーを披露してくれた。そして第3部ではマンクラワールド?「なんじゃい、これは?」と思いましたが、どうやら明大マンドリンが得意とするラテンのメロディー溢れるステージを、明大マンドリンクラブワールドと称したようだ。
しかし、私が今回の演奏会で最もマンドリンの音色の良さを感じたのは、さだまさし作曲の「秋桜」だった。抒情あふれるこの曲が、マンドリンの繊細な音色とともに私の耳に届いたとき、私の中の琴線が激しくふるえるのを感じた。

※ 抜群の技量を披露した第一マンドリンでコンサートマスターの篠山さん。
さて、ここからは私の単なる感想なのだが…。
まずクラブの人数が少ないのではないかと気になった。
学生のクラブであるから、その年度によって構成人数が変わってくるのはしかたないとしても、指揮者・司会者を入れても36名とはオーケストラとしてはいかにも寂しい。
音楽性の問題、学業との両立、個人主義の世相など、伝統あるクラブを維持していくことが難しい時代になっているのだろうか。関係者の勧誘活動の一層の奮闘を期待したい。
次に素人が音楽的なことに口を挟んでみたい。
あらゆるジャンルの音楽に挑戦するという姿勢は賛成なのだが、そのためにマンドリン以外の楽器が多くなっているキライはないだろうか。特に電気楽器や管楽器などにマンドリンの音がかき消されてしまう場面が何度かあったように思う。全体の人数の寂しさがここにも影響しているのか。
次に、選曲、編曲のことであるが、やはりマンドリンに合う曲、合わない曲があるように思う。もちろんクラブ関係者はそのことを常に意識されていると思うが、なお一層留意してほしいと思う。特に、優れた先輩がたくさんいるということなので、選定した曲を明大マンドリンにぴったりとくるような編曲に意を注いでほしいと思う。

※ 楽しそうに演奏している姿が印象的だったマンドラのパートトップの山本さん。
以上、勝手なことを書いてきたが、倶楽部員一人ひとりが心からマンドリンの演奏を楽しんでいることが伝わってきたし、聴衆の多くも心から演奏を楽しんでいた(もちろん私も)素晴らしい演奏会だった。
詰襟の学生服姿での演奏会は珍しいなぁ…。
選曲は聴衆のOBを意識して大人しい選曲になったのだろうか?
マンドリンに合う曲とそうでない曲があるなぁ…。
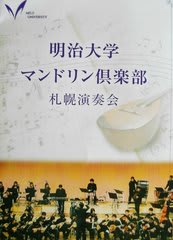
明大OBの知人からチケットを譲っていただき、思わぬ形で演奏会を聴く機会を得た。
9月10日(金)夕刻、ニトリ文化ホールを満杯に埋めた客の多くは私と同じようにかなり年齢が高い年代のようだった。
演奏会は、第1部「マンドリンとギターが奏でるクラシックの世界」、第2部「抒情あふれる珠玉のメロディー」、第3部「ザッツ・マンクラワールド」の三部構成だった。
倶楽部員は指揮者・司会者を含めて36名、それに数名の賛助出演があったようだ。
明大マンドリン倶楽部の創設は大正12年に遡るそうである。その当時は各大学にマンドリンのオーケストラができるなど一種のブームであったようだ。そうした数ある大学のマンドリンオーケストラの中で今日まで長く全国に名を轟かせているのは明大マンドリン倶楽部くらいしかないのではないだろうか。
その要因は倶楽部創設当初からクラッシックだけの選曲ではなく、童謡・民謡・歌謡曲、はてはラテンやジャズなどあらゆるジャンルの音楽を取り入れて演奏してきたことが多く方々から支持を得、今日に繋がっているのではないだろうか。

※ 真面目な指揮ぶりだけでなく、コミカルなパフォーマンス
が人気だった指揮者の前崎さん。
今回の演奏会でも1部・2部でクラッシックから、古賀メロディーや歌謡曲、民謡と多彩なメロディーを披露してくれた。そして第3部ではマンクラワールド?「なんじゃい、これは?」と思いましたが、どうやら明大マンドリンが得意とするラテンのメロディー溢れるステージを、明大マンドリンクラブワールドと称したようだ。
しかし、私が今回の演奏会で最もマンドリンの音色の良さを感じたのは、さだまさし作曲の「秋桜」だった。抒情あふれるこの曲が、マンドリンの繊細な音色とともに私の耳に届いたとき、私の中の琴線が激しくふるえるのを感じた。

※ 抜群の技量を披露した第一マンドリンでコンサートマスターの篠山さん。
さて、ここからは私の単なる感想なのだが…。
まずクラブの人数が少ないのではないかと気になった。
学生のクラブであるから、その年度によって構成人数が変わってくるのはしかたないとしても、指揮者・司会者を入れても36名とはオーケストラとしてはいかにも寂しい。
音楽性の問題、学業との両立、個人主義の世相など、伝統あるクラブを維持していくことが難しい時代になっているのだろうか。関係者の勧誘活動の一層の奮闘を期待したい。
次に素人が音楽的なことに口を挟んでみたい。
あらゆるジャンルの音楽に挑戦するという姿勢は賛成なのだが、そのためにマンドリン以外の楽器が多くなっているキライはないだろうか。特に電気楽器や管楽器などにマンドリンの音がかき消されてしまう場面が何度かあったように思う。全体の人数の寂しさがここにも影響しているのか。
次に、選曲、編曲のことであるが、やはりマンドリンに合う曲、合わない曲があるように思う。もちろんクラブ関係者はそのことを常に意識されていると思うが、なお一層留意してほしいと思う。特に、優れた先輩がたくさんいるということなので、選定した曲を明大マンドリンにぴったりとくるような編曲に意を注いでほしいと思う。

※ 楽しそうに演奏している姿が印象的だったマンドラのパートトップの山本さん。
以上、勝手なことを書いてきたが、倶楽部員一人ひとりが心からマンドリンの演奏を楽しんでいることが伝わってきたし、聴衆の多くも心から演奏を楽しんでいた(もちろん私も)素晴らしい演奏会だった。









