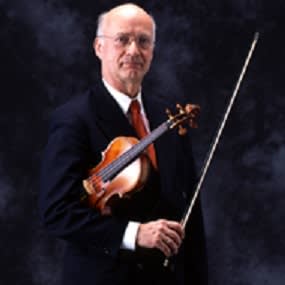「文学」などというと、私から最も遠い存在の一つである。札幌都心のオアシス「中島公園」内にある「北海道立文学館」(中央区中島公園1番地)は、側は通れども内部に足を踏み入れることはこれまでなかった。
7月17日(金)午後、私が所属する退職組織の団体の年に一度の研修先として「北海道立文学館」に選ばれたことで初めて訪れることになった。

※ 北海道立文学館の正面入り口です。
道立文学館は、エントランスのフロアーがある上階と半地下の下階からなっていたが、私たちが見た「北海道の文学」に関する展示は下階にあった。
文学館では学芸員が私たちのために説明についてくれ、逐一丁寧に説明してくれた。

※ エントランスフロアーから常設展のある地下フロアーを望んだところです。
「北海道の文学」の黎明期はやはり北海道の開拓の歴史との関わりが大きいようである。それは文学というよりも、間宮林蔵の樺太探検記や、松浦武四郎の北海道探索記のような類いのものがその最初である。
やがて、北海道農学校(現北大)の誕生により、そこから内村鑑三、新渡戸稲造、有島武郎といった逸材が輩出された。特に本格的な文学者としては有島武郎が最初に記される人材といってよいのかと思われる。
この明治期には、幸田露伴、国木田独歩、石川啄木などが、文学的興味からか北海道を訪れ、北海道に関する作品を著している。
文学館では、この明治期の北海道の文学を《20世紀への胎動/助走期の苦闘/漂白と彷徨》と呼称し、時代分けをしている。
続く大正期~昭和戦前期については《道産子作家の誕生/逆流のさなかで/モダニズムの台頭》と称している。
この時代には、子母澤寛、森田たま、小林多喜二、伊藤整といった明治期以来の移民の子弟から作家が誕生した時代である。小林多喜二のプロレタリア文学、伊藤整のモダニズム文学など、日本を代表する作家も誕生した時代である。
続いては昭和の戦中期~戦後期であるが、この時代を《戦火の中で/復興と再生》と文学館では時代分けをしている。
この時期の作家としては、坂本直行、亀井勝一郎、船山馨などが有名である。
最後の区分けは高度成長期~現代として、この時期を《成長期の精華/変転する現代》と称している。この時代になると、純粋に北海道に生れ、北海道に根ざした作家が誕生してきた時代とも言えよう。その代表格が「挽歌」の原田康子であり、「氷点」の三浦綾子である。
また、芥川賞や直木賞作家が誕生するのもこの時代になってからである。ちなみに北海道に関係する受賞者は、芥川賞が1979年上半期の高橋揆一郎、1988年下半期の池澤夏樹、直木賞が1989年下半期の藤堂志津子、2013年上半期の桜木紫乃などが道内関係者として挙げられる。

※ 「北海道の文学」の展示室の一部です。
以上のように北海道立文学館では、「北海道の文学」を4つの時代区分に区切って展示してあったが、感度の鈍い私としてはそこに北海道としての文学的特徴を見出すことはできなかった。ただ、生粋の道産子が作家として登場するのは戦後になってから、というところに北海道が開拓されてまだまだ日が浅いということの証しの一つなのかな?と思われた。
また、文学という営みがきわめて個人的な営為ということから、同人誌的な活動はあったものの、そこから大きなうねりのようなものは生れてこなかったようである。
なお、時代系列的な展示とは別に、口承文芸として語り継がれてきたアイヌ民族の文学のコーナーが設けられていたが、これも北海道の文学の一分野としてけっして忘れてはならない財産なのだと思う。
私のように文学に縁遠い人間であっても、北海道の歩みを理解する一助として北海道立文学館を訪れてみることは一興のように思われる。