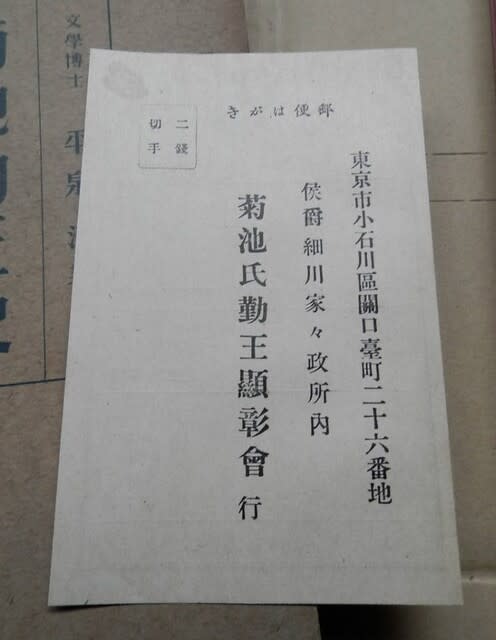先日■熊本城下屋舗割之図からを書いたあと、以前二の丸に居住した方々の四つの時代の屋敷の主の変遷を取り上げたと思い、過去のブログを調べてみたら■二の丸の屋敷群というのが出てきた。
これを眺めていたら、先の記事に間違いがあったことに気付いた。(後に訂正させていただく)
改めて当時の記事を引用して、再検討する。


加藤時代(上図)と細川家の四つの時代(下図)の屋敷の主の変遷。
加藤時代(寛永初期) (1)明暦期 (2)元禄前後 (3)宝暦年後半 (4)天明年前後
下津棒庵・・・大木
(へ)大木四郎・・・御目付屋敷
(ほ) 同上
a (は)・・・清田儀左衛門尉ヨリ上・・・・・→御用屋敷・・・・・・・・→( bに吸収 )
b (に)・明屋敷・・・芦村惣兵衛・・・・・・・→住江甚右衛門・・・・・・→長岡岩之助・・・・・・・・→長岡右門
c 相田内匠・他・・・・長岡監物(足屋敷二軒共)・→同左・・・・・・・・・・→同左・・・・・・・・・・・→長岡丹波
d 下川又左衛門・・・・平野茂左衛門・・・・・・→氏家甚左衛門・・・・・・→学校(時習館)・・・・・・→学校(時習館)
e 下川平吉・本庄某・・・川喜多九太夫・・・・・→川喜多治部右衛門・・・・→( 時習館敷地となる )
f 加藤右馬允・・・・・長岡佐渡守・・・・・・・・→高見三右衛門・・・・・・→沼田勘解由・・・・・・・・→沼田熊五郎
g 蟹江主膳・・・・・・ (不明)・・・・・・・→竹内吉兵衛・・・・・・・・→沼田勘解由・・・・・・・・→沼田熊五郎
h 新美八左衛門・・・・尾藤金左衛門・・・・・・→尾藤助之丞・・・・・・・・→有吉万之進・・・・・・・・→松井土岐
i 加藤右馬允・・・・・松井帯刀・・・・・・・・・→同左・・・・・・・・・・→松井主水・・・・・・・・・→松井帯刀
J 坂井内藏允・・・・・竹内吉十郎・・・・・・・・→小坂半之丞・・・・・・・→西山多膳・・・・・・・・・→長岡丹波添屋敷
k 真田安左衛門・・・・尾藤貞右衛門・・・・・・・→田中忠介・・・・・・・・→溝口蔵人添屋敷・・・・・・→長岡助右衛門添屋敷
l 随雲・・・・・・・・牧丞太夫・・・・・・・・・→松野半右衛門・・・・・・・→ 同上 ・・・・・・・・→同上
m 水野左膳・相田六左衛門・・住江求馬・・・・・→志水三右衛門・・・・・・・→溝口蔵人・・・・・・・・・→米田波門
n 庄林隼人・・・・・田中左兵衛(足屋敷共)・・→ 同左 ・・・・・・・・→田中兵庫・・・・・・・・・→田中左兵衛
o 不明・・・・・・・中村伊織・・・・・・・・・→中村庄兵衛・・・・・・・→住江甚右衛門・・・・・・・→同左
p 不明・・・・・・・志水伯耆・・・・・・・・・→柏原新左衛門・・・・・・→小笠原備前・・・・・・・・→同左
q 不明・・・・・・・下津縫殿助・・・・・・・・→下津求馬・・・・・・・・→小笠原備前添屋敷・・・・・→同左