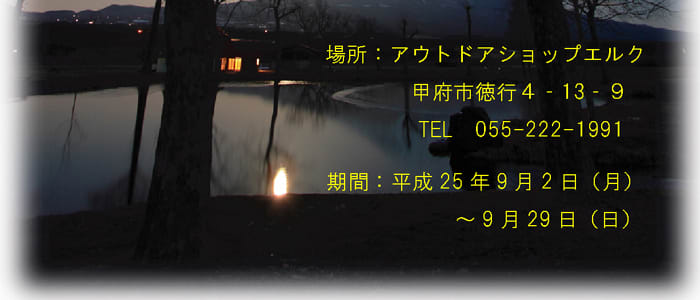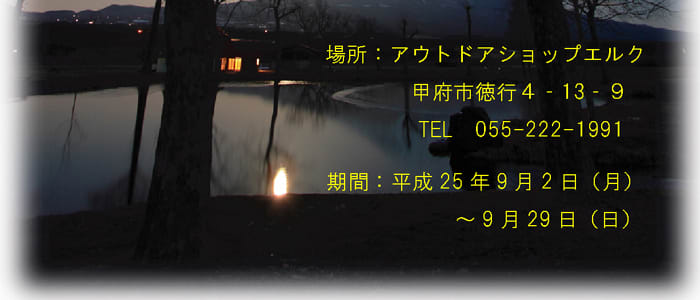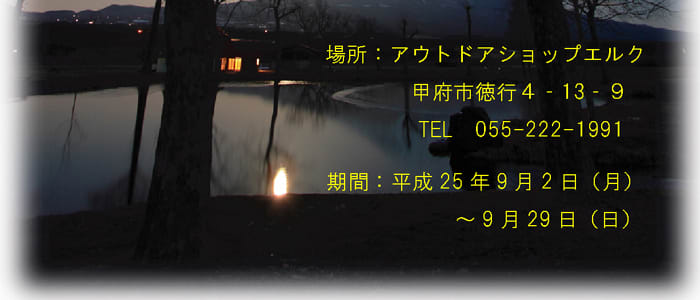暑い、とにかく連日の猛暑の甲府盆地。車の温度計は連日のように40℃を越えている。下手に近場の低山などに行こうものなら、暑さでうだってしまいそうだ。南アルプスに行くだけの時間もとれない。ならば、得意の夜登山、も考えたがそれだけの根性が出ず星も出てくれない。八ヶ岳以来、3週間も山歩きしていないと、さすがにヤバいのでは・・・と思って来る。そこで、近場の山をまだ朝の涼しいうちに登ってお昼ごろに下山、という手段をとることにした。早起きは苦手だが当直が無かった今週は比較的元気なので、なんとか起きられるだろう。
昨年もこの時期に訪れている御坂山系黒岳の森だが、レンゲショウマがたくさん咲き、オクモミジハグマで吸密するアサギマダラが飛び交う自然豊かな森だ。日向坂峠(どんべいとうげ)側からの登山道沿いにもレンゲショウマがたくさん咲くのだが、今回はほとんど人の入らない西側に派生する尾根を直登する。おそらくはレンゲショウマがたくさんあるはずだ。朝5時起き、7時を少し過ぎた頃から登り始める。

林道を歩き始めるとさっそくアサギマダラがお出迎え。

こちらのキアゲハは眠っているのか、カメラを近付けても全く動かない。

すずらん峠への登山道から黒岳の森に入る。
標高1500mあたりのところで登山道を外れて尾根に取り着く。道は無いのだが草籔ではなく、普通に歩ける。レンゲショウマらしき葉っぱはたくさんあるのだが、花はほとんど着いていないし、咲いた様子も無い。全てがレンゲショウマでは無く、トリアシショウマが半分ほど混ざっているようだ。まばらに咲いているレンゲショウマを見つけたが、1~2週間時期が遅く、もう花が痛んでいるものや散ってしまっているものが多い。

トリアシショウマが半分ほど混じる。

まばらにマルバタケブキが咲く。

ポツリポツリと咲くレンゲショウマはやや時期が遅い。

レンゲショウマの群生だが、ほとんど花の咲いた様子が無い。ハズレ年なのか、それとも咲かないのか、あるいは鹿の食害か??

咲き残っていたレンゲショウマ

逆光のレンゲショウマ
獣道を頼りに森を右に左にさまよいながら登って行く。ヤブレガサと思っていた葉っぱはどうやらモミジガサだったようで、たくさんの花茎を長く伸ばしていた。不思議なのは食害らしきトリカブトの花芽だ。毒草だと思うのだが、場所によってはほとんど食べつくされている。

モミジガサの大群落と花茎

モミジガサの花。もうほとんど散って痛んでいる。

食害と思われるトリカブトの花芽。
山頂まであと10分ほどのところで日向坂峠側の道と合流する。そのあたりから花の様子が少し変わり、ハクサンフウロ(カイフウロ?)やオクモミジハグマ、テンニンソウ、フシグロセンノウなどが咲き、吸密するアサギマダラが舞っている。

ハクサンフウロ(カイフウロ?)

テンニンソウで吸密するアサギマダラ。

シュロソウが登山道脇に咲く。

山頂に咲いたフシグロセンノウは今年は大当たり。

何アザミでしょうか?フジアザミ以外はほとんど区別できません。

黒岳山頂。
展望台に行くと、この季節にしては珍しく富士山が見えていた。時間は9時45分、気温は約20℃、さほど暑くは無く、快適だ。軽食をとって30分ほど富士山を眺めて下山する。富士山が見えているので、すずらん峠側のルートを下山し、花と富士山が一緒に写し込める場所が無いかどうか探しながら下ったが、残念ながら良さそうな場所は見つからなかった。

黒岳展望台から見る夏富士

下界は今日も猛暑日だが、空の上を流れる雲は秋の筋雲。

マルバタケブキ。バックに富士山は写し込めず。

再び逆光のレンゲショウマ。尾根筋よりもこちら側のルートのほうがたくさん咲いていた。
11時過ぎに下山したが、車の温度計は既に30℃を指していた。山上の気温もおそらくは午後になるとそのくらいの温度になると思われる。猛暑の中を歩くのは肥満体形で大汗をかく私にとってはかなり辛い。