就職や転職の場合、以前はコネや人脈を使うことが多かった。しかし最近の日本では転職支援の専門会社やインターネット転職情報があり、コネや人脈に頼らなくなって来た。誰にでも公平にチャンスを与えている。若者の転職の仕方は以前より倫理的な意味で前進したと思う。嬉しく思う。
しかし、アメリカ社会では昔から機会均等、努力すればチャンスはいつでも有る。コネや人脈を使うのは卑怯なことだ。そんな社会倫理がある。アメリカ社会にも暗部はいくらでもある。でも、以下のような体験は、現在の若者にも参考になるに違いない。若い方々のコメントを頂ければ幸いです。
◆黒人軍曹に教わった留学の方法
1959年、仙台の郊外の八木山に進駐軍が通信用のアンテナを立てる。山林の伐採、整地作業を20人ほどの日本人が行う。現場監督はひとりの黒人軍曹である。通訳として3日間働いた。作業をしない軍曹と通訳は暇である。
「キージンガー軍曹さん、アメリカへ留学したいがお金も無いし、方法も知らないし、どうしたら良いのでしょう?」「私も来年除隊して大学へ行くよ。理工学系の大学院では月謝と生活費を出しているのが普通だよ」
「どうすれば留学先を探せるのですか?」「簡単さ、行きたい大学の教授に手紙をだすのさ。何を研究したいか明快に書くことが肝心だよ」
「誰かそのような教授を紹介してくださいませんか?」「アメリカでは紹介無しで直接手紙を出した方が真面目に検討してくれるよ」
数学が得意だという黒人の青年が目を輝かせ、自信に満ちて教えてくれた。学会誌で調べ、アメリカ人教授10人へ航空便を送る。3人から月謝と生活費を出してあげると返事がくる。3人からは丁寧な断り状。あとの4人はナシのつぶて。
1960年、オハイオ州立大学のセント・ピエール教授のところへ行くことになった。しばらくして親しくなってから教授が言う。
「インドや台湾、日本からの推薦状はウソが多くて困ったものです」「推薦状では褒め言葉だけを書くという文化なのです。それは仕方ないのです」。弁護したが分かってもらえない。
◆月給と研究費は自分で稼げ
後にこのセント・ピエール教授がオハイオの材料科学の学科主任になった。1988年に客員教授として呼んでくれた。着任した最初の日に主任が言う。
「一年間、月給は10ケ月だけ出します。2ケ月は休むなり働くなり自由にしてください。最初の一年の研究費は学科で出します。しかし二年目からは自分の月給と研究費は外部の会社や軍隊の研究所から貰って来てください」「先生、そんなことは無理です。アメリカでは人脈も無いので一年以内に外部から研究費など持って来られません」。
セント・ピエール教授の目が静かな怒りでキラリと光り、筆者の顔を見つめながら言う。
「古い人間的なつながりを利用して経済的な利益を得ようとしてはいけない。その考えが社会を腐敗させるのです。研究費を貰うには人脈やコネを使ってはいけません。将来の研究計画をきちんと書いて先方に送り、会う約束を取り付けて自分の研究がなぜ先方の役に立つか明瞭に説明して研究費を貰いなさい。」「手紙を送る相手の名前も住所も知らないし、昔の友人に頼んでもいけないのですか?」
「君の研究内容に興味を持ちそうな人の名前と住所はあとで沢山教えるよ。しかし友人を使うのは止めなさい。自分の経済的利益の為に友人を使えばアメリカでは友人がいなくなりますよ」「人脈やコネが重要な国は良くないとおっしゃるのですね?」「いや、そのような文化の国も尊重します。でもアメリカは違うのです。いつも新鮮でダイナミックな社会を維持するにはアメリカでは人脈を排除しているだけなのです」
◆日本での就職・転職先の探し方がどのように変化したか?
就職・転職先はどのようにして探すか?人生の一大事。
その方法がその国の文化の性質を浮き彫りにしている。両親や学校の先生に頼る。人脈やコネを使う。それが望ましい方法であると周りの人が言う。社会からも歓迎される。
第2次大戦後のしばらくは人脈やコネの重要さが戦前とあまり違わない。第2次大戦後、日本で軍隊は無くなったが、人間関係はあまり変わらなかった。
和魂洋才を大切にして、工業技術のみ追いつき追い越せ。こんな風潮がなかったと言えばうそになる。
しかし1990年前後のバブル経済の崩壊によってこんな日本の文化も変り出した。特にインターネットの普及が文化の変質を加速する。就職情報、転職情報がインターネットで隆盛を極める。その勢いは人脈やコネという言葉を廃語にする。
ある人々は非常に淋しい思いでそんな変化を嘆いている。しかし、社会の公平性の前進という視点でみれば良いことではないだろうか?
就職・転職の仕方が変わったから日本の伝統文化も無くなるという議論は浅薄すぎると思う。
21世紀の日本文化の独自性は何か、老人も若者も一緒に議論出来れば良いと思う。 (続く)
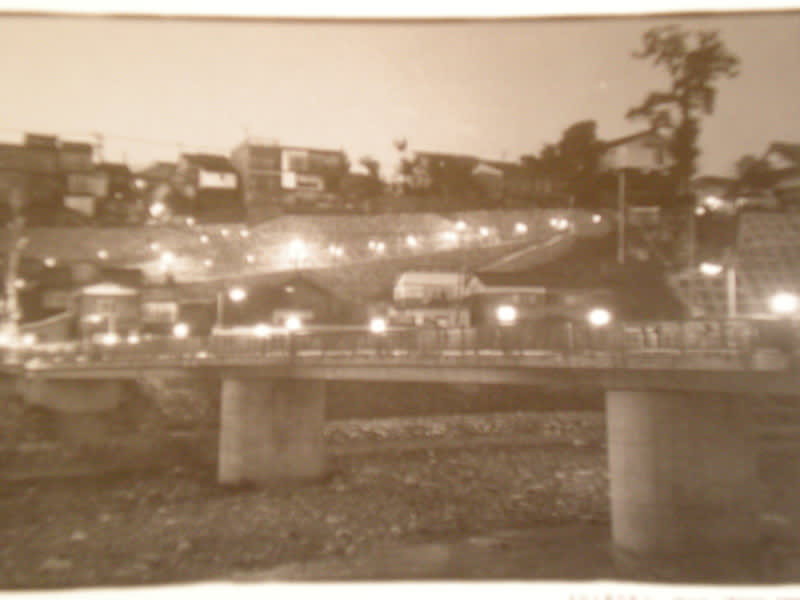 駐車場は町の外の川沿いにある。観光客は高台にある八尾の町へ登って行く。この写真のように夏の夕風にゆれる街灯の列の下をゆっくりと。風の盆を以前に見た人々が混じっているのか歩き方がもう優雅になっている。帰りにこの坂を下る人々は一層静かに歩く (終わり)
駐車場は町の外の川沿いにある。観光客は高台にある八尾の町へ登って行く。この写真のように夏の夕風にゆれる街灯の列の下をゆっくりと。風の盆を以前に見た人々が混じっているのか歩き方がもう優雅になっている。帰りにこの坂を下る人々は一層静かに歩く (終わり)





















