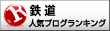長崎まで往復の飛行機中。一気に読み進めた本。作家・脚本家・映画監督・・・。84年、70歳で執筆した『愛人』から7年余りの後。自身の生涯の終わり間近に、その「愛人」の死を(それも何年も前に死んだ、と)人づてに聞いて、「小説の作者に戻った」と前書き風の文章には、ある。
巻末の訳者・清水徹氏の解説が懇切丁寧で、その背景の一部始終が紹介されていると、読後感にも揺らぎが出てしまうのは、恐い。「自伝「的(らしき)」小説であることということのこだわり(「自伝」ではない)・指摘は、まさにその通り。
「愛人ラマン」を先に読み、その後に映画化された作品・『愛人―ラマン』を観直し、そしてこの作品と、読み進めていけるのは、読者の最大の特権。
作品として原作を脚本化し、再構成した映画(制作準備段階からご本人はえらくご不満だったようだ)との内容的・映像的な重なりを意識しつつ、一方でその根本的な相違(制作費と興行収入とを常にはかりにかけなければならない「娯楽」としての映画制作は、原作者の意図に反することも、またそれ故に原作を越えて映像化できることも・・・)を感じることができるのが、強みでもある。
特に作者は、文字世界と映像(写真)世界との視点の往来を客観化(言語化)することに、実に卓越しているので、ますます読書する楽しみが増す。
この『北の愛人』(邦訳としてはこうなるしかないかも知れないが、ニュアンスがイマイチ伝わらない)で、気になったのは、「タン」という人物の存在。孤児になった男の子。母親が引き取って二人の兄と少女の3人の子どもたちとともに育てているという設定。いつも少女と行動し、兄と妹のような関係。女の子の方は、タンと性的関係を持ちたいが、タンは拒絶している。
いつかシャムに戻って、両親を探し妹や弟との再会を期している(かなわぬ願い)。さらに「中国の男」(少女の愛人で、困窮している一家への多額な金銭的な援助を行っている)とも密接な関わりをもち、行き来し、家族への多額の金銭を預かりもする。
フランスに帰国し、長い年月が経った後、ずっと関わりを持っていなかったかつての愛人(中国の男)からの電話の中で、タンはその後一度も便りがないこと、シャムの森の中に帰っていったがきっと道に迷って死んでしまったにちがいないと、男は言う。
小説の冒頭に、「タンに」との献辞が置かれてある。それほど「わたし」にとって重要な人物。公開された映画ではまったく存在しない人物でもある。タンは、「わたし」にとって、今もって(執筆的現在において)どういう存在なのか? 存在感があるようで、ない、という印象を読者に与える。
「あの中国の男の死、あの人の身体の死、あのひとの肌、あのひととのセックス、あのひとの手の死(注 映画の冒頭、車の中での少女と中国の男との手との微妙な触れあいから、性的関係の中での少女の繊細な体を洗う細やかな手つきなど、見事に映像化して印象深い)が起ころうなどとは想像もしていなかった。」・・・
「こんどは、物語を語っているうちに、突然、現れたのだ、まばゆい光を浴びて、タンの顔と―それから下の兄、私と同類だったもうひとりの男の子の顔とが。わたしは、あれらの人びとと一緒に、物語のなかにいつづけた、一緒にいたのはあの人たちだけだ。」
中国の男も、タンも、そして下の兄もすでに死して、この世(今)にはいない。取り残された「わたし」。「死」の匂いが色濃くなってきたとき、はじめて物語の作者になったのだ、と思える。愛の物語から死への物語、むしろ、死の物語から生の(人間が息づく)物語へとなっていったのではないか。
作者の、80歳近くになってもいまだ衰えを知らない、奥深く幅広い研ぎ澄まされた感性が、そして、その奥に潜む死へのおののきが濃密に展開される作品であった。
 映画のラストシーン。ショパンのピアノ曲を聴きながら、中国の男を愛していたことを実感し、涙する場面。『北の愛人』は、ここから遡っていく物語でもある。
映画のラストシーン。ショパンのピアノ曲を聴きながら、中国の男を愛していたことを実感し、涙する場面。『北の愛人』は、ここから遡っていく物語でもある。
巻末の訳者・清水徹氏の解説が懇切丁寧で、その背景の一部始終が紹介されていると、読後感にも揺らぎが出てしまうのは、恐い。「自伝「的(らしき)」小説であることということのこだわり(「自伝」ではない)・指摘は、まさにその通り。
「愛人ラマン」を先に読み、その後に映画化された作品・『愛人―ラマン』を観直し、そしてこの作品と、読み進めていけるのは、読者の最大の特権。
作品として原作を脚本化し、再構成した映画(制作準備段階からご本人はえらくご不満だったようだ)との内容的・映像的な重なりを意識しつつ、一方でその根本的な相違(制作費と興行収入とを常にはかりにかけなければならない「娯楽」としての映画制作は、原作者の意図に反することも、またそれ故に原作を越えて映像化できることも・・・)を感じることができるのが、強みでもある。
特に作者は、文字世界と映像(写真)世界との視点の往来を客観化(言語化)することに、実に卓越しているので、ますます読書する楽しみが増す。
この『北の愛人』(邦訳としてはこうなるしかないかも知れないが、ニュアンスがイマイチ伝わらない)で、気になったのは、「タン」という人物の存在。孤児になった男の子。母親が引き取って二人の兄と少女の3人の子どもたちとともに育てているという設定。いつも少女と行動し、兄と妹のような関係。女の子の方は、タンと性的関係を持ちたいが、タンは拒絶している。
いつかシャムに戻って、両親を探し妹や弟との再会を期している(かなわぬ願い)。さらに「中国の男」(少女の愛人で、困窮している一家への多額な金銭的な援助を行っている)とも密接な関わりをもち、行き来し、家族への多額の金銭を預かりもする。
フランスに帰国し、長い年月が経った後、ずっと関わりを持っていなかったかつての愛人(中国の男)からの電話の中で、タンはその後一度も便りがないこと、シャムの森の中に帰っていったがきっと道に迷って死んでしまったにちがいないと、男は言う。
小説の冒頭に、「タンに」との献辞が置かれてある。それほど「わたし」にとって重要な人物。公開された映画ではまったく存在しない人物でもある。タンは、「わたし」にとって、今もって(執筆的現在において)どういう存在なのか? 存在感があるようで、ない、という印象を読者に与える。
「あの中国の男の死、あの人の身体の死、あのひとの肌、あのひととのセックス、あのひとの手の死(注 映画の冒頭、車の中での少女と中国の男との手との微妙な触れあいから、性的関係の中での少女の繊細な体を洗う細やかな手つきなど、見事に映像化して印象深い)が起ころうなどとは想像もしていなかった。」・・・
「こんどは、物語を語っているうちに、突然、現れたのだ、まばゆい光を浴びて、タンの顔と―それから下の兄、私と同類だったもうひとりの男の子の顔とが。わたしは、あれらの人びとと一緒に、物語のなかにいつづけた、一緒にいたのはあの人たちだけだ。」
中国の男も、タンも、そして下の兄もすでに死して、この世(今)にはいない。取り残された「わたし」。「死」の匂いが色濃くなってきたとき、はじめて物語の作者になったのだ、と思える。愛の物語から死への物語、むしろ、死の物語から生の(人間が息づく)物語へとなっていったのではないか。
作者の、80歳近くになってもいまだ衰えを知らない、奥深く幅広い研ぎ澄まされた感性が、そして、その奥に潜む死へのおののきが濃密に展開される作品であった。
 映画のラストシーン。ショパンのピアノ曲を聴きながら、中国の男を愛していたことを実感し、涙する場面。『北の愛人』は、ここから遡っていく物語でもある。
映画のラストシーン。ショパンのピアノ曲を聴きながら、中国の男を愛していたことを実感し、涙する場面。『北の愛人』は、ここから遡っていく物語でもある。