差別表現、すぐ撤回=自民・溝手氏(時事通信) - goo ニュース
オートフォーカスコンパクトカメラの通称として、1980年代前半まで、「バカチョンカメラ」という呼び名が一般に用いられていた。語源には下記のような説がある。
1.英語のフール・プルーフの訳語で、「カメラの使い方を知らなくても、絞りやシャッタースピードの調整を気にせず使えるカメラ」つまりプログラムEE(当時の呼称。現在のプログラムAE)つきの、「ばかでもちょんでも使えるカメラ」という意味。
2.バケーションカメラのローマ字綴り (vacation camera) を日本語読みしたという説、あるいは英語発音の聴き取り間違い。
3.専門知識を要することなく、「バカでも(シャッターを)チョンと押せば撮影できる」の意。
1の説について、「『ちょん』が朝鮮人に対する蔑称である『チョン』『チョン公』のことを指している」とされ、「バカチョンカメラ」の呼称の使用が自粛されるようになった。
※「ちょん」
①たやすく物を切るさま。
②拍子木の音。また、芝居の幕切れに拍子木を打つことから物事の終了。
③しるしに打つ点。ちょぼ。
④おろかな者、取るに足らない者としてあざけり言う語。(西洋道中膝栗毛「かりそめにも亭主に向かって・・・ばかだの、ちょんだの、野呂間だのと」)。(『広辞苑 第五版』より)
ここでは、朝鮮人を蔑む意味を含んではいない。
1910年、「韓国併合条約」によって大日本帝国は大韓帝国を併合。これにより、朝鮮半島は第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争)終結まで、大日本帝国の統治下に置かれた。
これ以降、元々、侮蔑的な意味合いを持っていた「ちょん」が韓国・朝鮮人の蔑称として、日本人一般にも意識されるようになった、と思われる。(「ちょん」公などというように)。
その後、オートフォーカスコンパクトカメラのCMのキャッチコピーで、「専門知識がなくても誰でも使える」、操作が簡単なカメラとして、「バカチョンカメラ」という言葉が広まった。また、「カメラ」に対してだけではなく、「バカでもチョンでも・・・」、という(侮蔑的な)言い回しとして、ふだんの会話の中でも用いられた。
こうした用いられ方の歴史を踏まえ、一時、人口に膾炙した「バカチョン」は「馬鹿でも朝鮮人でも」と朝鮮人に対する差別的・侮蔑的言葉を含むものとして、現在は放送禁止用語となっている。
最近では、2012年5月24日放送の報道ステーションで、ゲストの飯田哲也が「原子力に反対する奴はバカだチョンだ」と発言し、キャスターの古舘伊知郎が謝罪。
また、今年8月7日、自民党の溝手顕正が党の会合で「安倍晋三首相のように非常に勢いのいい首相の下だと、ばかでもチョンでも(当選する)という要素があるのは否定できない」と発言、ただちに撤回するという事態も生じた。
そのことばを聞いたとき、対象とされた人間が嫌悪感、不快感などを持つことばを安易に用いないのは、人間関係(まして、国際化社会)では常識。本人はそういうつもりがないと弁明しても。したがって、「バカ(だ・でも)チョン(だ・でも)」は、公人が公の席で発する言葉ではないだろう。
しかし、正直なところ、久々に聞いたというのが実感。去年、今年と、こうして露骨に発言した(直ちに撤回、謝罪はしたが)とは、驚き。
ちなみに独身男性の蔑称「チョンガー」と言う言葉は、もともと朝鮮の言葉。実は、このことばも1910年「日韓併合」以降に、日本人社会にも持ち込まれたようだ。
昔の朝鮮の風習で、成人をした男性は結婚するまでの間、髪の毛にリボンをつけた(ポニーテールのような)お下げ髪にすることになっていた。この髪型を総角(チョンガー)と言った。
なかなか結婚しない(できない)人は、いつまでもチョンガーのままだった。それがいつしか、いい年をしていて、いつまでも独身で居る男性のことを指して、軽蔑した意味を込めて「チョンガー」と言うようになった、そうだ。(以上、「Wikipedia」など参照)
オートフォーカスコンパクトカメラの通称として、1980年代前半まで、「バカチョンカメラ」という呼び名が一般に用いられていた。語源には下記のような説がある。
1.英語のフール・プルーフの訳語で、「カメラの使い方を知らなくても、絞りやシャッタースピードの調整を気にせず使えるカメラ」つまりプログラムEE(当時の呼称。現在のプログラムAE)つきの、「ばかでもちょんでも使えるカメラ」という意味。
2.バケーションカメラのローマ字綴り (vacation camera) を日本語読みしたという説、あるいは英語発音の聴き取り間違い。
3.専門知識を要することなく、「バカでも(シャッターを)チョンと押せば撮影できる」の意。
1の説について、「『ちょん』が朝鮮人に対する蔑称である『チョン』『チョン公』のことを指している」とされ、「バカチョンカメラ」の呼称の使用が自粛されるようになった。
※「ちょん」
①たやすく物を切るさま。
②拍子木の音。また、芝居の幕切れに拍子木を打つことから物事の終了。
③しるしに打つ点。ちょぼ。
④おろかな者、取るに足らない者としてあざけり言う語。(西洋道中膝栗毛「かりそめにも亭主に向かって・・・ばかだの、ちょんだの、野呂間だのと」)。(『広辞苑 第五版』より)
ここでは、朝鮮人を蔑む意味を含んではいない。
1910年、「韓国併合条約」によって大日本帝国は大韓帝国を併合。これにより、朝鮮半島は第二次世界大戦(大東亜戦争、太平洋戦争)終結まで、大日本帝国の統治下に置かれた。
これ以降、元々、侮蔑的な意味合いを持っていた「ちょん」が韓国・朝鮮人の蔑称として、日本人一般にも意識されるようになった、と思われる。(「ちょん」公などというように)。
その後、オートフォーカスコンパクトカメラのCMのキャッチコピーで、「専門知識がなくても誰でも使える」、操作が簡単なカメラとして、「バカチョンカメラ」という言葉が広まった。また、「カメラ」に対してだけではなく、「バカでもチョンでも・・・」、という(侮蔑的な)言い回しとして、ふだんの会話の中でも用いられた。
こうした用いられ方の歴史を踏まえ、一時、人口に膾炙した「バカチョン」は「馬鹿でも朝鮮人でも」と朝鮮人に対する差別的・侮蔑的言葉を含むものとして、現在は放送禁止用語となっている。
最近では、2012年5月24日放送の報道ステーションで、ゲストの飯田哲也が「原子力に反対する奴はバカだチョンだ」と発言し、キャスターの古舘伊知郎が謝罪。
また、今年8月7日、自民党の溝手顕正が党の会合で「安倍晋三首相のように非常に勢いのいい首相の下だと、ばかでもチョンでも(当選する)という要素があるのは否定できない」と発言、ただちに撤回するという事態も生じた。
そのことばを聞いたとき、対象とされた人間が嫌悪感、不快感などを持つことばを安易に用いないのは、人間関係(まして、国際化社会)では常識。本人はそういうつもりがないと弁明しても。したがって、「バカ(だ・でも)チョン(だ・でも)」は、公人が公の席で発する言葉ではないだろう。
しかし、正直なところ、久々に聞いたというのが実感。去年、今年と、こうして露骨に発言した(直ちに撤回、謝罪はしたが)とは、驚き。
ちなみに独身男性の蔑称「チョンガー」と言う言葉は、もともと朝鮮の言葉。実は、このことばも1910年「日韓併合」以降に、日本人社会にも持ち込まれたようだ。
昔の朝鮮の風習で、成人をした男性は結婚するまでの間、髪の毛にリボンをつけた(ポニーテールのような)お下げ髪にすることになっていた。この髪型を総角(チョンガー)と言った。
なかなか結婚しない(できない)人は、いつまでもチョンガーのままだった。それがいつしか、いい年をしていて、いつまでも独身で居る男性のことを指して、軽蔑した意味を込めて「チョンガー」と言うようになった、そうだ。(以上、「Wikipedia」など参照)
















 「ベルリン陥落」。
「ベルリン陥落」。 「スペイン内戦」。第二次大戦前夜のスペインの内戦の実態を赤裸々に描く。
「スペイン内戦」。第二次大戦前夜のスペインの内戦の実態を赤裸々に描く。 「スターリングラード(注:ロシアの都市名 ヴォルゴグラードの旧名)」独ソ戦のすさまじい攻防を描く。
「スターリングラード(注:ロシアの都市名 ヴォルゴグラードの旧名)」独ソ戦のすさまじい攻防を描く。
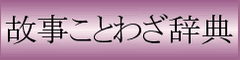 より。
より。




