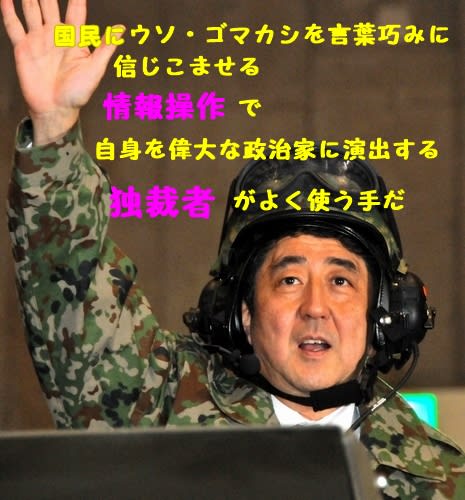
1月4日、今年早々のブログ、《天皇の年頭感想「戦争の歴史に学ぶべき」は安倍式歴史の学び、その歴史認識の否定に他ならない - 『ニッポン情報解読』by手代木恕之》に対して「森薫」氏から「歴史音痴極まれり」と題する以下のキツイお叱りのコメントを頂いた。
「森薫」氏 「歴史音痴極まれり」
〈天皇陛下がいつ独裁権を行使した?
ポツダム宣言受諾を決めた御前会議で継戦を主張する軍部の意見を退けた以外絶えて知らないけど!
形式的な主権在君をもって、戦前の日本を非民主国家と決めつけるステレオタイプの発想、中韓の言いがかりと全く同じ。
天皇主権なんてのは、現代のアメリカ大統領が宣誓式にバイブルを用いたり、政策を語るのに神の意思に触れるようなもの。
それよりむしろ戦前の日本には不十分であったにしろ、明らかに民主主義の萌芽が見られた。それが、占領軍憲法により、国民が国家の主権者即ち責任と負担を担うものという根幹から目を背けさせる歪な民主主義を刷り込んでしまった。
それをまともにしようとしているのが分からないなんて、ほんとにあきれ返るばかり。〉――
正月早々、「あきれ返」えらせて、済まないと思っている。
確かに天皇は歴史的に見て、「形式的な主権在君」に過ぎなかった。にも関わらず、天皇を現人神とし、大日本帝国憲法は第1章天皇第1条で、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条で「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラズ」、第11条で「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と、絶対権力者に位置づけていたのである
但し特に戦前の昭和天皇は日本的神の化身としての現人神たる超絶的存在と大日本帝国憲法の規定に反して「形式的な主権在君」の地位と権力しか与えられていなかった。
では、何のために権力の二重性が存在していたのかと言うと、既に多くの指摘があるように天皇に持たせた絶対性を政治権力や軍権力が集団で担うことで、「治安維持法」や「新聞紙条例」その後の「新聞紙法」、あるいは「出版法」といった国家権力側の権利・利益に立って制定した法律、あるいは「国体の本義」とか「教育勅語」等の思想教育を通して、国民の集会や結社の自由、思想・言論の自由、信教の自由等々の基本的人権に厳しい制限を課したり、天皇と国家への無償の奉仕を求めたりする国民統治装置としてその絶対性を利用し、独裁的な国家運営を行うことに便利不可欠としていたからだろう。
要するに民主主義体制に関して欧米と比較して遅れた頭をしていた。
天皇の絶対性を国民統治装置としていたことの最大の効果が国民の「天皇陛下のため、お国のため」の思い・声に象徴的に現れている。国民のこのような声・思いがなかったなら、国家権力はあれ程までに戦争を拡大することはできなかったし、人的犠牲をも含めて、あれ程までに甚大な損害を被ることはなかったろう。
例え天皇の意思に反したものであっても、全て天皇の名に於いて行われたのだから、世俗権力者たちにとっては間接的な独裁権力行使であっても、国民にとっては天皇による直接的な独裁権力の行使となる。
天皇のこの公的な存在としての絶対性と実際の権力者としての「形式的な主権在君」という権力の二重性は何も明治・大正・戦前昭和の時代に始まったわけではなく、歴史的な装いとしていた。
ブログに何度か書いてきたが、改めて歴史を簡単に振返ると、大和 朝廷で重きをなしていた最初の豪族は軍事・警察・刑罰を司る物部氏であり、天皇に代わって実質的な権力を握っていた。
それを滅ぼして取って代わったのが蘇我氏である。蘇我稲目は欽明天皇に二人のムスメを后として入れ、後に天皇となる用明・推古・崇峻の子を設けている。
稲目の子である崇仏派の馬子は対立していた廃仏派の穴穂部皇子と物部守屋を攻め滅ぼし、自分の甥に当たる崇峻天皇を東漢駒(やまとのあやのこま)に殺させて、推古天皇を擁立し、厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子にしている。このような皇室に対する恣意的な人事権は実質的な権力者が天皇ではなかったことの証明であろう。
親子である「蘇我蝦夷と蘇我入鹿は甘檮岡(あまかしのおか)に家を並べて建て、蝦夷の家を上の宮門(みかど)、入鹿の家を谷の宮門と称し、子を王子(みこ)と呼ばせた」と『日本史広辞典』に書かれているが、自らを天皇に擬すほどに権勢を誇れたのは、その権勢が天皇以上であったからこそであろう。
聖徳太子妃も馬子のムスメで、山背大兄王(やましろのおおえのお)を設けている。だが、聖徳太子没後約20年の643年に蘇我入鹿の軍は斑鳩宮(いかるがのみや)を襲い、一族の血を受け継いでいる山背大兄王を妻子と共に自害に追い込んでいる。
蘇我入鹿は大化の改新で後に天智天皇となる中大兄(なかのおおえ)皇子に誅刹されているが、後の藤原氏台頭の基礎を作った中臣鎌足(なかとみのかまたり)の助勢が可能とした権力奪回であるから、皇子への忠誠心から出た行為ではなく、いつかは天皇家に代って権力を握る深慮遠謀のもと、いわば蘇我氏に続く実質権力者を目指して加担したことは十分に考えられる。
その根拠は鎌足の次男である藤原不比等(ふじわらのふひと)がムスメの一人を天武天皇の夫人とし、後の聖武天皇を設けさせ、もう一人のムスメを明らかに近親結婚となるにも関わらず、外孫である聖武天皇の皇后とし、後の孝謙天皇を設けさせるという、前任権力者の権力掌握の方法の踏襲を指摘するだけで十分であろう。
藤原氏全盛期の道長(平安中期・966~1027)はムスメの一人を一条天皇の中宮(平安中期以降、皇后より後から入内〈じゅだい〉した、天皇の后。身分は皇后と同じ)とし、後一条天皇と後朱雀天皇となる二人の子を産んでいる。別の二人を三条天皇と外孫である後一条天皇の中宮として、「一家三皇后」という偉業(?)を成し遂げ、「この世をば我が世とぞ思ふ」と謳わせる程にも、その権勢を確かなものにしている。
藤原氏の次に歴史の舞台に登場した平清盛は実質的に権力を握ると、同じ手を使って朝廷の自己権力化を謀る。ムスメを高倉天皇に入内(じゅだい)させ、一門で官職を独占する。その権力は79年に後白河天皇を幽閉し、その院政を停止させた程にも天皇家をないがしろにできる程のものであった。
本格的な武家政権の時代となると、もはや多くの説明はいらない。それまでの天皇家の血に各時代の豪族の血を限りなく注いで、血族の立場から天皇家を支配する方法は廃れ、距離を置いた支配が主流となる。信長も秀吉も家康も京都所司代を通じて朝廷を監視し、まったく以って権力の埒外に置く。いわば天皇家は異なる形での名ばかりの存在と再び化すことになる。
そのように抑圧された天皇家が再び歴史の表舞台に登場するのは、薩長・一部公家といった徳川幕府打倒勢力の政権獲得の大義名分に担ぎ出されたことによってである。明治維新2年前に死去した幕末期の孝明天皇(1832~1866)に関して、「当時公武合体思想を抱いていた孝明天皇を生かしておいたのでは倒幕が実現しないというので、これを毒殺したのは岩倉具視だという説もあるが、これには疑問の余地もあるとしても、数え年十六歳の明治天皇をロボットにして新政権を樹立しようとしたことは争えない」と『大宅壮一全集第二十三巻』(蒼洋社)に書いてある。
天皇家と姻戚関係を結んで権力を確実なものとしていったかつての政治権力者は確実化の過程で不都合な天皇や皇太子を殺したり、幽閉したり、あるいは天皇の座から追い出したりして都合のよい天皇のみを頭に戴いて権力を握るという方法を採用している。そのような歴史を学習していたなら、再び天皇を頭に戴いて実質権力を握る方法を先祖返りさせて、倒幕派が天皇と言えども都合の悪い存在を排除するために「毒殺」という手段を選んだとしても、不思議はない。
明治以降実質的に権力を握ったのは薩長・一部公家の連合勢力であり、明治天皇は大宅壮一が指摘したように彼らの「ロボット」に過ぎなかった。天皇を現人神という絶対的存在に祭り上げることで、自分たちの政治意志・権力意志をさも天皇の意志であるかのように国民に無条件・無批判に同調・服従させる支配構造を作り上げたのである。これは昭和天皇の代になっても引き継がれた。実質的な権力を握ったのは明治政府の流れを汲む軍部で、彼らの意志が天皇の意志を左右したのである。軍服を着せられた天皇の意志によって戦争は開始され、天皇の意志によって国民は戦場に動員され、天皇の意志によって無条件降伏を受入れさせられるという形を取った。
森薫氏は天皇が独裁権力を行使したのは「ポツダム宣言受諾を決めた御前会議で継戦を主張する軍部の意見を退けた以外絶えて知らないけど!」と書いているが、では、なぜ発揮できる独裁権力を持っていたなら、対米開戦を反対していたのだから、開戦を決めた御前会議で自らの独裁権力を以てして反対しなかったのだろうか。
『小倉庫次侍従日記』(文藝春秋刊)には次のような記述がある。
〈昭和16年9月6日(土)<翌日> 内大臣御召(9・40-9・55)。第6回御前会議(10・00-11・55 東一の間)。(後略)
《半藤一利氏注〉「この日の御前会議でよく知られているように、近衛内閣は筋書きどおりに「戦争辞せざる決意のもとに」対米交渉を行い。10月上旬になっても交渉妥結の目途がつかぬ場合には「ただちに対米(英蘭)開戦を決意す」等国策を決定した。
天皇は憲法に則り、『無言』を守ることになっている。しかし、このときにかぎりポケットから紙をとりだして、天皇は歌一首を読み上げた。
『四方の海みなはらからと思ふ世に など波風のたちさわぐらむ』
明治天皇の御製である。そして、『なお外交工作に全幅の努力するように』と言った。が、その願いは空しくなる」
〈昭和16年12月1日(月)本日の御前会議は閣僚全部召され、陸海統帥部も合わせ開催せらる。対外関係重大案件、可決せらる。
《半藤一利氏注〉「開戦決定の御前会議の日である。
『杉山メモ』に記されている天皇の言葉は、
『此の様になることは已むを得ぬことだ。どうか陸海軍はよく強調してやれ』
杉山総長の感想は「童顔いと麗しく拝し奉れり」である」(以上)――
「御前会議」では「天皇は憲法に則り、『無言』を守ることになっている」としていることに反して、天皇は発言している。対米開戦に対して、「已むを得ぬ」と条件つきながら励ましの言葉を直接述べている。「立憲国の天皇は憲法に制約される」云々と昭和天皇自身が述べた政府の決定したことに従うとする規定からの発言だとしても、大日本帝国憲法が天皇に持たせた統治権も、神聖にして侵してはならない現人神としての存在性も統帥権も有名無実化させて、権力の二重性のみを露わにすることになる。
要するに大日本帝国憲法自体が権力の二重性を謳っていたことになる。
陸軍が戦争終結に反対して戦争継続を主張したのは大言壮語を吐いて戦争を主導したメンツから単に継続の拳を振り上げただけで、いくら陸軍が頭の悪い軍人の集団だったとしても、制空権・制海権共に米軍に握られていたのだから、既に日本が戦争継続能力を決定的に失っていたことは理解していたはずだ。
勿論、本土決戦の徹底抗戦を選べば、米軍に相当な損害を与えることはできるが、それ以上の犠牲を国民や国土に与えることは明白であって、米軍の自軍の損害を最小限にとどめるための最終手段としての原発の3発目、4発目も覚悟しなければならなかったはずだ。
つまり天皇は終戦決定に独裁権を行使したわけではない。陸軍のメンツが散々ゴネた末に天皇の裁可を必要とするプロセスを経ることで、それを大義名分に拳を振り降ろす口実にしたに過ぎない。天皇が戦争に反対し、内閣直属の総力戦研究所が対米開戦の総力戦机上演習をして日本必敗の結論を合理的根拠に基づいて導き出していながら、妄想と精神論でその結論を追い遣り、勝てない戦争に突き進んで敗退に敗退を重ねて絶壁に立たされながら、潔く負けを認めることができなかった程度の低い虚栄心を満足させるための口実としたのである。
でなければ、天皇なる存在が歴史的にも担わされていた権力の二重性は説明できない。
いずれにしても世俗権力が天皇に絶対的独裁権力を纏わせて、天皇の名に於いてその独裁権力を揮うことで実質的な国民統治装置としていたのだから、それが間接的なものであったとしても、天皇自身が国民にとって直接的な独裁権力行使者であったことに変わりはない。
戦前、不敬罪を成り立たせていたことがその最たる根拠の一つとなり得る。国民は確実に大日本憲法の規定通りに天皇を「神聖にして侵すべから」の存在と把えていた。
















