金(キム)多摩大学教授は強調する。台頭するアジア・ユーラシアダイナミズムに日本はどう対処するのか? その鍵は韓国経済の成長を見習い、リバース・イノベーションの方向に転換すべきだと…。
ニュージーランドへの旅立ちを明日に控え、一つだけレポートしておくべきことがあった。
それは、1月21日(月)午後、京王プラザホテル(中央区北5西7)で開催された「北海道で考える北東アジア情勢シンポジウム」に参加したレポートである。
シンポジウムは、標記タイトルの演題(サブタイトルに ~北東アジアにおける新しい日韓関係を展望する~とあった)で金美徳多摩大学教授が基調講演を行い、その後金氏を含めた3名の識者が登壇し、パネルディスカッションを行った。

パネルディスカッションにおいて傾聴に値する考えが多数提起されたが、ここでは基調講演に絞ってレポートすることにする。
金氏は日本生まれの在日朝鮮人三世ということらしいが、講演の中で何度も口にしていたが、「自分は韓国のことをどうとも思っていない。そのことより日本経済の再建に大きな関心がある」のだと…。
そして金氏は、韓国経済の成功モデルを日本は直視し、その良さを積極的に取り入れることによって日本経済の再建を図るべきだと強調された。
まず、アジア・ユーラシアダイナミズムである。
21世紀の経済は北東アジアを中心として、アジアと一部ユーラシアを含めた地域・国が大きくダイナミックに発展し始めている。
その中でも、東南アジアや中国の発展が目覚ましく、日本はそれらの国々に対する深い理解が求められるが、それ以上に隣国である韓国に対する理解を深めることが急がれると思うとした。
韓国経済の成功は、アジアや新興国に対するビジネス情報を集積し、積極的に打って出るというビジネスモデルを確立している。
その韓国のビジネス情報を把握するだけではなく、韓国の政治・経済・文化・歴史についても理解を深め、相互の連携を強化することによってアジア・ユーラシアダイナミズムのトレンドを掴みとり、その需要に応えるビジネス展開が今日本に求められていると強調された。

そして、リバース・イノベーションである。
語義的には、リバースは「逆にする」、「反対方向に動かす」などという意味である。そしてイノベーションとは「革新」、「新機軸」という意味である。
これまでイノベーションというと、富裕国において革新的な新製品が開発され、それが時間を経て途上国へ流れていくというのが一般的であったが、これからは途上国の事情に合ったものが開発され、逆にそれが富裕国に流れていくという反対の流れが出てくるということのようである。
つまり、アジア・ユーラシアダイナミズムの対象国であるアジアの国々や途上国では高品質・高付加価値の製品を求めていない。いわゆる実用本位の製品である。
今後はそうした製品がグローバルビジネスを展開する際にトレンドになってくるのではないかと金氏は指摘する。この類の話は以前「金融教育フォーラム」でも聞いた話と符合する。
ことはここに書いたような単純なものではないとは思うが、一つの示唆を与えてくれた話だったのではないかと思う。
躍進する韓国経済を苦々しく見つめるだけではなく、北東アジアの一員として共に成長していこうとする視点が必要ということだろう。
いよいよ旅立ちが明後日となりました。旅の準備もここにきてようやく整ったと云える状態になりました。毎日とはいきませんが、どうやら何度かはあちらからもブログを投稿できる状況もできてきました。
思い立ってから約20日、慌ただしく進めた旅の準備もようやくここにきて出発できるまでになった。
今回の旅では、ニュージーランドの自然を堪能するためのトレッキングを組み込んだことから、ザックを背負っての旅立ちとなる。これも一人旅だから成せる業である。
沢木耕太郎がそうしたように、できるだけ身軽に旅を楽しみたいと思っている。

※ トレッキングのコースは現地に行ってみないと分かりません。こんな風景の中を歩けたら…。
沢木といえば、先日BOOK-OFFに行って旅の友にする沢木耕太郎の文庫本を5冊ほど仕入れてきた。(私が所蔵しているのは新書版か、それより大きなものばかりのため旅の友には適していない)
また、ソフトバンクのショップにもまた伺って、念には念を入れて海外からのブログ投稿の要領を伝授されてきた。まったくアナログ人間である私はこれだけ聞いてもまだ自信がないのだが、まあなんとかなるだろう…。
飛行機を予定どおり乗り継いで、ニュージーランドのオークランド国際空港に降り立ったとき(1月24日、現地時間午後2時20分)、そこから私の本格的な一人旅である。
空港からホテルまで辿り着くのが一仕事である。「地球の歩き方 ニュージーランド編」を参考に、まず空港内の観光案内所アイサイトでエアバス・エクスプレスのチケットを購入する。
そして青い車体のエアバス・エクスプレスというバスを見つけ、乗り込むときにドライバーにホテル名と住所を示して、「どこの停留所で降りるとよいのか」を訊かねばならない。
教えられた停留所で降りたら、現在地を確認してホテルを探し当てる。(予め地図で確認しているのでそれほど困ることはないだろう)
ここまでが一つの勝負である。
これをクリアし、無事にホテルで部屋を確保できれば一段落つくことで、度胸もつき、それからのことは割合スムーズにコトを運ぶことが出来そうに思っている。
空港からホテルまで、ここが一つの壁である。
さて、どうなることやら…。
ご存じ健さんの出世作「網走番外地」である。網走番外地シリーズは計18作が制作され上映されたが、その第一作目を観賞し、「北の映像ミュージアム」の理事が解説してくれた1月の「北のシネマ塾」に参加した。

1月19日、今年最初のシネマ塾には17~8名の参加があった。半数以上は「北の映像ミュージアム」に関わっている方のように見えたが、解説は高村賢治さんという理事が務められた。
映画の内容・ストーリーについては3年前に「シネマの風景フェスティバル」で見たときの投稿に譲ることにして、ここでは高村理事からお聞きしたことを中心にレポートすることにします。
まずこの「網走番外地」シリーズが誕生した背景についての説明があった。
この映画のヒントは、実際に網走刑務所に服役した伊藤一という人が体験を元に著した小説に石井監督が映画化を会社側に懇願したのですが、当時の東映社長の大川博(小太りな体格、胴長短足、丸眼鏡、出っ歯、チョビ髭といった独特の風貌で有名だった)はけんもほろろに却下したそうだ。
そこで石井監督は当時のアメリカ映画でスタンリークレイマー主演の「手錠のままの脱獄」の日本版にするとの再度の要請でようやく許可を得たそうだが、予算難からシロクロ映画の上、二本立て映画の抱き合わせという扱いで上映にこぎつけたそうだ。
そうしたところ思わぬ大ヒットとなって、それからのシリーズ化が実現したということだ。
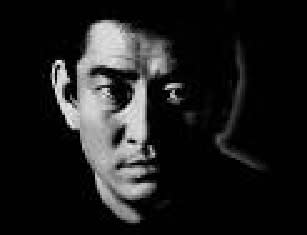
続いて、ロケ地についての話があったが、冒頭に主演の高倉らが網走刑務所に護送されるために降り立つ駅が網走駅に模した北浜駅だった。北浜駅は私が現職時代に3年間在職した(2001年から2004年まで)網走市北浜地区に立つ古い駅舎である。映画は1965年制作だから映画が制作された当時から現在まで変わらぬ姿でオホーツク沿岸に建っているということだ。
その他、トロッコのシーンは今はない新得の森林鉄道を、あるいは根室本線のベカンベウス付近、川湯の硫黄山など北海道各地をロケハンしてイメージに合ったシーンを撮影したということだ。
まだまだたくさんのエピソードや裏話をうかがった。
こうして映画に詳しい方のお話をうかがうことによって、その映画を深く味わうことができることは非常に興味深いことである。
今夕6時すぎに発生した我が家の停電は、結局三つの会社のサービスマンが我が家に駆けつけてくれたことによって、午後10時前にひとまず解決することとなりました。
その顛末を時系列的に整理しておくことにします。
何度もブレーカーが落ちる事態に北電のサービス部門に問い合わせたところ、最初にブレーカーが落ちたきっかけが電磁調理器を使用したときだったため、「電磁調理器に問題があるのでは?」ということで、電磁調理器メーカーのサービスマンに来てもらうことにしました。
しかし、電磁調理器を使用しなくても何度もブレーカーが落ちるので、ブレーカーをよく見るとブレーカー本体ではなく、漏電ブレーカーが落ちていることが分かりました。
そこで再度北電に連絡して「漏電の恐れがあるのではないか?」と問い合わせたところ北電のサービスマンが来てくれることになりました。
停電発生から約1時間半後に電磁調理器のサービスマンより、北電のサービスマンが先に駆けつけてくれ、調査したところ外部に設置してあるガスボイラーが漏電していることが判明しました。
そこで今度は北ガスに連絡して北ガスのサービスマンに来てもらうことにしました。
その間、電磁調理器のメーカーのサービスマンも来宅しましたが、予想通り電磁調理器には何も不具合はなかったようです。
三人目として登場した北ガスのサービスマンはガスボイラーを点検し、ガスボイラーの中に大量の氷が貯まっていて、それが漏電を起こしていることを突き止めました。
どうやらガス燃焼時に発生する水滴を排出する装置が故障していたようです。
氷を掻きだし、応急処置をすることによって一件落着となりました。(本格的修理は後日ということで)
大騒ぎしながら約3時間、3人のサービスマンが登場し、一件落着となりました。
この間、暖房が取れず夕食も中断して、厚着して寒さに耐えながらの3時間でした。
先の投稿で「もしも」の事前体験をしているなどと記しましたが、我が家には何の備えもないため、一時的ではあっても大変に不安で、不便な時間を過ごしました。
私たちの生活が一つの機器の故障で大きな不安に陥れられるという脆いものだということを実感することができました。
今一度、もしものために備える必要があることを痛感させられた今夜のアクシデントでした。
ほ―――っ、ホッと一息です。
周りを見渡したところ、どうやら我が家だけのようです。
ブレイカーを確認したところ、確かにブレイカーが落ちていたため回復措置を講じました。しかし、間もなくするとまた落ちてしまいました。そうしたことを何度か繰り返すうちに「これは尋常じゃないぞ」と思い始めました。
北電のサービス部門に電話を入れて尋ねると、電話でいろいろ指示されたり、教えられたりしたのですが解決できません。とうとう出張サービスをお願いしました。この寒空の中で暖房無しは耐えられませんからねえ。
もしも、は無いことにこしたことはありませんが、もしも、の事前体験をしているんだと思いながらサービスマンの到着を待ちたいと思います。
停電のため何も出来ないので、こうしてiPhoneからブログを投稿しました。
停電の顛末はまた後日レポートします。
旅立ちが4日後に迫っているというのに、私の準備は遅々として進んでいない。と言っても残すはパッキングだけなのだが…。そんな中、一つの朗報(?)とも言えることに今奔走しています。

※ ニュージーランドの国鳥キウイです。野生のものを見るのは無理ですが、飼育しているのを観察するチャンスがありそうです。
先に、「今回の旅はブログで毎日アップするようなことはしない」と記した。
それは旅に集中したいという思いと、何より通信費がかなりかかりそうということがその理由だった。
ところが先日ソフトバンクのショップを訪ねたところ「Wi-Fi環境ではそれほどかかりませんよ」というアドバイスを受けた。そしてその際の設定の仕方について説明を受けた。
ところが…。
すっかりアナログ人間と化している私にはなかなか理解できないのだ。
丁寧にその手順をメモして渡してくれたのだが、どうもその要領が呑み込めない。
思い余って他日、今度は別のショップを訪ねて再び教えを請うた。
そうすると、前の説明とやや違った方法を教えてくれた。
私は混乱し始めた。
何せ、画面のタップを間違えると相当な通信料の請求が来るとも言われ…。
私は二つのショップで教えてもらったことを私なりに整理してみた。
しかし、いま一つ自信が持てない。
出発前、整理したメモを手にもう一度ソフトバンクのショップを訪れてみよう思っている。
毎日とはいかないまでも、できるだけWi-Fi環境のところを見つけてブログの投稿ができればと思っている…。
ニュージーランドの友人を訪ねるにあたって、「お土産は何がいい?」と友人に訊いたところ、「沢木耕太郎の『馬車は走る』をお願いしたい」とのリクエストがあった。「沢木耕太郎!?」…、私はその名前を聞いて無性に嬉しくなってしまったのだった…。

※ 友人からリクエストのあった「馬車は走る」の表紙です。
月刊『文藝春秋』誌の新春1月号で沢木耕太郎が久々に「キャパの十字架」と題する長編(309枚というから長編とまではいかないかな?)を発表した。
久々の沢木ワールドに酔い、充足感を味わっていた私である。
沢木耕太郎については、私がこのブログを始めた初期(2007年5月)に「沢木耕太郎論」などと題して5日連続で投稿したことがある。
ちょっと青くさい沢木耕太郎論であるが、今日改めて読み直してみると、いささか面映ゆい。
「沢木耕太郎 Part Ⅰ」
「沢木耕太郎 Part Ⅱ」
「沢木耕太郎 Part Ⅲ」
「沢木耕太郎 Part Ⅳ」
「沢木耕太郎 Part Ⅴ」

※ 現在の沢木は写真よりは少し歳をとっているかもしれない。
私はブログで「沢木耕太郎論」を述べたことはあるが、他の方に彼のことをそれほど推奨したりすることはなかった。
ただ、その友人が大のサッカーファンだったことから、沢木が日韓ワールドカップを取材した「杯(カップ)」という本を刊行したことは紹介した記憶があった。
しかし、その後彼とは何度も会っているが、沢木耕太郎のことなど話したこともなかった。訊くと彼は沢木の著書である「彼らの流儀、人の沙漠、危機の宰相、右か左か、テロルの決算、壇」などかなりの沢木を読んでいることが分かった。
私はすっかり嬉しくなり、彼に刺激されたかのように沢木の本を再読し始めている。
枯れかけた私の脳に沢木の言葉はまるで砂漠に水が滲みわたるように広がっていくのを感じる。
私は今回のニュージーランドの旅に沢木耕太郎を旅の友とすることにした。
そして私は友人に「馬車は走る」と『文藝春秋』誌の1月号を持参することを約束した。
※ 一昨日の「嵐 ふるさと」のユーチューブを貼り付けることができました! まだお聞きになっていない方は一昨日の私のページをご覧ください。
旅程が確定してホッとしたためだろうか、「私のニュージーランド物語」のストーリーはその後ほとんど進展しておりません。旅立ちが一週間後に迫って、少々の焦りも感じ始めている今日この頃です。

※ 私が今回の旅で2日間遊ぼうと思っているクイーンズタウンの湖の風景です。
本来なら旅行社に任せるべき旅の手配を自分の手で行うという、私の能力からいってやや無謀なことにチャレンジしたものだから、その手配が一段落したことでどこかホッとした思いが私を支配し、その後の準備等がほとんど進展しないまま今日を迎えています。
今、あらためて今回の旅の意義を考えてみている。「いったい今回の旅の目的は何なのだろう?」と…。
私の中でそのことは明確なものとして意識はしていないのだが、どこかで私は45年前の旅を意識しているように思える。
45年前…。
1968年6月から1969年3月までの10か月間、私はヨーロッパ・中近東・アジアの国々を彷徨して歩いていた。それは究極のセルフプロデュースの旅だった。
今回の旅も私はセルフプロデュースにこだわった。とは言っても1968年当時とはまるで状況は異なっているのだが…。
つまり私は今回の旅は「ニュージーランドに語学留学している友人に会ってくる」ことだけが唯一の目的で、その旅を自らプロデュースしてやり遂げることに意義を見出したいと思っている。
1969年の旅はヒッチハイクの旅だったから予定も何もなく行き当たりばったりの旅だった。唯一の予定はイタリアで予約した、インド・ボンベイ(現在のムンバイ)から2月21日発のフランス郵船の出航に間に合わせることだった。
しかし、今回は飛行機に何度も乗り換えるのだが、それらが予定どおりゆくのか、あるいはトラブルに巻き込まれるのか…。ホテルの手配は思っているように成約されているのか…。バスは予定どおり走るのか…。等々、かっちりと組まれた予定がかえって不安を増幅する。トラブルに見舞われた時に、はたしてそれを切り抜けることができるのか…。
不安は尽きない…。
だから…。今回はやり遂げることに旅の意義を見出したいと思っているのです。
話は昨年末のNHK歌合戦である。
ここ数年、私はNHK紅白歌合戦を楽しむということはほとんどない。
昨年末も同様だった。家族(といっても息子夫婦と妻だけだが)はリビングで一応歌合戦にチャンネルを合わせていたが、私は自分の部屋で別の番組を見たりして過ごしていた。
たまたま私がリビングに戻ったときだった。
とっても心に染み入るようなメロディーが流れている。画面を見ると、あの“嵐”が歌っているではないか!
じーっと聴き入った私だったが、何かしら胸にジーンとくるものを感じた。
きっと多くの人が耳にしたに違いないが、今一度“嵐”が歌う「ふるさと」を聴いていだきたい。
こちらをクリックください。⇒
小山薫堂さんの詞がいいではないか。どこか懐かしさが漂うyouth caseさんのメロディーがいいではないか。
こんな素晴らしい歌をアイドルグループの“嵐”が歌っていたことに驚き、そして感動した。調べてみると、すでに一昨年の紅白歌合戦のときから歌っていたらしい。(知らなかったのは私だけか?)
この曲は今年(2013年)のNHK合唱コンクール小学校の部の課題曲にも選定されたらしい。むべなるかな、という感じである。
その「ふるさと」の歌詞をここに紹介します。
嵐/ふるさと*紅白版
1.
夕暮れ迫る空に 雲の汽車見つけた
なつかしい匂いの町に 帰りたくなる
ひたむきに時を重ね 想いをつむぐ人たち
一人一人の笑顔が いま 僕のそばに
巡り合いたい人がそこにいる
やさしさ広げて待っている
山も風も海の色も 一番素直になれる場所
忘れられない歌がそこにある
手と手つないで口ずさむ
山も風も海の色も ここはふるさと
2.
写真の中の声が ふと恋しくなった
夢を語りあった日々 輝いていた
あの頃と同じように 空を見つめる木々たち
揺るぎなきその強さが いま 僕の胸に
支えあいたい人がそこにいる
明日を信じて歩いてる
花も星も虹の橋も すべては心の中にある
生きることで感じる幸せを
いつまでも大切にしたい
花も星も虹の橋も 君の ふるさと
僕のふるさと
ここはふるさと
北大総合博物館(北区北10条西8丁目)では定期的に土曜市民セミナーが行われているが、1月12日は北大文学部の白木沢旭児教授による「食糧問題から見る昭和史」と題する講座があり受講した。
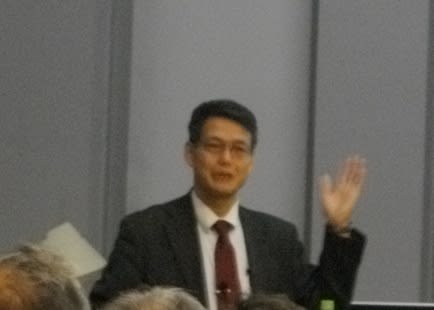
※ 北大総合博物館の土曜市民セミナーで講義する白木沢教授です。
白木沢教授に提供いただいた資料によって昭和の国民の食糧事情を概観してみると、第二次世界大戦前の1934年(昭和9年)当時の食料は当然のように「米」が主たる食料だった。この「米」の調達には国内はもとより、当時日本に併合されていた韓国・台湾からの移入によって賄われていたようである。
それが敗戦によって韓国・台湾からの移入の道が途絶えると共に疲弊した国内の生産力も低下し、食糧危機が叫ばれる状態(1千万人餓死説)となった。それを救ってくれたのがGHQによる食糧援助だった。1946年から6年間にわたり小麦・大麦の大量援助により危機を逃れることができたという。
そして1950年に朝鮮戦争が勃発したことが、日本に好景気をもたらし、1952年からはそれまでの援助から輸入に切り替え小麦・大麦類を調達したという。
また、それから一時期は米の輸入量も増加している。
ところが米の輸入量は1954年を境に急激に輸入量を減らしている。その原因は国内農家の生産力の増加と、食糧援助によって国民の食事情が欧米化したことがその理由のようである。
食の欧米化が進んだわけは、戦後の米供給が絶対的に不足している状況の中で、主食を変えることにより米不足に対処する方策だったそうだ。代わりの主食を小麦を用いたパン、麺類として、副食を充実させることが提唱された。(これを「食生活改善」と称していたようだ)このことが国民の米離れ、食の欧米化に拍車をかけることとなった。
現在では反対に食の欧米化から健康問題が顕著となるにつれ和食への回帰の動きが強まっていることは皮肉なことである。
別の資料で「輸入総額に占める食糧輸入額の割合」という資料を見ると、戦争直後は輸入総額の50%強が食糧であったものが、1960(昭和35)年には12%程度まで減少している。しかし、これは日本の国力が増すにつれて輸入総額が大きく膨らんだ結果、食料の輸入割合が相対的に減少したということで、食糧輸入額が減ったということではない。食糧輸入額としては高止まりのままであることを特記しておきたい。
そして現在ではその輸入額が莫大な額となっていることも触れておく必要がある。
ちなみにこれは私がウェブ上で調べたことであるが、日本の食料自給率(カロリーベース)についであるが、1965(昭和40)年に73%であったものが、2010(平成22)年には39%にまで落ち込んでいる。
このこととTPP問題をどう見るかについて、白木沢教授はご自身の意見を明確には表明されなかった。さて、私は…?
この講座の冒頭、戦後の日本で「1千万人餓死説」が流布されと聞いてゾッとした。そんな事態が再び到来するとは思えないが、将来世界的な食糧危機が勃発したとき果たして日本はどうなるのだろうか?
世界の人口爆発が食糧危機を招くと言われているのだが…。









