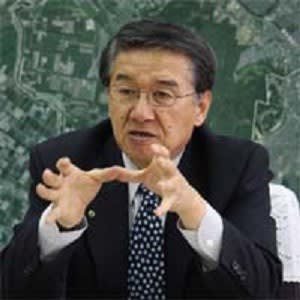2年ぶりのカルチャーナイトへの参加だった。今年の私は、華麗なトリオの音楽に浸り、若者たちの勢いのある書に目を見張ったカルチャーナイト2108だった。

札幌市内において、公共施設や文化施設、民間施設が夜間開放され、市民が地域の文化を楽しむカルチャーナイトが2003年から行われるようになって今回で16年目である。
毎年のように楽しんでいた私だったが、昨年は参加できなかった。
今年は7月20日(金)開催ということで、「どこを訪れようか?」と検討した。なにせ札幌市内105カ所で一斉に開催されるので訪れることができる施設は限られる。
検討の結果、18時から北海道銀行本店ロビーが行われるロビーコンサートを聴き、19時から道立近代美術館で行われる書道パフォーマンスを見ることにした。
お金に縁のない私は初めて北海道銀行の本店に入った。本店のロビーは天井が高く、コンサートには適した空間だった。
ステージに登場したのは、ソプラノの倉岡陽都美、フルートの大島さゆり、ギターの亀岡三典の三人だった。クラシックのステージをこれまでけっこう聴く機会があったが、この組み合わせのコンサートは初めてだった。
演奏された楽曲は次のとおり。
◇T.コットラ/「サンタ・ルチア」
◇G.ビゼー/オペラ『カルメン』より“ハバネラ”
◇F.タレガ/アルハンブラ宮殿の思い出(ギターソロ)
◇V.モンテ/チャールダーシュ(フルートソロ)
◇V.ベッリーニ/オペラ『ノルマ』より“清らかな女神よ”
ソプラノの倉岡陽都美は声量豊かに歌い上げる実力派と見た。

私が興味深く聴いたのは二人のソロだった。
ギターの「アルハンブラ宮殿の思い出」はクラシックギターの名曲である。若き実力者亀岡が爪弾くトレモロは繊細な響きを道銀ホールに響き渡らせた。

フルートの大島さゆりは、彼女の美貌が際立っていたが、技量の方もそれに負けてはいなかった。彼女が披露した「チャールダーシュ」は、ヴァイオリニストが挑む超絶技巧の曲として、これまで何度かヴァイオリンで聴いていたが、フルートでは初めてだった。フルートの世界でも超絶技巧の曲として有名らしい。その難しい曲を大島さゆりは見事に演奏し切った姿が眩しかった。

そして私にとって新しい発見は、ソプラノの伴奏としてクラシックギターの音がしっかりと耳に届き、その意外な存在感が私にとっては新たな発見だった。
北海道銀行から道立近代美術館に移動し、道立札幌南高等学校書道部による書道パフォーマンスを見た。
大きな紙に筆で大書いる書道パフォーマンスは、最近いろいろところで実施されているが、私はTVを通して見るだけで、実際に見たことはなかった。

すると、書道パフォーマンスは音楽をバックにして、12人の部員たちが代わる代わる入れ替わり立ち代り書を認めていった。一枚目は大きな赤い字と黒い墨を使った小さな字との組み合わせだった。
出来上がって披露してくれたが、私には一部判読できないところがあった。
どうやら高校生らしく(?)“どらえもん”の歌詞の一部のようだったので帰宅して調べたところ、次のように書いたものだと判明した。

今で繋ごう
僕ら繋ごう
だからここにおいでよ
一緒に冒険しよう
何者でもなくても
世界を救おう
いつか君に会えるよ
どらえもん
と書いたものだった。
そしてもう一枚。今度はほんとに大書して「百花繚乱」という4文字を書いた。
「百花繚乱」は、現在近代美術館で開催されている特別展のテーマでもあったが、太い筆を使って勢いよく筆を運ぶ姿に若者らしさを見た思いだった。

7月20日(金)夕刻は、札幌市内の各所にたくさんの人が出て、さまざまに趣向を凝らした催しを楽しんだことと思う。
カルチャーナイトは夏の夕刻のイベントとしてすっかり定着した感がある。来年も楽しめたらと思っている。