今日、多摩川上流沿いの道を車でゆっくり走っていました。紅葉の写真を撮ろうと彼方此方見回しながら。
青梅の町から西へ入ったところに たたずまいの良いお寺が高台の上に建っています。写真を撮り、案内板を見ました。青梅市一帯は南北朝の頃から三田氏という豪族が治めていたのです。これは変だとすぐ思いました。戦国時代の関東地方は北条早雲一族の所謂、後北条氏が占領してい筈です。案内板の後半を読んで納得しました。1559年に北条 氏照 に三田一族は殺されてしまったのです。この海禅寺は三田一族の菩提寺だったのです。その関係で後の人が立派な供養塔を寺の裏山の斜面に建てました。
皆死んで居なくなった後でも、山は変わらずに寺の後を包むように守っています。前には青梅の町が広がっていました。
三田氏を殺してしまった北条 氏照の最初に居た城は滝の城といって野火止めの地にありました。野火止めは八王子城と北関東の中間にある重要な場所です。しかし甲府の武田信玄一族は高尾山や奥多摩の山々を越えて関東平野に出ようと小競り合いを仕掛けてきます。そこで氏照はこの滝の城を部下に任せ高尾山近くの八王子城へ移ります。下の写真は野火止めの地にあった滝の城の本丸跡に建っている城山神社です。高台にあるので南の平林寺方向は見晴らしが良いです。
このように一時は東京の周りを広く占領していた北条氏照も天正18年、1590年の秀吉による小田原城の落城の直後、殺されてしまいます。滝の城も八王子城も、とにかく関東一円の小さな城の全てが落城し、秀吉一派の占領するところになったのです。
江戸時代になると徳川家康は関東一円の全ての城を直轄領にしてしまったのです。武田信玄の居た甲府城も直轄領にしたのです。
現在から考えると日本人同志が互いに殺し合うという残酷な時代だったと怖くなります。ちょっと注意してお寺や神社の説明文を読むと地方の歴史が書いてあります。皆様の住んでいらっしゃる地方はどのような歴史があったのでしょうか?(終わり)








































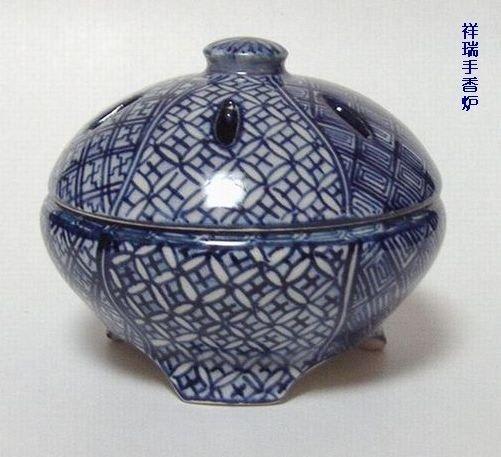
















ショッキングなタイトルを見て来ちゃいましたぞ。
「自然のまんま=何も手を入れない」というのが、自然保護と
思われてますが、自然の定義が不確かでもありますな。
私が大分前に森林インストラクターとして、鎌倉のとある場所で、
活動していた時に、下草刈りとかしていると、近所の人に
通報された事がありました。勿論、その活動は鎌倉市からの依頼、
つまり許可を取っていた訳ですが、住民の目からは、山に入って、
草とかツルを切っている=自然破壊(?)と映った様です。
元々、里山は充分に人の手が入っていて整備されていた訳ですが、
何も手を入れないと、荒れてくる訳です。ツルは木々を締め付けて
殺し、鬱蒼とした森は光が入らず、荒廃する訳です。
全く手を入れないで自然のままにするのが良いか、適度に手を入れて、
保全するのが良いか、難しい判断ですな。
投稿 大福写真館 | ======終わり=====
大福写真館さんのご意見に私は賛成です。下の荒れた雑木林の写真をご覧下さい。小生の山林の中の小屋の近所の美しい里山が毎年荒れる一方なのです。そんな光景を見て心が痛んでいます。村人は昔は薪にするために雑木林に手を入れて管理していたのです。燃料がプロパンになり、山に薪を取りに入らなくなって20年以上になります。イノシシや鹿や猿が異常に繁殖して農産物の被害が莫大になっています。適切な、そして最善の自然保護とは一体どうすれば良いのでしょうか? 何方かお教え下さいませんか?