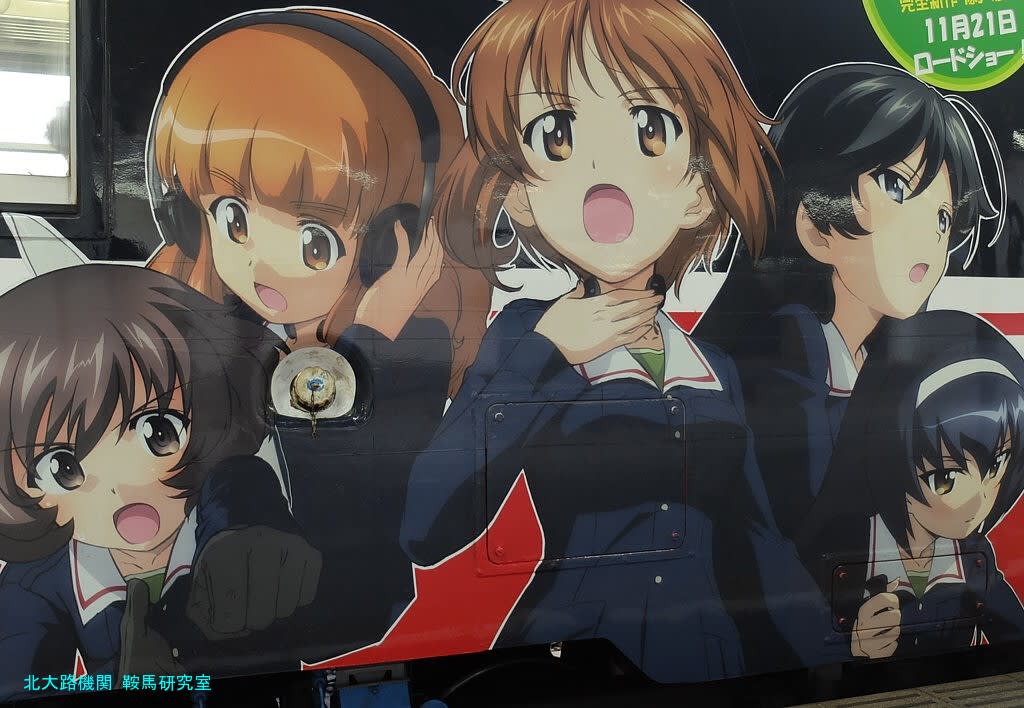■戦車大隊長への遠い道のり
戦車道の試合では大規模な場合、劇中に30両vs30両の戦車戦闘が描かれていました、30両といえば実質的に戦車大隊の規模です。軍事検証:ガールズ&パンツァー、最終回はこの視点について考えてみましょう。

戦車長、指揮官となりますので戦車長養成もまた長い時間を要するものといえるでしょう、また戦車の数が6両を越えた場合は一個小隊とするには規模が大きくなる過ぎるので、小隊を二個に分ける必要が出てきます、この場合はもう一人小隊長が必要となるのですが、その養成にもやはり時間がかかります、勿論、ガールズ&パンツァーの世界では10両以上の戦車、場合によっては30両の戦車を一つの部隊で運用する事がありますが、こうなりますと中隊長と大隊長を養成する必要があります、すると指揮官養成と調整しなければならない。

指揮官としての素養養成分野やその規模の戦車が参加する事での戦術体系の複合化はより一層強くなりますので、このように戦車を動かすことは簡単でも、戦車が戦車としての能力を、戦車同士が連携して戦車部隊としての能力を発揮できるような体制の構築は非常に時間を要するのです、ガールズ&パンツァーの世界において、実際の戦術と戦車道の違いが顕著だな、と思う点はあくまで競技であり、戦争ではない、サンダース学園のケイさんも劇中で仰っていた言葉ですが、この点から複雑な戦車の描写をかなり軽めている点に気付かされます、戦車中隊長や戦車大隊長への道のりは遠いのです。

それは、彼我戦力が試合開始の時点で明確となっている事から、実戦では非常に難しい相対戦力見積の難易度が払拭されていますし、砲兵が、劇場版では別としまして、間接照準射撃を行う脅威を考える必要がありません。また、全国大会では砲弾数が決まっているとの話でしたので、弾薬補給も想定しなくとも対応出来る事でしょう、更に二次創作の世界では“女子は戦車道、そして男子は、対戦車道!”と往年の名画が紹介されていることで知られるのですが、戦車道の世界では試合に歩兵が存在しませんので、このあたりは考え易く設定しているのでしょう。

演出の限界といいますか、整備補給の面で多種多様な戦車を一つの部隊に置くことは非常に非効率ですし、戦車砲の初速と射程が全部違っている場合は小隊集中火力の利点を全く発揮できませんし、戦車部隊としての連携は機動力に格差があれば全く生かせず、早い快速戦車や軽戦車が先に第一線に到達し結果的に戦力逐次投入となる危惧や、そもそも整備補給体系と戦術教育など部隊としてまとめる事は出来ません、無論過去の末期戦では雑多な戦車を集積し防御戦闘に効力を発揮した事例は無くもないのですが、これは歩兵火力や防御陣地との連携の一部に戦車としての能力の一部を限定的に活かしただけのもので、やはり戦車部隊として機能しません、これはあらゆる戦車部隊の編成が最大限車種の統一を指向している事に表れています。

ただ、アニメーションで戦車がこれまでにない水準で描かれていまして、そちらの技術には驚かされます、戦車は駆動部分が多く、セル画方式の作画では永らく描くことが出来ないものとされてきました、妥協しますと“アニメンタリー決断”のような止め絵と砂塵などで隠す演出主体となってしまうものでした、戦車の描写は現場対立も招くもので、その昔、テレビ版ルパン三世最終話に74式戦車を登場させようとしたところ、作画側が履帯の駆動動作を描くことは不可能として、演出と作画の深刻な現場対立となり、結局当時74式には無かったサイドスカートを追加し、履帯の描写を少なくすることにて妥協しました。

それが2010年代には、CGの発展により旧式戦車も滑らかな動きにて描写できていることは驚かされました、東映の劇場アニメーション“FUTURE WAR 198X年”では戦車が頑張って描かれていまして、こんな内容描けるか辞めてやる、と労組と制作側の対立はありましたが、全体はさておき、劇場アニメーションであればこその戦車の水準でもありました、しかしそれにしても今日的視点からは少々難色があり、全体はさておき、限界を考えさせられるものです。そのあたりを技術で解決したガールズ&パンツァーは、技術の進歩を感じる事が出来る作品といえるでしょう。

ガールズ&パンツァーはこうした戦車がある、という認識を得るには興味深い作品ですが、戦車を実際に運用する方には違和感があるという方もいらっしゃるようで、それは戦車のむずかしさを知っている故のものだといえるでしょう、他方、戦車が主役の映画“フューリー”が公開されたさい、なかなか戦車運用の視点からは幾つか留意点があるのですが、当方の知っている方で戦車乗りの方は、大絶賛でして、さてあの展開であの判断は如何なものか、と問うてみましたらば、うむ俺が戦車長ならばね、と更に熱く語ってくれました。

その上で視線とは様々なものがあり、戦車乗りだからこそ深い知識と経験故のお話を聞けました、上から視点で語る方々、嬉しそうで羨ましかったですね、こうしてみますと、一歩引いてみますか、エリカは不憫、と異なる視点から見てみる、またはヒロイン中の人が同じ、蒼き鋼のアルペジオ、のように見た目は従来装備でも中身が完全別物、であればSF作品として更に広く受け入れられたのかもしれません。
北大路機関:はるな くらま
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
戦車道の試合では大規模な場合、劇中に30両vs30両の戦車戦闘が描かれていました、30両といえば実質的に戦車大隊の規模です。軍事検証:ガールズ&パンツァー、最終回はこの視点について考えてみましょう。

戦車長、指揮官となりますので戦車長養成もまた長い時間を要するものといえるでしょう、また戦車の数が6両を越えた場合は一個小隊とするには規模が大きくなる過ぎるので、小隊を二個に分ける必要が出てきます、この場合はもう一人小隊長が必要となるのですが、その養成にもやはり時間がかかります、勿論、ガールズ&パンツァーの世界では10両以上の戦車、場合によっては30両の戦車を一つの部隊で運用する事がありますが、こうなりますと中隊長と大隊長を養成する必要があります、すると指揮官養成と調整しなければならない。

指揮官としての素養養成分野やその規模の戦車が参加する事での戦術体系の複合化はより一層強くなりますので、このように戦車を動かすことは簡単でも、戦車が戦車としての能力を、戦車同士が連携して戦車部隊としての能力を発揮できるような体制の構築は非常に時間を要するのです、ガールズ&パンツァーの世界において、実際の戦術と戦車道の違いが顕著だな、と思う点はあくまで競技であり、戦争ではない、サンダース学園のケイさんも劇中で仰っていた言葉ですが、この点から複雑な戦車の描写をかなり軽めている点に気付かされます、戦車中隊長や戦車大隊長への道のりは遠いのです。

それは、彼我戦力が試合開始の時点で明確となっている事から、実戦では非常に難しい相対戦力見積の難易度が払拭されていますし、砲兵が、劇場版では別としまして、間接照準射撃を行う脅威を考える必要がありません。また、全国大会では砲弾数が決まっているとの話でしたので、弾薬補給も想定しなくとも対応出来る事でしょう、更に二次創作の世界では“女子は戦車道、そして男子は、対戦車道!”と往年の名画が紹介されていることで知られるのですが、戦車道の世界では試合に歩兵が存在しませんので、このあたりは考え易く設定しているのでしょう。

演出の限界といいますか、整備補給の面で多種多様な戦車を一つの部隊に置くことは非常に非効率ですし、戦車砲の初速と射程が全部違っている場合は小隊集中火力の利点を全く発揮できませんし、戦車部隊としての連携は機動力に格差があれば全く生かせず、早い快速戦車や軽戦車が先に第一線に到達し結果的に戦力逐次投入となる危惧や、そもそも整備補給体系と戦術教育など部隊としてまとめる事は出来ません、無論過去の末期戦では雑多な戦車を集積し防御戦闘に効力を発揮した事例は無くもないのですが、これは歩兵火力や防御陣地との連携の一部に戦車としての能力の一部を限定的に活かしただけのもので、やはり戦車部隊として機能しません、これはあらゆる戦車部隊の編成が最大限車種の統一を指向している事に表れています。

ただ、アニメーションで戦車がこれまでにない水準で描かれていまして、そちらの技術には驚かされます、戦車は駆動部分が多く、セル画方式の作画では永らく描くことが出来ないものとされてきました、妥協しますと“アニメンタリー決断”のような止め絵と砂塵などで隠す演出主体となってしまうものでした、戦車の描写は現場対立も招くもので、その昔、テレビ版ルパン三世最終話に74式戦車を登場させようとしたところ、作画側が履帯の駆動動作を描くことは不可能として、演出と作画の深刻な現場対立となり、結局当時74式には無かったサイドスカートを追加し、履帯の描写を少なくすることにて妥協しました。

それが2010年代には、CGの発展により旧式戦車も滑らかな動きにて描写できていることは驚かされました、東映の劇場アニメーション“FUTURE WAR 198X年”では戦車が頑張って描かれていまして、こんな内容描けるか辞めてやる、と労組と制作側の対立はありましたが、全体はさておき、劇場アニメーションであればこその戦車の水準でもありました、しかしそれにしても今日的視点からは少々難色があり、全体はさておき、限界を考えさせられるものです。そのあたりを技術で解決したガールズ&パンツァーは、技術の進歩を感じる事が出来る作品といえるでしょう。

ガールズ&パンツァーはこうした戦車がある、という認識を得るには興味深い作品ですが、戦車を実際に運用する方には違和感があるという方もいらっしゃるようで、それは戦車のむずかしさを知っている故のものだといえるでしょう、他方、戦車が主役の映画“フューリー”が公開されたさい、なかなか戦車運用の視点からは幾つか留意点があるのですが、当方の知っている方で戦車乗りの方は、大絶賛でして、さてあの展開であの判断は如何なものか、と問うてみましたらば、うむ俺が戦車長ならばね、と更に熱く語ってくれました。

その上で視線とは様々なものがあり、戦車乗りだからこそ深い知識と経験故のお話を聞けました、上から視点で語る方々、嬉しそうで羨ましかったですね、こうしてみますと、一歩引いてみますか、エリカは不憫、と異なる視点から見てみる、またはヒロイン中の人が同じ、蒼き鋼のアルペジオ、のように見た目は従来装備でも中身が完全別物、であればSF作品として更に広く受け入れられたのかもしれません。
北大路機関:はるな くらま
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)