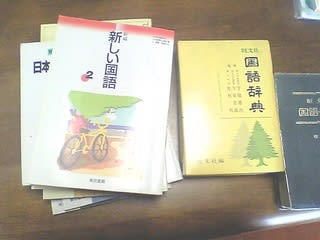1970年前後の学園紛争の盛んな時期に、高校生、大学生として多感な時期を過ごした。学生時代最後は、実験心理学の研究に集中したが、研究室に残ることもなく就職した。
就職したのは、社会の流れや価値観に妥協したところがあった。そして、抵抗していた父親のアイデンティティを踏襲していた。入社して、しばらくは違和感もあったが、コンピュータの営業やマーケティングの仕事は楽しく、そして結婚し子供が生まれいつのまにか35歳を越えた。
青春時代は終わりつつあり、社会も1990年代に向けて大きく変わろうとしていた。そして、家庭を顧みず仕事をしていた「つけ」も、それから徐々に現れてきた。自分自身の基本的な青春時代に育んできた理想やアイデンティティがいつの間にか危機にさらされてきた。
1999年1月、ふらっと立ち寄った教会で、ありのままの自分を受容できたとき、期せずして幸福感を感じ新しい何かがスタートした。
「生き甲斐の心理学」では、理想や夢が時として、人を思いがけず傷つけることを記している。青春時代を通し育んだ、生き残るために身につけた理想・夢。それは、ナイーブな何かを傷つけてしまうこともある。
人と自分を大切にしていきたい。
 人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)
人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)

「生き甲斐の心理学」:ユースフルライフ研究所、植村高雄著・監修