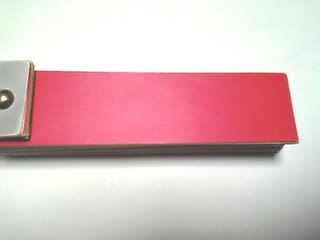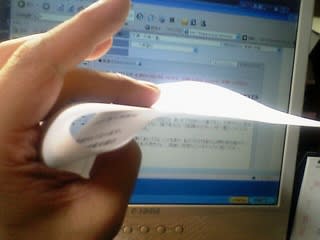7歳の夏、アラスカのシトカに住み始め、近くの米国の小学校のクラスに編入された。周りは全て英語を話すだけで、日本語を理解する人は皆無であった。私は日本語しか解せない。ただ、クラスメートは、日本人と同じ肌のネイティブが多かった。そしてクラスの女性の先生も日本人と同じ肌の色であった。
ネイティブはベーリング海を越えてきたモンゴロイドという説もあるが、日本海流に乗って、日本やアジアから漂着した人々の子孫でもあるという説もあった。クリンギット族という北米インディアンが主体である。
先生が、何も言葉を理解せず、不安げに机に座っているわたしを心配しているのが判った。
なにかいろいろ話しかけてくる。そのうち、カードを見せ、「・・・・・」と何か聞いて来る。
今度はカードを替えて、「・・・・・・・」と聞いて来る。ああ、色のことを言っているのだと思った。でも英語は全くわからない。察知してくれていいのにと思う。さらに熱心に訊いてくる。

「キイロ」と答える。そんな風にして、日本語で答えると先生は目を輝かせて、クラスの皆に日本語の色の単語を私から発表させた。
そんな、先生とクラスの温かさは今でも忘れない。最後にそのクラスを別れるときに、先生がチョークや色紙などを袋に入れて私にくれた。忘れられないプレゼントであった。カルチャーショックを乗り越えはじめたころのエピソードである。
言葉ではない、秘められた力をもつ人の温かさ!どれだけ大切なことか!
 人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)
人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)