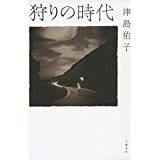昨年2月、惜しくも亡くなった津島佑子さんの遺作(亡くなられた後の、未発表の作品)。
主人公の絵美子は、12歳の時、3歳年上のダウン症の兄、耕一郎と死別するという痛切な体験を持っています。すでに父を早くになくした絵美子は、以来、母カズミと2人で生活しています。
絵美子には、甲府にいる母方、仙台にいる父方には祖母、叔父、叔母、いとこなど親戚がたくさん。中でもアメリカに移住した父の兄(叔父)家族との交流、いとことの関わりなど、世代、時代を超え、現実と夢とを交錯させながら、たくさんの親戚たちの視点で、戦争期から現代に至るまでの一族の歴史を描いていきます。
読み始めは小説の舞台、展開がわかりにくい点があります。津島佑子さんが肺がんで息を引き取る寸前まで手を入れていたことが娘さんの後書きで明らかにされます。健在ならばもっと推敲されていたかもしれません。
いうまでもなく、津島さんは太宰治と美知子さんの間に生まれた次女の方。15歳で亡くなったダウン症の兄がいたことも知られています。父が玉川上水で入水自殺(心中)した後、母と姉との3人母子家庭で育ったことや自ら娘と二人で生活していた経験などが色濃く反映されているように感じますが、そんな作者の身辺の下世話ばなしではすまされない内容を持った作品となっています。
読み始めて間もなく、絵美子の伯父、創、叔母ヒロミたち3人が戦中の幼少期に体験したことが出てきます。ヒトラー・ユーゲント・少年団が使節団として来日、3人の住む甲府駅に少年たちが乗った列車が着いた歓迎のとき、3人は親兄弟の注意も聞かず、ヒトラー・ユーゲントを見に駅へ行きます。そこである出来事が起こります。肌の色が黄色ではなく、透き通るような白い少年をも巻き込んでの行為、叔母は誰にも話すこともできないまま長い年月が経ちます。その内容は後半になって明らかにされます。
さらに戦後、絵美子が10歳のころ、いとこの同年代の晃か秋雄のどちらから、「フテ・・・」という言葉をささやかれたという、曖昧な記憶にこだわり続けます。はたしてどちらが言ったのか?
いとこたちと遊んでいる最中、ダウン症の兄・耕一郎の行動に腹を立てたどちらかが、絵美子に投げつけた言葉なのです。「フテ」は「フテキカクシャ」それは「アンラクシ」、「ジヒシ」につながる言葉であったことを後になって知る絵美子。
兄が亡くなった後、それがヒトラーによる優生思想に基づいて「不適格者」を「安楽死」、「慈悲死」させたという歴史から来ている言葉で、兄・耕一郎を社会に不要な存在として、抹殺する言葉だった。でも、誰が言ったのか?
絵美子は、いとこのどちらかがどんな理由でどんな気持ちで、耕一郎の存在を根本から否定する言葉を口にしたのか、長い間、尋ねることに躊躇しています。ようやく実現したのは、小説も終わりのほうになってからです。それがまた絵美子の心に重くのしかかります。
子どもの頃、耕一郎と二人で面白半分で万引きしたときの興奮を記したあと、
わたしはこうちゃんにすべてを押しつけるつもりなのだろうか。こんなことでは、わたしこそがこうちゃんを「フテキカクシャ」と指弾して、にやにや笑いながら「ジヒシ」もしくは「アンラクシ」に追い込もうとする連中のひとりになってしまうではないか。「フテキカクシャ」ということばを絵美子がはじめて聞かされたのは、そういえば、十歳のときだった。(P231)
こうちゃんがいなくなって、そのあと、わたしはナチスについて書かれた本を読んで、おびえるようになった。忘れたくたって、忘れられない。・・・晃さんになんとか復讐してやる、と思いつづけてきた。だけど、わたしに「フテキカクシャ」ってささやいたのは晃さんじゃなかった。あなただった。ばかみたいね。復讐もへったくれもない。わたしこそ、聞きたい、どうしたらいいのって。
マンションの前にふたりは立っていた。(P249)
秋雄さんそうは思わない?
ああ、ちがうわね。あのとき無理に話をしていたらなにもかもぶちこわしになっていた。わたしたち、憎み合うようになっていたわ、きっと。「フテキカクシャ」ということばは、それだけおそろしい憎しみを含んでいた。わたしたちはきっと、それに耐えられなかった。だって、わたしたちはまだほんの子どもで、実際の憎しみとはどんなものなのかまったく知らなかったんだもの。そんな憎しみにもし本当に指一本だけでも触れてしまったら、あのあと心の底から笑うこともできなくなっていたのかもしれない。(P254)
(死を意識した、絵美子の父・遼一郎の兄永一郎の独白)
耕一郎は愛情深い子どもです。家族だけではなく、まわりのひとたちに無類の笑みを見せてくれるのです。そこには計算というものがありません。自意識もございません。ひととして、それで充分なのではあるまいか。わたしはそう思うに至りました。(P267)
ナチス・ドイツとかつての日本帝国は、とてもよく似ておりました。役に立たないものは容赦なく切り捨てる。近代日本とナチス・ドイツは徹底して、そうした考え方で繁栄を自らのものにすることができました。
しかし戦争に負けて、ドイツは考え方を根底から変えました。変えざるを得なかった。・・・日本はなにも変えようとしなかった。チャンスに恵まれれば、いつでも復活するつもりでした。その象徴が、原子力発電所だったのです。原子力発電所さえあれば、かの偉大なる日本はいつでも復活できる。そのように信じつづけ、結局、日本は、原子力発電所の大爆発を経験しなければならなかったのです。
・・・ヒロシマの惨状にショックを受けたアインシュタインの、核兵器廃絶の主張はまちがってはいなかった。……(P276)
絵美子にまつわるたくさんの縁者たちの、生者、死者の語りが何重にも積み重ねられながら物語を紡いでいきます。津島さんの、臨終に至るまでこだわり続けた差別への怒り、障がい者への寄り添いなど、そして、粗削りにならざるを得なかった無念さもひしひしと感じる作品です。
「狩りの時代」。
「狩猟者」は誰か? 「狩り」の対象は誰か? 「狩り」をするものも「狩」られるものも紙一重の世の中、時代の恐ろしさよ!
「言葉」は人の生き死にまでも左右します、そのシビアな言葉の働きを心身で受け止める作家としての遺作です。
ひとしく嗅覚、感性を鋭くしたいものです。
参考に、違う視点、というよりも「日本(人)的」差別意識についての「内田樹の研究室」から内田樹さんの、興味深い文章を引用させて頂きます。
「愛国的リバタリアン」という怪物
金満里さんたちが出している「イマージュ」という媒体が、相模原の「やまゆり園事件」についての考察を特集した。そこに私も一文を寄稿した。あまり目に触れる機会のない媒体なので、私の書いたものだけここに再録する。
相模原の大量殺人事件のもたらした最大の衝撃は、植松聖容疑者が事前に安倍晋三首相宛てと大島理森衆院議長宛てに犯行を予告する内容の書簡を届けていたことにある。それは権力者を挑発するための犯行予告ではなく、自分の行為が政権と国会多数派には「好ましい」ものとして受け止められ、権力からの同意と保護を得られるだろうという期待をこめたものだった。逮捕後も容疑者は「権力者に守られているので、自分は死刑にはならない」という趣旨の発言をしている。
もちろん、これは容疑者の妄想に過ぎない。けれども、何の現実的根拠もない妄想ではない。彼の妄想形成を強化するような現実が今の日本社会内部にはたしかに存在しているからである。
アナウンサーの長谷川豊は事件の直後の2016年9月に自身のブログに「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!」というタイトルの記事を投稿した。これには批判が殺到し、専門医からも事実誤認が指摘されたが、この人物を日本維新の会は千葉一区から衆院の立候補者として擁立するということが先日発表された。
重篤な病人や障害者に対する公然たる差別発言にはまだ一定の社会的な規制が働いており、有名人の場合には、それなりの批判を受けて、社会的制裁が課されているが、在日コリアン、生活保護受給者やLGBTなどの社会的弱者に対する差別や攻撃の発言はほとんど何のペナルティもないままに垂れ流しされている。
際立つのが片山さつき議員で、生活保護受給者は「実質年収4百万円」の生活をしているという無根拠な都市伝説の流布に加担するなどして、生活保護叩き発言を繰り返してきたが、最近も捏造投稿に基づいてNHKのニュース内容にクレームをつけて、生活保護受給者が社会福祉の「フリーライダー」だという世論の喚起に励んでいる。もちろん、本人がそう「信じている」という信憑の問題もあるのだろうが、「そういうこと」を公言すると選挙で票が集まるという現実的な打算も同時に働いているはずである。
アメリカではドナルド・トランプ大統領が「弱者叩き」の代表格である。「ラストベルト」のプア・ホワイトたちの輿望を担って登場したはずのトランプだが、就任後実施された政策は富裕層への厚遇措置ばかりで、移民排斥や、海外企業の国内移転への圧力などの「雇用対策」は今ここにいる社会的弱者のためには何の利益ももたらしてはいない。選挙公約だったオバマケアの廃止は、それによって2400万人が医療保険を失うという予測が公表されて、さすがに与党共和党も加担できず、改廃法案を撤回するという騒ぎになった。アメリカの有権者はそのような人物を大統領に選んだのである。
これはおそらく全世界的な傾向である。社会的弱者たちは、自己責任で弱者になったわけであり、いわばそういう生き方を選択したのだから、政府や自治体が、公金を投じて彼らを支援することは「フェアではない」というロジックは目新しいものではない。これはアメリカにおいては「リバタリアニズム(libertarianism)」というかたちで、建国当初からつねにアメリカ社会に伏流していた。アメリカが世界に冠絶する覇権国家となり、その国の作法や価値観が「グローバル化」したことによって、アメリカ的な「リバタリアニズム」もまたグローバル化したということだと私は理解している。
「セルフメイドマン(self made man)」というのは建国以来のアメリカ市民の理想像だが、要するに誰にも頼らず独立独行で自己実現を遂げる生き方のことである。「リバタリアン(libertarian)」は、その過激化したかたちである。
リバタリアンは、人間は自分の運命の完全な支配者であるべきであり、他者であれ公共機関であれ、いかなるものも自分の運命に介入する権利はないと考える。だから、リバタリアンは政府による徴税にも、徴兵制にも反対する。当然ながら、社会福祉のための原資の提供にも反対する。
ドナルド・トランプが徴税と社会福祉制度につよい嫌悪感を示すのは、彼がリバタリアンの伝統に連なっていることを示している。
トランプは選挙期間中に対立候補から連邦税を納めていないことを指摘されて、「すべてのアメリカ人は納税額を最小化するために日々知恵を絞っている。私が連邦税を払っていないのは私が賢いからである」と述べて支持者の喝采を浴びた。これは別に露悪的な発言をしたわけではなく、ほんとうにそう思っているからそう言ったのである。彼に喝采を送ったプア・ホワイトたちは、自分たちとは桁が違う大富豪であるトランプの「納税したくない」というリバタリアン気質が「自分と同じだ」と思って、その発言に賛意を評したのである。
トランプは軍務の経験も、行政の経験もないはじめての大統領だが、それは軍務に就くことも、公共機関で働くことも、どちらもリバタリアンとしては「やらないにこしたことはない」仕事だからである。アメリカの有権者たちは彼の「公的権力を用いて私利私欲を満たすが、公益のためには何もしない」という態度がたいそう気に入ったのである。
今の日本で起きている「弱者叩き」はアメリカ原産のリバタリアニズムが日本に漂着し、日本独特の陰湿なしかたで退廃したものだと私は理解している。トランプのリバタリアニズムはこう言ってよければ「あっけらかん」としている。ロシアとの内通疑惑が暴かれたことによって、彼が「愛国者」であるかどうかについてはアメリカ人の多くが疑問を抱いているだろう。けれども、リバタリアンにおいて、愛国者であることは実は「アメリカ人的であること」のための必要条件ではない(国家や政府などというものは「ない方がいい」というのが正統的なリバタリアンの立場だからである)。
けれども、日本では公的立場にある人間は「国よりも自分が大事」というようなことを(心で思っていても)口には出さない。仮に、安倍晋三が所得税を払っていなかったことが発覚したとしても、彼は「私は賢いから税金を払わずに済ませた」という言い訳をしないだろうし、その言い訳に喝采を送る有権者も日本にはいないはずである。
日本ではリバタリアンも愛国的なポーズをすることを強いられる。
だから、日本では「リバタリアンでありながら、かつ愛国的」という奇妙な生き物が生まれてくる。現代日本に跋扈しているのは、この「愛国的リバタリアン」という(「肉好きのベジタリアン」とか「気前のいい吝嗇漢」というような)形容矛盾的存在である。
一方において、彼らは自分が獲得したものはすべて「自己努力によって獲得されたもの」だから、100%自分の所有に属し、誰とも分かち合う気がないと断言する。同じ理屈で、貧困や疾病や障害や不運などによって社会的弱者になった者たちについても「すべて自己責任で失ったもの」であるので、そのための支援を公的機関に求めるのは筋違いであると主張する。
ここまではリバタリアン的主張であるが、日本の「愛国的リバタリアン」はこれに愛国主義(というより排外主義、外国人嫌い)をぱらぱらとまぶして、社会的弱者というのは実は「外国人」であるという奇妙な社会理論を創り出す。ここに日本のリバタリアニズムの独特の歪みがある。
日本型リバタリアンによると、社会的弱者やあるいは社会的弱者を支援する人たちは「外国人」なのである。仮に血統的には日本人であったにせよ、外国渡来のイデオロギーや理説に「感染」したせいで、「外側は日本人だが、中身は外国人」になっているのである。だから、社会福祉や教育や医療などの活動に公的な支援を求める組織や運動は本質的には「日本の国益よりも、彼らが忠誠を誓っている外国の利益に奉仕するもの」なのだという妄説が出来上がる。生活保護の受給者は多くが在日コリアンであるとか、日教組の背後にはコミンテルンがいるとか、朝日新聞は反日であるとか、翁長沖縄県知事は中国に操られているといった類のネトウヨ的妄説はその典型的なものである。
語っている本人もさすがにほんとうだと思ってそう言っているわけではいないだろう。にもかかわらず、彼らが「反政府的な人間=外国人」というスキームに固執するのは、彼らにリバタリアンに徹底する覚悟がないからである。
リバタリアンであれば、話はすっきりしている。貧乏なのも、病気なのも、障害者であるのも、すべては自己責任である。だから、それについては他者からの同情や公的支援を当てにしてはならない。医療保険制度はいらない(医療は「サービス」なのだから金を出して買え。金がないやつは死ね)。公立学校も要らない(教育は「サービス」なのだから、金を出して買え。金がないやつは働いて学費を稼ぐか、有利子で借りろ)。社会福祉制度はいらない(他人の施しがないと生きていけないやつは死ね)と、ずいぶん非人情ではあるけれど、バケツの底が抜けたように「あっけらかん」としている。
しかし、さすがに日本では(心ではそう思っていても)そこまでは言い切れない(居酒屋のカウンターで酔余の勢いで口走ることはあるだろうが、公的な立場ではなかなか口にはされない)。
その不徹底をとりつくろうために、日本的リバタリアンは「排外主義」的イデオロギーを装飾的に身にまとう。そして、貧乏人も、病人も、障害者も、生活保護受給者も、みな本質的には「外国人」であるという摩訶不思議な理説を噛ませることで、話のつじつまを合わせようとするのである。
相模原事件の植松容疑者はその意味では障害者支援をめぐる問題の本質をよく見抜いていたというべきだろうと思う。彼自身は生活保護の受給者であったが、その事実は「わずかな賃金を得るために、他人に顎で使われて、自分の貴重な人生を空費したくない」という彼のリバタリアン的な気質と齟齬するものではなかった。けれども、自分以外の生活保護受給者や障害者は彼の目には許し難い社会的寄生者に見えた。この矛盾を彼はどう解決したのだろうか。自分には公的支援を受けることを許すが、他人には許さないという身勝手な識別を可能にする境界線として最終的に彼が思いついたのは「私は日本人として日本の国益を優先的に配慮しているが、彼らはしていない」という「日本人/非日本人」スキームであった。
だから、植松容疑者がこれは「日本のために」したのだとか、「社会が賛同するはずだった」とかいう自己弁明を繰り返し、「国益を害するものたち」を「処分」する「官許」を首相や衆院議長に申請したことには論理的には必然性があったのである。
彼は自分が「愛国的リバタリアン」という政治的奇形物であり、現在の日本の政界の指導者たちの多くが程度の差はあれ自分の「同類」だと直感していたのである。
津島さんの憂いをはるかに越えて、早晩、日本のみならず、世界が、言葉による暴力にとどまらず、排外主義的な肉体的暴力へいっそう突き進む時を迎えているような思いがしてなりません。
主人公の絵美子は、12歳の時、3歳年上のダウン症の兄、耕一郎と死別するという痛切な体験を持っています。すでに父を早くになくした絵美子は、以来、母カズミと2人で生活しています。
絵美子には、甲府にいる母方、仙台にいる父方には祖母、叔父、叔母、いとこなど親戚がたくさん。中でもアメリカに移住した父の兄(叔父)家族との交流、いとことの関わりなど、世代、時代を超え、現実と夢とを交錯させながら、たくさんの親戚たちの視点で、戦争期から現代に至るまでの一族の歴史を描いていきます。
読み始めは小説の舞台、展開がわかりにくい点があります。津島佑子さんが肺がんで息を引き取る寸前まで手を入れていたことが娘さんの後書きで明らかにされます。健在ならばもっと推敲されていたかもしれません。
いうまでもなく、津島さんは太宰治と美知子さんの間に生まれた次女の方。15歳で亡くなったダウン症の兄がいたことも知られています。父が玉川上水で入水自殺(心中)した後、母と姉との3人母子家庭で育ったことや自ら娘と二人で生活していた経験などが色濃く反映されているように感じますが、そんな作者の身辺の下世話ばなしではすまされない内容を持った作品となっています。
読み始めて間もなく、絵美子の伯父、創、叔母ヒロミたち3人が戦中の幼少期に体験したことが出てきます。ヒトラー・ユーゲント・少年団が使節団として来日、3人の住む甲府駅に少年たちが乗った列車が着いた歓迎のとき、3人は親兄弟の注意も聞かず、ヒトラー・ユーゲントを見に駅へ行きます。そこである出来事が起こります。肌の色が黄色ではなく、透き通るような白い少年をも巻き込んでの行為、叔母は誰にも話すこともできないまま長い年月が経ちます。その内容は後半になって明らかにされます。
さらに戦後、絵美子が10歳のころ、いとこの同年代の晃か秋雄のどちらから、「フテ・・・」という言葉をささやかれたという、曖昧な記憶にこだわり続けます。はたしてどちらが言ったのか?
いとこたちと遊んでいる最中、ダウン症の兄・耕一郎の行動に腹を立てたどちらかが、絵美子に投げつけた言葉なのです。「フテ」は「フテキカクシャ」それは「アンラクシ」、「ジヒシ」につながる言葉であったことを後になって知る絵美子。
兄が亡くなった後、それがヒトラーによる優生思想に基づいて「不適格者」を「安楽死」、「慈悲死」させたという歴史から来ている言葉で、兄・耕一郎を社会に不要な存在として、抹殺する言葉だった。でも、誰が言ったのか?
絵美子は、いとこのどちらかがどんな理由でどんな気持ちで、耕一郎の存在を根本から否定する言葉を口にしたのか、長い間、尋ねることに躊躇しています。ようやく実現したのは、小説も終わりのほうになってからです。それがまた絵美子の心に重くのしかかります。
子どもの頃、耕一郎と二人で面白半分で万引きしたときの興奮を記したあと、
わたしはこうちゃんにすべてを押しつけるつもりなのだろうか。こんなことでは、わたしこそがこうちゃんを「フテキカクシャ」と指弾して、にやにや笑いながら「ジヒシ」もしくは「アンラクシ」に追い込もうとする連中のひとりになってしまうではないか。「フテキカクシャ」ということばを絵美子がはじめて聞かされたのは、そういえば、十歳のときだった。(P231)
こうちゃんがいなくなって、そのあと、わたしはナチスについて書かれた本を読んで、おびえるようになった。忘れたくたって、忘れられない。・・・晃さんになんとか復讐してやる、と思いつづけてきた。だけど、わたしに「フテキカクシャ」ってささやいたのは晃さんじゃなかった。あなただった。ばかみたいね。復讐もへったくれもない。わたしこそ、聞きたい、どうしたらいいのって。
マンションの前にふたりは立っていた。(P249)
秋雄さんそうは思わない?
ああ、ちがうわね。あのとき無理に話をしていたらなにもかもぶちこわしになっていた。わたしたち、憎み合うようになっていたわ、きっと。「フテキカクシャ」ということばは、それだけおそろしい憎しみを含んでいた。わたしたちはきっと、それに耐えられなかった。だって、わたしたちはまだほんの子どもで、実際の憎しみとはどんなものなのかまったく知らなかったんだもの。そんな憎しみにもし本当に指一本だけでも触れてしまったら、あのあと心の底から笑うこともできなくなっていたのかもしれない。(P254)
(死を意識した、絵美子の父・遼一郎の兄永一郎の独白)
耕一郎は愛情深い子どもです。家族だけではなく、まわりのひとたちに無類の笑みを見せてくれるのです。そこには計算というものがありません。自意識もございません。ひととして、それで充分なのではあるまいか。わたしはそう思うに至りました。(P267)
ナチス・ドイツとかつての日本帝国は、とてもよく似ておりました。役に立たないものは容赦なく切り捨てる。近代日本とナチス・ドイツは徹底して、そうした考え方で繁栄を自らのものにすることができました。
しかし戦争に負けて、ドイツは考え方を根底から変えました。変えざるを得なかった。・・・日本はなにも変えようとしなかった。チャンスに恵まれれば、いつでも復活するつもりでした。その象徴が、原子力発電所だったのです。原子力発電所さえあれば、かの偉大なる日本はいつでも復活できる。そのように信じつづけ、結局、日本は、原子力発電所の大爆発を経験しなければならなかったのです。
・・・ヒロシマの惨状にショックを受けたアインシュタインの、核兵器廃絶の主張はまちがってはいなかった。……(P276)
絵美子にまつわるたくさんの縁者たちの、生者、死者の語りが何重にも積み重ねられながら物語を紡いでいきます。津島さんの、臨終に至るまでこだわり続けた差別への怒り、障がい者への寄り添いなど、そして、粗削りにならざるを得なかった無念さもひしひしと感じる作品です。
「狩りの時代」。
「狩猟者」は誰か? 「狩り」の対象は誰か? 「狩り」をするものも「狩」られるものも紙一重の世の中、時代の恐ろしさよ!
「言葉」は人の生き死にまでも左右します、そのシビアな言葉の働きを心身で受け止める作家としての遺作です。
ひとしく嗅覚、感性を鋭くしたいものです。
参考に、違う視点、というよりも「日本(人)的」差別意識についての「内田樹の研究室」から内田樹さんの、興味深い文章を引用させて頂きます。
「愛国的リバタリアン」という怪物
金満里さんたちが出している「イマージュ」という媒体が、相模原の「やまゆり園事件」についての考察を特集した。そこに私も一文を寄稿した。あまり目に触れる機会のない媒体なので、私の書いたものだけここに再録する。
相模原の大量殺人事件のもたらした最大の衝撃は、植松聖容疑者が事前に安倍晋三首相宛てと大島理森衆院議長宛てに犯行を予告する内容の書簡を届けていたことにある。それは権力者を挑発するための犯行予告ではなく、自分の行為が政権と国会多数派には「好ましい」ものとして受け止められ、権力からの同意と保護を得られるだろうという期待をこめたものだった。逮捕後も容疑者は「権力者に守られているので、自分は死刑にはならない」という趣旨の発言をしている。
もちろん、これは容疑者の妄想に過ぎない。けれども、何の現実的根拠もない妄想ではない。彼の妄想形成を強化するような現実が今の日本社会内部にはたしかに存在しているからである。
アナウンサーの長谷川豊は事件の直後の2016年9月に自身のブログに「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!」というタイトルの記事を投稿した。これには批判が殺到し、専門医からも事実誤認が指摘されたが、この人物を日本維新の会は千葉一区から衆院の立候補者として擁立するということが先日発表された。
重篤な病人や障害者に対する公然たる差別発言にはまだ一定の社会的な規制が働いており、有名人の場合には、それなりの批判を受けて、社会的制裁が課されているが、在日コリアン、生活保護受給者やLGBTなどの社会的弱者に対する差別や攻撃の発言はほとんど何のペナルティもないままに垂れ流しされている。
際立つのが片山さつき議員で、生活保護受給者は「実質年収4百万円」の生活をしているという無根拠な都市伝説の流布に加担するなどして、生活保護叩き発言を繰り返してきたが、最近も捏造投稿に基づいてNHKのニュース内容にクレームをつけて、生活保護受給者が社会福祉の「フリーライダー」だという世論の喚起に励んでいる。もちろん、本人がそう「信じている」という信憑の問題もあるのだろうが、「そういうこと」を公言すると選挙で票が集まるという現実的な打算も同時に働いているはずである。
アメリカではドナルド・トランプ大統領が「弱者叩き」の代表格である。「ラストベルト」のプア・ホワイトたちの輿望を担って登場したはずのトランプだが、就任後実施された政策は富裕層への厚遇措置ばかりで、移民排斥や、海外企業の国内移転への圧力などの「雇用対策」は今ここにいる社会的弱者のためには何の利益ももたらしてはいない。選挙公約だったオバマケアの廃止は、それによって2400万人が医療保険を失うという予測が公表されて、さすがに与党共和党も加担できず、改廃法案を撤回するという騒ぎになった。アメリカの有権者はそのような人物を大統領に選んだのである。
これはおそらく全世界的な傾向である。社会的弱者たちは、自己責任で弱者になったわけであり、いわばそういう生き方を選択したのだから、政府や自治体が、公金を投じて彼らを支援することは「フェアではない」というロジックは目新しいものではない。これはアメリカにおいては「リバタリアニズム(libertarianism)」というかたちで、建国当初からつねにアメリカ社会に伏流していた。アメリカが世界に冠絶する覇権国家となり、その国の作法や価値観が「グローバル化」したことによって、アメリカ的な「リバタリアニズム」もまたグローバル化したということだと私は理解している。
「セルフメイドマン(self made man)」というのは建国以来のアメリカ市民の理想像だが、要するに誰にも頼らず独立独行で自己実現を遂げる生き方のことである。「リバタリアン(libertarian)」は、その過激化したかたちである。
リバタリアンは、人間は自分の運命の完全な支配者であるべきであり、他者であれ公共機関であれ、いかなるものも自分の運命に介入する権利はないと考える。だから、リバタリアンは政府による徴税にも、徴兵制にも反対する。当然ながら、社会福祉のための原資の提供にも反対する。
ドナルド・トランプが徴税と社会福祉制度につよい嫌悪感を示すのは、彼がリバタリアンの伝統に連なっていることを示している。
トランプは選挙期間中に対立候補から連邦税を納めていないことを指摘されて、「すべてのアメリカ人は納税額を最小化するために日々知恵を絞っている。私が連邦税を払っていないのは私が賢いからである」と述べて支持者の喝采を浴びた。これは別に露悪的な発言をしたわけではなく、ほんとうにそう思っているからそう言ったのである。彼に喝采を送ったプア・ホワイトたちは、自分たちとは桁が違う大富豪であるトランプの「納税したくない」というリバタリアン気質が「自分と同じだ」と思って、その発言に賛意を評したのである。
トランプは軍務の経験も、行政の経験もないはじめての大統領だが、それは軍務に就くことも、公共機関で働くことも、どちらもリバタリアンとしては「やらないにこしたことはない」仕事だからである。アメリカの有権者たちは彼の「公的権力を用いて私利私欲を満たすが、公益のためには何もしない」という態度がたいそう気に入ったのである。
今の日本で起きている「弱者叩き」はアメリカ原産のリバタリアニズムが日本に漂着し、日本独特の陰湿なしかたで退廃したものだと私は理解している。トランプのリバタリアニズムはこう言ってよければ「あっけらかん」としている。ロシアとの内通疑惑が暴かれたことによって、彼が「愛国者」であるかどうかについてはアメリカ人の多くが疑問を抱いているだろう。けれども、リバタリアンにおいて、愛国者であることは実は「アメリカ人的であること」のための必要条件ではない(国家や政府などというものは「ない方がいい」というのが正統的なリバタリアンの立場だからである)。
けれども、日本では公的立場にある人間は「国よりも自分が大事」というようなことを(心で思っていても)口には出さない。仮に、安倍晋三が所得税を払っていなかったことが発覚したとしても、彼は「私は賢いから税金を払わずに済ませた」という言い訳をしないだろうし、その言い訳に喝采を送る有権者も日本にはいないはずである。
日本ではリバタリアンも愛国的なポーズをすることを強いられる。
だから、日本では「リバタリアンでありながら、かつ愛国的」という奇妙な生き物が生まれてくる。現代日本に跋扈しているのは、この「愛国的リバタリアン」という(「肉好きのベジタリアン」とか「気前のいい吝嗇漢」というような)形容矛盾的存在である。
一方において、彼らは自分が獲得したものはすべて「自己努力によって獲得されたもの」だから、100%自分の所有に属し、誰とも分かち合う気がないと断言する。同じ理屈で、貧困や疾病や障害や不運などによって社会的弱者になった者たちについても「すべて自己責任で失ったもの」であるので、そのための支援を公的機関に求めるのは筋違いであると主張する。
ここまではリバタリアン的主張であるが、日本の「愛国的リバタリアン」はこれに愛国主義(というより排外主義、外国人嫌い)をぱらぱらとまぶして、社会的弱者というのは実は「外国人」であるという奇妙な社会理論を創り出す。ここに日本のリバタリアニズムの独特の歪みがある。
日本型リバタリアンによると、社会的弱者やあるいは社会的弱者を支援する人たちは「外国人」なのである。仮に血統的には日本人であったにせよ、外国渡来のイデオロギーや理説に「感染」したせいで、「外側は日本人だが、中身は外国人」になっているのである。だから、社会福祉や教育や医療などの活動に公的な支援を求める組織や運動は本質的には「日本の国益よりも、彼らが忠誠を誓っている外国の利益に奉仕するもの」なのだという妄説が出来上がる。生活保護の受給者は多くが在日コリアンであるとか、日教組の背後にはコミンテルンがいるとか、朝日新聞は反日であるとか、翁長沖縄県知事は中国に操られているといった類のネトウヨ的妄説はその典型的なものである。
語っている本人もさすがにほんとうだと思ってそう言っているわけではいないだろう。にもかかわらず、彼らが「反政府的な人間=外国人」というスキームに固執するのは、彼らにリバタリアンに徹底する覚悟がないからである。
リバタリアンであれば、話はすっきりしている。貧乏なのも、病気なのも、障害者であるのも、すべては自己責任である。だから、それについては他者からの同情や公的支援を当てにしてはならない。医療保険制度はいらない(医療は「サービス」なのだから金を出して買え。金がないやつは死ね)。公立学校も要らない(教育は「サービス」なのだから、金を出して買え。金がないやつは働いて学費を稼ぐか、有利子で借りろ)。社会福祉制度はいらない(他人の施しがないと生きていけないやつは死ね)と、ずいぶん非人情ではあるけれど、バケツの底が抜けたように「あっけらかん」としている。
しかし、さすがに日本では(心ではそう思っていても)そこまでは言い切れない(居酒屋のカウンターで酔余の勢いで口走ることはあるだろうが、公的な立場ではなかなか口にはされない)。
その不徹底をとりつくろうために、日本的リバタリアンは「排外主義」的イデオロギーを装飾的に身にまとう。そして、貧乏人も、病人も、障害者も、生活保護受給者も、みな本質的には「外国人」であるという摩訶不思議な理説を噛ませることで、話のつじつまを合わせようとするのである。
相模原事件の植松容疑者はその意味では障害者支援をめぐる問題の本質をよく見抜いていたというべきだろうと思う。彼自身は生活保護の受給者であったが、その事実は「わずかな賃金を得るために、他人に顎で使われて、自分の貴重な人生を空費したくない」という彼のリバタリアン的な気質と齟齬するものではなかった。けれども、自分以外の生活保護受給者や障害者は彼の目には許し難い社会的寄生者に見えた。この矛盾を彼はどう解決したのだろうか。自分には公的支援を受けることを許すが、他人には許さないという身勝手な識別を可能にする境界線として最終的に彼が思いついたのは「私は日本人として日本の国益を優先的に配慮しているが、彼らはしていない」という「日本人/非日本人」スキームであった。
だから、植松容疑者がこれは「日本のために」したのだとか、「社会が賛同するはずだった」とかいう自己弁明を繰り返し、「国益を害するものたち」を「処分」する「官許」を首相や衆院議長に申請したことには論理的には必然性があったのである。
彼は自分が「愛国的リバタリアン」という政治的奇形物であり、現在の日本の政界の指導者たちの多くが程度の差はあれ自分の「同類」だと直感していたのである。
津島さんの憂いをはるかに越えて、早晩、日本のみならず、世界が、言葉による暴力にとどまらず、排外主義的な肉体的暴力へいっそう突き進む時を迎えているような思いがしてなりません。