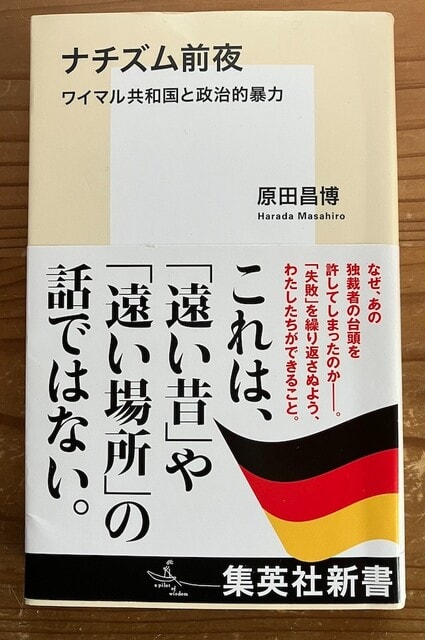行政裁判を経験した時に違和感を覚えたことがあった
(裁判は経験しないで済ませられるなら、それが一番いい)
「あれっ、もう終わり?」
「裁判官という人々は専門的な知識があるとはいえ
普通の人が感じるように感じるのだろうか?」
行政裁判はテレビドラマのような証人が出て丁々発止で行われる
ものではなく、準備書面という原告・被告の言い分を書いたもので戦われる
相手側の言い分に対する反論は2ヶ月ほどかけて裁判所に提出されるので
裁判の進行はとてものんびりしている
行政裁判は2回経験したが、最初のものはゆっくり進んでいった
しかし、2回目の養鶏場のそれはあっけないほど早く終わりとなった
「まだ肝心な購入価格が高い安いの話が十分に戦われていないのに、、」
自分が覚えているのはそういう気持ちだった
「手続きの不自然さの指摘が終わって、さあ、問題の価格について、、」
と意気がったが、手続き論だけで判断がくだされそうになった
そしてその結果は「手続きに瑕疵はない」
外形的事実といわれる言葉がある
兵庫県の優勝パレードの問題では、金融機関に補助金を出すとした時期と
実際に金融機関がパレードにお金を出したタイミングが隣接して
しかも副知事が絡んでいるので、疑われても仕方ない(外形的事実があるということ)
と橋本徹氏も公言していたし、第三者委員会でもその旨が書かれている
このように普通の感覚ならそうだよな!
と思われることは自分たちの場合もあった
肝心な価格について、心理学にはアンカリング効果と言われる考え方で
価格決定に影響を与えると思われる行為が行政によってなされたのだが
裁判官はそれを奇妙だとは認識しなかった
(試しに数人に裁判の結果を知らせずに、行政の行為をどう思うか聞いてみると
勘の良い人はその行為に「ええっ、なんで」と反応した)
同じものを見ても(聞いても)おかしいと思う人と思わない人がいる
白黒結論を決める人は、本当に正しい判断ができるのだろうか?
それが、ずっと頭に残っていた
そして公には結果が出たが、こころはスッキリしないでいた
そのせいか「絶望の裁判所」を目にした時、直ぐにアマゾン購入することにした
裁判絡みでは昨年に「裁判官の良心とは何か」竹内浩史の本を読んだ
竹内氏の本の中に「ヒラメ」という言葉で裁判官の出世主義を
紹介した部分があったが、どうもそれは竹内氏の独断ではなく
その空気は「絶望の裁判所」にも書かれていた
そしてこの本で頷いてしまったのは
裁判は素早く処理するもの、それが評価につながると書かれた部分で
「だからあの時もそうだったのか!」
とついわかった気になってしまった
裁判官という職業の人達の実態は部外者にはわからない
頭が良くて、正義感に燃えて、何事も公平に応じる
そうした人たちと思われるが、中にいる人達(竹内氏、瀬木氏)は
必ずしもそうでは無いとされている
瀬木氏は、失策をしない、手際良く片付けるなどの評価基準の検討
民間の常識的な判断力を活かすためにの裁判官任用のシステムなどを
提案している
ざっと読んだだけだが、ちょいと変わった人かもしれない
と思えないことも無いが、その指摘は的を得ている気もする
(キャリアシステムの変更や事務総局の解体など)
人間社会というのは、欠点のある人間同士がどこか折り合いをつけて成り立っている
できる限る妥当な落とし所を、理性と感情で求める様になっていると思っていた
でも実態は、必ずしもそうではなさそうな雰囲気だ
結局のところ、いろんなことは無条件(無関心)にスルーすることは良くない
ということかもしれない
気がついた人が声を上げたり行動したりする
それがあって初めて少しは良くなるのかもしれない
(悪いことが少なくなるのかもしれない)