「選挙はまちづくり」という本があるが、一番知られているのは
おそらく新城市だろう
日本の地方自治体のなかで新城市が一番最初に「市長立候補者による公開討論会」
を条例で定めたが、その経緯とか意味合いを本にしたもので
幸か不幸か自分も少しだけ関係している部分がある
自分はこの条例自体に肯定的には捉えることができなかった
それは4年に一度、直前になって公開討論会をすることで
まちづくりが可能になるとは到底思えなかったからだ
まちづくりは「我が事のように考える」習慣が市民の間に根付いて
その問題点を実際に話し合う機会だとか
意見を表現できる機会を確保することが大事だと思っていた
そして、それはおそらく教育の分野の充実が不可欠だと思っていた
安倍さんの事件以来、選挙は民主主義の根幹をなすだとか
民主主義の実践の機会であると表現されているが
現実的な話、一度でも選挙の現場を経験すると
それらの言葉は世間知らずの能書きに過ぎないと思えてくる
落ちればただの人になってしまう選挙は、勝つことが至上命題になっている
そして勝つための手段は、意識高い系の人が取り上げる政策ではなく
むしろ、選挙のプロが指導するようなテクニックなり知識(経験則)が必要となる
先ずは団体票・組織票が喉から手が出るほど欲しいと思う
その焦りから今大騒ぎになっている統一教会の協力を期待してしまう気持ちは
選挙の当事者なら無理からぬ話だ
勝たなければ意味をなさない立場の人たちは
応援してくれた人々の利益を代弁しなければならない
応援する人々の立場はいろいろあるので
最終的には無条件に応援してくれた人々の代弁だけができるわけではなく
様々な意見の中で多数決による決断をすることになる
世の中にある多数の意見の戦いが、危うい大衆意見の暴走を防いでいる
と、ものの本には書かれているが、現実はそのような理想的な姿は見られない
現実は無関心層の存在と少数者の支配によっていろんな物事が決められていく
それは国でも地方自治体でもそうだ
物事を決めるのは多数決で、日本ではそれが民主主義とされているようで
数学的には多数決は一人の判断よりは間違いの少ない可能性がある
と説明できるらしいが、実はこの論法には大前提があって
採決する人がその問題に対して偏見なく向かうことが要求されるのだ
だがそんなことは現実的に不可能だ
裁判官のようにどの意見や主張が適切か?などと立ち向かうことはない
予め党なり利益団体の意向が採決の判断に強く影響する
つまりは戦国時代の場所取り合戦みたいなのが、現実社会で
のんびりと「選挙はまちづくり」などとは言っていられない
ならば代わりにどういう良い方法があるのか?
となるのだが、残念ながら全くわからない
結局は一人ひとりが少しでも賢くなるしか手はない気もする
その賢くなる人(あるいは意識高い系の人)の全体における
パーセンテージは12.5%だったか17.5%だったか忘れたが
その閾値を超えると大きく変わると何かで読んだ気がする
12.5%の人々の心に響くようにするには、単なる一市民としては
何をすべきなんだろう
とても不思議なことが起きている
別に不思議でもなんでもないと思っている人は数多くいるだろうが
疑いだすと連鎖的にいろんな疑いがでてくるのは人の世の常だ
安倍さんの事件から再び火がついたように見える旧統一協会の件
テレビ局は一時期、ある宗教団体と名称をぼかしたり
深く突っ込まなかったりしていた
だが、流石にスルーするのはできないらしく、嫌々ながら扱い始めた
ところが、それかパタッとこの件について報道しなくなった
それは前日まで鋭い追及をしていたテレビ局だけに変わり様は違和感を感じるものだ
(テレビ朝日)
現在のところ、しつこく追求しているのは日テレ系の「ミヤネ屋」とTBSの「ニュース23」らしい
他にもBSの「報道1930」があるらしいが、昼の時間だったり、遅い時間だったり
BS放送なのでみんなが見られる時間ではなさそうだ
テレビ局は民放で視聴率が上がらないとスポンサーにとって番組の存在意義が無くなるが
そうした経済的な面だけでなく民放には報道機関としての存在意義もあるはずだ
民主主義がうまく回っていく前提として、国民が正確な情報を知らされていることがある
それが現実世界でなされているのだろうか
このような実態を見ると甚だ不安を感じざるを得ない
そこで、先の戦争時のメディアはどうだったのだろうと
最近読み直しているのが「戦争と新聞」だ
「なぜあの時戦争反対といえなかったのか?」
知り合いの女性は親たちに向かってそう問いただした事があったそうだ
「そんな雰囲気ではなかった」
答えはこれだった
その時の世の中に蔓延していたのはそういう空気だったのだろう
この本を読んでいても次第に空気に飲み込まれていく感じがわかる
問題は、このときと今は似ていないか?という点だ
知らず識らず大衆の気持ちがある方向に流されていく
それは正確な情報を得られないためだが
そんなことは今の時代にあるはずない!
と言い切れるか!が大いに疑問だ
田舎にいても自分は現在のテレビメディアの異様さを実感する
確かに大衆の多くが意識高く持つことは不可能だが
それでも、あまりにもその時の空気に流されやすい人が多すぎるのは問題だ
時々、テレビ局は自滅していると思うことがある
こうした報道についての姿勢もその現れだが、
タレントを使った番組も粗製乱造の域を出ないものばかり
嫌なら見なければいい!
で済まされるような状態ではないと思えて、不安が募る
サッカーはよく点の入るスポーツではない
だから、点を取る選手は才能としか言えない面もある
一芸に秀でた人間はどこか変なところがあるのは、皆がうすうす感じているのではないか
あのミスターと言われる人も、屈託ないがどちらかといえば変わってる人だ
日本社会でストライカーを育てるのは規格外の行動をしがちな人を
大目に見る環境も必要な気がする
昨日は得点力不足の日本が昨日の東アジア選手権で、ライバル韓国に3−0で快勝した
いつもの韓国らしくなく、闘志を前面に出すこともなく奇妙な試合だった
勝敗よりもワールドカップの登録メンバーに入るチャンスをつかむか
どうかがモチベーションになっている選手もいたようだ
日本のスタメンは海外組ではなくJリーグの選手なので、
いつも見ているグランパス以外は知らない選手が多い
その中で印象に残ったのは、西村、藤田、町野、それにグランパスの相馬くらい
町野も西村もシュートが上手いという印象
少し驚いたのは20歳の藤田
香港戦で中継役とか守り運動量で目についたが、昨日は攻撃の際の
スペースがないところでのプレーの落ち着きとかボールを奪われないところに
目を引かれた
一点目の相馬へのアシストは藤田で柔らかいいいボールだった
ワールドカップにはもう時間がないので、
今から大きく登録選手が変わることはないだろ
だが藤田は経験させたいな、、と思う
直に世界のトップレベルの選手と相対する経験は
まだ時間がたっぷりある彼にはきっと有益だと思う
ということで、直近の三試合での個人的な収穫は
藤田という選手の存在を知ったこと
毎晩、7時45分になると防災無線で新型コロナの感染者数が伝えられる
第7波の真っ只中、田舎のこの町でもこの放送は途切れることがない
最近の数字の経過はこんなだ
気分的に慣れっこになっていたが、流石に昨日の81名には驚きを覚える
予定されていた議会報告会も延期となった
少し前に購入したコンサートのチケットも、またもや無駄になりそうな気配
4回目のワクチン接種は多分8月に案内状が届くだろう
自分と家族は大したことはなかったが、妹は3回目はひどい目にあって
熱は出るは、食べ物は戻すはで、次はうちたくないと言っている
仕方ない、できることをするしかない
基本的に横着者だから巣ごもりでもさほどストレスは感じない
(でも、外出するとやはり外の空気は大切だとは感じるが)
それにしても、コロナ、長雨、ウクライナのこと
良いことが無さすぎる
ドイツ人はサッカーの練習を始めると、シュートばかりするという話を聞いたことがある
オランダ人はパスの練習ばかりで、国民性の違いはこのように現れるという
本当か嘘かわかないが、おもしろい話だ
日本人はどうだろう
先日Youtubeで静岡の高校のサッカー部の練習を見た
さすがに静岡の有名校だけに、一人ひとりのボール扱いがうまい
体幹を鍛えるような準備もあって、選手一人一人が丁寧に育てられている
練習の仕上げはミニゲームとなるが、それらはパスのタイミングとかコース取りとか
パスコースの限定とかを瞬時に行うおさらいをしているわけだが
不意に、シュート練習をしていないことに気がついた
日本の高校とかユースチームはどのくらいシュート練習をしているのか
と、少しばかり気になった
いつも日本人のゲームではゴールの上を通過するシュートが多いし
打てば良いところをパスの選択をしたりしている
そしてキーパーと一対一になったときでもやたらと慌てて
自分のタイミングでシュートできていないシーンが頭に浮かぶ
(それらはシュート練習が少なすぎるためではないかと思ってしまった)
ちょっと前の東アジア選手権で中国と対戦した日本チームは
このシュート力の欠如を実感した
確かに守り主体で試合に臨んだ中国に対抗するのは難しいのはわかる
おまけに選手同士は初めて一緒にするようなメンバーで
パスも少しづつずれて、円滑なパスワークができていなかったのも事実だが
これが韓国だったらどうだったろうと考えると
韓国は前の試合で中国に3点奪っている
つまりは、急造チームの韓国は3点とったが、日本のチームは取れなかったということだ
これから連想するのは日本代表がブラジルと戦った試合で
日本はPKでの失点1に抑えて、善戦したかのような数字に見える
日本の前に戦った韓国はブラジルに5失点しているが、1得点している
(日本チームは得点の可能性を感じなかった)
この差は国民性の違い以上に大きいのではないかと思えて仕方ない
ロシア・ワールドカップで韓国はドイツにに2得点して勝っている
ところが日本のチームは、ドイツ戦では失点するイメージは
あまり浮かばないとしても、得点シーンも浮かばない
結局のところ、サッカーは相手よりたくさん点をとったほうが勝ち
という考え方と、失点しなければ負けない
とする考え方の選択の違いのような気もする
(練習時間のかけ方もこれで決まる)
日本人のメンタリティは、野球の野村監督が好きそうな
後者をなんの違和感も持たずに選んでしまいそうな気がする
日本人にストライカーが誕生するのは、残念ながら本当に難しそうだ
新城市の小中学校の給食室の老化は、なぜ放ったらかしになっていたのか?
を疑問に思ったことがあって、いろんな人に尋ねてみたが
それらの結果より、実感として「これだ!」と思えるようになったものがある
田舎に住んでいると、地域の役目は順番にやってくる
区長さんや地区総代とか生活環境委員とか
一生のうち一回はやらなければならないことが回ってくる
今年度その中の一つが自分に回ってきた
10年ほど前に大きな役わりを終えているので、今度が最後のお役目になりそうだが
その役割というのは、地区のお祭り関係の仕切りだ(単なる連絡係ぽいが)
お祭りといってもみんなが知っていて、盛大に行われるというよりは
昔からの人は知っているが、新しくこの地区に来た人は全く知らないよう祭りで
祭り当日に現地に来る人も僅かだ
その祭りの会場の稲荷さまの本堂は随分昔に建てられており
現在は屋根に木が生えて、雨漏りはするは建物は傾き
出入り口や引き戸の開け締めは相当な力を要する
特に雨漏りは悲惨で、よく降ったあとに出かけると
ビニールシートを敷いた床にはしっかり雨が溜まっている
ビニールシートは雨漏り対策の一つだが、
とにかくどうしようもないほどの状況なのは明らかだ
とりあえず、雨の翌日はビニールシートに溜まった水をかき出しに出かけて
締め切った本堂の空気の入れ替えをしている
だが、実感としてそれらは対処療法に過ぎず、
もう根本から考えねばならない時期にきていると思われる
根本からというのは本堂を改修するのか、解体するのかという問題で
本堂はこのまま放ったらかしにしておいても自分の年は何とか
前年並みにできるかもしれないが、次の年、また次の年にこの役目を担った人は
頭を痛めるだろうことは容易に想像がつく
こうした雨漏り等の問題に、なぜ今まで具体的な対策がされていなかったか?
というのが、今回関連して気づいたことの一つで
たとえ問題が目の前にあったとしても、わずかばかりの(自分の)任期の間に
面倒くさい判断や作業をするのは避けたいと思うのは人に常ではないか
ということだ
とりあえず、任期期間のうちは前年と同じようにできそうと思った担当者は
問題を保留にして、とにかくその年だけをやり終える
給食室の老化を感じている担当者は、真面目に考えればなにか手を打たないと
問題はクリアしないことは分かっている
だが、そのための予算とか手続きとか、、、、諸々の面倒なことは
自分の任期期間に行いたくはない
そんな風に思うのは、その人が横着というより
普通の人間がつい思っていまいそうなことだ
稲荷様の本堂の老化を問題にしなかったのも
給食室の老化に手を付けなかったのも
どうやら夏休みの宿題を最後の最後まで残しておくことが多い
人間ゆえの、どうしようもない傾向のような気もする
人間は真面目な人ばかりがいると円滑に回っていきそうだが
どういう訳か、ある一定数はそうでない人が存在する
何年か前に出版された「働かないアリには理由がある」
という変なタイトルの本があったが
みんながみんな同時期に真面目に行動を起こすことは
実は持続可能な種族保存にはふさわしくない
と言ったような内容だったと記憶している
世の中はこうして気づいた人が貧乏くじをひいて
何かを進めていくしか手はないのかもしれない
今日は土用の丑の日
我が家でも午後に鰻をスーパーに買いに行く予定
子供の頃、なんで土曜の丑の日なんだろう?
火曜の丑の日ってのはないのかな?
と思ったものだった(子どもはそんなものだ)
今日は久しぶりに朝から晴れ
雨漏りする近くのお稲荷さんの本堂の扉を開けて
空気の入れ替えに出かけた
鬱蒼と木が茂って、湿り気の多い場所となっているが
セミがしっかり鳴いている
不意にセミの思い出が浮かんだ
子供の頃、親戚の家を訪ねると急にみんなで佐久間ダムに行くことになった
我が家と、親戚二軒のメンバーだったと思う
覚えているのは急に決まったということと
佐久間ダムへ行く(帰り)途中の坂道でセミが狂うほど鳴いていたということ
なぜだか坂道の風景まで覚えているような気がする
(妹とだらだら文句言いながら歩いている光景が浮かぶ)
もう一つ、蝉しぐれという言い方にふさわしいほど鳴いていた場所を思い出した
まだ腰がさほど悪くならず、山に行けた頃
白馬岳の登山口猿倉に向かうバスに圧倒的な音量で聞こえてきたのがセミの鳴き声だった
どれだけの間生きられるか知らないが、その必死さは健気でどこか悲しいような気もした
高校時代の国語のとき芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声」のことも覚えている
「静かさや」と「山寺や」、「しみ入る」と「しみつく(?)」とした場合の比較をあげて
出来上がったもののほうが数段良いことを紹介していた
セミは夏の風物詩だ
うるさいがそれがないと寂しい
かつて「セミと風鈴」というタイトルでメルヘンなるものを作った
風鈴は人に心地よさを感じさせる良い音でも、風がないと音を出すことができない
だが、セミは自分で音を出すことができる
自分でなにかするということの意味を、「かもめのジョナサン」風にまとめたものだが
これなども、自分のある時期にしかできないものだったかもしれない
ということで、久しぶりの晴れは直ぐに暑くなりそうだが
ダラダラの雨模様よりはずっと良いかも
ちなみに以前作ったメルヘンは→セミと風鈴
夏に最適、お気楽な本だが、思いのほか興味深い「解剖図鑑シリーズ」
百人一首に続いて手にしたのが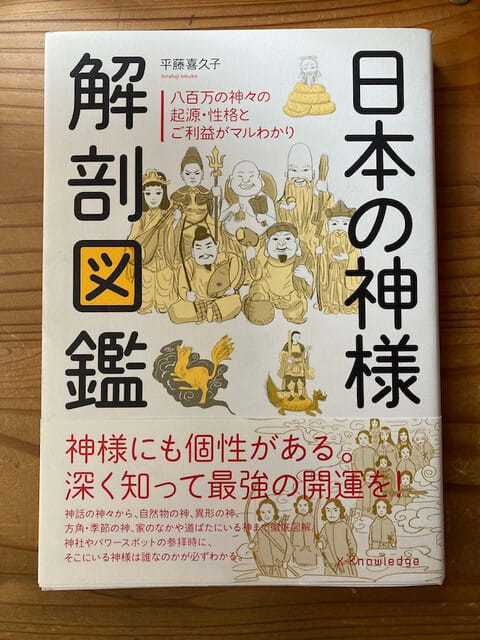
早速、そうなのか!とうなずくところに出くわした
それは京都の祇園祭に関することで、この祭りは疫病退散を願って行われたのだが
そもそも八坂神社の御祭神は牛頭天王(ごずてんのう)で、この牛頭天王は仏教では
ブッダが生まれた祇園精舎で疫病から守る役目を担ったメンバーだそうだ
決して思いつきで疫病退散ではなく、その役目を担った神様のお祭りだそうだ
牛頭天王は日本特有の曖昧な神と仏の関係から、別名素戔嗚尊となっている
以前、八坂神社の御祭神がなぜ素戔嗚尊なのか?
と思ったが、これでなんとなく分かった気がした
そもそも京都のあの地区の名前が「祇園」という意味も分かった気がした
この気楽な本とは別に、同時進行でちょいと真面目な本にも挑戦中
最近の本ではなくて1900年代の本で、想像したより古い本だった
だがまだ最初の部分だが、示唆に富んでいる
この本ではギュスターヴ・ル・ボンの「群集心理」との意見の相違も
それとなく書かれていて(群衆と公衆の違いなど)、
現在とはメディアの背景が違うが、最後まで読み終えることができそうな印象
最後まで行けないのが
何度か挑戦していても、いつも途中でやめてしまう
有名な「一般意志」が出てくる本だが、
ジョン・ロックの「リヴァイアサン」と同様に
こねくり回した理屈についていけないかもしれない
でも古典は一度は体験すべきだとは思う
ということで、これらの本は明るい昼の内に
畳に寝転びながら読むことになるが
いつも驚くのは、その寝転がっていた畳の部分が随分温かいこと
体温が畳に残っているだけでなく、背中の汗もそこに残って少し湿っぽい
蝉の声も少し前から聞こえている
小学生の夏休みも始まった
エアコンをつけなくても、畳の部屋には風が入ってくる
入ってくる風が熱くなるまでは、節約ができそうだが、これはまずいかな?
二三日前は衝撃的な統一教会の報道が、いろんなテレビ局で放送されていた
ところが、急に統一教会絡みの報道が少なくなった
新聞のテレビ番組欄は少ししかない
代わりに出てきたのが羽生結弦のニュースで
それはタイムリーとか明るい話題だとしてもこの急激な変化は異様だ
それを異様と感じるかどうかは人それぞれだろうから
自分の感覚からすると変だということだが
今回の参議院選挙で落選した有田芳生氏がテレビ番組で
一瞬で固まるような衝撃的な(実は薄々分かっていた?)話をした
二十年ほど前のこと、ジャーナリストとして霊感商法等の統一教会絡みの
調査をしていた彼に、警察・公安関係の人がその当時の統一教会の実態の
レクチャーをしてくれと依頼があった
出席者は2.30人くらいで目つきが鋭い人が多かったそうだ
有田氏は「なぜレクチャーするような運びになったのか?」
と聞くと「オウムの次は統一教会に手を付ける」と話したそうだ
ところが、その後一向にその気配はなく20年ほど過ぎたころ
レクチャー依頼をした(?)人に偶然会うことがあって
「なぜ、あの時から動きはなかったのか?」
と聞いたそうだ
その答えは「政治の力だ」と答えたらしい
このテレビ番組はSNSの世界では驚きをもって拡散した
しかし、SNSと遠い世界にある人は、
世の中はいつもと何も変わることのない日の連続としてしか感じていない
安倍晋三氏が銃殺されたのは衝撃的で悲惨な事件だが
その背景と、自民党(政治)と統一教会の関係が、田舎にいる人間でも気になる
この襲撃の際「民主主義の根幹たる選挙」という言葉がよく使われた
だが、これには違和感があった
「選挙は民主主義の根幹だろうか?」という疑いだ
理想としての民主主義ではなくて実態(現実)として選挙は
およそ民主主義的な要素よりももっと別の力が大きく左右する
選挙は勝たねば意味がない
勝つための方法は残念ながら議論を重ねた上での政策論争ではない
選挙は勝負事で、その勝負事には戦いになれた人や応援する組織が必要だ
その応援する人というのは、主に利害関係者だ
つまりは選挙は田舎でも国政でも、利害関係者の力が大きく左右するというのが現実だ
そうした現実があるなかで、物事を決めるのは多数決となれば
結果的には少数者の利害関係者の力が政策に反映するということだ
利害関係者の活動は選挙だけでなく、ロビー活動というやや優しげな表現のものもある
統一教会は自分たちに問題があるとされていることを自覚していて
この問題を解決してくれるのは「〇〇党の△△さん」と投票を間近に控えたある会場で
絶叫している(この場面はテレビで紹介された)
これなどは悪しきWin-Winの関係で、だからこそ政治とこれらの宗教団体との関係を
深堀りする必要はあると思われるが、なぜか報道は一気にトーンダウンしている
放送免許を仕切る政府からの何らかの圧力か、それとも自発的な自粛か
戦前戦中では新聞紙法で肝心な紙の供給が政府によって仕切られ
その結果自由な報道はできなかったらしいが、ふとそれを思い出してしまった
現在の日本は民主主義国家とされているが、
実は少しづつ独裁国家に近づいているのではないかと思えてならない
問題なのはそう感じていない人がとても多いことだが、そう感じるのは間違いだ
とちゃんと説得してくれる人がいれば少しは安心できるのだが
とにかく、田舎にいても、、不安な時代の空気を感じる
気になっていることの発露、、まとまらない話
台風以後、戻り梅雨のような天気が続く
やる気の出ない雨の日は、晴耕雨読が良い
だが夏の日は集中力の必要な本を読むのは辛い
ということで、最近購入したのが「百人一首解剖図鑑」
この本が思いのほか楽しめた
高校時代に習った百人一首は残念ながら全部は覚えていない
最初のいくつかと、リズムのいいものだけ勢いで覚えているだけだ
この解剖シリーズは前に「源氏物語解剖図鑑」を手にしたが
よくまとまって参考になったので、今回も気楽に楽しめそうと求めた
和歌の意味とか文法的な要素が主体ではなく、むしろ作者の背景(地位とか人間関係)が
わかりやすく紹介されていて(すぐ忘れてしまうが)確かに生きていた人たちの
呼吸のようなものを感じることができる
歌は恋愛がらみが多いが、その気持ちは時代を超えて納得するところもある
平安時代の恋愛は、女性は部屋に籠もって顔を見せないでいる
何かのきっかけを掴んだとしても、まずは和歌を送らなければならない
これはまるで動物の求愛動作のようなものに思えてしまう
動物は本能的とか自然と備わっている体の変化で異性を引き寄せるが
人間は知恵を使ってその力量を発揮しなければならない
これなどは、知恵とか頭こそが生命力の証と見ているからのだろうか
女性も返事が必要だが、下手な人は代筆という手があるらしい
これなどは、いかにもありそうな話だ
女の家に泊まった男は朝には女の家から出なければならない
それにしても、この時代の人たちはよく泣く
袖が涙でいっぱいになるとか、枕が濡れるとか
今の感覚からすると、少しばかり女々しくて口にするのをためらいそうなことも
まるで自慢のように泣いている姿を描写する
泣くのがみっともないとなったのは、いつの時代からなのか?
と少しばかり興味が湧いてくる
歌は100あるけれど、自分が何となく覚えていそうなのはいくつあるだろう
口に出して言えそうなのは少しだけ、見ればなんとなく覚えているというのも少し
あとはさっぱりで、そんなのあったのかな、、というくらいだが
高校の授業ではないので、覚えていなくても平気だ
百人一首は、その時代の空気感とかをそれとなく感じることができる
一見実生活に役立たないような歌が、現実的に大きな力をもったという事実は
今の時代と比べると、もしかしたら昔のほうがまともな社会だったかもしれない
と思ってしまう
ということで、この解剖シリーズは楽しめそうなので
次は「日本の神様解剖図鑑」に挑戦しよう
夏はこのくらいの本が良いかも

















