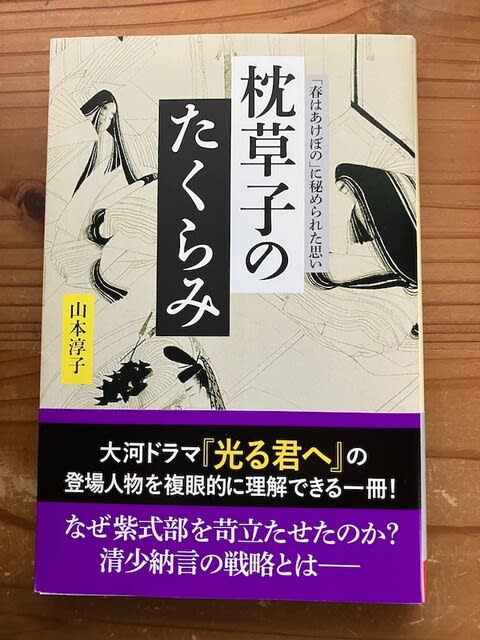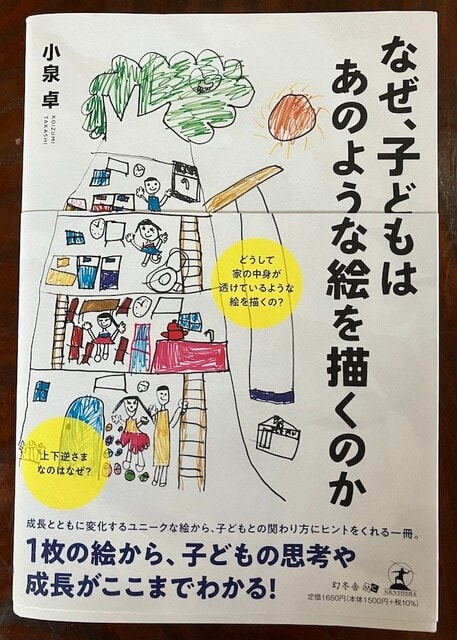何にでも逆張りをするタイプではないが、それでも何故なんだろうと思うことがある
共産党は何故そんなに嫌われるのだろう?
ほどんど無条件に否定されることの多い共産党、社会主義
でもそんなに嫌われるべきものなのか、、と少し不思議な気がする
マルクスが共産主義の元を作りあげたとしても
その考えに至るにはある程度の必然性とか時代性があったはず
そんな風に考えて、ちょいとマルクス絡みの本を読んでみた
手にしたのは分厚い「資本論」ではなく新書の「超訳資本論」(的場昭弘著)で一種の啓蒙書だ
実はこの本は以前にちょっとだけ読んだ
でも途中で投げ出したか、読み終えても全然覚えていないかのどちらかで
わずかに覚えているのはどんな商品にも「労働」という過程が含まれているという考察
その考え方はなかなか興味深いと感じた
労働力の言葉があるから、そこから搾取の概念が説明されるわけだが
すぐに理解できるほどの知識も素養もない
言えるのは、こうした考え方とか持って行き方はなかなか面白いということ
そしてこれだけ読んでいると、そんなに嫌われる理由はわからないな、、が実感
実は社会主義関係の本では全く想像外の内容だった物がある
レーニンの「帝国主義論」がそれで、単なる決済機関である銀行が
お金を十分に蓄えるようになると、移動が容易なお金はその特性を活かして
世界中に回って、それが支配的な状況をつくる可能性があるという論旨
これも考え方としてはなかなかおもしろい捉え方だ
ということで、何故そんなに嫌われるのかは、、よくわからないが現時点での思い
逆に大手企業の内部留保の過剰な蓄積とか格差の拡大は
もしかしたら資本主義に内在する問題点ではないのかと思ったりする
「資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか」
「資本主義の宿命」
これらを読むとその思いを強くする