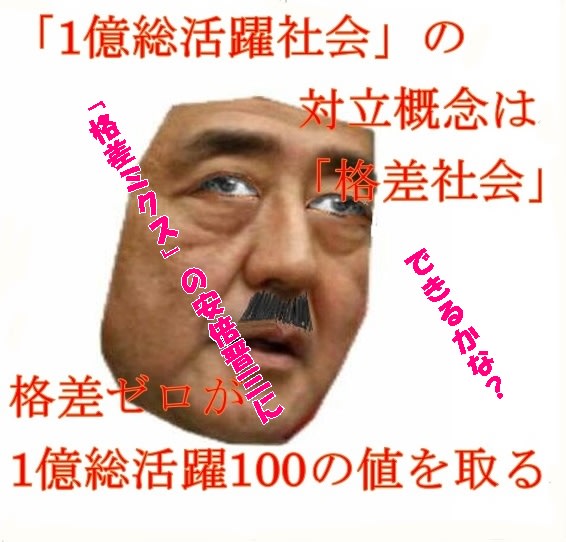 無所属の鈴木貴子衆院議員が2月18日の参議院予算委員会での横畠内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」との発言に関して核兵器の保有や使用についての政府見解を質す質問主意書を提出し、政府は4月1日の閣議で答弁書を決定した。
無所属の鈴木貴子衆院議員が2月18日の参議院予算委員会での横畠内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」との発言に関して核兵器の保有や使用についての政府見解を質す質問主意書を提出し、政府は4月1日の閣議で答弁書を決定した。
政府答弁書「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然である。
核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていない。現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしている」(NHK NEWS WEB/2016年4月1日 16時01分)
憲法のどこをどう読めば憲法9条が一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解釈できるのか皆目見当がつかないが、「必要最小限度」というキーワードをマジックに使っているから、そのように解釈可能とさせることができるのだろう。
横畠内閣法制局長官は2月18日の参議院予算委員会で次のように答弁している。
横畠裕介内閣法制局長官「憲法上、あらゆる核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない。(但し)核兵器に限らず、武器の使用には国内法、国際法上の制約がある」
白真勲議員「集団的自衛権行使の一環として日本が海外で核兵器を使用することは可能か」(解説体を会話体に直す)
横畠裕介内閣法制局長官「そうならないと思う。我が国を防衛するための必要最小限度を超える海外派兵は許されないという考え方は変わらない」(時事ドットコム)
要するに自衛隊の海外での核兵器使用は「必要最小限度」を超える武力の行使に当たるから、核兵器を使用することには「ならないと思う」と推測している。断定ではない。
2014年7月1日に安倍内閣が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定にしても、「必要最小限度」を集団的自衛権行使のキーワードとしている。
《自衛の措置としての武力の行使の新3要件》(2016年7月1日閣議 決定)
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
「必要最小限度」の武器使用であれば集団的自衛権であろう憲法には違反しないとする趣旨となっている。
日本国憲法は必要な自衛の措置としての個別的自衛権までは禁じていはいないが、集団的自衛権までは認めていないとする《1972年自衛権に関する政府見解》にしても、個別的自衛権は〈外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。〉としている。
つまり「必要最小限度」の武力行使にとどまる限り、日本国憲法は個別的自衛権を禁じていないとしている。
そして安倍政権は同じ「必要最小限度」という枠をはめて、集団的自衛権の行使容認に走った。
要するに「必要最小限度」をキーワードにして個別的自衛権を集団的自衛権にまで広げるマジックを見事成功させた。
と言うことは、今回の政府答弁書が「憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」と閣議決定している以上、横畠長官の国会答弁で既に明らかになっているのだが、「必要最小限度」をキーワードににすれば、非核三原則や、原子力基本法、NPT=核拡散防止条約等の政府政策や国内法、あるいは国際法上の制約を取り払って核兵器の保有や使用に向かうことも可能とすることができることになる。
だから、横畠長官は核兵器を使用することには「ならないと思う」と推測にとどめたのだろう。
推測ではなく断定した場合、核兵器を使用する状況に迫られたとき困ることになる。
核兵器の使用は保有を前提とする。
では、「必要最小限度」の武器使用とはどの程度の範囲としているのだろうか。
「必要最小限度」という言葉の意味自体は「必要とする最小の範囲」を言うが、「必要」という言葉は周囲に対応させる意味を含むから、相手の武力攻撃の規模・態様に対して武器使用の範囲を“最小”に限定するのではなく、対応させて変化させていくケースバイケースの可変性を構造とした、その範囲内の「必要最小限度」ということになる。
相手がライフル銃で攻撃してこれば、こちらはライフル銃かそれ以上の武器を必要とすることになる。相手が機関銃で攻撃してこれば、こちらは機関銃か、それ以上に威力のある武器を必要とすることになる。
いわば相手が行使する武力の規模・態様に対応させてより優位な地位の確保に動くことになる。
ここで注意しなければならないことは、敵勢力の武力行使の縮小に合わせてこちらも段階的に縮小していく逆の構造の「必要最小限度」は敵勢力が降伏か撤退しない限り存在しないということである。
相手の使用武器の縮小に合わせてこちらも縮小した場合、相手が突然使用武器を元に戻した場合、素早い対応で応えることができなければ、混乱を招くことになる。常に相手の勢力に対して優位な地位を取ることが得策となる。相手も優位性の確保に動くだろうから、双方共に使用武器や兵力を相互にエスカレートしていく。
最終的には国力・経済力の戦いとなる。
「必要最小限度」が相手の武力攻撃の規模・態様に対応させて変化を余儀なくされるケースバイケースの可変性を構造としていることは今夏参院選で自民党の推薦を受けて神奈川選挙区から立候補予定の元みんなの党、現在無所属の中西健治(52)が2015年6月9日、質問主意書で政府が言う「必要最小限度」は国際法上の範囲・内容を指すのか問い質したのに対する2015年6月16日閣議決定の政府答弁書が明らかにしている。
〈お尋ねの「我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために、個別的自衛権を行使する場合」「必要最小限度」とは、武力の行使の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたものでなければならないことを内容とする国際法上の用語でいう均衡性に対応するものであるが、これと必ずしも「同一の範囲・内容」となるものではない。
新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」については、その国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合であれ、個別的自衛権となる場合であれ、お尋ねの「必要最小限度の実力行使」の「範囲・内容」は、武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。〉(以上一部抜粋)
前半では、言っているところの「必要最小限度」とは国際法上の用語で言う相手の武力攻撃の態様と均衡性の取ることのできる規模を言うが、〈必ずしも「同一の範囲・内容」となるものではない。〉とし、後半では、個別的自衛権と集団的自衛権とを問わず敵勢力の「武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である」としている。
全体を通すと、国際法の取り決め通りに相手の武力攻撃の態様との均衡性を必ずしも取るわけではなく、相手の武力攻撃の規模、態様等に応じるから、その「範囲・内容」については「一概に述べることは困難である」との趣旨となる。
「必要最小限度」とは、いわば相手の武力攻撃の規模・態様等に対応させて決める武器使用の想定を構造としていることになる。
だから、「国際法上の用語でいう均衡性」に「必ずしも『同一の範囲・内容』となるものではない」し、相手の武力攻撃の規模・態様等に合わせるから、どの程度の範囲・内容となるかは「一概に述べることは困難である」ということになる。
これが「必要最小限度の実力行使」の実態である。
安倍政権は自衛隊の武器使用ばかりか、自衛隊の武力攻撃の規模・態様等に関しても、さらには自衛隊の行動規模・行動態様・行動範囲を決める安全保障政策に関しても、「必要最小限度」を主たるキーワードとして憲法解釈まで変更し、それぞれを拡大させていくマジックを物の見事に成功させた。
このマジックをいつ何時日本の核兵器の保有・使用にまで広げない保証はない。
安倍政権は既に「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」と政府答弁書を閣議決定しているのである。
小さなハンカチの中から鳩を出すマジックのように日本の核兵器の保有・使用の現実が飛び出さないとも限らない。
安倍政権のその危険性に気づかなければならない。