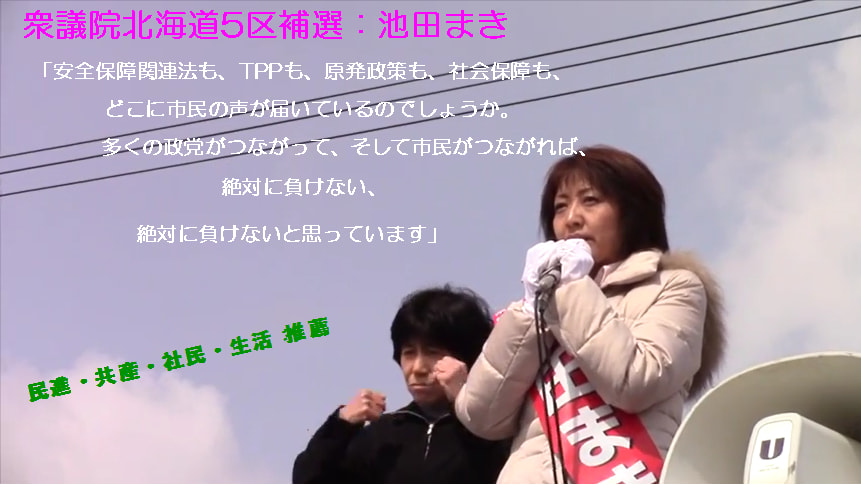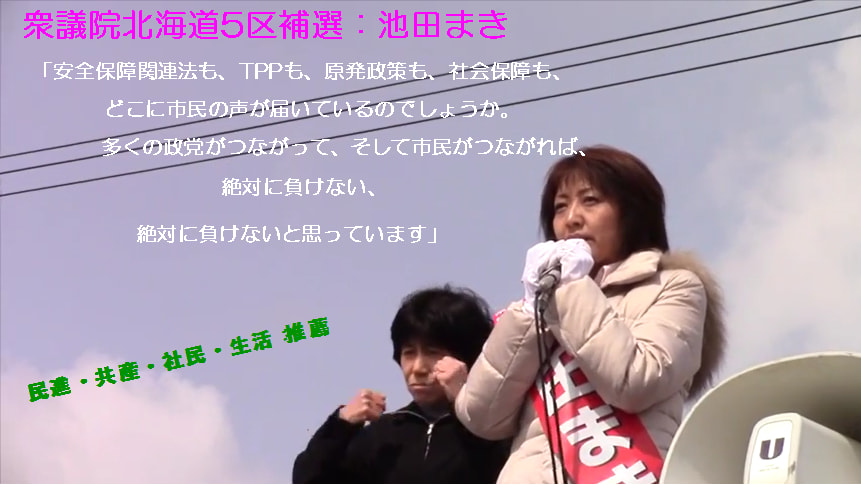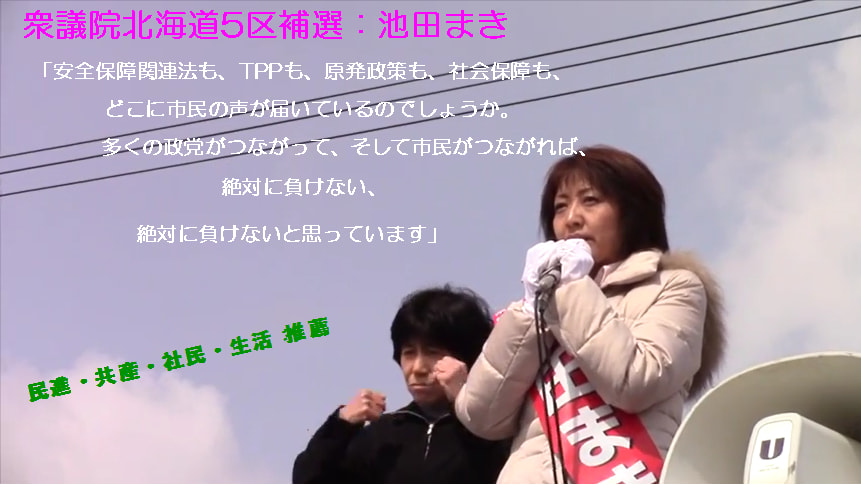4月14日21時26分頃の熊本地震発生から2日目以降からか、生活物資の不足を伝える報道が増えた。発災直後は人的・物的被害の広がりを伝えるのに手一杯で、物資不足まで伝える余裕がなかったということもあるかもしれない。
大災害時に於ける物資不足を我々は最近、と言っても5年前のことだが、東日本大震災で経験した。「水が足りない」、「食料が足りない」、「医薬品が足りない」
原因の一つは例え住民が大災害を予想して食料品や医薬品を備蓄していたとしても、その多くを津波が多くの人命と共に一瞬にして無にしてしまったからであろう。役に立てるべき備えを津波が荒々しく奪い去り、手の届かないものに変えてしまった。
商店の品々もその多くを津波が奪い、破壊してしまった。
原因の二つ目は道路が寸断されて輸送が滞り、支援物資を必要とする場所に迅速に届けることができなかった。
我々はこういったことを経験した。
今回の多くの家屋倒壊を招いた熊本地震にしても、災害に備えた食料品等の備蓄品、あるいは備蓄していなくても、冷蔵庫やその他の場所に買い備えていた食料品その他は家屋倒壊の場合は中に入って持ち出すことが不可能ゆえ、役に立たない点では津波に奪い去られるのと同じである。
例え半壊でも、中に入るのが危険な状態なら、役に立てることができない点で全壊と変わりはない。
結果、政府や自治体の支援物資の配布が遅れると、水不足や食糧不足が生じることになる。紙オムツがないとか、医薬品がないということが起きる。
但しこのような物資不足の発生は何も東日本大震災や今回の熊本地震だけに限ったことではない。現地時間2015年4月25日正午前マグニチュード7.8のネパール地震でもそうだったし、現地時間2010年1月12日午後5時前マグニチュード7.0のハイチ地震でも似た事態を招いていた。その他の災害でも同じであろう。
いわば何が不足し、何を必要とするようになるのかは災害という性質によって定番化させることになっている。それがないと生活上切実な問題を引き起こして早急に必要とする飲料水、食料、寒さ凌ぎの毛布、体調不良を起こしたり、怪我をしていた場合、あるいは持病があって常備薬を切らした場合の医薬品、持ち出すことができても、切らしてしまったオムツや生理用品等々。
参考までに東日本大震災時に新聞記事から抽出した定番化していた不足物資を「東日本大震災・緊急支援物資の流動実態の定量的把握」(平成23年度国土政策関係研究支援事業研究成果報告書)から挙げておく。
当然、国や自治体は規模の大きな災害が発生した時点で定番化している必需品の配布と充足に迅速に対応すべく行動しなければならないことになる。
被災を免れた近隣の自治体の災害に備えた食料品や医薬品、毛布等の備蓄品を災害発生後の早い時間内に災害地近くに輸送する。道路が寸断されている可能性を考慮して自衛隊のヘリコプターを準備させる。
今朝のNHKテレビのニュースでは熊本市では物資集積所に一度に大量に届いた支援物資を振り分けるボランティア等の人手不足や自治体自体がどこの避難所でどのような物資が必要なのか、各避難所のニーズの把握が追いついていないために満足に捌ききれていないといった趣旨の報道をしていたが、必要とする物資が定番化している以上、定番となっている物資をトラックに積んで先ずは各避難所に向かい、そこで必要とする物資と個数を聞いて降ろしていく。不足なら、次の便で不足分を届ける。余った物資は次の避難所に届ける。
道路が寸断されていたなら、自衛隊のヘリコプターを利用して先ずは隊員一人をロープで吊り降ろして、その隊員が避難所とヘリコプター間の意思疎通を無線機で仲介して必要とする物資を伝え、伝えた物資を地上の隊員の誘導で同じくロープで吊り降ろして、物資調達を果たす。
こういう方式にすれば、迅速に被災者のニーズに応じることができるはずだ。
必要物資が定番化しているにも関わらず、その種類と個数の把握に手間取って却って配達が遅れるのはバカげている。遅れる程、被災者の生活を難儀にする。
不足物資が定番化していることはマスコミの報道を見れば一目瞭然である。
〈熊本市内の多くの避難所では、食料や水などの物資が不足しています。〉(NHK NEWS WEB)
〈16日に同県益城町に入った福岡市のボランティアグループ「夢サークル」の吉水恵介代表(59)は、避難所で寒さをしのぐ毛布類や、プライバシーを守る仕切り、避難所を清潔に保つ消毒液などが足りていない、と指摘する。〉(asahi.com)
どれもが東日本大震災で被災者が経験した不足物である。海外の大災害でも報道された不足物であろう。
4月17日(2016年)、安倍晋三が「平成28年熊本地震被災者生活支援チーム」を立ち上げ、その第1回会合を首相官邸で開催した。
「被災者生活支援チーム」と銘打っているし、その挨拶からも先ずは被災者の基本的な衣食住の充足を図る組織ということなのだろう。充足のニーズとして食料や水、紙おむつ等の生活必需品、トイレ、医薬品や医療を挙げている。
全て災害時に被災者が不足に陥り、必要に迫られる定番化した品々であり、定番化したサービスである。
安倍晋三「この支援チームで緊密な連携をとりながら、政府一丸となって、先手先手で被災者の生活支援に対応してまいります。『現場主義』を徹底して、最前線で災害対応に当たっている被災市町村を支援するとともに、被災者のニーズを的確に把握して、迅速に対応することが重要です」
各避難所で既に生活必需品の不足状態が生じているのに「先手先手」の生活支援を言う。
殆どの避難所で何が不足し、何を必要とするのか、それらが定番化した現場となっていることを把握できずに被災者のニーズの的確な把握を先に持っていって、それを「現場主義」だと言う。
定番化に迅速に対応できていれば、極力抑えることができる食料不足であるはずだが、その報道が目立つようになってから、「今日中に70万食届ける」と決断実行を見せる。
要するに安倍晋三は大災害が発生した場合に被災者が避難してある一定の期間生活の場所とする“現場”を殆ど理解していない。
このような無理解の延長上に現れることとなった生活支援遅れであろう。