ちょっとショッキングなタイトルであるが、日本の死刑制度の是非を問う投げかけである。こうした問いに、これまで深く考えたことのなかった自分であるが、ちょっと真面目に考える機会を持った。
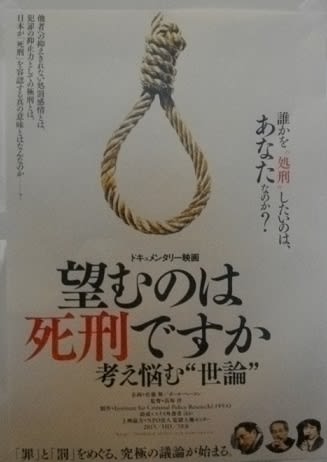
3月4日(金)夜、札幌弁護士会の主催による「死刑制度の是非を考える」市民集会が札幌弁護士会館で開かれ参加してみた。
市民集会では、まず死刑制度の是非について悩む市民の姿を描いたドキュメンタリー映画「「望むのは死刑ですか 考え悩む“世論”」を上映した。
映画は60分程度のものであったが、大学講師が主催した死刑制度に関する「審議型意識調査」の様子を記録したものだった。その内容は、市民が二日間にわたり刑事司法の専門家や犯罪被害者の遺族らの意見を聞き、死刑について議論する姿を追ったものである。
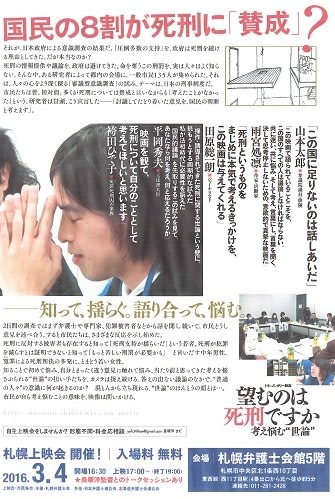
集められた市民135人の約8割の人たちは日本の死刑制度を支持する人たちだった。この数字は、政府による国民の意識調査と同じ傾向だそうだ。
2日間のワークショップに集まった市民の多くも、私同様に深く考えたことがなかった人が多かったようである。
そうした人たちがいろんな意見を聞き、参加者同士で話し合う中で、死刑制度の支持の考え方に揺らぎがみえはじめてきた人も出てきた。そんな様子をカメラは克明に追った。
ところが!二日間のワークショップを終え、参加者に再び同じ問いをしたところ、数字的に大きな差がなかったという。ただ、参加者たちはふだん何気なく考えきたこの問いに対して、深くに考える機会を持てたことには感謝した姿が多かった。
映画が終わり、この映画を制作した長塚洋監督、札幌弁護士会の死刑廃止検討委員の弁護士二人が登壇し、意見を交換した。
その中で映画を制作した長塚監督は、ワークショップを終えて数字的に大きな変化はなかったが、参加者たちの思いは確実に変わり始めていることを実感したと語った。
それはどういうことか、というと…。
犯罪被害者の遺族が死刑を望まないと語ったり、人(裁判官)が犯罪を裁くかぎりそこには誤判や冤罪の可能性が捨てきれないこと、また死刑と懲役刑ではあまりにも大きな差があることを専門家が語ったりする中で、その話を聞いた人たちの中に単純に死刑制度を支持してきたことに対する揺らぎがインタビューの中からうかがえたということだ。
ただ、僅か二日間だけでは、それまでの考えを簡単には覆すまでにはいたらなかったということなのだろう。

先にも述べたが、この問題に対する日本国民の意識は約8割が死刑制度を支持するという調査結果が出ているという。私もその多数派の一人だった。それはこれまで死刑を適用されるような犯罪者の犯罪はあまりにも非人間的であり、残虐な例が多く、因果応報というべきか、死をもって償うのが当然とも思ってきた。
しかし、アメリカの例では実に130人もの無実の人が死刑に処せられたという事実もあるという。それは日本でもけっして他人事ではないように思える。
死刑制度の廃止は世界の潮流だとも聞く。しかし、世論の8割が支持するとなると、今すぐに廃止とはいかないかもしれない。それでも長塚監督も主張していたように、少なくとも死刑判決が出た場合は、三回の裁判所(三審制度)の判断を仰ぐような慎重なうえにも、慎重な対応が望まれるということには私も同意できた。
う~ん。ちょっと重たい話題でしたね。
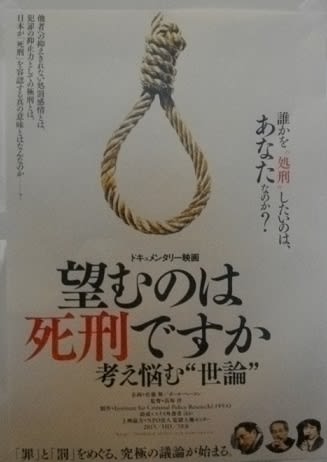
3月4日(金)夜、札幌弁護士会の主催による「死刑制度の是非を考える」市民集会が札幌弁護士会館で開かれ参加してみた。
市民集会では、まず死刑制度の是非について悩む市民の姿を描いたドキュメンタリー映画「「望むのは死刑ですか 考え悩む“世論”」を上映した。
映画は60分程度のものであったが、大学講師が主催した死刑制度に関する「審議型意識調査」の様子を記録したものだった。その内容は、市民が二日間にわたり刑事司法の専門家や犯罪被害者の遺族らの意見を聞き、死刑について議論する姿を追ったものである。
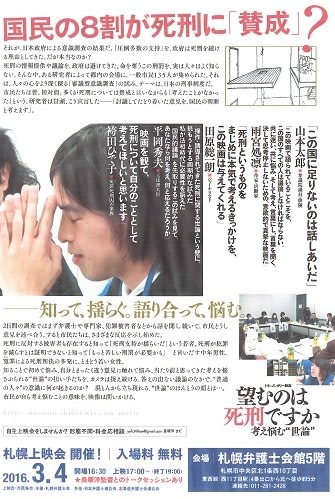
集められた市民135人の約8割の人たちは日本の死刑制度を支持する人たちだった。この数字は、政府による国民の意識調査と同じ傾向だそうだ。
2日間のワークショップに集まった市民の多くも、私同様に深く考えたことがなかった人が多かったようである。
そうした人たちがいろんな意見を聞き、参加者同士で話し合う中で、死刑制度の支持の考え方に揺らぎがみえはじめてきた人も出てきた。そんな様子をカメラは克明に追った。
ところが!二日間のワークショップを終え、参加者に再び同じ問いをしたところ、数字的に大きな差がなかったという。ただ、参加者たちはふだん何気なく考えきたこの問いに対して、深くに考える機会を持てたことには感謝した姿が多かった。
映画が終わり、この映画を制作した長塚洋監督、札幌弁護士会の死刑廃止検討委員の弁護士二人が登壇し、意見を交換した。
その中で映画を制作した長塚監督は、ワークショップを終えて数字的に大きな変化はなかったが、参加者たちの思いは確実に変わり始めていることを実感したと語った。
それはどういうことか、というと…。
犯罪被害者の遺族が死刑を望まないと語ったり、人(裁判官)が犯罪を裁くかぎりそこには誤判や冤罪の可能性が捨てきれないこと、また死刑と懲役刑ではあまりにも大きな差があることを専門家が語ったりする中で、その話を聞いた人たちの中に単純に死刑制度を支持してきたことに対する揺らぎがインタビューの中からうかがえたということだ。
ただ、僅か二日間だけでは、それまでの考えを簡単には覆すまでにはいたらなかったということなのだろう。

先にも述べたが、この問題に対する日本国民の意識は約8割が死刑制度を支持するという調査結果が出ているという。私もその多数派の一人だった。それはこれまで死刑を適用されるような犯罪者の犯罪はあまりにも非人間的であり、残虐な例が多く、因果応報というべきか、死をもって償うのが当然とも思ってきた。
しかし、アメリカの例では実に130人もの無実の人が死刑に処せられたという事実もあるという。それは日本でもけっして他人事ではないように思える。
死刑制度の廃止は世界の潮流だとも聞く。しかし、世論の8割が支持するとなると、今すぐに廃止とはいかないかもしれない。それでも長塚監督も主張していたように、少なくとも死刑判決が出た場合は、三回の裁判所(三審制度)の判断を仰ぐような慎重なうえにも、慎重な対応が望まれるということには私も同意できた。
う~ん。ちょっと重たい話題でしたね。









