自分には少し難解かな?という思いをもちながらも、敢えて受講することにした。予想どおり私にはやや難解だった。主催するCoSTEPが科学技術の専門家と市民の橋渡し役を養成する機関だとすれば、私はもっとレベルを低くして、私なりの解釈を、ブログを通して紹介し、私自身の感想を述べてみたい。
3月12日(土)午後、北大の CoSTEP(Communication in Science & Technology Education & Research Program)が主催する公開シンポジウム『「デュアルユース」と名のつくもの~科学技術の進展が抱える両義性を再考する~』が北大のフロンティ応用化学研究棟で開催されたので受講した。
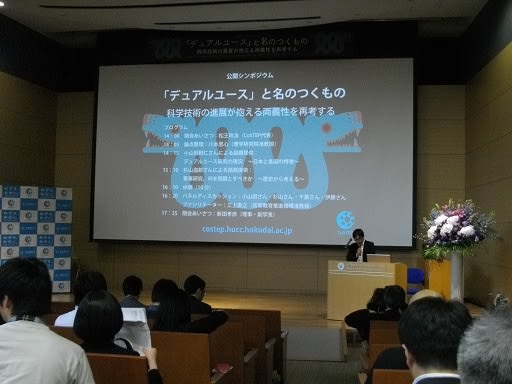
なぜ私がこのシンポジウムに参加しようと思ったかというと、デュアルユース(dual-use)という言葉に興味を抱いたからである。dual-useとは、字義的には「両用の」とか、「二通りの」と訳されるが、そこから科学技術の世界では「民生用と軍事用のどちらにも利用できること」を指す言葉だという。つまり、科学技術が進歩することは、私たちの生活を豊かにさせると同時に、軍事面で武器等の発達にも繋がることから、その問題をどう考えるか、ということがシンポジウムの趣旨であった。
こうしたことへの懸念は、アルフレッド・ノーベルがダイナマイトを発明したことが、大量の殺戮兵器を生んだことに繋がり、そのことが科学者の間では常に気懸かりな問題として論議されてきたようである。
ノーベル自身は、そのことを後年悔やみ、ノーベル賞の創設に繋がったことは有名な話である。
さて、シンポジウムは二人の方が話題提供という形で、この問題について論じた。
一人は、科学技術政策の専門家である小山田和仁氏が「デュアルユース研究の現況~日本と各国の特徴」題して、もう一人科学史研究家で北大名誉教授の杉山滋郎氏が「軍事研究、何を問題とすべきか~歴史から考える」と題して、それぞれ論じた。

※ 最初に話題提供として論じた小山田和仁氏です。

※ 続いて話題提供した杉山滋郎北大名誉教授です。
その後のパネルディスカッションでは、話題提供をしたお二人に加え、毎日新聞の科学部記者の千葉紀和と、北大大学院工学研究院教授の伊藤肇氏が登壇して意見を交換した。
話題提供、パネルディスカッションともに、それぞれの立場から、さまざまな考え方が提起されたが、それを的確に再現する力が私にはなく、発言者に迷惑がかかることも考え、ここでは私の総体的な感想を述べるにとどめたいと思う。
まず、小山田氏、杉山氏ともに、デュアルユースの問題については、研究開発のグローバル化が進展し、防衛・軍事の態様が変化している現状では、一様に研究者側にその責を問うのは難しい現状になっていると指摘されたと私は解釈した。
そうした中で、科学ジャーナリストである千葉氏は科学者には一定の責任があり、研究が軍事的に活用されるようになることに慎重になるべきではないかと、ジャーナリストらしく、現状への危機感を表明した。
ところが、科学の世界の一線で研究に従事している伊藤氏は、科学者は知的好奇心から研究を進めているものであり、その結果をどう利活用するかということについては、使う側の問題であり、科学者が自らの研究の結果の後、どのように利活用されたということについて責任を負う必要はない、的な発言をされた。

※ パネルディスカッションの様子です。
話は私がまとめたように単純なものではなかったのだが、概ね各氏の論旨についての間違いはないと思う。
日本の大学においては、大学法人化以降、研究予算が減少傾向にあるという。
そうした中で、防衛省が「安全保障技術研究推進制度」(耳で聞いただけなので正確でないかもしれない)を設けて、各大学での研究費を助成する制度を発足させたという。
喉から手が出るほど研究予算の増額を願う大学にとっては、魅力的とも映る助成制度のようだが、ここでどのような対応が相応しいのか、その判断が問われるという。
このシンポジウムにおいて結論的なことには論及しなかったが、ファシリテーターの三上氏(北大高等教育推進機構准教授)のまとめ、閉会時の新田副学長の挨拶から、科学者には研究結果についての一定の責任が発生する、という言葉がこの問題に対する現状の中でコンセンサスを得る考えなのではないか、というのが私の感想でもある。
3月12日(土)午後、北大の CoSTEP(Communication in Science & Technology Education & Research Program)が主催する公開シンポジウム『「デュアルユース」と名のつくもの~科学技術の進展が抱える両義性を再考する~』が北大のフロンティ応用化学研究棟で開催されたので受講した。
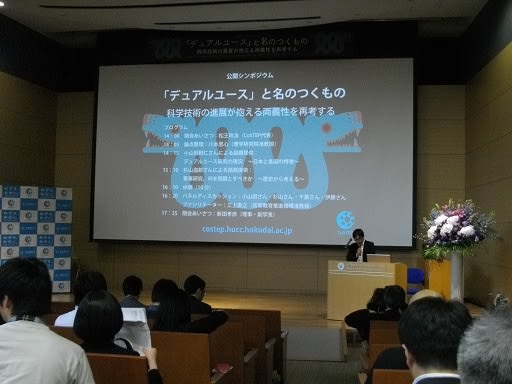
なぜ私がこのシンポジウムに参加しようと思ったかというと、デュアルユース(dual-use)という言葉に興味を抱いたからである。dual-useとは、字義的には「両用の」とか、「二通りの」と訳されるが、そこから科学技術の世界では「民生用と軍事用のどちらにも利用できること」を指す言葉だという。つまり、科学技術が進歩することは、私たちの生活を豊かにさせると同時に、軍事面で武器等の発達にも繋がることから、その問題をどう考えるか、ということがシンポジウムの趣旨であった。
こうしたことへの懸念は、アルフレッド・ノーベルがダイナマイトを発明したことが、大量の殺戮兵器を生んだことに繋がり、そのことが科学者の間では常に気懸かりな問題として論議されてきたようである。
ノーベル自身は、そのことを後年悔やみ、ノーベル賞の創設に繋がったことは有名な話である。
さて、シンポジウムは二人の方が話題提供という形で、この問題について論じた。
一人は、科学技術政策の専門家である小山田和仁氏が「デュアルユース研究の現況~日本と各国の特徴」題して、もう一人科学史研究家で北大名誉教授の杉山滋郎氏が「軍事研究、何を問題とすべきか~歴史から考える」と題して、それぞれ論じた。

※ 最初に話題提供として論じた小山田和仁氏です。

※ 続いて話題提供した杉山滋郎北大名誉教授です。
その後のパネルディスカッションでは、話題提供をしたお二人に加え、毎日新聞の科学部記者の千葉紀和と、北大大学院工学研究院教授の伊藤肇氏が登壇して意見を交換した。
話題提供、パネルディスカッションともに、それぞれの立場から、さまざまな考え方が提起されたが、それを的確に再現する力が私にはなく、発言者に迷惑がかかることも考え、ここでは私の総体的な感想を述べるにとどめたいと思う。
まず、小山田氏、杉山氏ともに、デュアルユースの問題については、研究開発のグローバル化が進展し、防衛・軍事の態様が変化している現状では、一様に研究者側にその責を問うのは難しい現状になっていると指摘されたと私は解釈した。
そうした中で、科学ジャーナリストである千葉氏は科学者には一定の責任があり、研究が軍事的に活用されるようになることに慎重になるべきではないかと、ジャーナリストらしく、現状への危機感を表明した。
ところが、科学の世界の一線で研究に従事している伊藤氏は、科学者は知的好奇心から研究を進めているものであり、その結果をどう利活用するかということについては、使う側の問題であり、科学者が自らの研究の結果の後、どのように利活用されたということについて責任を負う必要はない、的な発言をされた。

※ パネルディスカッションの様子です。
話は私がまとめたように単純なものではなかったのだが、概ね各氏の論旨についての間違いはないと思う。
日本の大学においては、大学法人化以降、研究予算が減少傾向にあるという。
そうした中で、防衛省が「安全保障技術研究推進制度」(耳で聞いただけなので正確でないかもしれない)を設けて、各大学での研究費を助成する制度を発足させたという。
喉から手が出るほど研究予算の増額を願う大学にとっては、魅力的とも映る助成制度のようだが、ここでどのような対応が相応しいのか、その判断が問われるという。
このシンポジウムにおいて結論的なことには論及しなかったが、ファシリテーターの三上氏(北大高等教育推進機構准教授)のまとめ、閉会時の新田副学長の挨拶から、科学者には研究結果についての一定の責任が発生する、という言葉がこの問題に対する現状の中でコンセンサスを得る考えなのではないか、というのが私の感想でもある。









