岩木山…。「津軽富士」とも称され、その山容の美しさは見事である。昨年秋、私もその山容を見た時に思わず「登ってみたい!」と思ったほどだ。昭和39(1964)年冬、その岩木山で高校生が遭難し、4人が落命した。その悲劇を追ったノンフィクションである。
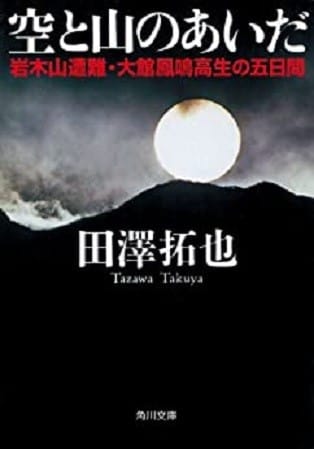
このところすっかり山岳小説(?)にハマっている。今回は高校生の遭難事件を追ったものである。著書には「岩木山遭難。大館鳳鳴高校生の五日間」という副題が付いている。
昭和39年1月、青森県の岩木山で秋田県鳳凰高校の山岳部員5人が遭難し、うち1人が4日ぶりに奇跡の生還を果たしたものの、4人が死亡するという遭難事故が発生した。5人は山岳部とはいえ初めての冬山だった。遭難の原因は、経験不足、準備不足、未熟さを指摘されても仕方ないものだった。例えば、冬山登山なのに用意したアイゼンは3足分で彼らは片足ずつアイゼンを付けて登るという無謀さだった。
それよりも著者が指摘するのは、地元警察署を中心とした対策本部のお粗末さである。冬山に精通した地元の山岳関係者の助言に耳を傾けず、二重遭難を恐れて及び腰の捜索活動に終始する。また所轄の警察署間(弘前署、鯵ヶ沢署)の軋轢などのためから、三日間で延べ500人も捜索隊を投入しながら何の手がかりもつかめなかった。
そうした中、捜索隊が捜索しているところとは正反対の場所でただ一人の生還者・村井秀芳君が発見された。
本書はその生還した村井君の証言を中心として、地元関係者、捜索隊、警察などに精力的に取材を重ねて、虚飾を排し淡々と綴る文章がかえって読む者を惹き付けた。
特に村井君の証言に基づいた遭難に至る状況は壮絶である。下級生をかばう上級生。村井君自身も極限状況にありながら動けなくなった友に自らのヤッケをかぶせたことなど、猛吹雪ののなかをさまよいながらも、最後までお互いをかばい合う5人の姿は、読む者の胸を熱くする。
この遭難事件でまず誰よりも非難を受けねばならないのは、遭難事件を引き起こしてしまった高校生自身だろう。岩木山は登山愛好者に言わせると標高1,625mという低山だという。しかし、冬山は夏山の常識では推し量れないくらい状況は激変する。初めての冬山ということであれば、経験者と同行することが最低条件だったのではないだろうか?若気の至りとはいえ、尊い若い命が奪われてしまったことは残念でならない。
さらに非難を受けねばならないのは、地元警察をはじめとした捜索隊の官僚的な姿勢ではないだろうか?人の生死がかかっている状況下においても事なかれ主義に陥ってしまっているところに病巣の深さを感じずにはいられない。
著者の田澤拓也氏は、そうしたことも含めてありのままを淡々と書き進めることで、かえって読者を惹き寄せたように思われる。作品は第8回の開高健賞を受賞している。









