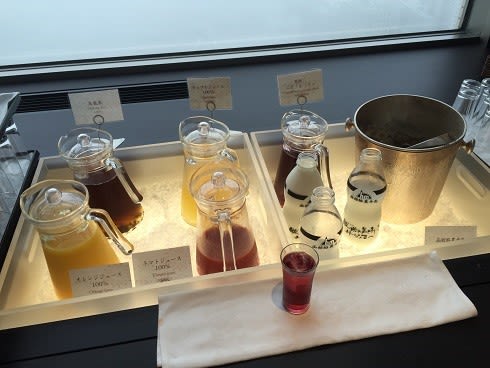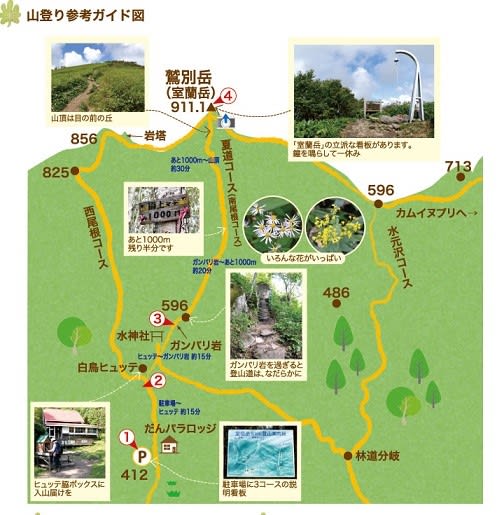7月5日(水)午後、連続受講している札幌大学の公開講座「地域創生入門」の第12講があった。12回目の講座は「北海道ブランドはコミュニケーションで創る」と題して(株)北海道ブランド研究所々長の高堂理氏が講師を務めた。

高堂氏の電通での社歴は、まるで画に描いたような企業戦士としての半生である。
コピーライターから始まって、CMプランナー、クリエイティブディレクター、あとはその上にシニア、エグゼクティブと冠が付いて出世し、電通北海道の社長まで務め、最後は本社に戻りビジネス統括局長で電通マン人生を終えている。
その間、出会った有名人や、海外出張などについても語ったが、そこのところは割愛するが、ともかく広告業界大手の電通という会社の中で広告マンとして王道を歩いてきた人のようだ。
そうした背景の中で、高堂氏は今「北海道をブランディングする」仕事に就いているという。
「北海道をブランディングするとは?」という問いに対して、高堂氏は、北海道の素晴らしい商品やサービス、環境を「素晴らしいもの」として国内外にアピールすること、と捉えて日夜汗を流しているということだった。
高堂氏は「北海道をブランディングする」際に、最も意識していることは「本質的なところを整える」ことだという。
本質的なところを整えるとは、「それは正しいか?」という問いだという。例えば、北海道の酪農製品を売り出そうとするとき、「それは美味しいか?」、「それは美しいか?」、「それは面白いか?」等々、という問いを自らに問いかけることだという。
「酪農王国北海道」と喧伝し、広々とした放牧地での酪農風景がCMなどで流されるが、北海道酪農の実態は、放牧酪農はわずか8%で、実に70%は繫ぎ飼いであるという事実。(フリーストールという方法が20%あるという)
北海道酪農の実態は、繋ぎ飼いにして、本来牛が食べなくても良い穀物を大量に食べさせて、乳量を多くする酪農をしている実態にある、高堂氏は「これが本質だろうか?」と問うているのだと理解した。

「アニマル・ウェルケア」(動物の幸せな生活)という考え方が広まってきているという。そうした実践をする農家も増えているようだ。
牛本来の生き方を取り戻す放牧によって、質の高い牛乳を確保し、そうした牛乳を使っている街のお菓子屋さん、ケーキメーカーが世の中に受け入れられつつある事例を紹介されたが、そのことについては割愛したい。
こうした事例を紹介し、高堂氏は学生たちに「就活」という自己ブランディングの在り方について語りかけた。
それは「どれだけ自分を考え抜いたか」であるという。そのことによって「対応力」が生まれるという。自分を考える…やりたいことをとことん考えることが大切だと…。やりたいことが変わってくることもあるから、そのことは気にする必要はないと…。
そして高堂氏は次のようにも言った。「対応力は、自己洞察、自己努力に比例する」と…。
ここまでレポしてきて、今回の講義のテーマである「コミュニケーション」について触れられていないきらいがあるが、高堂氏は「本質」を見極めるために徹底して現地・現場を歩き、そこで話を聴き、意見を交換し、議論し、本質を見極めようとしてきたことを事例の中で何度も述べられた。
氏が若者たちに言いたかったこと、それは「まやかしではなく『本質』に迫れ!」ということだったと私は理解した。