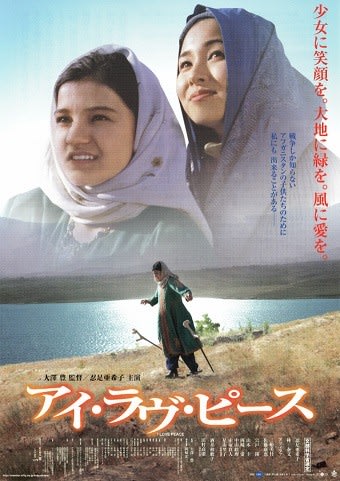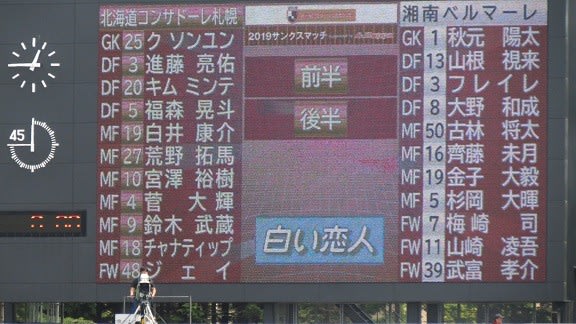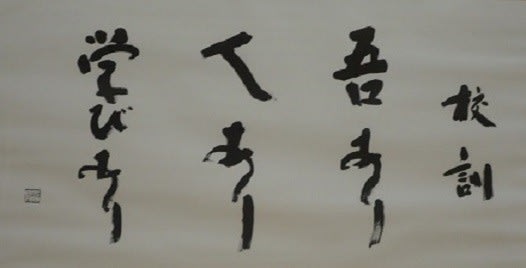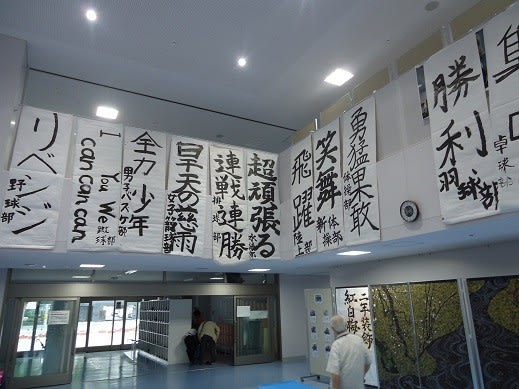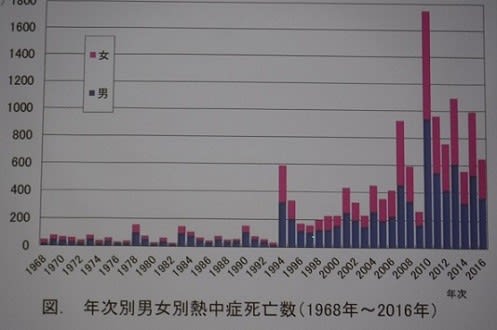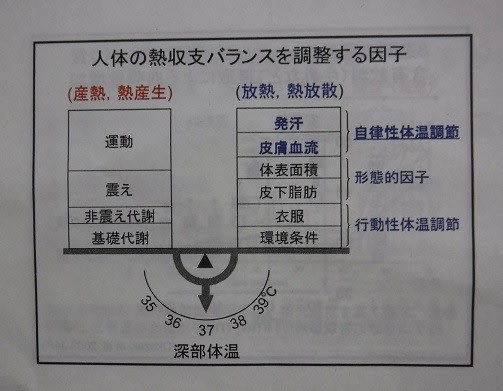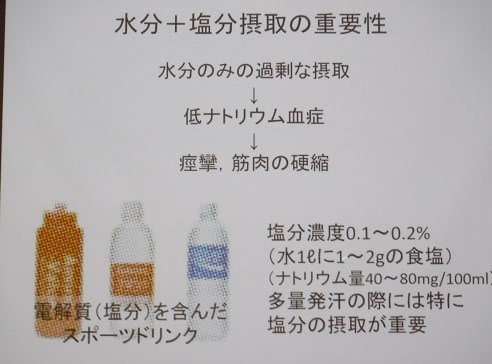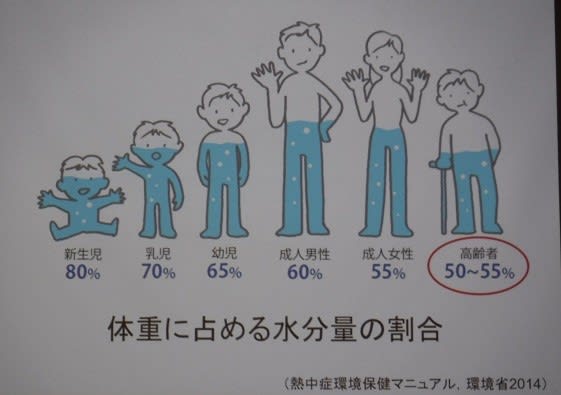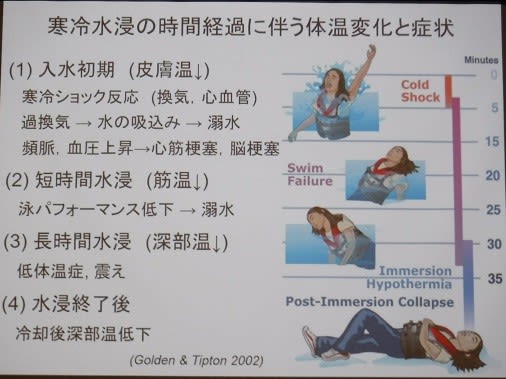小さな山だったが、雨模様ということもあり、かなり自分自身を急き立てた。さらには眺めの良いはずの山頂は厚い雲に覆われ眺望はゼロだったためか?帰宅した私は疲れと落胆から昼寝を決め込んだのだった…。

※ 盤渓山の山頂標識です。
私には前回の朝里天狗岳と同様にリベンジしなければならない山が残っていた。それがこの「盤渓山〈夏〉」である。その経緯は次のとおりである。
2016年の冬(2016/1/14)に私はスノーシューで盤渓山の登頂を果たしていた。続いて同年の夏に盤渓山に登ろうと山に向かった(2016/7/23)。冬に登ったのだから容易だろうと思ったのだが…。ところが周りの様相は一変していて盤渓山への取り付き口が一向に分からないのだ。登山口の周辺であちらこちらへと右往左往しながらも、とうとう取り付き口を発見できずに敗退したのだった。
本日(7月12日)、天気は良くなかったがそれでも近景は眺めることが出来るだろうとリベンジ登山に出掛けた。

※ 盤渓市民の森の入り口にはこのような駐車帯があります。

※ 市民の森入り口からしばらくは車道を上ります。
8時20分、盤渓市民の森の入り口に車を停め登山を開始した。約350mの車道を上ると緩く右にカーブする地点に小さなゲート(丸太が2本)があり、そこから左の沢へ下りていく。すると、幅広く下草刈りをした道が現れた。私はすっかりそこが登山道だと思い込んだ。その下草刈りをした道を進んでいくのだが、いっこうに沢の方に下っていかないので「?」と思った。記憶では丸太のゲートのところからグングンと下って行くのに…。私は再び前回と同じ過ちを犯しているらしいことに気づき、ゲートのところまで戻ってみた。するとゲートから10mも離れていないところに左に折れる微かな踏み跡を見つけ出した。頭上を見るとピンクのテープも招いていた。「間違いない!」と確信して、微かな踏み跡を辿り沢へと下りて行った。

※ 車道をそのまま行くと「妙福寺」というお寺に至ります。登山道は左の丸太のゲートから入ります。

※ 丸太のゲートを通過すると写真のような刈り取りされた道があり、つい誘われてしまいます。
しかし、登山道は手前の草むらから下の方へ下った行くのが正解でした。
下りていく途中、この登山で唯一の山アジサイが見事な紫色の花を付けていた。後にも先にもこの時だけ目にした花だった。やがて小さな渡渉地点を渡った。冬の時も水は涸れていた確かに渡った渡渉地点だった。もう間違いはない!このまま踏み跡を辿ればいい!と確信した。

※ 緑一色の山中で唯一目に入った山アジサイの花です。

※ ピンクのテープが登山道であることを示しています。

※ おぼろげに覚えていた渡渉点に至り「間違いない!」と確信しました。
渡渉地点まで下った登山道はそれから尾根に向けての急登に入った。休む間もない急登で一気に汗にまみれながら登り続けた。ようやく尾根に出て、けっこうな時間登り続けたと思ったが、時計で確認するとそれほどの時間ではなかった。

※ 渡渉点の後、尾根に向かっての急登が続きました。
尾根に出てからは緩急を繰り返しながら高度を上げていく。特にポイントとなるところもなく、登り続けた。登りながら、他の登山道では見られない異変(?)に気づいた。それは、登山道のところどころに何やら同じような植物の欠片(?)が固まっておかれてあるのだ。いくら登って行ってもそれが目に入る。「何だろう?」と思い、たまらず手に取ってみた。するとそれはササの先にあたる生長点のところを抜き取ったものだと判明した。それが結局登山道の全体におかれていた。私にとっては初めて見る光景だった。いったいあれは何なんだろうか?山の事情に疎い私は次のように推察してみた。ササの生長点を抜き取ることによってササの生長が止まり、登山道がササに覆われてしまうのを防ごうとしているのではないか?ちょっとガセネタっぽいが、私にはそうとしか考えられないほど、登山道のいたるところにそうした光景が広がっていた。そして、私も真似してササの生長点を抜き取り、先においた固まりの上に置いて行ったのだった。

※ 尾根に至ると、こうした緩やかなところもありました。

※ 周りの木は樺の木や広葉樹が多かったようです。

※ このような草の固まりがいたるところで見られました。何だろう?

※ 手に取ってみると、ササの生長点のところでした。

※ 私も真似して生長点を抜き取り、こうした登山道上に置きました。
登山道の方は相変わらず緩急を繰り返しながら高度を上げていた。ガイドブックでは最後の急登に汗をかく、と書かれていたので「ここが最後の急登?」と何度も騙されながら何度目かの急登の後、ようやく山頂に到達することが出来た。

※ この「火の用心」と書かれた石標は何でしょうか?水溜には小さいし???

※ 山頂近くの急登の一つです。

※ 山頂手前にケルンが積んでありました。

※ 私には珍しい自撮りの写真を掲載しました。

※ 山頂はご覧のように眺望はゼロでした。
山頂は、朝自宅を出た時よりも雲が厚く覆っていて、眺望はゼロだった。私は冬に登ったときに眺めた見事な眺望を思い浮かべながら自分を慰めた。
眺望の効かない山頂での長居は無用である。10分後には山頂を後にしていた。下山開始後まもなく、雨がぽつりぽつりと私の頬を叩いた。本格的な降りとなる前に下山を完了したいと先を急いだ。結局、最後までぽつりぽつり以上の降りにはならず、下山を完了した。標準のコースタイムでは1時間というコースを珍しく私は50分で完了した。標準タイムを上回るなんて珍しい。雨が私を追い立てたのだ。

※ 下山時には雨がポツリポツリと落ちてきました。雨に濡れた葉です。
帰路、盤渓山の近くにある幌見峠のところにある札幌の新名所「ラベンター園」を覗いて帰宅した。



【盤渓山〈夏〉 登山データ】
標 高 604m (標高差 334m)
駐車場 盤渓市民の森の入り口に5~6台が駐車できるスペースがある。
行 程 ※ グランドシニアの足とお考えください。
市民の森入り口→(70分)→盤渓山山頂→(50分)
時 間 上り(1時間10分) 下り(50分)
天 候 曇り、弱風
登山日 ‘19/07/12